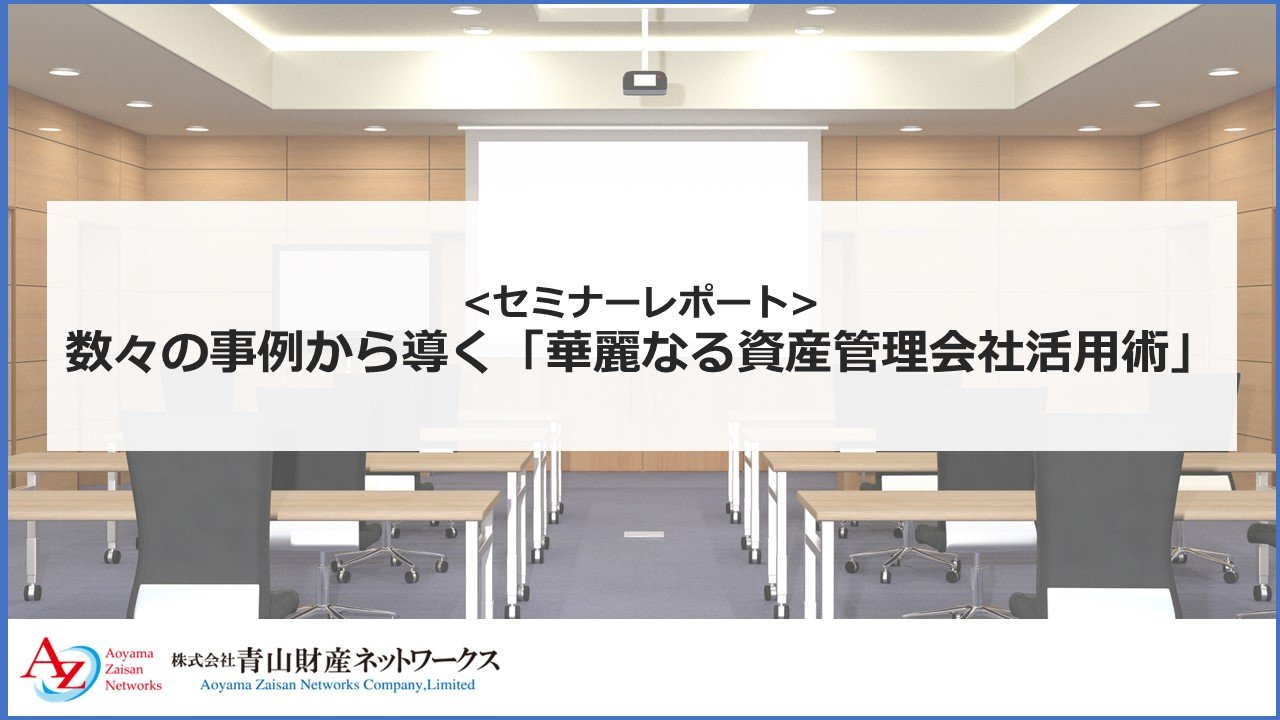資産管理会社はどの程度の資産や収入を満たせば設立したほうがよいのでしょうか。事業や投資で利益や所得が増えたため資産管理会社を設立したいものの、どの段階で設立すべきか分からないという人も多いと思います。本記事では、その疑問に答えます。
そのほか、資産管理会社設立のメリットやデメリットも詳しく解説します。資産管理会社の設立を検討している人はぜひ参考にしてください。
資産管理会社とは
そもそも資産管理会社とはどのような会社でしょうか。
本章では、資産管理会社とは何か、資産管理会社を設立すべき金額、資産管理会社を設立すべき人について解説します。
資産管理会社とは
資産管理会社とは、不動産や株式などの資産を持つ個人が資産管理を目的として設立する会社であり、プライベートカンパニーとも呼ばれます。設立の主な目的は、不動産や株式などの個人資産の運用や管理です。
メインとなる収入は、不動産の賃貸による賃料収入、株式の所有や運用による配当収入です。
一般的に会社の形態は株式会社または合同会社であり、不動産の賃料収入や株式の配当収入を資産管理会社が受け入れ、役員報酬としてオーナーである個人へ配分します。
資産管理会社の設立を検討すべき所得はいくらから?
それでは、どれくらいの所得があれば資産管理会社を設立すべきでしょうか。
一般に、個人の課税所得が900万円を超えれば、資産管理会社を設立するメリットがあるといわれます。所得(=収入マイナス経費)が900万円を超えると、法人税率が所得税率より低くなるからです。資産管理会社には設立コストや、維持していくためのコストも発生するため、所得が1,200万円を超える水準が続くようなら検討してみましょう。
所得金額が多くなると累進課税制度により所得税率が高くなりますが、法人税では比例税率により所得金額の税率は一定です。
課税される所得金額が900万円での所得税率は33%ですが、同じケースでの法人税率は23.2%になります。なお、資本金が1億円以下の中小企業であれば800万円以下については税率がさらに低くなります。
引用:国税庁 所得税の税率
資産管理会社を設立すべき人(税金面でメリットがある人)
それでは資産管理会社を設立すべき人とは、どのような人たちでしょうか。
具体的には下記の人たちです。
- 相続税の発生が見込まれる資産家
- オーナー社長
- 副業や資産運用で一定の所得があるサラリーマン
・相続税の発生が見込まれる資産家
個人が被相続人の財産を相続すると、相続税や所得税、住民税などの税金を納めなければなりません。例えば、法定相続分に応ずる取得金額が1億円とすると、相続税率は30%と非常に高くなります。
法定相続分に応ずる取得金額とは、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた金額を法定相続分に応じて分けた額です。
資産管理会社を設立し、配偶者や子を役員にして役員報酬を支払えば資産を移転できます。
生前贈与での非課税枠は1年間で110万円です。仮に3,000万円を超える財産を贈与すると、55%の贈与税が課されます。
しかし配偶者や子などの家族を役員とし、役員報酬を支払うのであれば、多額の財産を贈与したときの贈与税よりも低い税額で財産の移転が可能です。
また、個人の所有資産を相続人等が相続したときに相続税の納税義務が発生します。相続税の納税期限は、相続人等が被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内です。
不動産を含む財産を相続したケースでは相続税を現金で支払えなければ、不動産を売却して相続した不動産を手放さなければならないこともあり得ます。
しかし、資産管理会社に不動産を移転しておけば、不動産そのものは相続税の対象ではなくなるのです。被相続人の保有資産は資産管理会社の株式となります。一般的に株式には議決権が備わっているため、資産管理会社を設立する前に将来相続が発生した際には、株式を誰に集約するのかも決めたおいた方がトラブルの予防になります。
・オーナー社長
自社株をどのようにして後継者に相続させるか悩んでいるオーナー社長も多いでしょう。
資産管理会社が保有する自社株について普通株式と無議決権株式を発行し、後継者へ普通株式を相続させ、後継者以外の人には無議決権株式を相続させます。
無議決権株式とは、株主総会での議決権がない、もしくは制限されている株式のことです。相続人全員が普通株式を相続すると、会社の経営方針について意見が割れたときに、会社の運営が非常に困難となるリスクが発生します。
その点、財産価値はあるが議決権がない無議決権株式を後継予定者ではない相続人に相続させておけば、会社の事業がスムーズに承継されます。
・副業や資産運用で一定の所得があるサラリーマン
住居費や車両関連費など個人では経費にできなかったものが、法人になれば経費にできる範囲が広がり、結果として利益が残りやすくなります。
加えて、勤務実態に応じて家族に給与を支払えば、すべて自分が所得を得て税金を支払うよりも税金は少なくなり、資産管理会社を設立する前より手元にお金が残るというメリットがあります。
資産管理会社設立のメリット

多くの収益不動産を所有する地主や評価額が高い自社株式を所有するオーナー社長など、いわゆる富裕層の人たちが資産管理会社を設立すれば多くのメリットが期待できます。
では、資産管理会社を設立するとどのようなメリットがあるのでしょうか。主なメリットとして下記が挙げられます。
- 所得に対する税金が変わる
- 所得を分散できる
- 経費として計上できる範囲が広がる
- 損失の繰越控除の期間を延長できる
- 社会保険への加入
- 相続によるトラブルを回避
それぞれ見ていきましょう。
・所得に対する税金が変わる
不動産や自社株式を個人所有から資産管理会社所有に変更すると、所得・利益に課される税金の種類が変わります。
不動産や自社株式を個人が所有する場合と、資産管理会社が所有する場合とでは、所得・利益に課される税金の種類が異なってきます。
個人が不動産や自社株式を所有している場合に課される税金は、所得税、住民税、個人事業税です。
所得税は課税対象額が大きくなるほど高くなる累進税率が適用されており、課税所得が4,000万円以上で適用される税率は45%になります。
住民税のうち所得に応じた所得割は、課税所得に対し一律10%となっています。
個人事業税では事業的規模で不動産貸し付けをしたとき、290万円を超える不動産所得(青色申告特別控除前)に適用される税率は5%です。
資産管理会社が不動産や自社株式を所有している場合に課される税金は法人税、法人住民税、法人事業税です。
資本金1億円以下で年所得が900万円の中小法人の実効税率は、およそ33.8%となります。
※2024年時点での実効税率は下記の計算式で算出します。
{法人税率×(1+地方法人税率+住民税率)+事業税率+特別法人事業税率}÷(1+事業税率+特別法人事業税率)
このように個人に課される所得税などと資産管理会社に課される法人税などには大きな差があり、高所得者ほど税負担の差は大きくなります。
・所得を分散できる
例えば配偶者や子どもなどの家族を資産管理会社の役員あるいは従業員とし、会社から役員報酬や給与を支給することにより、オーナーに集中していた所得を、家族に分散できます。
家族を役員や従業員とした場合、役員報酬や給与は給与所得に該当するため、当該役員や従業員は給与所得控除が適用されます。
・経費として計上できる範囲が広がる
経費として計上できる範囲は、個人事業オーナーと資産管理会社とでは大きく異なっています。個人事業主として計上できる経費は、収入を得るため直接に要した費用(直接経費)に限られます。例えば、自宅兼事務所や自家用自動車を事業活動に利用して、家賃や自動車の車検代などの全額を経費として計上しても、まず認められません。
これに対し資産管理会社の場合、業務上必要なものであれば経費として認められます。法人では、直接経費に加え、間接経費の一部も費用として計上できます。下記は個人事業主では認められないものの、資産管理会社では認められる経費の例です。
- 役員報酬
- 福利厚生費用(例:社員旅行は4泊5日まで)
- 健康診断費用
- 生命保険費用(資産管理会社が契約者)
- 出張時の日当
- 社宅の家賃
福利厚生費用や健康診断費用などは業務とは直接の関係はありませんが、経費として計上可能です。
役員報酬の場合は、定期同額給与や事前確定届出給与のいずれかに該当することが条件です。ただし、支給金額が過大であると税務署が判断すれば、経費としては認められません。
*定期同額給与:1カ月以下の頻度での定額報酬
事前確定届出給与:定期同額で支払うことを事前に税務署に届け出た給与
・繰越控除の期間を延長できる
繰越控除とは、本年分の損失を控除しきれないときに次年度以降にその損失を繰り越し、次年度以降の利益から控除できる制度です。
青色申告で確定申告している個人事業主の繰越控除期間は最長3年ですが、資産管理会社の繰越控除期間は最長10年間まで認められます。
仮に、過去10年間に毎年500万円の赤字が発生していて、本年度は5,000万円の黒字とします。
個人事業主がこの財務状況であれば、繰越控除は最長3年間適用されるため、課税対象額は3,500万円です(=5,000万円-500万円×3年)。これに対し資産管理会社では、最長10年間繰越控除が適用されるため、課税対象額は0円(=5,000万円-500万円×10年)です。
不動産投資がメインの事業の場合は初期費用が非常に高額となることが多く、事業開始時から大きな損失が発生する傾向があります。資産管理会社を設立し、繰越控除を受けることにより、長期間にわたって損益を平均化できます
・社会保険への加入
資産管理会社を含むすべての法人は、社会保険に加入しなければなりません。資産所有者が個人事業主であれば加入するのは国民健康保険・国民年金ですが、資産管理会社になると保険は健康保険(社会保険)に切り替わり、国民年金にプラスして厚生年金にも加入することになります。結果として、将来的に受け取る年金額は増えることになります。役員報酬を支払っている役員(=家族)だけでなく、役員が扶養している家族がいれば社会保険の扶養親族になることができます。
・相続によるトラブルを回避
資産所有者が死亡した後の相続人間の争いを回避するために資産管理会社が役立ちます。
遺産が預金や株式だけであれば分割しやすく相続争いに発展しにくいですが、不動産のように分割しにくい資産は、相続人間でのトラブル発生につながりかねません。
また、不動産を相続人同士で共有という選択をしても、売却時に共有者全員の合意が必要になるため売却に時間がかかる傾向があります。
あらかじめ不動産を資産管理会社に移転し株式に転換することにより、相続によるトラブル発生を回避し、結果として資産継承をスムーズに進められるでしょう。
資産管理会社設立のデメリット

資産管理会社を設立すると、メリットだけでなくデメリットも発生します。
資産管理会社設立による主なデメリットは下記のとおりです。
- 法人設立費用や維持するコストが発生
- 資産管理会社の保有資産は自由に使えない
・法人設立費用や維持するコストが発生
合同会社、株式会社どちらの形態でも資産管理会社は設立可能ですが、前者のほうが安く設立できます。
| 合同会社 | 株式会社 | |
| 設立費用 | 10万円程度 ※出資金の額に応じて変動 |
22万円程度 *資本金の額に応じて変動 |
|---|---|---|
| 運営・維持コスト (官報掲載費・登録免許税など) | 役員の任期:なし 決算公告:不要 官報掲載費・重任登記にかかる登録免許税:不要 |
役員の任期:通常2年、最長10年 決算公告:必要 官報掲載費・登録免許税:必要 |
資産管理会社の設立費
資産管理会社を設立するには、さまざまな費用がかかります。合同会社を設立する場合と株式会社を設立する場合に、資本金以外の必要な費用は次のとおりです。
- 合同会社を設立する場合
- 登録免許税:6万円または資本金×0.7%の高いほう
- 定款認証料:0円
- 定款謄本手数料:0円
- 定款用の収入印紙代:4万円(電子定款では0円)
- 会社印の作成費用:数千円
- 株式会社を設立する場合
- 登録免許税:15万円もしくは資本金×0.7%の高いほう
- 定款認証料:3万円(資本金100万円未満)、4万円(資本金100万円以上300万円未満)、5万円(資本金300万円以上)
- 定款謄本手数料:1ページあたり250円、全体で約2,000円
- 定款用の収入印紙代:4万円(電子定款では0円)
- 会社印の作成費用:数千円
資産管理会社の維持費
資産管理会社を運営するには、法人税や法人住民税、社会保険料など、さまざまな維持費が必要です。主な費用は下記のとおりです。
- 法人税:法人の所得に対して課税されます。普通法人の場合、資本金1億円以下の法人に課される税率は、所得金額800万円以下の部分に対して15%(原則は19% 2025年3月31日まで軽減税率適用)もしくは19%、800万円超の部分に対して23.2%です
- 法人住民税:法人住民税とは、法人都道府県民税と法人市町村民税との総称です。法人税割と均等割との合計が法人住民税額となります。東京都の場合、資本金1,000万円以下、特別区内の従業員数50人以下の法人には、7万円が課されます。
- 法人事業税:法人が事業を行う際に利用した行政サービスに対して、その経費の一部を負担するために法人に課される税金です。
- 固定資産税:資産管理会社の設立後は、資産所有者が支払っていた固定資産税を資産管理会社が納めます。標準税率は原則1.4%です。
- 社会保険料:会社と従業員がそれぞれ社会保険料の半分を負担します。
- 事業所税:事業所税とは、主に人口30万人以上の都市や政令指定都市などが都市環境整備、改善のために一定の規模の個人や法人に課す税金です。
資産管理会社の保有資産を自由に使えない
資産管理会社を設立し、役員に就任した家族に役員報酬を支払うことは、所得の分散や相続対策として有効です。ただし、役員報酬の金額や支払い方法をいったん決めると、資産所有者であっても勝手に変更できません。会社法第361条1項には役員報酬について次のように規定されているからです。
「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。」
役員報酬額や支払い方法を変更するためには、定款で別の方法を定める、もしくは株主総会で決議しなければなりません。資産が資産管理会社の保有になると、資産所有者個人の意思で自由に使用できなくなります。
まとめ
資産管理会社を設立する際には、あらゆる面でのメリットとデメリットを慎重に検討することが大切です。自分で判断できないときは、税理士やコンサルティング会社などの専門家に相談することをおすすめします。
監修者
- 相澤 光Aizawa Hikaru
- コンサルティング事業本部 コンサルティングサービス室 室長 兼 第四事業部 ダイレクトグループ グループ長
不動産や法人を活用した財産防衛策の立案・実行に従事し、財産と想いを次世代に承継するための支援を提供。最適な選択肢を見つけられるよう、中立的な立場で家族全体の意向調整もサポートすることを信条とする。
当社の30年にわたるナレッジを集約した書籍を発行し、セミナー登壇実績も多数。
趣味:学び(税理士資格の勉強中)、ギター、サウナ
- 専門分野
- 土地持ち資産家、金融資産家向けコンサルティング
- 資格
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
- 著書
- 「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策