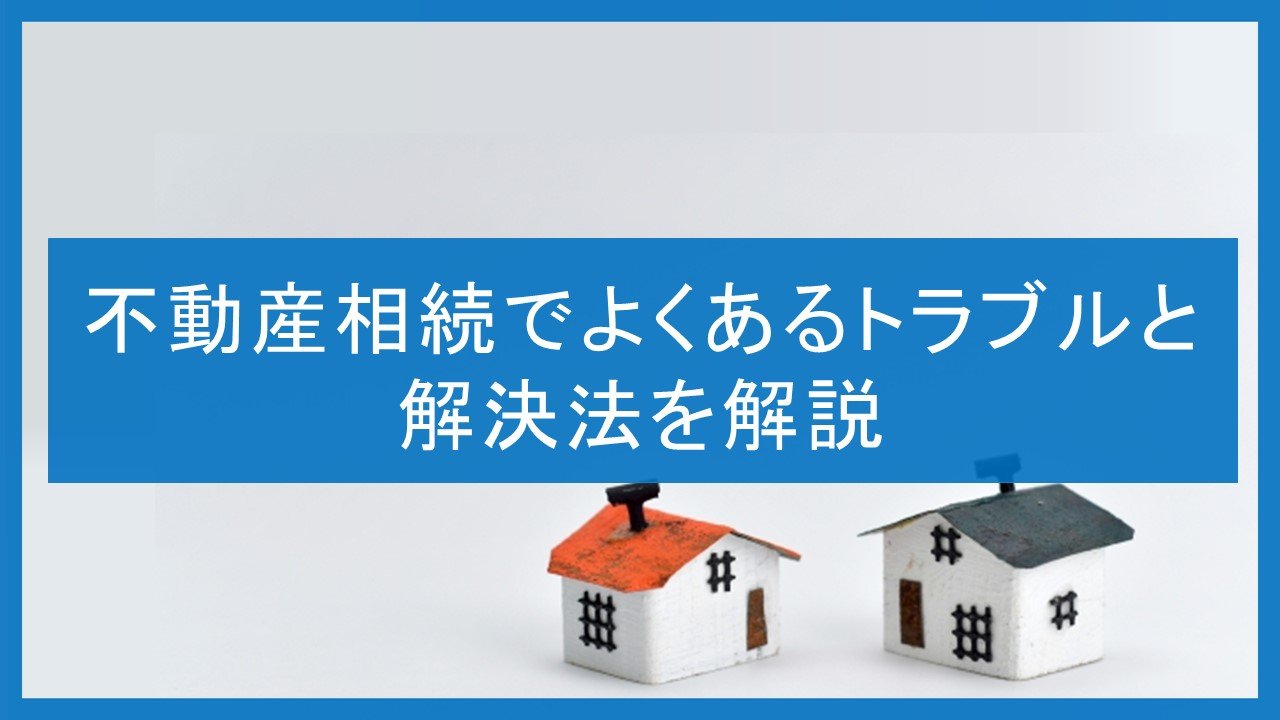相続した土地や建物などの不動産がいくらで購入されたものか分からない人は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、取得費が分からない場合の計算方法から、かかる税金について詳しく解説します。
相続した不動産の取得費が分からない人はぜひ参考にしてください。
不動産を売却したときの税金とは
不動産を売却したときには、所得税と住民税が課されます。ここで得た利益を譲渡所得といい、長期譲渡所得の場合は20.315%の税金が課されます(所得税が15.315%、住民税が5%)。この税率は極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置は考慮していない税率です。
譲渡所得の計算式は次のとおりです。
譲渡所得=収入金額(売却価格)-取得費-譲渡費用
取得費は主に下記のとおりです。
- 土地や建物の購入代金
- 購入手数料
- 設備費、改良費など
また、譲渡費用とは売却するために直接かかった費用をいい、主なものは下記のとおりです。
- 土地や建物を売却するために不動産会社に支払った仲介手数料
- 売主が負担した印紙税
- 土地を売却するために土地上の建物の取り壊しにかかった費用
- その他の売却するために売主に義務づけられたこと(例:確定測量等) にかかった費用
修繕費や固定資産税などは譲渡費用に該当しないので注意してください。
この計算式を使って計算すると、例えば収入金額1,000万円、取得費200万円、譲渡費用100万円の場合、譲渡所得は700万円になります(1,000万円-200万円-100万円=700万円)。
そして、このケースでの税金の計算式は次のとおりです。
所得税:700万円×15.315%=107万2,050円→107万2,000円(百円未満は切り捨てるため)
住民税:700万円×5%=35万円
所得税+住民税=107万2,000円+35万円=142万2,000円
相続した不動産の取得費
相続した不動産を売却したとき、譲渡所得の計算はどうすればよいのでしょうか。
前章で解説したように、譲渡所得は売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて算出します。相続した不動産の取得費とは、亡くなった人(被相続人)が不動産を購入した金額であり、相続人が相続したときの時価ではありません。
被相続人が200万円で不動産を買って、相続人が500万円で売却し譲渡費用が100万円かかったとすると、譲渡所得は200万円になります。
譲渡所得(200万円)=売却価格(500万円)-取得費(200万円)-譲渡費用(100万円)
このやり方は、何代も前のご先祖様から受け継いでいる不動産にも適用されます。ただし、ご先祖様の取得費をベースとして、譲渡所得を計算しなければなりません。
ご先祖代々受け継いでいるような土地は現在と比べ、非常に低い金額で買われていることが多く、売却した金額のほとんどが譲渡所得になってしまいます。その結果、多額の所得税と住民税が課せられてしまうのです。
相続した不動産の取得費が分からないときはどうする?

実際に被相続人から土地を相続しても、被相続人がその土地をいくらで買ったか正確に答えられる人は少ないと思います。
「だいたいの金額は見当がつくが、はっきりした金額は分かりません」という人が多いのではないでしょうか。
しかしながら、亡くなった人(被相続人)が土地を買った金額が分からなければ、譲渡所得を計算できません。このようなケースでは、5%ルールが適用できます。
原則として5%ルール(概算取得費)が適用
5%ルールとは、購入時の価格(取得費)が分からないときは、売却価格の5%相当額を概算取得費として譲渡所得を計算できるというルールです。
例えば、亡くなった父親(被相続人)から相続した土地が1,000万円で売れた。しかし、父親がいくらでこの土地を買ったか分からない。
このようなケースでは、売った金額1,000万円の5%相当額の50万円が、買ったときの金額(概算取得費)ということになります。
したがって、譲渡費用が100万円とすると、譲渡所得は850万円(=1,000万円-50万円-100万円)です。この譲渡所得に20.315%の税金が課されます。
取得費を推測する方法
「亡くなった父親はこんなに安い金額で買ったはずはない」と考えている人は、過去の取得費を推測してみてはいかがでしょうか。
取得費を推測する方法として、一般的には以下のようなものがあります。ただし取得費の合理的な算出方法として法律で定められているわけではないため、算出方法として使用される際には、税理士や税務署等にご相談ください。
・登記簿謄本の抵当権の欄で、購入時のローン情報から推測していく方法
住宅ローンの金額は、全部事項証明書(登記簿謄本)の乙区事項欄に記載されています。具体的には、権利部(乙区)の権利者その他の事項の中の「債権金額」が金融機関などからお金を借りて購入に充てた金額です。
・不動産鑑定士に過去の取得費を算出してもらう方法
不動産鑑定士とは、土地や建物などの不動産の価値を鑑定評価し、鑑定評価額を決定する専門家です。
・路線価で取得費を推計する方法
路線価とは、道路に面している宅地の1㎡あたりの価額を1,000円単位で表示しているものです。
国立国会図書館では、所蔵する路線価図のうち1995年までのものをデジタル化し公開しています。
1955年から1972年までの路線価は3.3㎡(約1坪)あたり1,000円単位で表示されていますが、1973年以降は1㎡あたり1,000円単位で表示されています。
また、路線価は1992年分の路線価評価から、評価する時点を前年の7月1日から当年の1月1日に変更し、評価割合を公示地価の70%程度の水準から80%程度の水準に変更しました。
このように評価対象となる土地の路線価をベースにして、評価水準により割り戻し取得費を推計できます。
・市街地価格指数を参考にする方法
市街地価格指数とは、全国の主要198都市の約1,300地点の地価を日本不動産研究所が毎年3月末と9月末に評価し指数化したものです。この指数の算出目的は、市街地の宅地価格(商業地や住宅地、工業地、最高価格地)の動きを表すためです。
市街地価格指数による土地の取得費の計算式は次のとおりです。
「譲渡(売却)金額×取得(購入)時の市街地価格指数÷譲渡(売却)時の市街地価格指数」
・地価公示価格から取得費を推計する方法
地価公示価格とは、地価公示法に基づいて国土交通省土地鑑定委員会が毎年3月に公表している標準地の価格であり、公示地価ともいいます。
国土交通省土地鑑定委員会に属する鑑定評価員(=不動産鑑定士)が毎年1月1日時点の標準地の1㎡あたりの正常な価格を判定しています。
地価公示価格は通常の土地取引に指標を与えており、不動産鑑定ならびに公共事業用地における取得費算定の基準にもなっております。その他にも土地の相続税評価や固定資産税評価のベースとして使われています。
地価公示価格を調べるには国土交通省の「不動産情報ライブラリ」を活用するといいでしょう。調べたい土地の都道府県や市町村を選択し、検索条件を入力すれば地価情報が表示されます。
・住宅ローン借入金額を証明する「金銭消費貸借契約書」により確認する方法
金融機関から住宅ローンを借り入れる際には、通常「金銭消費貸借契約書」などを取り交わします。この契約書には、住宅ローンによって借り入れる総額が記載されています。借り入れたローンの総額が分かれば、購入した不動産の取得費を推定できます。
まとめ
本記事では、不動産を売却したときにかかる税金や相続した不動産を売却したときの譲渡所得の計算、相続した不動産の取得費が不明なときの算出方法について解説しました。
相続した不動産の取得費により支払う税金の額は大きく左右されます。
もっと詳しく知りたい人や、売却時の残りを把握されておきたい方は税理士や不動産コンサルティング会社に相談することをおすすめします。
監修者
- 相澤 光Aizawa Hikaru
- コンサルティング事業本部 コンサルティングサービス室 室長 兼 第四事業部 ダイレクトグループ グループ長
不動産や法人を活用した財産防衛策の立案・実行に従事し、財産と想いを次世代に承継するための支援を提供。最適な選択肢を見つけられるよう、中立的な立場で家族全体の意向調整もサポートすることを信条とする。
当社の30年にわたるナレッジを集約した書籍を発行し、セミナー登壇実績も多数。
趣味:学び(税理士資格の勉強中)、ギター、サウナ
- 専門分野
- 土地持ち資産家、金融資産家向けコンサルティング
- 資格
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
- 著書
- 「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策