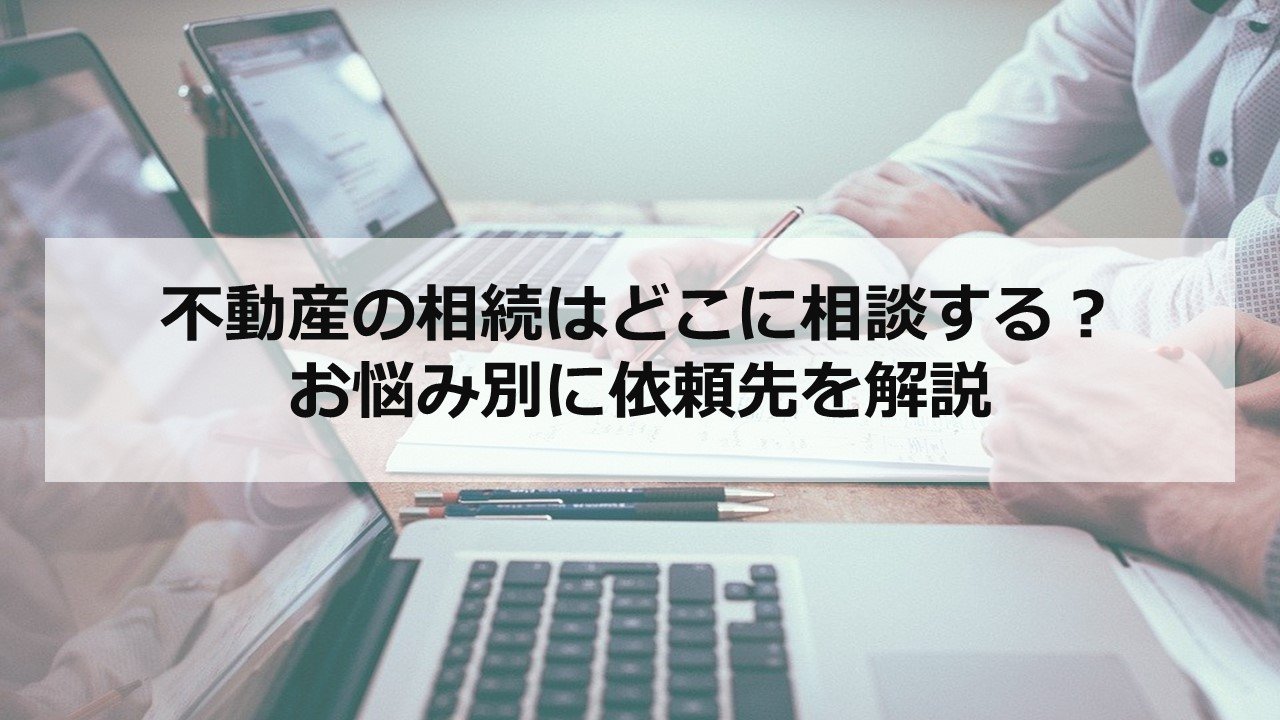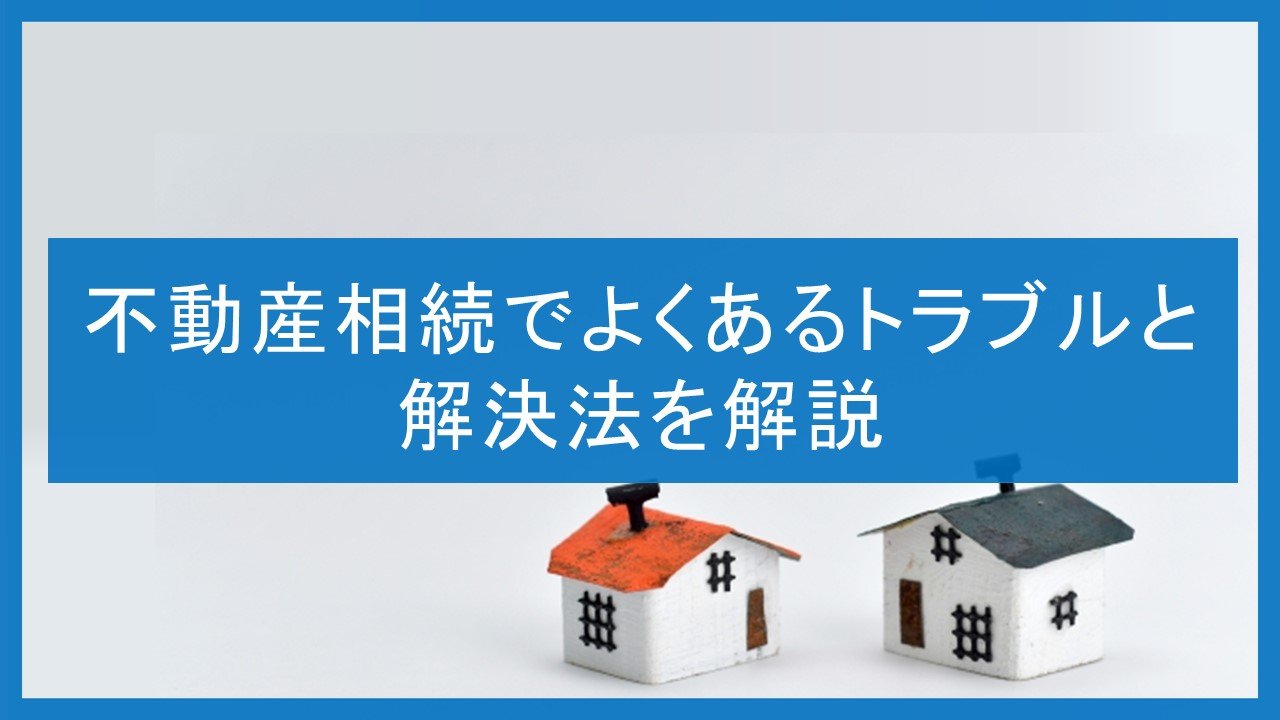財産の承継・運用・管理を上手く行っていく手段の一つとして、生前贈与を活用することは有効です。生前贈与により、次世代への資産移転を計画的に進めることが可能です。ただし、現金や預貯金の贈与は比較的手続きが簡単で実行しやすい一方、不動産の生前贈与においては異なる側面に注意が必要です。
不動産を贈与する際には、名義変更をはじめとする法的手続きや評価額の計算が必要で、現金贈与と比べて手続きに一定の手間がかかる場合があります。しかし、不動産の生前贈与には独自のメリットもあり、具体的な状況によっては、効果的な対策です。
そこで本記事では、不動産を生前贈与する際の具体的な手続きやメリットについて詳しく解説するとともに、相続との比較も行いました。不動産が相続財産の大部分を占める方や、不動産を相続予定の方は、ぜひ参考にしてください。
「生前贈与」とは
生前贈与は個人が存命中に自分の財産を他者に無償で譲渡する行為を指します。これは、亡くなった後に行われる「相続」とは異なり、贈与者が生きている間に自分の意志で財産を誰にでも渡すことができるという特徴があります。
生前贈与には様々なメリットがありますが、タイミングや手続きによっては税金の負担が増加したり、親族間でトラブルが生じたりする可能性もあるため注意深く行うことが重要です。
不動産を生前贈与するメリット

自分が所有する不動産を、生前に配偶者や子どもなどに贈与しようと考えている方もいるでしょう。生前に不動産を贈与する方法が生前贈与であり、いくつかのメリットがあります。
- 希望する相手やタイミングで贈与が可能
- 相続に関係なく財産を確実に引き継げる
- 相続税額に影響する
- 家賃収入を受け取る人を変更できる
希望する相手やタイミングで贈与が可能
贈与は自分の財産を自分の意志で、他人に無償で渡す行為であり、贈与を行う際には自分が希望する相手(たとえば配偶者や子ども、その他特定の人)に対して、自分が選んだタイミングで財産を贈ることが可能です。贈与は特定の条件に縛られず、基本的には財産を持っている人の自由な判断で行えるため、財産をスムーズに譲渡する手段としてよく利用されます。
ただし、贈与を成立させるためには、単に贈与者の意志だけではなく、受贈者(贈与を受ける人)の同意も必要です。
贈与は法律上の契約行為とされており、贈与を行う側と受ける側の双方がその内容について合意することで成立します。そのため、実際に贈与を行う際には、相手がその財産を受け取ることに同意していることを確認することが非常に重要です。
特に高額な財産を贈与する場合には、贈与契約書を作成し、双方の合意内容を文書として残しておくことが望ましいとされています。これにより、贈与の条件や内容が明確になり、将来起こり得るトラブルを未然に防ぐことができます。
贈与は、自分の意志で財産を渡すことができる便利な手段ですが、その一方で、受贈者との事前の話し合いや合意形成、法的な準備が欠かせません。贈与をスムーズに行い、相手にとっても自分にとっても有益な結果を得るためには、慎重な計画と十分なコミュニケーションが必要です。
財産を確実に引き継げる
生前に不動産の名義を変更しておくことで、希望する相手に確実に不動産を譲渡できます。
特に不動産は高額な資産であり、相続時に相続人同士が所有権を巡って争う可能性もあります。もし裁判に発展した場合、最終的に不動産を譲り受ける予定だった相続人がその不動産の相続を断念することも考えられます。
しかし、生前贈与を利用して不動産を事前に譲渡しておくことで、こうした争いを避けることができます。
相続税額に影響する
控除の適用方法や、贈与時および相続時の不動産の価格など、いくつかの条件が関わりますが、生前贈与を行い、贈与税を事前に支払うことで、最終的に相続税の負担が軽減される場合があります。
家賃収入を受け取る人を変更できる
賃貸マンションやアパートなどの収益を得るための不動産を生前贈与することで、将来的にはその家賃収入も受贈者が受け取ることができるようになります。
不動産を相続するメリット
不動産を相続する際の利点について見ていきましょう。
贈与税より大きい額の基礎控除
相続には「基礎控除」が設けられており、遺産総額がこの基礎控除の範囲内であれば、相続税の支払い義務は発生しません。基礎控除の計算方法は次の通りです。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の人数)
たとえば、被相続人に配偶者と子ども2人がいる場合、「3,000万円 +(600万円 × 3人)=4,800万円」となり、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。
贈与税との比較
同じ財産総額であれば、相続税の方が贈与税よりも税額が少なくなります。その理由は、相続税には基礎控除があるためです。
贈与の場合、「暦年贈与」によって税負担を減らすことができますが、不動産(持ち分の一部)を暦年贈与する際には、その都度登記費用や司法書士への報酬がかかり、所有権移転登記費用や不動産取得税が相続税と比較して高額になります。
よって、相続は基礎控除や特例制度を利用することで、税負担を軽減できる点が大きなメリットと言えるでしょう。
不動産の生前贈与の手続きと必要書類
贈与においては、双方の「贈る」「受け取る」という意思が合致していれば、口頭での約束でも法的には成立します。しかし、財産が高額である場合、後々のトラブルを避けるために、必要な書類をきちんと整えておくことが重要です。次に、具体的な手続きの流れと必要書類について詳しく説明します。
登記事項証明書などの書類取得
贈与契約を締結する前に、必要な書類をあらかじめ揃えておくことが大切です。必要な書類は主に以下のものです。
- 登記事項証明書
- 登記済証(不動産権利書)
- 固定資産評価証明書
- 贈与者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 受贈者の住民票
登記事項証明書には、不動産の詳細情報が記載されており、贈与契約書を作成する際に必須となります。証明書の取得方法は、法務局の窓口、郵送、オンライン請求の3つの方法がありますが、オンライン請求が最も料金が安く済みます。
ただし、土地の場合は地番、建物の場合は家屋番号が必要となるため、これらが不明な場合は、固定資産税納税通知書の明細書、権利書、または法務局の窓口で確認してください。
贈与契約書の作成
不動産の名義変更を行う際には、「登記原因証明情報」を法務局に提出する必要があります。売買の場合に作成されることが多い書類ですが、贈与の場合は贈与契約書が登記原因証明情報に該当します。
贈与契約書には、贈与者と受贈者、贈与の日時、贈与される不動産の詳細を明記し、両者が署名し、印鑑を押印することが求められます。印鑑は認印でも問題ありませんが、実印を使用する方が望ましいです。
また、不動産名義変更には「所有権移転登記申請書」も必要となるため、事前に法務局の窓口や公式ウェブサイトで取得し、記載例に従って作成しておくことをおすすめします。
所有権移転登記の手続き
不動産の名義変更手続きは「所有権移転登記申請」と呼ばれ、対象となる不動産が所在する地域の法務局で行います。これまでに準備したすべての書類を、この法務局に提出する必要があります。
不動産の贈与税に関する制度
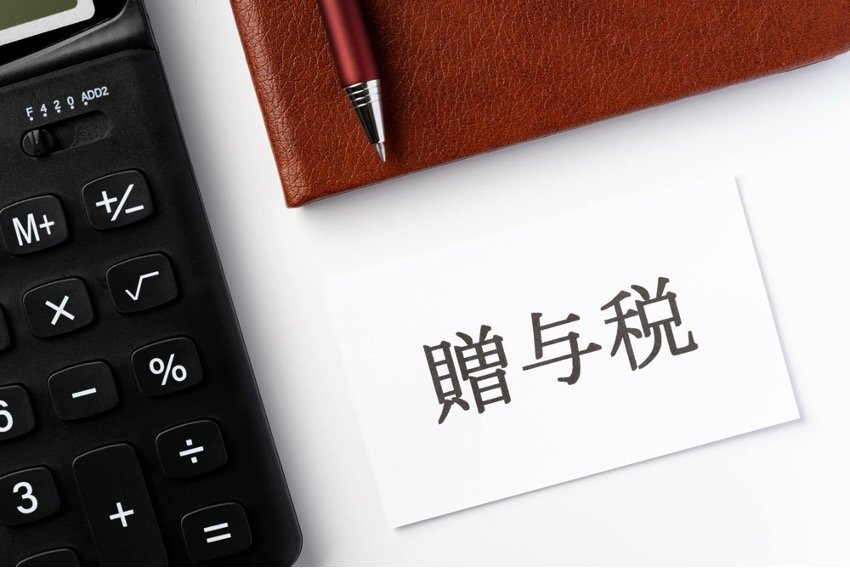
この章では贈与税に関する制度について説明します。
相続時精算課税制度
「相続時精算課税制度」とは、贈与を受ける人(子や孫)が最大2,500万円まで贈与税を免除されて贈与を受けることのできる制度です。そして、贈与者が亡くなった際には、その贈与財産の贈与時の価値と相続財産の価値を合算して相続税を計算し、一括で相続税として納税します。
さらに、2024年1月からは新たに年間110万円の基礎控除が設けられています。この基礎控除は特別控除(2,500万円)の対象には含まれず、相続が発生した際に相続財産に加算されることはありません。
暦年課税
暦年課税とは、財産を贈与された際に特別な手続きを行わなかった場合に適用される制度です。この場合、「暦年贈与」として贈与税の課税対象となります。ただし、1年間に110万円までの贈与であれば非課税となります。
配偶者控除の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産やその購入資金を贈与する場合、最大2,000万円まで贈与税が控除される制度があります。
不動産の生前贈与をおすすめできるケース
相続では不動産取得税は課税されませんが、贈与では課税されます。さらに、不動産の名義変更を行う際の登録免許税については、相続よりも贈与の方が税率が高くなる傾向があります。
そのため、相続に比べて贈与の方が高額になりやすいですが、以下のような場合には生前贈与が有利に働くことがあります。
将来的に不動産価値の上昇が見込まれる場合
相続税と贈与税は、それぞれ相続または贈与の時点での不動産(資産)の評価額に基づいて税額が決定されます。したがって、将来的に不動産の価値が上昇すると予想される場合、その前に生前贈与を行うことで、将来支払うことになる相続税よりも贈与税の方が低く抑えられる可能性があります。
不動産収入を次世代に移転させたい場合
贈与であれば被相続人の意思によって受贈者を決めることができるため、不動産収入を次世代に移転させたい場合にも有効です。
賃貸マンションなどの不動産物件
特に家賃収入が得られる賃貸マンションなどの投資用不動産の場合、被相続人がその家賃収入を得ることで、保有する資産が増加します。よって、相続時に課税対象となる資産が増え、最終的に支払うべき相続税が増額することがあります。
そのため、生前に不動産を贈与しておくことで、贈与を受けた人がその家賃収入を受け取ることができ、相続時の税負担を軽減できます。
結婚20年以上の夫婦
婚姻期間が20年以上の夫婦は、前述したように「配偶者控除の特例」を利用できます。この特例を活用することで、自己の住居に関して最大2,000万円まで贈与税が控除されます。また、年間110万円の基礎控除も適用されるため、合計で2,110万円まで贈与税がかからないことになります。
将来的に相続人間で遺産を巡る争いが予想される場合
生前贈与では、財産を譲渡する相手や内容を自由に決めることができるため、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。
また、急な病気や事故によって予期せぬタイミングで相続が発生し、自分が望む相手に財産を譲れなくなる事態を回避することもできます。
相続人間の争いを防ぎ、自分が希望する相手に確実に財産を譲るために、生前贈与を検討してみることをおすすめします。
認知症などによる判断能力の低下に備える場合
判断能力が衰えてしまうと、不動産を売却する必要が生じた際に、その手続きが難しくなる恐れがあります。そのため、早期に生前贈与を考えることが重要です。
例えば、親が介護を必要とし、親の所有する不動産を売却して老人ホームの入居費用にあてようとした場合、親の判断力が低下していると不動産の売却が難しくなってしまいます。また、建物がある場合は、空き家問題が発生する可能性もあります。
不動産の売却が将来問題になることを避けるためにも、生前贈与を検討することをおすすめします。
土地を相続する方が有利な場合
土地を相続で承継することを検討するべきケースは、以下のような場合です。
- 相続財産の評価額が基礎控除額に達していない場合
- 小規模宅地等の特例を活用したい場合
- 土地の相続先を指定したい場合
相続財産の評価額が基礎控除以下の場合
相続税の課税対象となる財産の価値が、基礎控除額(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数)を超えていない場合、相続税が発生しないため、相続による承継が適切な可能性が高いです。
生前贈与で特例や制度を活用しない場合、基本的に年間(1月1日~12月31日)の贈与額が110万円を超えると贈与税が課せられます。
事前に相続税の課税対象となる遺産額を確認し、相続と生前贈与のどちらが有利かを検討することが重要です。
小規模宅地等の特例を活用したい場合
小規模宅地等の特例を利用したい場合は、相続による承継を選ぶことをおすすめします。生前贈与を行うと、小規模宅地等の特例が適用できなくなる場合があるためです。
例えば、被相続人が居住していた土地や事業用の土地を相続する場合、要件を満たせばその土地の評価額を最大80%まで減額することができます。これにより、相続税の節税が可能になります。
しかし、生前贈与を行った場合、小規模宅地等の特例が適用できなくなる可能性があるため注意が必要です。これは、宅地の種類や取得者によって適用要件が異なるためです。
小規模宅地等の特例が適用されるためには、取得者が以下のいずれかに該当する必要があります。
- 被相続人の配偶者が自宅の土地を相続する場合
- 被相続人と同居していた親族が土地を相続する場合
- 被相続人に配偶者や同居の親族がいない場合、3年以上賃貸住宅に住んでいた相続人が土地を相続する場合
例えば、配偶者や同居の親族がいない人が、借家住まいの相続人に土地と建物を生前贈与したとします。その後相続が発生した場合、相続人は土地と建物を所有しているため、「3年以上賃貸住宅に住んでいた相続人」の要件を満たさず、小規模宅地等の特例が使えなくなります。
小規模宅地等の特例を利用したい場合は、適用要件を事前に確認し、特例の対象外にならないように注意することが重要です。
土地を特定の相手に譲りたい場合
健康なうちは自分で土地の管理をしたいなどといった理由で、生前贈与を避けたく、最終的には特定の人物に土地を譲りたい場合、遺言書か死因贈与契約書(贈与者が死亡した時点で、受贈者に財産の所有権が移転する「死因贈与」の契約を締結するための書類)を作成する方法があります。
相続では故人の意思が優先され、通常は遺言書に書かれた通りに遺産が分配されます。もし土地を特定の人物に譲りたいと考えている場合、その人を遺言書で指定するのがよいでしょう。
遺言書には「自筆証書遺言」や公証人によって作成される「公正証書遺言」などの種類があります。遺言書には法的な要件があり、これを満たしていない場合は効力が失われます。
また、自筆証書遺言は自分で書くので、形式に不備があれば無効になってしまうリスクがあります。
一方で、公正証書遺言は公証人が作成をサポートするため、無効になる可能性が低く、紛失や偽造のリスクも少なくなります。遺言書が無効になるリスクを避けたいのであれば、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
生前贈与を行う際に注意すべき点
生前贈与を行うのであれば、親族間での不和を避けるために慎重に進めることが大切です。以下に、生前贈与を行う際の注意点を紹介します。
受贈者以外にも納得してもらえる贈与にすること
受贈者以外の親族にも、できるだけ理解してもらえるような贈与にすることが重要です。贈与の理由や相続に関する考え方を受贈者以外の親族にも事前に伝えておくことが望ましいです。
遺留分に配慮する
遺留分とは、法定相続人に法律で保証された最低限の相続分のことを指し、相続時に遺留分を主張できるのは、被相続人の配偶者や子ども、子どもが亡くなっている場合はその代わりに相続する孫などの代襲相続人、または父母などの直系尊属です。特定の相続人に対して多額の贈与を行った場合、その贈与が遺留分を侵害しているとみなされ、遺留分侵害額請求がされることがあります。
生前贈与を行う際には、相続人の遺留分にも配慮する必要があります。遺留分を計算する際の基準となる財産には、相続発生時の財産のほか以下を含みます。
- 相続開始前1年以内に行われた相続人以外への贈与
- 上記以外の遺留分を侵害すると知りながら行った贈与
- 相続開始前10年以内に行われた相続人への贈与(条件を満たした場合)
相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象に
相続人などが被相続人から相続の開始前に贈与された財産については、贈与が行われた時期に応じて、以下のように生前贈与加算として相続税の課税対象になります。この場合、110万円の基礎控除の範囲内の贈与であっても加算される対象となるため、相続税対策として生前贈与を行っても、その効果が失われてしまうことになります。ただし、生前贈与に対して贈与税をすでに支払っている場合、その税額は相続税から控除されます。
【2023年12月31日までの贈与】 相続開始前3年以内に行われた贈与は、たとえ110万円の非課税枠内であっても相続税の課税対象となり、相続税の計算に加算されます。
【2024年1月1日以降の贈与】 相続開始前7年以内に行われた贈与も同様に、110万円の非課税枠内であっても相続税の計算時に課税価格に加算されます。ただし、相続開始前3年以内に取得した財産以外の場合、その価額から100万円を差し引いた額が加算対象となります。
ただし、経過措置が設けられており、2030年末までに相続が発生する場合は、2024年1月1日以降の贈与が相続税の課税対象となります。相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象となるのは、2031年1月1日以降に相続が発生した場合です。
なお、以下の贈与については、相続開始前であっても相続財産に加算されません。
- 相続などにより財産を取得しない人(例:相続人でない孫や子の配偶者など)への贈与
- 夫婦間で居住用不動産を贈与し、配偶者控除が適用された贈与
- 祖父母などから教育資金として一括贈与を受け、一定の要件を満たす管理残額
特別受益として相続財産に持ち戻されることがある
相続人の中に被相続人から生前贈与などの特別な利益を受けた者がいる場合、相続における不公平を是正するため、その利益を「特別受益」として相続財産に戻す制度があります。
相続分を算定する際、相続発生時における各相続人の持っていた財産の評価額に、特別受益にあたる贈与額を加算します。特別受益を受けた相続人は、その金額を考慮した相続分から、実際に受けた特別受益額を差し引いた分だけを相続します。
生前贈与が特別受益として相続財産に戻されるのは、婚姻、養子縁組、生計の資本として受けた贈与が該当します。具体的には、結婚や養子縁組時に贈与された持参金や開業資金、住宅購入資金などが対象となり、一般的な扶養に関連する贈与は含まれません。
なお、被相続人が特別受益の持ち戻しを免除する意思を示した場合、その贈与は持ち戻しの対象外となります(ただし、遺留分の制約は適用されます)。また、婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与については、持ち戻しの対象にはなりません。
まとめ
土地を生前贈与することで、将来的な相続税を軽減できる可能性があるだけでなく、相続に伴うトラブルを未然に防いだり、認知症対策として活用したりすることも可能です。
しかし、贈与と相続のどちらが有利かは状況によって異なるため、税金面でのシミュレーションを十分に行うことと、経済的合理性だけに目を奪われて、後々に家族で揉めないように配慮することが重要です。
不明点があれば、専門家に相談することをおすすめします。
監修者
- 相澤 光Aizawa Hikaru
- コンサルティング事業本部 コンサルティングサービス室 室長 兼 第四事業部 ダイレクトグループ グループ長
不動産や法人を活用した財産防衛策の立案・実行に従事し、財産と想いを次世代に承継するための支援を提供。最適な選択肢を見つけられるよう、中立的な立場で家族全体の意向調整もサポートすることを信条とする。
当社の30年にわたるナレッジを集約した書籍を発行し、セミナー登壇実績も多数。
趣味:学び(税理士資格の勉強中)、ギター、サウナ
- 専門分野
- 土地持ち資産家、金融資産家向けコンサルティング
- 資格
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
- 著書
- 「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策