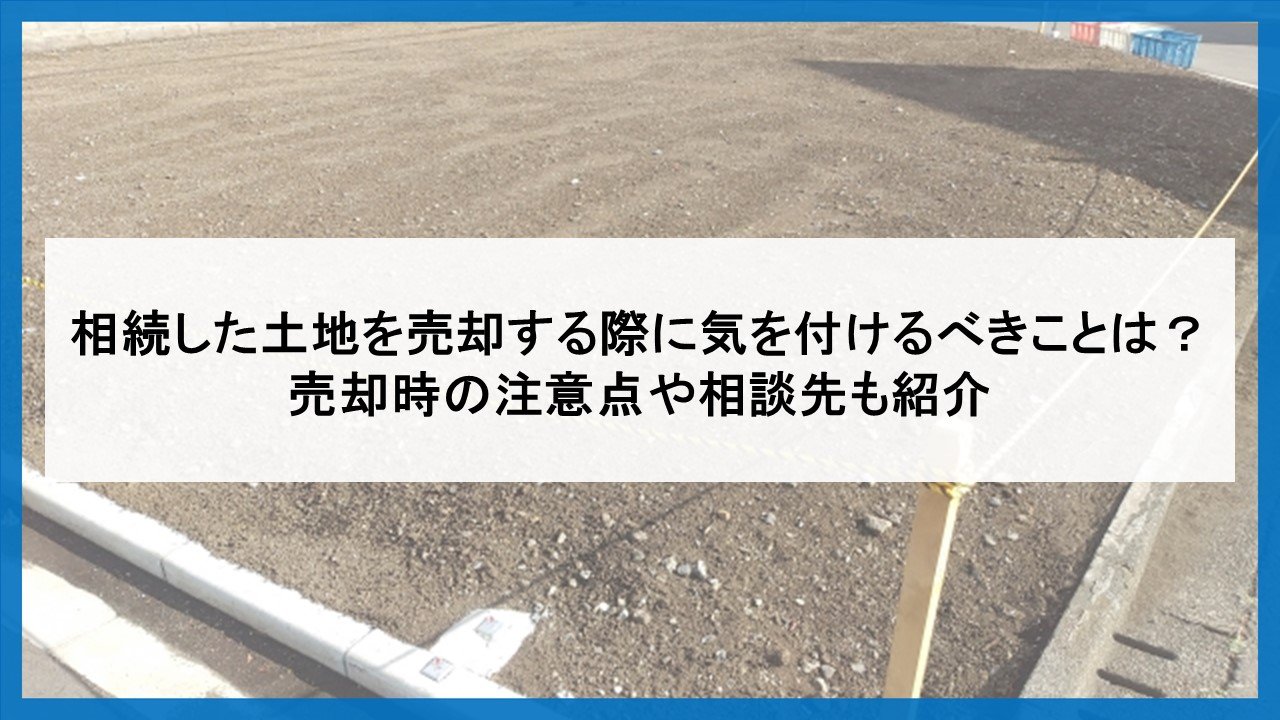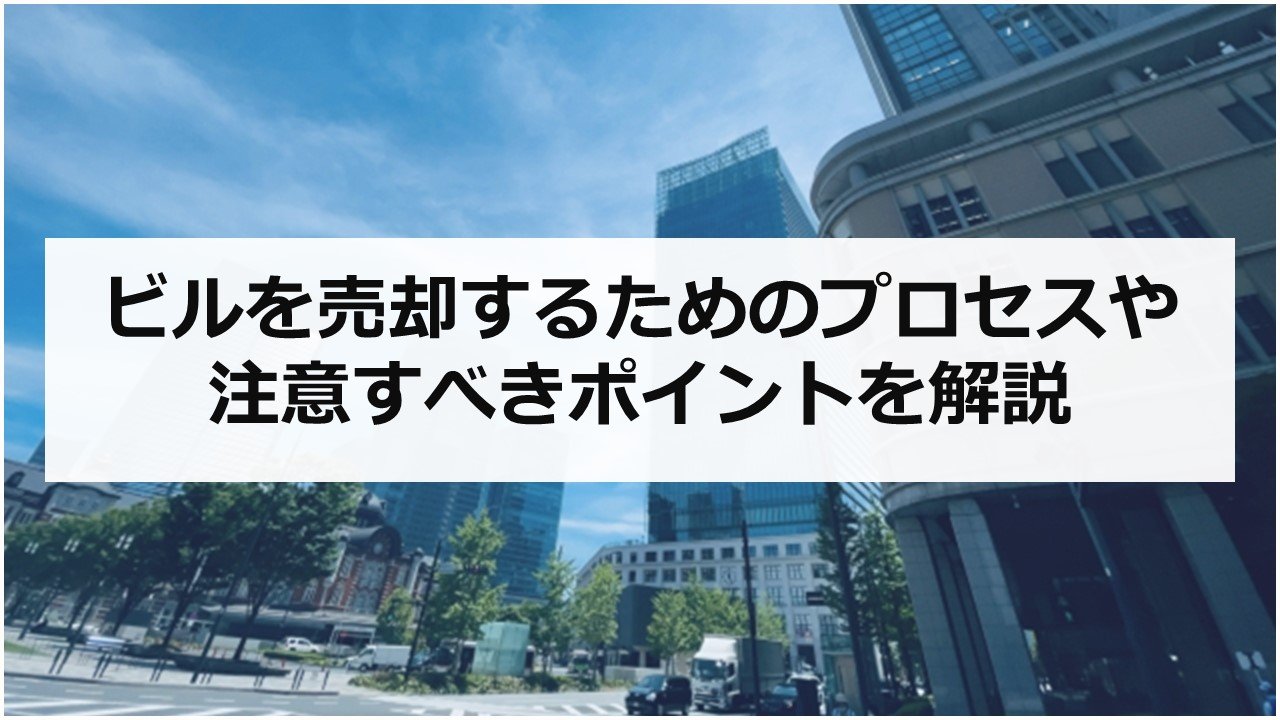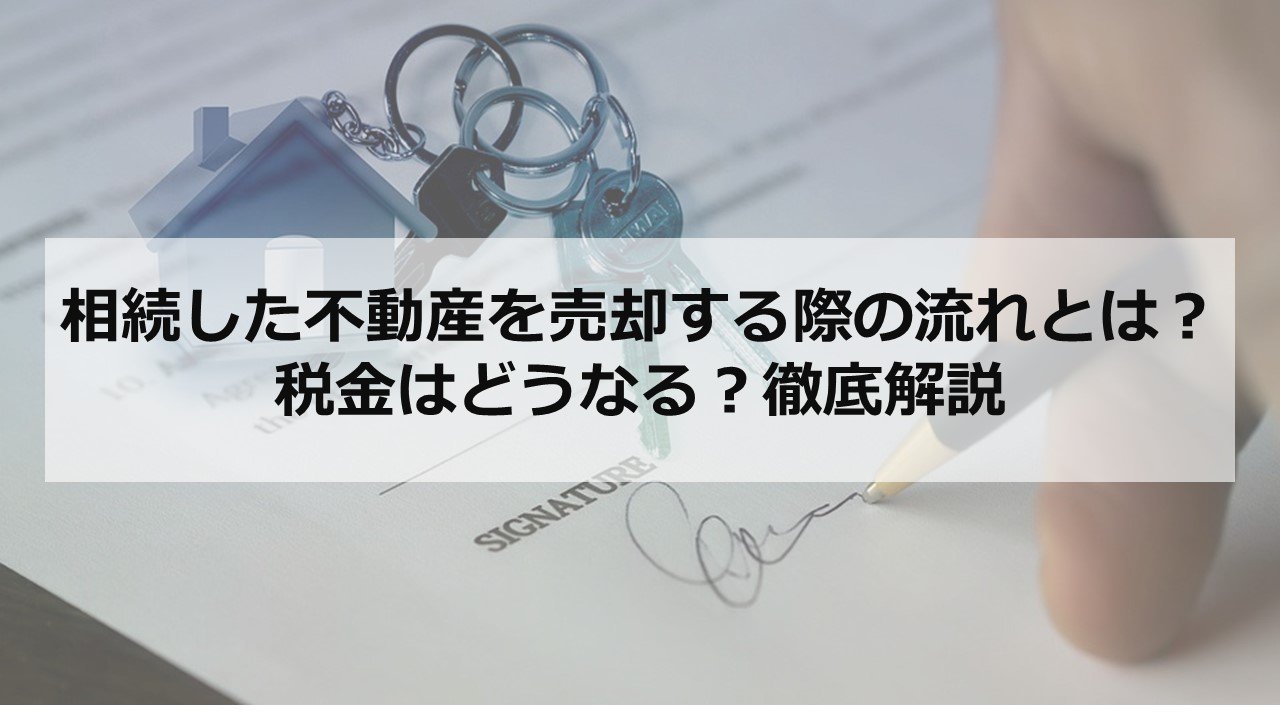戸建て住宅や土地などの相続した不動産を売却するためには、不動産の分割や名義変更が必要となります。
また、居住用財産の売却とは利用できる税金の特例が異なり、期限や要件を意識して売却することも必要です。
不動産の相続を受ける機会は、生涯のうちでそうあることではありません。売却をどのように進めたらいいか分からない方がほとんどではないでしょうか。
本記事では、相続した不動産の売却に悩んでいる方のために、下記を詳しく解説します。
- 相続した不動産を売却するときの流れ
- 相続した不動産を売却するための必要書類
- 相続した不動産売却で利用できる特別控除
- 相続した不動産を売却するときに注意すべきポイント
相続した不動産の売却にお悩みの方はぜひ参考にしてください。
相続した不動産を売却する7ステップ
相続した不動産を売却するまでの手続きは以下の7ステップの順に行われます。
- 1.名義変更
- 2.価格査定
- 3.媒介契約
- 4.売却活動のスタート
- 5.売買契約の締結
- 6.決済・代金の受け取り
- 7.確定申告
順に見ていきましょう。
1.名義変更 法務局へ所有権移転登記を申請することを名義変更といいます。また、名義人が死亡した場合、名義人(被相続人)から相続人へ名義変更することを相続登記といいます。民法改正により、2024年から相続登記は手続きが義務化されています。
2.価格査定 不動産査定価格の算出方法には、簡易査定(机上査定)と訪問査定の2つがあります。価格査定は、複数の不動産会社に依頼することをおすすめします。
なぜなら、査定金額は不動産会社が独自に見積もった価格であるため、査定する不動産会社によって査定金額が異なるからです。
3.媒介契約 不動産会社と媒介契約を締結します。媒介契約とは、不動産会社に不動産の買主を探してもらうために、売主と不動産会社が結ぶ契約です。
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
4.売却活動がスタート 媒介契約が締結されると、不動産会社は広告や現地案内などの営業活動を始めます。
5.売買契約の締結 売買契約締結の際に、買主は売主に手付金を支払います。手付金は残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当されます。
6.決済・代金の受け取り 不動産の引き渡しと代金の受け取りは、所有権移転登記申請と併せて行われます。
所有権移転登記申請手続きは売主と買主が共同で進める必要があります。一般的に、買主が司法書士に依頼して代理で行ってもらうことが多いです。
7.確定申告
相続した不動産を売却した際には、譲渡所得の申告が必要になります。
相続した不動産売却に必要な書類
相続不動産の売却に必要な主な書類は、下記のとおりです。
- 登記簿謄本または登記事項証明書
- 売買契約書
- 物件購入時の重要事項説明書
- 登記済権利書または登記識別情報
- 土地測量図・境界確認書
- 固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
- 物件の図面
- 設備の仕様書
- 建築確認済証および検査済証
- マンションの管理規約または使用細則(マンション売却の場合)
- マンション維持費関連書類(マンション売却の場合)
相続不動産に活用できる4つの特例【譲渡所得控除・相続税軽減】

相続した不動産の売却により利用できる主な特別控除は次の4つです。
- 居住用財産3,000万円の特別控除
- 相続空き家の3,000万円の特別控除
- 取得費加算の特例
- 小規模宅地等の特例
それぞれ解説していきます。
居住用財産3,000万円の特別控除
居住用財産の譲渡に関する特例とは、自ら居住していた不動産を売却した場合に適用される税制上の優遇措置です。この特例では、一定の条件を満たす居住用財産の売却について、居住用財産を売却して得られた譲渡所得が3,000万円まで非課税となります。このため、譲渡所得が3,000万円以下であれば、税金はかかりません。
譲渡所得とは不動産の売却による所得であり、下記の計算式で求められます。
譲渡所得 = 成約価格 -(取得費 + 譲渡費用)
控除を受けるための要件
3,000万円特別控除の適用要件は5つあります。本特例適用の前提条件は、売却する物件がマイホームであることです。この前提条件をクリアした上で、適用要件は以下のとおりです。控除を受けるには、これら5つの項目をすべて満たしている必要があります。
[ 1 ] 下記のいずれかを満たすマイホームであること
a. 現在自分が住んでいる家
b. 以前住んでいた家(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限る。)
c. 上記aまたはbに当てはまる家を取り壊した場合、その土地の売却契約締結が取り壊しから1年以内かつ、その間賃貸していない
d.災害によって売却する場合、災害があった日もしくは住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売ること
[ 2 ] 売った年の前年および前々年に3,000万円の特別控除(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」により適用を受けている場合を除く)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと
[ 3 ] 売った年、その前年および前々年に、マイホームの買い換えや交換の特例の適用を受けていないこと
[ 4 ] 売却した不動産について、収用等の特別控除などほかの特例の適用を受けていないこと
[ 5 ] 物件の買主が親族や夫婦など、「特別の関係がある人」でないこと
参考:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
相続の場合
自分が相続人となった空き家の場合、もともと不動産の所有者が居住していた家屋であることが条件です。
確定申告期間と必要書類
- 確定申告期間
3,000万円の特別控除を受けるには、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行う必要があります。例えば、2025年に売却したのであれば、2026年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行わなければなりません。
申告する際には、いくつかの必要書類を提出します。ここで注意したいのは、譲渡所得が3,000万円以下の場合の申請です。この場合、3,000万円の特別控除が適用されると譲渡所得はゼロになるため税金もゼロになりますが、確定申告はしなければなりません。確定申告しなければ、3,000万円の特別控除も適用されなくなります。
- 必要書類
3,000万円の特別控除を適用する際の主な必要書類は下記のとおりです。
- 確定申告書・譲渡所得の内訳書
- 戸籍の附票
- 譲渡した土地・建物の全部事項証明書
- 売却時の書類の写し
- 取得時の書類の写し
- 住民票の写しあるいはマイナンバー
※税務署から別途提示提出を求められる可能性があるため、多めに必要書類を掲載しております。
個々のケースにより必要書類が変わる可能性があるため、期限に余裕をもち、税務署や税理士などに必要書類を確認しましょう。
相続空き家の3,000万円の特別控除
相続または遺贈により取得した被相続人が居住していた家屋または被相続人が居住していた家屋の敷地などを、2016年4月1日から2027年12月31日までに売却し、一定の要件を満たすときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できます。
一人暮らしだった被相続人が亡くなってから3年を経過した日の属する年の12月31日までに、相続によって取得した空き家を売却したときは、その空き家の売却利益から最大3,000万円の控除が可能となります。ただし、2024年1月1日以降の譲渡から、相続により家屋や土地を取得した人が3人以上であれば、特別控除は2,000万円です。
要件①一人暮らしでなければならない
本特例の目的は空き家をなくすことなので、被相続人の死亡時に一人暮らしであった場合に限定されます。
要件②1981年以前に建てられた建物に限定
本特例が適用される不動産は、被相続人が居住していた「1981年5月31日以前に建てられた建物とその敷地」に限定されます。
マンションなどの区分所有建築物は除外され、建物を壊して敷地だけを売却するか、建物については耐震基準をクリアするように耐震リフォームをした上で売却する必要があります。なお、耐震基準をクリアしている建物であれば、そのまま売却しても特例が適用可能です。
ちなみに2024年1月1日以後は、売却してから一定の期限までに買主が除却工事や耐震リフォームした場合であっても、特例の適用が可能になりました。
要件③相続から売却まで空き家の状態であること
相続した後で、その建物や建物を取り壊した後の土地を事業の用、貸付けの用または居住の用に供した場合には、本特例は適用できません。相続から売却までは引き続き空き家の状態である必要があります。
「相続開始から譲渡まで空き家であったこと等」については、売買契約書の写しや電気またはガスの閉栓証明書、水道の使用廃止届出書、使用状況が分かる写真などを添付し、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を建物を管轄する市区町村に提出し、「被相続人居住用家屋等確認書」を交付してもらい、確定申告書に添付する必要があります。
*老人ホーム等へ入居していたケースも適用対象
被相続人が老人ホーム等に入居していたときでも、下記の要件を満たせば、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例の適用が可能となります。
①被相続人が「老人ホーム等」に入った時点で、介護保険法に定められた要介護等に認定され、かつ相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと。
②被相続人が老人ホーム等に入所してから相続の開始の直前まで、その家屋について、「一定の使用」がなされ、かつ事業の用、貸付けの用またはその者以外の者の居住の用に供されていなかったこと。
本特例での「老人ホーム等」とは下記の住居を指します。
- グループホーム
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 有料老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- サービス付き高齢者向け住宅
- 障害者支援施設
- 障害者共同生活援助を行う住居
本特例での「一定の使用」とは、被相続人が居住していた家屋が被相続人が居住しなくなったときから相続の開始直前まで、引き続きその被相続人居住用家屋がその被相続人の物品の保管やそのほかの用に供されていたことをいいます。
実務においては、下記のいずれかの書類による確認も必要となります。
- 1.電気・水道・ガスの契約者と使用を中止した日を確認できる書類
- 2.入居者の外出、外泊等の記録(老人ホーム等が保有しています)
- 3.市区町村による認定者が家屋を管理していたことの証明書
- 4.不動産所得がなかったことを確認できる地方税の所得証明書など
*2024年1月1日以後の売却から買主が耐震リフォームなどを行っても適用対象
2024年1月1日以後の売却から、売買契約などに基づいて、買主が売却した日の属する年の翌年2月15日までに耐震リフォームまたは除却工事をしたとき、工事が売却の後でなされても本特例の適用対象となります。
本特例の適用要件を一覧表にまとめましたのでご覧ください。
| 被相続人居住用家屋 | ・相続開始の直前において被相続人の居住用家屋であったこと (老人ホーム等へ入所していても一定の要件を満たせば場合は適用可能) ・相続開始の直前において被相続人以外に居住者が存在しなかったこと ・家屋が1981年5月31日以前に建てられていること(マンションなどの区分所有建築物は除外) |
| 土地等 | 相続開始の直前において「被相続人居住用家屋」の敷地の用に供されていたこと |
| 対象者 | 相続したために「被相続人居住用家屋」と敷地の用に供されていた土地等を取得した個人(法人は本特例の適用不可) |
| 適用期間 | 2016年4月1日から2027年12月31日まで |
| 譲渡期限 | 相続したときから相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
| 譲渡対象限度額 | 譲渡対価の額が1億円超のときは本特例の適用不可。2回以上に分けて売却したケースでは合計して1億円を超えたか否かで判定されます。共有者がいるケースでは合計金額で判定されます。 |
取得費加算の特例
相続した不動産を売却したとき、相続税の額を取得費に加算することにより、譲渡所得を減らして譲渡所得税を減額できます。
譲渡所得税は、不動産売却により発生した譲渡所得にかかる税金です。
取得費加算の特例とは、相続が開始された日から3年10カ月以内に相続財産を売却した場合、相続税額の一部を取得費に加算することにより、譲渡所得税の負担を軽減することができる特例です。
譲渡所得は下記の計算式で求めます。
譲渡所得 = 収入金額 -(取得費 + 譲渡費用 - 特別控除)
取得費に相続税の一部を加算することで収入金額から引かれる金額が増えるため、所得税の負担が軽減されます。
取得費加算の特例の適用要件
取得費加算の特例には3つの適用要件があります。
- 相続、遺贈により財産を取得した人であること
- その財産を取得した人が相続税を納めていること
- その財産を相続開始日から3年10カ月以内に譲渡していること
取得費加算の特例を利用するときの3つの注意点
取得費加算の特例が適用されるためには注意すべきポイントが3つあります。
- 遺産分割協議を早めに完了させる
- 取得費加算の特例の期限である相続開始日の翌日から3年10カ月以内に終わらせる
- 代償分割は特例の効果が減少する
遺産分割協議を早めに完了させる
相続財産の分割が確定していないと、取得費加算の特例を適用できません。遺産分割協議が長引くと、売却のタイミングを逃してしまう可能性があるため、早めに協議を進めることが重要です。
取得費加算の特例の期限である相続開始日の翌日から3年10カ月以内に終わらせる
取得費加算の特例は、相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に売却した場合に適用されます。この期限を過ぎると特例の適用ができなくなるため、売却のタイミングには注意が必要です
代償分割は特例の効果が減少する
代償分割とは、特定の相続人に遺産を取得させるために、ほかの相続人に金銭(代償金)を払うことです。代償金の支払いにより得られた不動産を売却するケースでは、取得費に加算できる相続税額の算出方法は通常とは異なります。
通常のケースと比較して加算額が少なくなるため、取得費加算の特例による効果にはあまり期待できません
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、一定要件を満たした場合に宅地の評価額を最大80%減額できるという特例です
評価額1,000万円の土地であれば、200万円まで評価額を下げられます。
土地の評価額が下がれば、相続税も下がります。
小規模宅地等の特例は、80%を限度として評価額を抑え、相続税の負担を軽くすることにより、配偶者や子などの遺族が相続した不動産に引き続き住めるように作られた制度です。
「小規模宅地等」の種類、面積、減額割合
なお、小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は大きく分けて、次の4つに分けられます。
特定居住用宅地等
死亡した人の自宅として使用していた宅地等に対する特例
特定事業用宅地等
死亡した人が個人事業(貸付用を除く)として使っていた宅地等に対する特例
貸付事業用宅地等
死亡した人が貸付用(貸地または貸家など)としていた宅地等に対する特例
特定同族会社事業用宅地等
死亡した人の会社(同族会社)として使っていた宅地等に対する特例
本章では、死亡した人が自宅として使っていた宅地等を対象とする「特定居住用宅地等」について解説していきます。
小規模宅地等の特例の適用要件
特定居住用宅地等とは、死亡した人が自宅として使っていた宅地等に適用される特例です。相続または遺贈により宅地等を取得した親族は、一定の要件を満たせば、その宅地等のうち330㎡までの部分について評価額を80%下げることができます。
- 配偶者
被相続人の配偶者は、制約なしで特例が適用されます。
- 同居親族
同居親族とは、相続発生時(死亡時)に被相続人と同居していた親族です。同居とは、生活の拠点が同じであることを指します。仮に住民票が一緒であっても、同居の実態がなければ本特例は適用されません。
なお同居の期間について縛りはありません。ただし、相続税の申告期限である相続が開始されてから10カ月経つまで、当該宅地等を所有して当該建物に居住することが要件です。したがって、子が親の死亡する前に同居しただけで、その後で自分の家に戻ってしまったケースでは、特例の適用は認められません
- 同居親族以外(家なき子)
同居親族以外の親族が小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、次の要件をクリアする必要があります
・被相続人に配偶者や同居相続人がいないこと
・相続開始前3年以内において、宅地等を相続した親族が、その親族やその親族の配偶者、3親等内の親族、同族会社等が所有する家屋(相続開始直前に被相続人が住んでいた家屋を除く)に居住したことがないこと
・相続時にその親族が住んでいる家屋を過去に所有していないこと
・申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること
小規模宅地等の特例を受ける際の注意点
- 小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税申告が必要
小規模宅地等の特例を受けるためにもっとも注意すべきことは、相続税の申告書の提出が小規模宅地等の特例適用の前提条件であるということです。
相続税の申告書は、被相続人の財産額が基礎控除を超える場合に提出する必要が出ます。ただし、小規模宅地等の特例の優遇措置を受ける場合は、小規模宅地等の特例を受ける前の財産額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるか否かで判断されます。
例えば、死亡した人が、評価額4,000万円の自宅(面積300㎡)とそのほかの財産1,000万円を子ども2人が相続するとします。この場合、基礎控除額は4,200万円となります。
このケースでは、自宅に小規模宅地等の特例を受けると、自宅の評価額が4,000万円から800万円になるため、被相続人の財産額は基礎控除(4,200万円)以下になります。しかし、小規模宅地等の特例を適用する前が基礎控除を超えているため、相続税の申告書の提出は必要になります。一方、自宅の評価額を含めた財産額が基礎控除額を下回る場合は相続税がかからないため、特例を適用する必要はありません。
- 相続税の申告期限前に売却すると、特例は適用されない
相続税の申告期限までに小規模宅地等の対象となる宅地等を保有することが適用要件となっているため、相続税の申告期限に売却すると特例は適用されません。ただし、無条件で特例の適用を受けられる配偶者は、相続税申告期限前であっても対象の不動産を売却することができます。
- 相続時精算課税による贈与により取得した宅地等は適用の対象外
相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等に、小規模宅地等の特例は適用されません。
相続時精算課税制度とは、一定要件を満たした贈与者と受贈者間の2,500万円までの贈与は非課税とし、相続が発生したときに相続財産として合計する制度です。2024年1月からは、2,500万円の控除とは別に、年間110万円以下の贈与であれば非課税となる基礎控除が新しく制度化されました。ただし、相続時精算課税制度を選択すると、撤回ができなくなります。
小規模宅地等の特例を受ける際の必要書類
- 共通する添付書類
以下の書類は、共通で必要となります。
被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍の謄本または図形式の法定相続情報一覧図の写し
遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合)
- 同居の有無などに応じて必要なその他添付書類
・被相続人と同居している場合
→特例の適用を受ける宅地等に自己が住んでいることを証明できる書類(特例を適用される人がマイナンバーを持っている場合は提出不要)
・被相続人と同居していない場合
→相続開始前3年以内の住所等が分かる書類(特例を適用される人がマイナンバーを持っている場合は提出不要)
→相続開始前3年以内に住んでいた家屋が、自己や自己の配偶者、3親等以内の親族もしくは同族会社等が所有する家屋でないことを証明できる書類
→相続時に自己が居住している家屋を、相続開始前に所有していないことを証明できる書類
・被相続人が養護老人ホーム等に入所していた場合
- 被相続人の戸籍の附票の写し
- 介護保険の被保険者証の写しなど、被相続人が要介護認定や要支援認定、障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
- 施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前に入所していた住居または施設の名称や所在地、その住居または施設が一定の老人ホームに該当することが分かる書類
相続不動産売却時に注意すべき税金と落とし穴
相続不動産を売却する際に注意すべき主なポイントは次のとおりです。
一つずつ見ていきましょう。
- 高値で売却できる不動産会社に依頼する
- 共有不動産の売却には所有者全員の同意が必要
- 単独登記による売却は贈与にならないようにする
- 売却期限の目安は3年
- 取得費は親の購入額を引き継ぐ
- 所有期間は親の購入日を引き継ぐ
- 取得費が分からないときは代替資料を探す
高値で売却できる不動産会社に依頼する
相続不動産を可能な限り高値で売却するために、複数の不動産会社で見積もりを取りましょう。
ただし、実際の売却価格よりも多く見積もって提示してくることも少なくないため、不動産会社の実績や評判などを確認しておくのがおすすめです。
共有不動産の売却には所有者全員の同意が必要
共有名義の不動産を売却するためには、共有者全員の同意が必要です。
共有者全員の同意でポイントとなるのは、売却することの同意と売却価格の同意です。
売却することに全員の同意が取れたら、価格についての同意が必要となります。
価格の同意を得るには、共有者全員で最低売却価格を決めておくことが必要です。
最低売却価格とは、「いくら以上であれば売却する」「いくら以下なら売却しない」という売却価格の最低ラインです。
単独登記による売却は贈与にならないようにする
不動産を売却して現金で分割する換価分割には、共同登記と単独登記の2種類があります。
単独登記とは、まず特定の相続人が不動産を単独で所有し、売却した後、売却代金をほかの相続人に分配する方法です。
単独登記では、単独所有物件の売却となるため、所有者本人だけで売却手続きを進められます。
相続人が遠方に散らばっていて集まることが難しい場合には、単独登記型が適しています。
ただし、何も対策をせずに単独登記タイプで売却すると、所有者が受け取った現金をほかの相続人に分配する行為が税務署に贈与と見なされるリスクがあります。
そこで、単独登記での現金の分配が贈与と見なされないようにするためには、遺産分割協議書に換価分割目的で遺産を取得することを明記しておくことが必要です。
売却期限の目安は3年
相続した不動産の売却期限は3年以内が目安となるという点が注意点です。
なぜなら、相続不動産で利用できる2つの特例(取得費加算の特例、相続空き家の3,000万円特別控除)の期限は3年を目安としているからです。
取得費は親(被相続人)の購入額を引き継ぐ
相続不動産の取得費は親(被相続人)の購入額を引き継ぎます。
個人が不動産を売却した際には、譲渡所得を計算します。
譲渡所得とは、以下の計算式で求められる売却益です。
譲渡所得 = 譲渡価額(売却価額)- 取得費 - 譲渡費用(例:仲介手数料や印紙税など)
取得費とは、親(被相続人)が購入した不動産の額です。
土地については購入額を取得費として、建物については購入額から減価償却費を差し引いた価額を取得費とします。
取得費 = 土地取得費 + 建物取得費
= 土地購入額 +(建物購入額 - 減価償却費)
所有期間は親(被相続人)の購入日を引き継ぐ
相続不動産の所有期間は親(被相続人)の購入日を引き継ぐというのが注意点です。
譲渡所得が発生すると、譲渡所得税は下記の計算式で算出します。
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
税率は、所有期間によって異なります。
売却する年の1月1日時点において所有期間が5年超のときは「長期譲渡所得」、1月1日時点において所有期間が5年以下のときは「短期譲渡所得」と呼ばれます。
取得費が分からないときは代替資料を探す
取得費が不明の場合は代替資料を探しましょう。
取得費が不明な場合には、概算取得費を用います。
概算取得費とは「譲渡価額の5%」です。
しかし、概算取得費を用いてしまうと取得費が小さくなるため、譲渡所得が大きく計算されてしまいます。
すなわち、概算取得費を用いると、税金が高くなってしまうのです。
そこで、取得費が不明な相続不動産の売却をする際には、取得費を証明できる代替資料を探すようにしましょう。
取得費の代替資料とは、主に以下のようなものが挙げられます。
- 新築物件の場合、購入当時の売買契約書の写し
- 通帳の出金履歴から購入額を推測する
- 住宅ローンの金銭消費貸借契約書から購入額を推測する
- 抵当権設定額から購入額を推測する
- 一般財団法人日本不動産研究所が公表している市街地価格指数から土地の取得費を算定する
- 一般財団法人建設物価調査会が公表している着工建築物構造別単価から建物の取得費を算定する
まとめ
本記事では相続した不動産を売却するときの流れや売却するための必要書類、売却するときに注意すべきポイントなどを解説しました。
相続した不動産の売却の手続きは専門知識が必要であり、時限性もあるため、できるだけ早い段階で専門家青山財産ネットワークスにご相談ください。
- 相澤 光Aizawa Hikaru
- コンサルティング事業本部 コンサルティングサービス室 室長 兼 第四事業部 ダイレクトグループ グループ長
資産家の方々が抱える「資産を守り、次世代へつなぐ」という課題に向き合い、不動産や法人を活用した円滑な財産の承継・運用・管理をサポートしてきました。
私が何より大切にしているのは、「まずお話をじっくり伺うこと」。資産の規模や構成だけでなく、ご家族の想いや背景を丁寧に理解したうえで、収益性の向上や財産分割などを一緒に考えていきます。なぜなら、家族の数だけ“正解”があると考えているからです。
「〇〇が気になっている」「何から手をつければいいかわからない」といったご相談を多くいただきますが、「専門家に任せる」のではなく、「一緒に進めていく」スタイルを大切にしながら、これまで多くのご家族の資産承継に伴走してきました。
- 専門分野
- 土地持ち資産家、金融資産家向けコンサルティング
- 資格
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
- 著書
- 『「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策』
(青山財産ネットワークス刊)
資産承継における実務と心情の両面に寄り添った内容が評価され、2021年11月には紀伊國屋書店新宿本店のビジネス書ランキングで第1位を獲得しました。