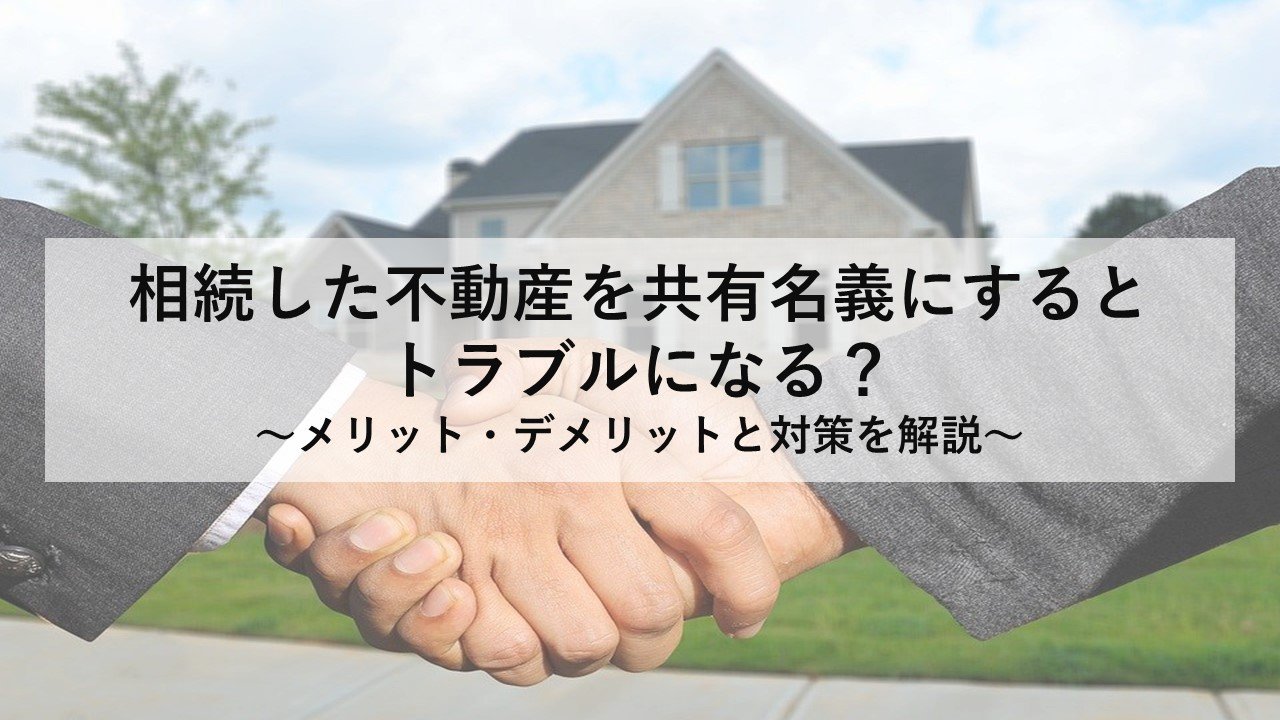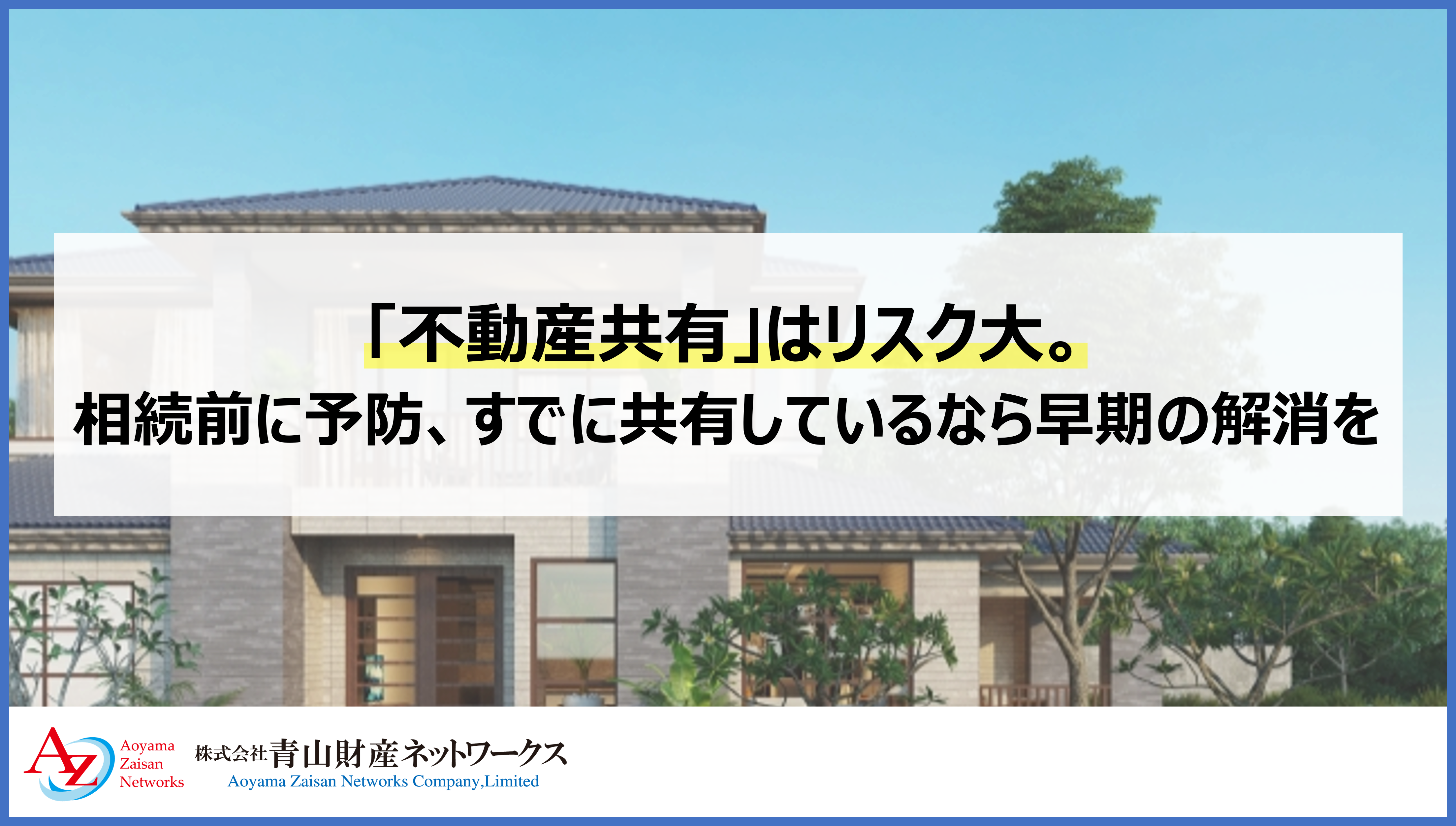「不動産を複数人で共有する形で相続しても問題ないのだろうか」と気になる方は多いのではないでしょうか。
共有状態にある不動産は、売却やリフォームをする際、共有者の一定人数の合意が必要になるため、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。
本記事では、共有不動産の相続における基本的なルールや共有不動産が抱えるリスクと対処方法などを詳しく解説します。すでに共有不動産を所有している方やこれから相続を控えている方は、ぜひご覧ください。
1.共有不動産は誰が相続するのか
不動産を複数人で共有している場合、共有者はそれぞれ「共有持分」という権利を持っています。
ここでは、相続が発生したときの共有持分の取り扱いについて解説します。
1-1.共有名義人ではなく法定相続人が相続する
不動産の共有者が亡くなった場合、その人の共有持分は相続の対象になります。
共有持分を相続するのは、亡くなった方(被相続人)の法定相続人です。そのため、亡くなった人の共有持分が自動的に他の共有者に移転するわけではありません。
法定相続人になれる人は民法で定められています。亡くなった人の配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の親族は以下の優先順位にしたがって決まります。
- 第1順位:亡くなった人の子
- 第2順位:亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位:亡くなった人の兄弟姉妹
※参考:国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
例えば、夫Aさん、妻Bさん、長男Cさん、次男Dさんという構成の家族がいたとしましょう。Aさんと長男Cさんは二世帯住宅に住んでおり、それぞれ2分の1ずつ共有持分を持っていました。
Aさんが亡くなった場合、法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、次男Dさんの3人です。遺言書がない場合、妻Bさん、長男Cさん、次男Dさんの3人はAさんの共有持分を含めた遺産をどのように分けるのかを話し合って決めることができます。
全員の合意があれば、Aさんの共有持分を妻Bさんが相続することもできますし、長男Cさんが相続して住宅を単独所有とすることも可能です。
ただし、相続人の全員が相続放棄した場合や相続人が1人もいない場合、亡くなった人の共有持分は他の共有者に移ります。
1-2.遺産分割協議が終わるまでは共同相続の状態となる
亡くなった人が遺言書を残していない場合、被相続人が所有していた不動産は、法定相続人の全員で共有する「共同相続」の状態になります。これは、共有持分を相続するケースについても同様です。
共同相続の状態を解消するためには、相続人全員で「遺産分割協議」という話し合いを行い、遺産の分け方を決める必要があります。
遺産分割協議により共有持分を相続する人が決まったあと、法務局で「相続登記」をして不動産や共有持分の名義人を変更します。
2.不動産の共有名義人が亡くなったときの手続きの流れ
不動産の共有名義人が亡くなったときは、以下の手順で手続きを進めます。
- 1.遺言書の有無を確認する
- 2.相続人を確定する
- 3.相続財産を調査する
- 4.遺産分割協議を行う
- 5.遺産分割協議書を作成する
- 6.相続税の申告と納税をする
- 7.相続登記をする
2-1.遺言書の有無を確認する
遺産相続では、財産を所有していた人の意思がもっとも尊重されます。そのため、被相続人が遺言書を残しており、共有持分を引き継ぐ人が指定されていた場合は、基本的にはその記載内容にしたがって承継されます。
不動産の共有名義人が亡くなったときは、遺言書が作成されていないか確認しましょう。被相続人が生前に遺言書を作成していると明言していなくても、机の引き出しや金庫、タンスなどに保管されているかもしれません。
被相続人が自筆で作成した「自筆証書遺言」が見つかった場合、家庭裁判所の手続きの中で開封し、内容を検認する必要があります。
ただし、自筆証書遺言が遺言書保管制度を利用して法務局で保管されていた場合、公証役場で「公正証書遺言」を作成していた場合、検認を受ける必要はありません。
2-2.相続人を確定する
相続が開始されたときは、亡くなった共有名義人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集め、法定相続人を特定する必要があります。
戸籍謄本のみでは出生から死亡まで連続しない場合は、必要に応じて除籍謄本や改製原戸籍を取得します。
遺産分割協議に参加していない法定相続人の存在が発覚すると、再度協議をしなければなりません。認知された非嫡出子(婚外子)や元配偶者との子どもなどは見落とされやすいため、戸籍謄本等で法定相続人を入念に調査しましょう。
戸籍謄本等の取得先は、亡くなった方の本籍地がある市区町村役場です。結婚や離婚、住宅購入、引っ越しなどで本籍地が変更されている場合は、変更前の市区町村でも戸籍を請求する必要があります。
2-3.相続財産を調査する
法定相続人の特定とあわせて、預貯金や不動産、有価証券など相続の対象になる遺産を調査します。
預貯金を調査するときは、通帳やキャッシュカードなどを確認して被相続人が利用していた金融機関を特定し、残高証明書や取引履歴を取得します。
不動産については、被相続人の自宅に送付されている固定資産税の納税通知書や、保管されている権利証などで確認するのが一般的です。
ただし、共有状態にある不動産の場合、固定資産税の納税通知書は代表者にしか届かないため、相続財産として見落とされることがあります。
見落としを防ぐためには「名寄帳(なよせちょう)」を取得すると良いでしょう。名寄帳とは、個人が所有している不動産の情報を所有者別にまとめた書類のことです。
法定相続人等であれば、不動産の所在地を管轄する市区町村役場(東京都23区の場合は都税事務所)で故人の名寄帳を取得できます。
2-4.遺産分割協議を行う
遺言書がないときは、法定相続人の全員で遺産分割協議をして共有持分や預貯金、有価証券などの遺産を、誰がどのように相続するのかを決めます。
遺産の取得割合を決める際には「法定相続分」が1つの目安となります。法定相続分とは、民法で定められている相続割合のことです。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、法定相続分は配偶者2分の1、子どもは1人につき4分の1です。
相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を相続することもできます。それぞれの事情を考慮し、全員が納得できる分割方法を決めることが大切です。
2-5.遺産分割協議書を作成する
遺産の分割方法に相続人の全員が合意したら、その内容をもとに遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、相続人間で話し合った結果を文書に残すことで、後々のトラブルを防ぎやすくなります。
また、遺産分割協議をして承継方法を決めた場合、不動産の相続登記や預貯金口座の名義変更などをする際は、原則として相続人全員の署名と押印がある遺産分割協議書が必要です。
手続きの際は、押印された実印が本物であることを証明するために、相続人全員の印鑑証明書も必要です。
2-6.相続税の申告と納税をする
相続税の申告と納税の期限は、相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内です。
相続税は、原則として遺産の総額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた部分に課税されます。
例えば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」です。
各相続人等が亡くなった人から相続や遺贈(遺言により遺産を無償で譲ること)などで受け継いだ財産の合計価額が基礎控除額を超える場合は、期限内に申告と納税をする必要があります。
期限内に申告をしないと、相続税の負担を軽減する特例を適用できなくなる場合や、無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生する可能性があります。
2-7.相続登記をする
不動産の共有者が亡くなったときは、その方が持っていた共有持分の名義を相続人に変更するための「相続登記」が必要です。
相続登記は、2024年(令和6年)4月1日から義務化されており、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に申請する必要があります。
正当な理由なく期限内に相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあるため、共有持分を相続したときは速やかに手続きを進めましょう。
相続登記をする際には、亡くなった方の出生から死亡まで連続した戸籍謄本等や相続人全員の戸籍謄本などを準備し、申請書と共に法務局へ提出する必要があります。
共有持分を相続した方が自身で相続登記を行うこともできます。しかし、法律や不動産に関する専門的な知識が求められ、提出書類を揃えるのにも手間や時間がかかるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
3.不動産を共有名義で相続することは避ける
相続人が不動産の共有者となるのは、被相続人が所有する共有持分を相続するケースだけではありません、例えば、遺産の大半を被相続人の単独で所有している不動産が占める場合、複数の相続人で共有することがあります。
不動産は現金や預貯金と違い、物理的に均等に分けることが難しい財産です。遺産が土地であれば、相続人の数や相続割合に応じて区切ることもできますが、形状や日当たり、接道状況などが異なるために価値が公平にならないことも多いのです。
被相続人が遺言書を残していない場合、不動産を平等に分けられると考え、とりあえず相続人の共有名義で相続してしまうケースがあります。
しかし、共有名義の不動産は、さまざまなトラブルを引き起こす可能性が高いため、安易に選ぶべきではありません。
例えば、将来的に売却したい、あるいは第三者に貸して賃料を得たいと考えた際に、共有者間で意見が食い違って何も進まなくなることがあります。
遺産分割協議をする際は、不動産を共有状態にするとどのような問題が起こりうるのか、それを解決できるのかなどを相続人間でよく話し合うことが大切です。
4.不動産を共有名義で相続する5つのリスク
不動産を共有名義で相続することには、以下のようなリスクがあります。
- 共有者の意見が合わず売却や有効な活用などができない
- 管理費や税金の負担割合で揉めることがある
- 将来的に権利関係が複雑化することがある
- 不動産が適切に管理されないリスクがある
- 共有者が持分を勝手に売却する可能性がある
4-1.共有者の意見が合わず売却や有効な活用などができない
共有名義の不動産を売却する場合や大規模なリフォーム・増改築などを行うためには、共有している人たち全員の合意が必要です。
共有者の中に1人でも反対する人がいれば、不動産全体を売却したり大規模な改修工事をしたりすることはできません。
例えば、ある共有者は「早く現金化してしまいたい」と考える一方、別の共有者は「先祖代々受け継いだ家だから持ち続けたい」と考えている等の場合、意見が対立し不動産の売却が難しくなる可能性があります。
また、不動産を第三者に貸し出す場合も、一部の例外を除いて共有者の同意が必要なため、反対する人がいることで活用が困難になるケースもあります。
4-2.管理費や税金の負担割合で揉めることがある
共有名義の不動産にかかる固定資産税や、建物の修繕費をはじめとした維持管理費用は、原則として共有者の持分の割合に応じて負担するとされています。
例えば、固定資産税は納付書を受け取った代表者が1年分の税金を立て替えて支払い、後で他の共有者に各人の負担分を請求するケースが多くみられます。
しかし、共有者の1人が不動産に住んでいる場合、他の共有者から「自分は不動産に住んでいるわけでもないのに、なぜ税金だけ負担しなければならないのか」といった不満が出て、トラブルに発展することが少なくありません。
また、経済的に余裕のある共有者が税金や維持管理費を肩代わりし続けたことで不満が募り、共有者間の対立に発展するケースもあります。
4-3.将来的に権利関係が複雑化することがある
共有者が亡くなり、共有持分の相続が繰り返されると、共有者の人数が徐々に増えていき、権利関係がますます複雑になってしまうことがあります。
例えば、最初は兄弟2人で不動産を共有していた場合、その兄弟が亡くなり共有持分が子どもや孫の世代に相続されたことで、共有者の数が10人や20人などに膨れ上がるケースもあります。
共有者の数が増えれば増えるほど、不動産を売却したりリフォームをしたりする際に合意を取ることが難しくなっていくでしょう。
叔父や甥、姪など、普段あまり付き合いのない親族が新たな共有者になると、意見をまとめるどころか、連絡を取ること自体が難しくなる可能性があります。
4-4.不動産が適切に管理されないリスクがある
共有者間の意見がまとまらず、売却や活用などが進まないことで、誰も積極的に不動産に関わろうとしなくなり、放置されるケースもあります。
適切に管理されていない空き家を放置し続けると、以下のような事態が起こり、近隣住民から苦情が寄せられる可能性があります。
- 建物の老朽化が進み建物が倒壊するリスクが高まる
- 景観が悪化する
- 不法侵入や放火などの犯罪が起こりやすくなる
- 害虫や雑草の繁茂が起こる など
また、空き家の管理を放置し続けた結果、自治体から「管理不全空家等」として認定されてしまうと、固定資産税等の軽減措置が受けられなくなり税額が最大6倍に増加することがあります。
4-5.共有者が持分を勝手に売却する可能性がある
不動産の共有持分のみであれば、他の共有者の同意を得ることなく売却が可能です。そのため、共有者の1人が持分を第三者に売却し、それまで親族や信頼関係のある人と共有していた不動産が、まったく面識のない他人との共有状態になるケースがあります。
とくに、買取業者に共有持分を売却したことにより、その買取業者が他の共有者に対して持分の買い取り、または売却を要求してトラブルに発展した事例が数多くあります。
5.共有名義での不動産相続を回避する分割方法
共有名義で不動産を相続することを避ける方法は、主に以下の3種類です。
- 不動産を現金化して分割する
- 1人の相続人が代償金を支払って相続する
- 持分割合に応じて土地を分筆する
5-1.不動産を現金化して分割する
不動産などの遺産を売却して現金に変え、得られた金銭を各相続人で分ける方法を「換価分割」といいます。
換価分割により、不動産を売却して現金化すると法定相続分やそれぞれの相続人の事情などに応じて遺産を分けることが可能です。また、共有持分を単独で売却するよりも、不動産全体を売却して得られた売却代金を相続人間で均等に分けた方が、1人あたりの受取額は高くなるケースがほとんどです。
被相続人が残した不動産を誰も使用する予定がなく、協議の時点で相続人全員が売却することに合意している場合は、換価分割をするのも1つの方法です。
5-2.1人の相続人が代償金を支払って相続する
相続人の1人が不動産を取得し、他の相続人に対して金銭等を支払って精算する分割方法を「代償分割」と呼びます。
例えば、評価額3,000万円の家を3人の法定相続人で分ける場合、代償分割により1人が家を相続する代わりに他の2人へ1,000万円ずつ支払うことで、相続人間で公平に分割できます。
代償分割であれば、思い出のある実家や先祖から受け継いだ土地などを手放す必要はありません。また、不動産を1人の相続人が単独で所有することになるため、売却や活用などが所有者自身の意志で自由に行えます。
ただし、代償分割を行うためには、不動産を取得する相続人に代償金を用意できるだけの資力が必要です。また、不動産の評価額や代償金額について、相続人間で話し合いがスムーズにまとまらない場合もあります。
5-3.持分割合に応じて土地を分筆する
相続する財産が土地である場合、持分割合に応じて「分筆」をする方法もあります。分筆は、登記簿上では1つの土地を複数の土地に分割して登記し直し、各相続人の単独所有とする方法です。
分筆により、法定相続分や遺産分割協議で決まった割合にもとづいて土地を分けることで、より公平に遺産を分割しやすくなります。分筆後の土地はそれぞれの所有者が自由に売却したり、活用したりすることが可能です。
ただし、土地を同じ面積に分けたとしても、形状や日当たり、接している道路の状況などが異なるために、価値が同じにならない場合があります。また、測量や登記申請などに手間や費用がかかる点にも留意する必要があります。
6.相続放棄をすると共有不動産を含むすべての遺産を相続できない
相続放棄とは、亡くなった人が残した資産や負債などを一切引き継がず放棄することです。不動産を相続しても管理が難しい場合や、故人に多額の借金がある場合などは、相続放棄をすることも検討すると良いでしょう。
ただし、後から価値のある財産が見つかったとしても相続放棄をしていると相続できません。
相続放棄ができるのは、相続の開始があったことを知ったとき(通常は被相続人が死亡した日)から3か月以内です。
相続が開始されたときは、相続の対象となる財産を速やかに調査し「プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか」「不動産の管理や活用が可能か」なども踏まえて、相続放棄すべきかよく検討しましょう。
7.不動産の相続後に共有状態を解消する方法
すでに不動産を相続人で共有する形で相続している場合は、以下の方法で解消が可能です。
- 不動産の全体を売却する
- 共有持分を売却・移転する
- 共有持分を買い取る
- 共有持分を放棄する
7-1.不動産の全体を売却する
共有者全員の同意が得られるのであれば、不動産を売却することで共有状態を解消できます。
換価分割で不動産を相続する場合と同様に、売却代金を共有者で公平に分けることができ、共有持分のみを売却するよりも、多くの金銭を得られる可能性があります。
共有者の関係が良好であり、不動産を問題なく管理・使用できているために「まだ売却しなくて良いだろう」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、今後も同じ状態が続くとは限りません。例えば、共有者が亡くなり相続が発生したことで権利関係が複雑になり、売却や活用が難しくなることもあるため、そうなる前に不動産を手放すのも1つの方法です。
7-2.共有持分を売却・移転する
他の共有者が不動産の売却を望んでいない場合、自身の共有持分を移転したり売却したりする方法があります。
共有者の1人が不動産の単独所有を希望しているのであれば、その共有者に持分を移転できないか打診してみると良いでしょう。
持分を他の共有者に移転する際は、相場をもとに買取価格を適切に設定することが大切です。買取価格が相場に比べて著しく安いと、税務署から贈与とみなされ、贈与税が課されるリスクがあります。
自身の共有持分を不動産取引の専門業者など第三者に売却することも可能です。しかし、売却価格が割安な傾向にあり、共有持分専門の買取業者に売却するとトラブルが生じるケースもあるなどの注意点があります。
7-3.共有持分を買い取る
自身が不動産の売却に反対しているときは、他の共有者の共有持分を買い取る方法があります。他の共有者の全員から持分を買い取ることができれば、不動産の単独所有が可能です。
例えば、自身が共有状態の不動産に住んでいる場合、他の共有者の持分を買い取って単独所有にすることで、売却やリフォームなどを自由に行えるようになります。
ただし、他の共有者から持分を買い取るためには、相応の資金力が必要です。また、買取価格が市場価格よりも著しく低い場合、税務署から贈与と判断され、贈与税の課税対象となるリスクがあるため、適正な価格に設定する必要があります。
7-4.共有持分を放棄する
持分放棄とは、自身の共有持分を手放す行為のことです。放棄された持分は、原則として他の共有者に帰属することになります。
持分を放棄する場合、その対価として金銭などを受け取ることはできません。共有不動産にほとんど金銭的な価値がなく、持分の売却や他の共有者への移転が難しい場合に、持分放棄が検討されることがあります。
持分放棄をするときは、法務局で共有持分の移転登記が必要です。また、他の共有者と共同で申請をする必要があります。そのため、登記手続きをする前に他の共有者に対して持分を放棄する意思を伝えて了承を得るようにしましょう。
なお、民法では共有持分の放棄は贈与にはあたりませんが、税法上は実質的に財産を無償で譲渡したとして共有者に贈与税が課税されることがあります。
8.生前にできる共有不動産の相続対策
生前に適切な対策を講じることで、不動産の共有に関するさまざまな問題を未然に防ぐことが可能です。主な対策方法は、以下の3つです。
- 遺言書を作成する
- 共有持分を生前贈与する
- 家族信託を利用する
8-1.遺言書を作成する
被相続人が遺言書に、不動産を特定の人に単独で相続させることを記載していた場合、基本的にはそのとおりに承継されるため、相続人同士での共有状態になることを防げます。
また、遺言書に誰がどの遺産を受け継ぐのか詳細に記載されていれば、遺産分割協議は不要です。相続登記の際も遺産分割協議書を提出する必要がなくなり、新しい所有者以外の相続人の戸籍謄本や印鑑証明書を集める手間も省けるため、手続きを迅速に進められるでしょう。
ただし、遺言書を作成する際には「遺留分」に配慮する必要があります。遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取れる遺産の割合です。
遺留分を侵害する内容の遺言書を作成すると、相続人間で争いが生じる原因となりかねません。法的に有効で、かつ相続人間の無用な争いを避ける遺言書を作成するためには、司法書士や弁護士などの専門家に相談することが大切です。
8-2.共有持分を生前贈与する
相続が始まる前に不動産がすでに共有状態である場合、共有持分を他の共有者である親族などに生前贈与するのも1つの方法です。
例えば、長男Aさんと次男Bさんが不動産を共有しているとしましょう。Aさんには2人の子どもがいます。そのため、Aさんが亡くなったとき、共有持分を相続する権利を持つのは2人の子ども達であり、Bさんには承継されません。
一方、AさんはBさんに共有持分を生前贈与することで、Bさんは不動産を単独所有とすることができます。
ただし、共有持分を生前贈与すると受け取る側に贈与税が課税される可能性があるなどさまざまな注意点があります。共有持分の生前贈与を検討する際は、財産承継に詳しい税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
8-3.家族信託を利用する
家族信託は、財産の所有者である「委託者」が、「受託者」に財産の管理や運用などを任せられる制度です。不動産の運用や売却で生じた家賃や売却益などは「受益者」が受け取れる仕組みです。
家族信託であれば、生前に不動産の管理や運用などを信頼できる家族に託すことができます。また、所有者が亡くなったときに不動産を承継する人もあらかじめ信託契約で定められるため、相続発生時に複数の相続人で共有される事態を防げます。
また、遺言では1代先までしか財産の承継先を指定できませんが、家族信託では次世代以降も定めることも可能です。
9.共有不動産の相続対策は専門家に相談を
不動産を共有名義で相続すると「共有者の意見が対立して売却や活用ができない」「将来的に権利関係が複雑化する」など、さまざまなトラブルが生じる恐れがあります。
トラブルのリスクを回避するためには、遺言書の作成や共有持分の生前贈与、家族信託などで、財産を所有する人が生前に対策することが重要です。
とはいえ、効果的な対策方法を検討するためには、相続や法律などの専門知識が求められます。そこで、共有不動産を相続する可能性がある方は、青山財産ネットワークスまでお気軽にご相談ください。遺言書の作成や生前贈与などの支援だけでなく、すでに共有状態にある不動産の共有解消もサポートいたします。
- 相澤 光Aizawa Hikaru
- コンサルティング事業本部 コンサルティングサービス室 室長 兼 第四事業部 ダイレクトグループ グループ長
不動産や法人を活用した財産防衛策の立案・実行に従事し、財産と想いを次世代に承継するための支援を提供。最適な選択肢を見つけられるよう、中立的な立場で家族全体の意向調整もサポートすることを信条とする。
当社の30年にわたるナレッジを集約した書籍を発行し、セミナー登壇実績も多数。
趣味:学び(税理士資格の勉強中)、ギター、サウナ
- 専門分野
- 土地持ち資産家、金融資産家向けコンサルティング
- 資格
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
- 著書
- 「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策