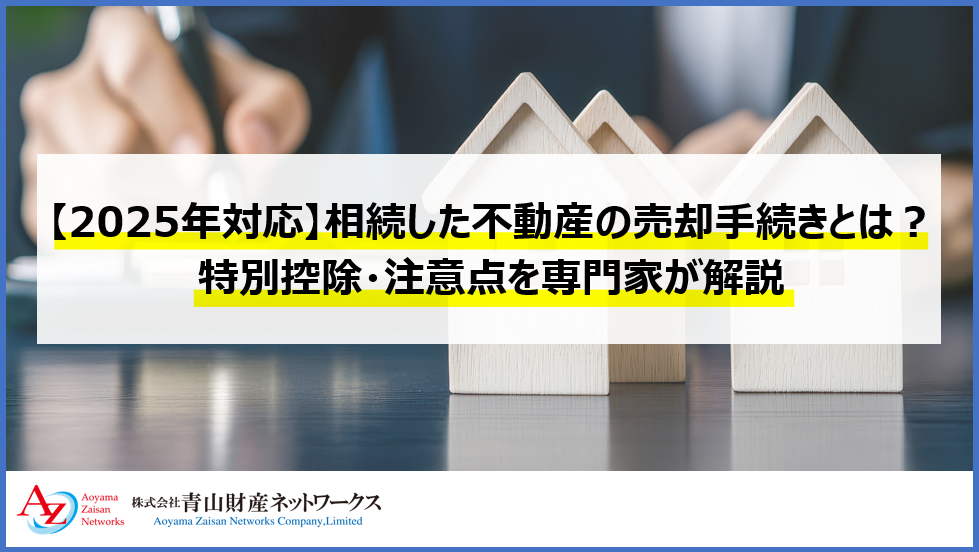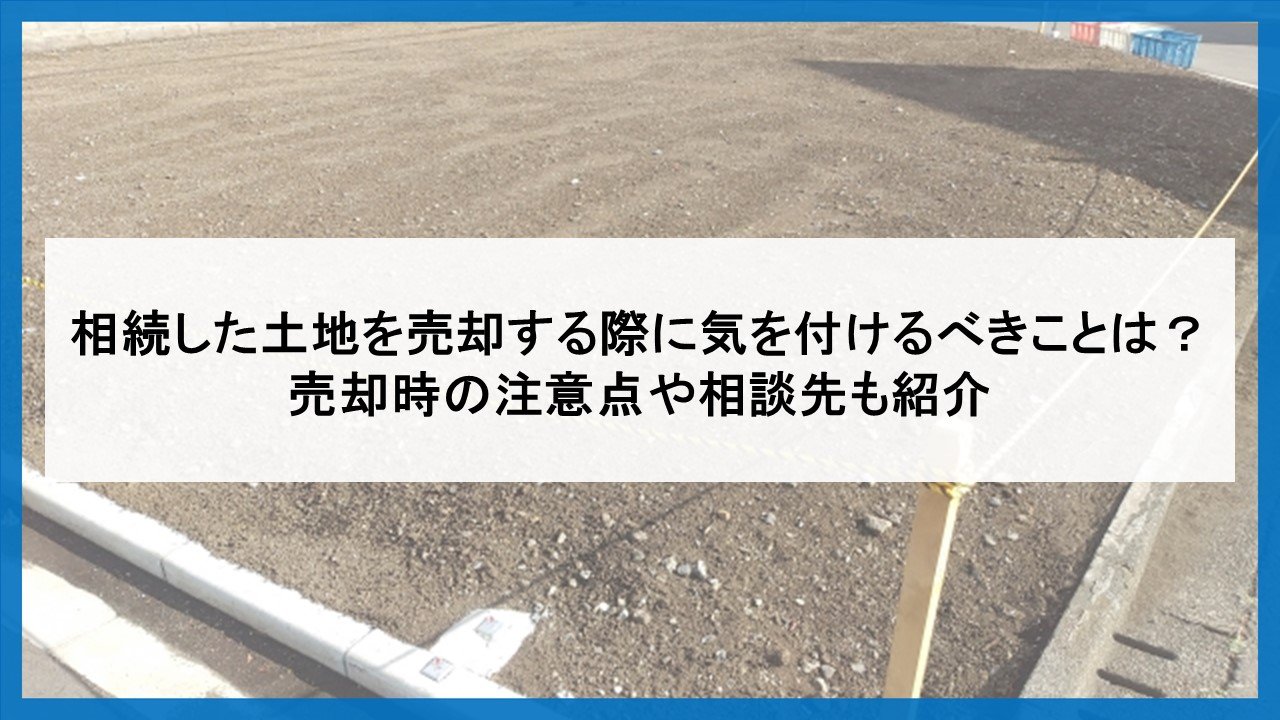相続税は被相続人の財産を相続した際に、相続財産にかかる税金です。
原則として相続税は現金一括で納付する必要があるため、相続税評価額の高い土地を相続したとき、相続税を支払えないというケースもあるでしょう。
相続税が払えないときはどうしたらいいのでしょうか。
本記事では、相続税が払えないときの対処法を4つ詳しく解説します。
土地の相続税を支払えないときの対処法を知りたいという人は、ぜひ参考にしてください。
土地の相続税が払えない状況とは?
対処法を説明する前に、どのようなときに相続税が払えなくなるのかを見ていきましょう。相続税を支払えなくなる状況としては主に次の2点が考えられます。
- 相続財産の中の現金預金が少ない
- 遺産分割協議が合意に至らず預金が引き出せない
一つずつ見ていきましょう。
相続財産の中の現金預金が少ない
相続財産に含まれる現預金だけでは、相続税の支払いをカバーできないという状況は十分に考えられます。相続財産の大半が不動産や貴金属など、すぐには現金化できないもので占められているケースがこれに該当します。
相続税の支払いは原則として現金により一括納付しなければならないため、相続財産に含まれる現預金が少ない場合は相続税の支払いに支障をきたしてしまうことになります。
遺産分割協議が合意に至らず預金が引き出せない
遺産分割協議とは、相続人同士による財産の配分を決めるための話し合いです。法定相続分の割合は民法で規定されていますが、必ずしも財産を法定相続分どおりに配分する必要はありません。「親の介護は弟夫婦に任せきりだったから、弟に多めに相続させよう」といったことも可能です(ただし遺言書があるケースでは、原則として遺言書どおりに執行されます)。
ただ相続が「争続」となり、遺産分割協議がなかなかまとまらないケースが往々にして発生します。このような場合、被相続人の財産に相続税に相当する金額を支払えるだけの現預金があっても、支払いが難しくなります。
というのも、個人が亡くなるとその預金口座は金融機関により凍結されて簡単に引き出せなくなり、凍結を解除するためにはすべての相続人が遺産分割協議の内容に合意していることが必要だからです。
土地の相続税が払えないときの4つの対処方法
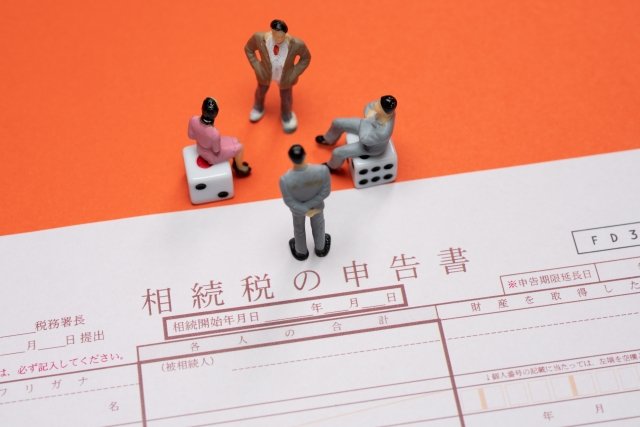
土地の相続税が払えないときの対処方法として、下記の方法が挙げられます。
- 相続税の分割払い(延納)
- 相続財産で相続税を支払う (物納)
- 相続放棄により相続税の支払いを回避する
- 金融機関からの融資金で相続税を支払う
それぞれ見ていきましょう。
相続税の分割払い(延納)
相続税は原則として現金一括払いですが、一定の要件を満たすことにより分割払いに変更することができます。これを「延納」といいます。
相続した財産の75%以上を不動産等が占める場合は、20年を限度として延納できます。ただし、延納には利子税がかかるため、結果として本来の相続税額よりも多額の税金を支払うことになります。その点は注意してください。
延納の要件
相続税の延納の申請は税務署に対して行いますが、申請が認められるには下記の4つの要件がすべて満たされなければなりません。
- 1.相続税の金額が10万円を超えていること
- 2.現金納付が困難であること
- 3.申告期限までに延納申請書・担保提供関係書類・金銭納付を困難とする理由書を提出すること
- 4.延納税額および利子税額に見合う担保を提供すること
それぞれ見ていきましょう。
1.相続税の金額が10万円を超えていること
延納制度を利用するためには相続税額が10万円を超えていなければなりません。相続人が複数いるケースで相続税額の合計金額が10万円を超えていても、延納制度は利用できません。なぜなら、税務署は相続人ごとに延納制度を利用できるか否か判定するからです。
2.現金納付が困難であること
相続人が相続前から所有していた財産を相続税の納付に充当しても、相続税の全額を支払えないことは、延納の要件です。
3.申告期限までに次の書類を提出すること
- 延納申請書
- 担保提供関係書類
- 金銭納付を困難とする理由書
相続人は被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に、相続税を申告・納付しなければなりません。申告・納付の期限日が土・日・祝日の場合は次の平日が期限日となります。その申告期限までに「延納申請書」「担保提供関係書類」「金銭納付を困難とする理由書」を税務署に提出する必要があります。
4.延納税額および利子税額に見合う担保を提供すること
延納を利用するときには、税務署から延納税額および利子税額に見合う担保を提供するよう求められます。担保として認められるものには不動産や国債証券、上場株式などがありますが、通常は不動産を担保とするケースが多く見受けられます。ちなみに延納税額が100万円以下であることに加え、延納期間が3年以下であれば担保の提供は求められません。
相続財産で相続税を支払う (物納)
延納が適用されても現金で相続税を支払えないケースでは、不動産や船舶などの「物」で相続税を支払うこともできます。これが「物納」です。
物納に使用できる財産は被相続人からの相続財産に限られ、相続人が相続前から所有していた財産を物用に使用することはできません。
そして、物納に充てられる財産の内容は下記のように決められています。
| 順位 | 物納に充当できる財産の種類 |
|---|---|
| 第1順位 | 1.不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式 など 2.不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの |
| 第2順位 | 3.非上場株式 など 4.非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの |
| 第3順位 | 5.動産 |
物納劣後財産とは、ほかに物納適格財産がないときにのみ物納することが認められている財産のことです。具体的には地上権、永小作権などが設定されている土地や法令に違反して建築された建物およびその敷地などです。
「不動産や国債証券を相続後も持ち続けたいから、宝石(動産)で物納をする」ということは認められないため注意が必要です。
また、物納として納める財産は時価よりも低い金額で評価されることも有り得るため、その点にも注意してください。物納を利用するよりも、その財産の売却代金で相続税を支払ったほうがよいケースもあります。
物納の要件
物納は次のすべての要件をクリアしたときに許可を受けることができます。
- 延納によっても金銭で納付することが不可能であり、納付を困難とする金額を限度としていること
- 物納に充てる財産が規定されている種類の財産および順位で、日本国内に存在すること
- 物納に充当する財産が管理処分不適格財産に該当せず、物納劣後財産に該当するときにはほかに物納に充当できる財産がないこと
- 物納申請期限までに物納申請書と物納手続き関係書類を税務署に提出すること
管理処分不適格財産とは、物納が認められる財産であるが、国が管理・処分するのに適していない財産のことです。したがって管理処分不適格財産は物納できません。具体的には、担保権の設定登記がなされている土地や、権利の帰属について紛争が発生している土地、譲渡制限株式などがあります。
相続放棄により相続税の支払いを回避する
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産、マイナスの財産すべてを相続しないことです。
相続放棄をすれば、相続当初から相続人ではなくなるため、相続税を支払う必要はありません。ただし、預貯金・株式・不動産などのプラスの財産もすべて相続できなくなります。したがって、相続放棄を行う前にプラスの財産とマイナスの財産の内容・金額をしっかり把握することが重要です。
相続放棄を行うには、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります(民法915条1項)(民法938条)。
相続をする財産には、プラスの財産以外にも借金や保証債務のようにマイナスの財産もあります。相続をするということは、プラス、マイナスすべての財産を継承することであるため、もしマイナスの財産額がプラスの財産額より多ければ、相続放棄をするという選択肢もあるのです。
相続をしなければ当初から相続人ではなくなるため、相続税を支払う必要はありません。ただし、相続放棄をするべきか否かは個々のケースで異なるため、慎重に考える必要があります。できるだけ早い段階で司法書士や弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。
金融機関からの融資金で相続税を支払う
金融機関から相続税相当額の融資を受けて相続税を支払うというやり方もあります。このケースでは次の2パターンがあります。
①納税用の資金を借り入れるパターン
②相続した不動産を売却することを前提にして借り入れるパターン
「実家を残して居住したい」といったケースでは①の単純な借り入れパターン、将来的に使用する見込みのない不動産を相続したケースでは②の売却を前提とした借り入れパターンを選ぶとよいでしょう。
ただし、融資は必ず受けられるとは限りません。相続税の納税資金借り入れを検討したら、早い段階で金融機関や専門家に相談することをおすすめします。
土地の相続税を払わないと差し押さえも有り得る
もし、相続税の納付期限を過ぎても相続税を支払えないときはどうなるのでしょう。期限内に支払わないときはペナルティとして追加の税金が課せられます。それも払えずに放置していると、最終的には国に財産を差し押さえられてしまいます。国はその財産を現金化し、相続税に充当するのです。
- 相続税の納税期限
- 期限内に申告しない場合は無申告加算税が課される
- 期限内に支払わない場合は延滞税が課される
- 最悪の場合は差し押さえ
相続税の納税期限
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内と定められています。
例えば、知った日を2024年5月15日とすると、提出期限は2025年3月15日になります。
もしも、期限日が土曜日や日曜日、祝日であれば、その翌日が申告期限です。
期限内に申告しない・支払わないときは無申告加算税や延滞税のペナルティ
相続税の申告・納税を期限までに行わないと、無申告加算税や延滞税が課せられます。
無申告加算税とは、期限内に申告しないことに対して課せられる税金です。納付すべき税額に対し50万円までは15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分には30%の税金が上乗せされます。
延滞税とは、納税を延滞したことに対して課せられる税金です。
税率は納付期限の翌日から2カ月を経過する日までは原則として年7.3%(令和7年1月1日~令和7年12月31日は、延滞税特例基準割合+1%となる2.4%が適用)、納付期限の翌日から2カ月を経過した日以降は原則として年14.6%(令和7年1月1日~令和7年12月31日は、延滞税特例基準割合+7.3%となる8.7%が適用)になります。
相続税の申告は、被相続人が死亡したときの居住地を管轄する税務署で行います。相続税は金融機関やインターネットで納付します。
相続税は相続を知った翌日から10カ月以内に申告しないと、無申告加算税が課されます。また相続税を10カ月以内に納付しないと、延滞税が課されます。
最悪の場合は差し押さえ
仮に無申告加算税や延滞税などのペナルティを受けて、さらに支払いができなくなった状況をそのままにしていると、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。
一般的に差し押さえは下記のプロセスを経て行われます。
【差し押さえまでの流れ】
- 1.督促状が届く
- 2.税務署からの電話・税務署員の訪問
- 3.財産や人物の調査
- 4.差押予告書が届く
- 5.差し押さえの実施
それぞれ見ていきましょう。
1.督促状が届く
国税徴収法では、督促状を発送した日から10日を過ぎても納付されないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められています(国税徴収法47条1項1号)。
2.税務署からの電話・税務署員の訪問
督促状の送付に加え、税務署から電話が来たり、税務署員が訪問したりして、納税を促すことがあります。
3.財産や人物の調査
差し押さえる財産の決定のために、滞納者の身辺調査が行われ、口座の預金残高や給料など、財産に関する調査が行われます。
4.差押予告書が届く
差押予告書とは、指定された日までに税金が納付されないときに差し押さえが執行される旨が記された文書です。
5.差し押さえの実施
無申告加算税や延滞税などのペナルティを受けて、さらに支払いができない状態を放置すると、最終的には財産が差し押さえられる可能性があります。
税金滞納に伴う差押えは、国税徴収法に基づき行われ、税務署が裁判所の許可を得ることなく滞納者の財産を強制的に処分できる「自力執行」の手続きが採られます。
差し押さえの対象には、不動産や預金、給料などが含まれます。一方で、生活に必要な一部の財産については、法令や通達により差押えが制限されることもあります。ただし、その範囲はケースによって異なり、差押禁止財産とされる基準も国税徴収法上は明確に規定されていないものもあるため、具体的には専門家に確認することが重要です。
まとめ
土地の相続税が課税される場合、相続税は高額になる傾向があります。相続税が支払えない場合、相続人の金融資産や土地を差し押さえられてしまう可能性もあります。
土地相続時に際した相続税の支払いに関してお悩みの方は、ぜひ青山財産ネットワークスへご相談ください。
- 相澤 光Aizawa Hikaru
- コンサルティング事業本部 コンサルティングサービス室 室長 兼 第四事業部 ダイレクトグループ グループ長
不動産や法人を活用した財産防衛策の立案・実行に従事し、財産と想いを次世代に承継するための支援を提供。最適な選択肢を見つけられるよう、中立的な立場で家族全体の意向調整もサポートすることを信条とする。
当社の30年にわたるナレッジを集約した書籍を発行し、セミナー登壇実績も多数。
趣味:学び(税理士資格の勉強中)、ギター、サウナ
- 専門分野
- 土地持ち資産家、金融資産家向けコンサルティング
- 資格
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
- 著書
- 「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策