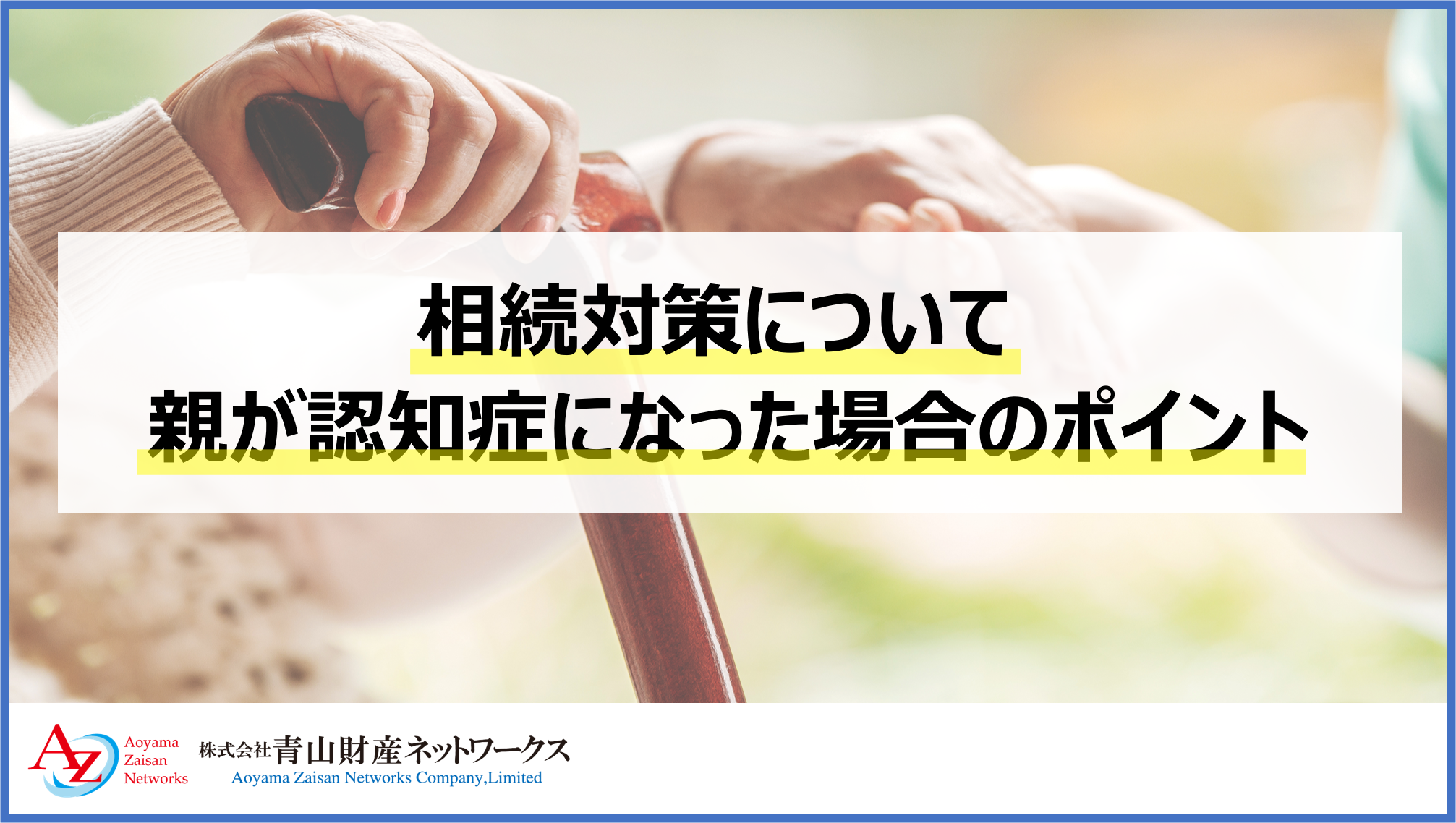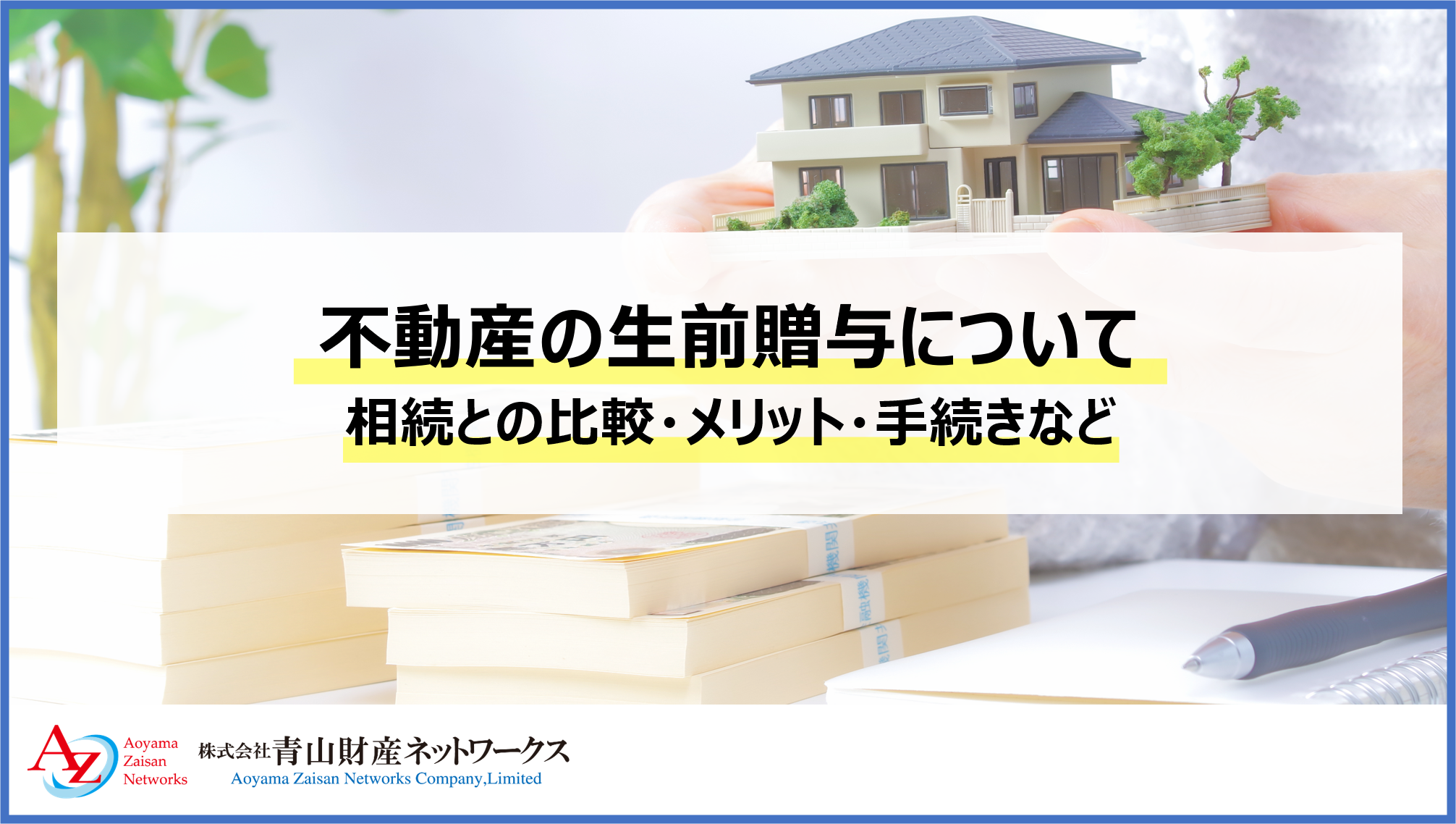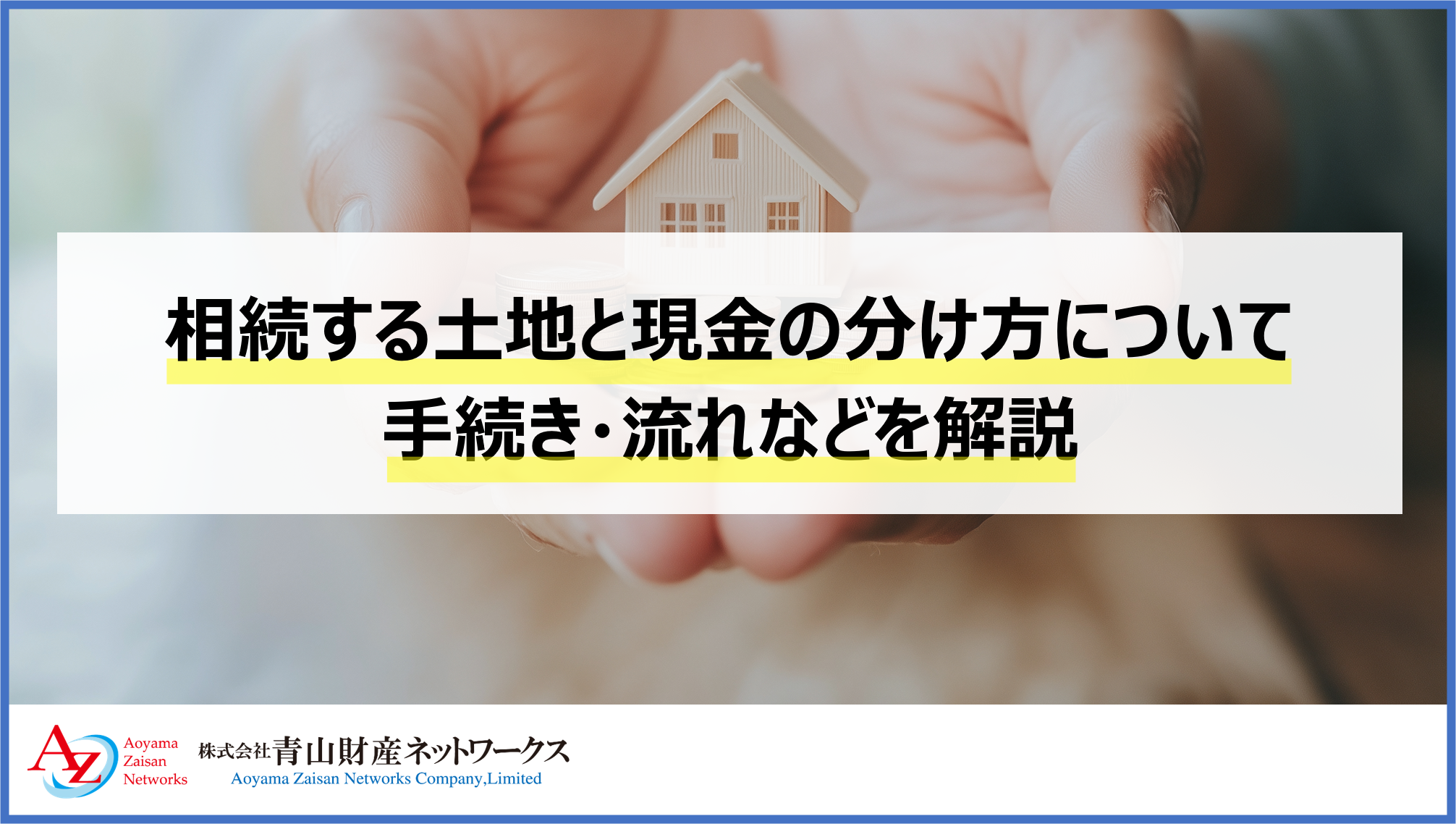代襲相続は、本来の相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。一見シンプルな制度に思えますが、実は通常の相続よりもトラブルが発生しやすいという特徴があります。
代襲相続人となる孫や甥・姪などは、他の相続人と世代が異なり、また未成年者の場合もあります。そのため、代襲相続人は他の相続人との関係性が希薄になりがちです。
この記事では、代襲相続で起こりうる8つの典型的なトラブルと、それぞれの対処法について詳しく解説します。トラブルを未然に防ぐための対策もご紹介しますので、代襲相続にかかわる可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。
1.代襲相続の基礎知識
代襲相続は、相続人となるはずだった人が相続開始よりも前に死亡等の理由で相続権を失っている場合に、その人の子ども(被相続人から見た孫や甥、姪など)が代わりに財産を承継する制度です。
例えば、被相続人がAさん、本来の相続人が配偶者Bさん、長男Cさん、長女Dさんであるとしましょう。Aさんが亡くなった時点で、長男Cさんはすでに他界しており、Eさんという子ども(Aさんの孫)がいました。
この場合、代襲相続により、他界しているCさんに代わり、Eさんが代襲相続人となりAさんの遺産を承継する権利を取得します。
また、被相続人に子どもがおらず、兄弟姉妹が相続人となるケースにおいて、相続開始時点ですでにその兄弟姉妹が亡くなっている場合には、甥・姪が代襲相続人となります。
2.代襲相続で起こりうる8つのトラブル
代襲相続で起こりうるトラブルのうち、とくに発生しやすいものは以下の8つです。
- 代襲相続人に無断で遺産分割協議が進められる
- 代襲相続人が強引に遺産分割協議書への署名を求められる
- 代襲相続人が相続財産の情報を開示してもらえない
- 代襲相続人が相続放棄を一方的に迫られる
- 遺産の承継方法や割合で揉めてしまう
- 代襲相続人となかなか連絡が取れない
- 代襲相続人が遺産分割協議に協力的でない
- 代襲相続人が被相続人の借金を意図せず相続してしまう
2-1.代襲相続人に無断で遺産分割協議が進められる
被相続人が遺言書を残していない場合、法定相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、遺産の承継方法を決める必要があります。
代襲相続が発生した場合は、代襲相続人も含めて相続人全員で遺産分割協議を行わなければ法的には成立しません。
しかし、代襲相続人となる人と疎遠であると、代襲相続人を除く法定相続人のみで遺産分割協議を進めてしまうことがあります。また、法定相続人が代襲相続という制度そのものを知らず、代襲相続人が参加しないまま遺産分割協議が行われてしまうケースもあります。
代襲相続人が不在で行われた遺産分割協議は、法律上無効です。その場合、代襲相続人は、協議が無効であることを主張し、改めて協議に参加できます。
法定相続人のみで協議を進めると「自分にも遺産を相続する権利がある」と主張する代襲相続人とのあいだでトラブルに発展するケースが少なくないのです。
2-2.代襲相続人が強引に遺産分割協議書への署名を求められる
遺産は、法律で定められた相続分(法定相続分)のとおりに分ける必要はなく、相続人全員の合意があれば、承継する財産の内容や割合を自由に決めることができます。
しかし、代襲相続人は孫や甥、姪など、被相続人の実の子どもや兄弟姉妹である相続人よりも年齢が若いケースがほとんどです。また、相続に関する知識があまりないケースも少なくありません。
そのため、他の相続人が自分たちにとって都合の良い内容で遺産分割の案を作成し、代襲相続人に遺産分割協議書への署名や押印を強要してくることがあるのです。
2-3.代襲相続人が相続財産の情報を開示してもらえない
代襲相続人は、被相続人や他の相続人との人間関係が希薄であるために、預貯金や不動産、有価証券などの遺産が具体的にいくらあるのか知らされないまま協議が進められることがあります。
とくに、代襲相続人が被相続人の保有する遺産の内訳、金額などを詳細に把握しているケースは多くありません。
そのため、実際にはもっと多くの財産があるにもかかわらず、一部しか開示されなかったために、代襲相続人の取り分が本来よりも少なくなることがあります。
また「遺産がいくらあるのか詳しく教えてほしい」と代襲相続人が他の相続人に依頼しても、開示を拒まれてトラブルに発展することがあります。
2-4.代襲相続人が相続放棄を一方的に迫られる
他の相続人が「代襲相続人に遺産を相続させたくない」と考え、一方的に相続放棄を求められてトラブルになることもあります。
相続放棄とは、預貯金や不動産などプラスの財産に加え、被相続人が残した借金や未払金などマイナスの財産も一切相続しない手続きのことです。
相続放棄をするかどうかは、相続人自身の意思で自由に決めるべきことであり、誰かから強制されるものではありません。
しかし、他の相続人が被相続人の実の子どもや兄弟姉妹など歳上で立場も強いと、代襲相続人に対して強い口調で相続放棄を迫ることもあります。
「亡くなった人と疎遠だったあなたに財産を受け取る権利はない」などと、半ば脅しのような形で迫られるケースもあります。
2-5.遺産の承継方法や割合で揉めてしまう
代襲相続人が遺産分割協議に参加してはいるものの、相続する遺産の種類や取得割合などで他の相続人と意見が対立するケースもあります。
遺産分割協議では、被相続人が存命であるときに相続人が行った貢献や、生前に贈与された財産などを考慮して遺産の分割方法を決めることが可能です。
例えば、被相続人の経営する会社を手伝っていた相続人や、寝たきりの被相続人を献身的に介護していた相続人などは、多くの遺産を相続したいと主張できます。
しかし、代襲相続人がこうした事情を知らず「法定相続分にしたがって公平に遺産を分けるべきだ」などと主張してトラブルになることがあります。
また「生前に多くの財産を贈与された人と同じ割合で相続するのは不公平だ」と代襲相続人が主張して、遺産分割協議が合意に至らない場合もあります。
2-6.代襲相続人となかなか連絡が取れない
遺産分割協議は、遺産を相続する権利を持つ人の全員が合意しないと成立しないため、相続が開始されたときは速やかに代襲相続人となる人と連絡を取らなければなりません。
しかし、代襲相続人となる人が遠方に住んでいる場合や、亡くなった人や他の相続人と長年にわたり疎遠であると、連絡を取れず協議が一向に進まなくなるケースがあります。
その結果「いつまで経っても遺産が分割されない」「預貯金口座や不動産などの名義変更ができない」といった事態に陥りやすくなります。
2-7.代襲相続人が遺産分割協議に協力的でない
代襲相続人の中には、遺産相続が発生したことや自身が遺産を相続する権利を持っていることに関心がない人もいます。
そのため「遺産分割協議へ参加するよう呼びかけても応じてくれない」「相続手続きに必要な書類を提出するよう連絡しても返事がない」といった対応をする代襲相続人もいます。
代襲相続人の連絡先が分かっていても、協力的でないために遺産相続が進まず、他の相続人のストレスが積み重なって、深刻なトラブルに発展する場合があります。
2-8.代襲相続人が被相続人の借金を意図せず相続してしまう
相続の対象となる財産には、現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金といったマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産が多いときは、相続放棄をするのも1つの方法です。しかし、相続放棄をするためには相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で申述をしなければなりません。
しかし、代襲相続人は被相続人や他の相続人との関係が希薄であり、故人が多額の借金を抱えていたことを知らないケースが少なくありません。
自身が代襲相続人であることは承知しているものの、借金の存在までは把握できず、期限内に相続放棄の手続きをしなかったために、意図せずにその負債を相続してしまうことがあります。
また、被相続人が残した負債を誰がどのように負担するのかを巡って、他の相続人と意見が衝突してトラブルになる場合もあります。
3.代襲相続におけるトラブルの対処法
代襲相続により、代襲相続人と他の相続人とのあいだでトラブルが生じたときは、以下の方法で対処できる可能性があります。
- 当事者の事情や立場なども尊重して話し合いを進める
- 遺産の全体像をよく確認する
- 自身が主張できる相続割合を整理する
- 遺産分割協議書には納得してから署名する
- 調停や審判での解決を視野に入れる
3-1.当事者の事情や立場なども尊重して話し合いを進める
同じ相続人であっても、生活背景や故人との関わりなどさまざまな点が異なります。
例えば、故人と長年にわたり生活を共にしてきた方もいれば、遠方で暮らしており数年に1度しか故人と顔を合わせなかった方もいるでしょう。また、配偶者や子どもを養っており生活に金銭的な余裕がない方もいるかもしれません。
このように人それぞれ状況が異なるため、自身にとって不利だと思われる分割方法を提案されたとしても、感情的にならず意見に耳を傾けることが大切です。
権利だけでなく、過去に同居や介護等の貢献有無や、今後も代々の財産を承継していく義務を負うかどうか等も含めて、それぞれの立場を尊重し、協力して話し合いを進めることで、無用な対立が避けられ、円満に解決しやすくなるでしょう。
3-2.遺産の全体像をよく確認する
相続権を持つ人の全員が納得できる遺産分割を行うためには、相続の対象となる財産の全体像を正確に把握することが不可欠です。とくに、相続放棄をすべきか検討するために、被相続人が残した負債はよく確認する必要があります。
代襲相続人は、他の相続人から財産目録を見せてもらうなどして相続財産が全体でいくらあるのかを把握するよう努めることが大切です。
他の相続人が遺産の開示を拒む場合は、あいだを取り持ってくれるような親族などの第三者を交えて話し合いを進めるのも1つの方法です。
代襲相続人自身が遺産を調査することも可能ですが、被相続人とあまり交流がなかった場合はあまり現実的ではありません。そのため、話し合いが難航するときは、弁護士に交渉や調査を依頼することも検討しましょう。
3-3.自身が主張できる相続割合を整理する
代襲相続のトラブルに対処するためには、相続で自身がいくらの遺産を取得する権利があるのかをよく理解することが重要です。
法定相続分や寄与分、特別受益といった制度を理解することで、他の相続人から示された遺産の分割方法が適切かどうかを判断しやすくなります。
代襲相続人の法定相続分は、亡くなった相続人が受け取るはずだった割合と同じです。亡くなった相続人に子どもが複数いる場合は、その相続分を子どもたちで均等に分けます。
寄与分と特別受益については以下のとおりです
- 寄与分:相続人が被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした場合に、その貢献度合いに応じて遺産を多く相続できる制度
- 特別受益:一部の相続人が生前贈与や遺贈※によって被相続人から受け取った利益のこと
※遺言によってその財産の全部または一部を無償で与えること
例えば、代襲相続人が被相続人の事業を手伝っていた場合や、仕事を辞めて献身的に被相続人を療養看護していた場合、寄与分が認められる可能性があります。
法的な根拠をもとに自身の相続割合を主張することで、他の相続人にも納得してもらいやすくなります。
法定相続分については以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
3-4.遺産分割協議書には納得してから署名する
遺産分割協議書に相続人の全員が署名・押印すると、その内容にもとづいて遺産分割が正式に成立します。後で「やはり納得できない」と思っても、協議内容を覆すことは困難です。
また、署名・押印をしたあと、被相続人に多額の借金があったことが発覚したり、価値のある財産が隠されていたことが判明したりするなどで、トラブルが生じることもあります。
そのため、遺産分割協議書に記載されている内容によく目を通し、十分に納得した上で、署名と押印をしましょう。
3-5.調停や審判は解決が著しく困難な場合の最終手段とする
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での「遺産分割調停」を検討する手段もあります。
一方で、調停では原則法定相続分に基づく和解が促される傾向があり、各相続人が望む柔軟な分割が実現しにくいケースが多いのが実情です。
さらに、調停で合意に至らなければ「審判」に移行し、裁判官が相続人の主張と提出書類などをもとに遺産分割の内容を決定します。このような裁判所の手続きは、申立書の作成、必要書類の収集、証拠の提出など多くの事務的対応が求められ、解決までに1年以上かかる場合があるため、時間的・金銭的負担が大きくなるリスクがあります。
よって、調停や審判による解決は最終手段として留め、まずは当事者間での話し合いや、柔軟な内部交渉による合意形成を行うことがおすすめです。
4.代襲相続でのトラブルを防ぐための対策
代襲相続のトラブルを防ぐためには、相続が発生する前に対策しておくのが望ましいです。具体的な対策方法は以下のとおりです。
- 生前に遺言書を作成する
- 生前に財産目録を作成・共有する
- 相続開始前に親族間で相続について話し合う
- 生前贈与や死因贈与を検討する
- 生命保険を活用する
- 家族信託を活用する
4-1.生前に遺言書を作成する
被相続人が生前に遺言書を作成し、遺産の承継方法を詳細にしている場合、原則としてその記載内容にしたがって財産が引き継がれるため、遺産分割協議をする必要がなくなります。
そのため「代襲相続人と他の相続人の意見が対立して話し合いが進まない」「代襲相続人がいることを他の相続人が知らずに遺産分割を進めてしまう」といったトラブルを抑える効果が期待できます。
代襲相続でのトラブルが想定される場合は、父母や祖父母などが健在なうちに遺言書を作成してもらうのも1つの方法です。
ただし、遺言書の内容が特定の相続人や代襲相続人が最低限受け取れる遺産の割合である「遺留分」を侵害している場合、新たなトラブルが生じる可能性があります。
そのため、作成の検討段階や少なくとも作成後は、配偶者や後継者には内容をお伝えし、遺留分に対する対応策も考えておくことが「まさかへの備え」になります。
また、遺言書の内容や形式に不備があると記載内容が無効になることもあるため、作成の際は相続に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。
4-2.生前に財産目録を作成・共有する
親や祖父母などが健在なうちに「財産目録」を作成してもらうのもトラブルを防ぐ効果が期待できます。
財産目録は、ある時点で保有する財産を一覧にした書類です。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなくローンやクレジットカードなどのマイナスの財産も記載します。
財産目録があれば、相続人は被相続人の財産を調査する負担が大きく減り、遺産分割の話し合いがスムーズに進みやすくなります。
とくに、代襲相続人は被相続人との関係が薄く、遺産の全貌を把握するのが難しいケースも多いため、他の相続人が遺産を隠してしまうなどのトラブルを防ぐ上で財産目録の存在が重要な役割を果たします。
また、財産目録には借金といったマイナスの財産も記載されるため、代襲相続人や法定相続人は相続を放棄すべきか判断しやすくなるでしょう。
ただし、財産目録だけでは遺産の分割方法を指定できないため、必要に応じて遺言書も作成することが大切です。
4-3.相続開始前に親族間で相続について話し合う
相続が始まる前に親族間で遺産の分割方法についてよく話し合っておくことが効果的です。
親や祖父母などが健在なうちに話し合いの場を設け、相続人や代襲相続人になる可能性がある人物同士でコミュニケーションを取り、連絡先を交換するなどして関係性を築くことでトラブルを防ぐ効果が期待できます。
また、被相続人が生前に「誰にどのような意図で財産を渡したいか」を親族に直接話すことで、遺言書の文面だけでは表現しきれない思いや願いを伝えられます。これにより、相続人間での理解が深まり円満な相続を実現しやすくなるでしょう。
年末年始やお盆など、親族が集まる機会に少しずつ話し合いを進めてみることをおすすめします。
4-4.生前贈与や死因贈与を検討する
遺産分割協議をすることになると、代襲相続人となる人物が十分な遺産を承継できない可能性がある場合は、生前贈与や死因贈与を活用する方法もあります。
- 生前贈与:存命中に財産を無償で渡すこと
- 死因贈与:亡くなったときに特定の財産を特定の人物へ渡す契約
生前贈与や死因贈与であれば、所有者本人が希望する人物に財産を渡すことが可能です。また、所有者が存命のうちに行うため、家族や親族に対して財産を渡す理由や事情などを丁寧に伝えて納得してもらうことで、遺産相続時のトラブルが生じにくくなる可能性があります。
祖父母のような直系尊属が孫に教育資金や住宅購入資金などを生前贈与する場合、特例を適用することで一定額まで贈与税が非課税となります。通常は、1年間の贈与財産110万円を超えると贈与税が課税されますが、特例を適用するとそれ以上の金額も非課税で贈与が可能です。
死因贈与で贈与された財産は相続税の課税対象にはなるものの、遺産分割協議の対象にはなりません
ただし「生前贈与や死因贈与で贈与された財産は遺留分の計算に含まれる」など、さまざまな注意点があります。贈与という形で財産を渡すときは、財産承継の専門家へ事前に相談することをおすすめします。
4-5.生命保険を活用する
生命保険に加入し、亡くなったときに代襲相続人となる人に保険金を受け取れるようにする方法もあります。
生命保険の死亡保険金は「受取人固有の財産」であり、遺産分割協議の対象にならないため、特定の人物に確実に財産を渡すことができます。
また、被保険者が亡くなったとき、受取人は保険会社に請求をすると数日程度で保険金が支払われるため 、葬儀費用や相続税の納税資金などの準備にも活用が可能です。
亡くなった人が契約者(保険料負担者)と被保険者(保険の対象となる人)の場合、死亡保険金はみなし相続財産であり相続税の課税対象です。一方、受取人が相続人(代襲相続人含む)であれば「500万円×法定相続人の数」までの死亡保険金が非課税となります。現金や預貯金などの形で遺産を承継する場合に、相続税を節税する効果も期待できる点も生命保険のメリットです。
4-6.家族信託を活用する
家族信託は、預貯金や不動産、有価証券など保有する財産の管理や運用、処分などを信頼する家族に任せることができる制度です。
財産の所有者は「委託者」として、信頼する家族を「受託者」に指定して信託契約を結ぶことで、受託者は契約内容にしたがってその財産の管理・運用・処分などを代わりに行います。
財産の運用・処分で得られた家賃や配当金などの利益は「受益者」が受け取ります。実務上では、委託者と受益者は同一人物となるのが一般的です。
家族信託であれば、遺言と同様に自身が亡くなったときの財産の承継方法を定めることが可能です。また「複数世代にわたる資産の承継先を指定できる」「認知症で法律行為ができなくなったあとも受託者に財産の管理や運用、処分を任せられる」といった遺言にはない機能もあります。
5.代襲相続でのトラブルの対策方法は専門家に相談を
代襲相続のよくあるトラブルとしては「代襲相続人を無視して遺産分割協議が進行した」「相続財産の情報を開示してもらえない」「遺産分割協議書への署名・押印を強要された」などが挙げられます。
トラブルを未然に防ぐためには、健在なうちに遺言書や財産目録を作成し、親族間で相続について話し合っておくことが効果的です。また、生前贈与や生命保険、家族信託などを活用する方法もあります。
青山財産ネットワークスでは、遺言書作成や生前贈与の支援など生前・相続対策サービスを行っています。代襲相続に備えた生前の相続対策を検討している方は、青山財産ネットワークスまでお気軽にご相談ください。
- 相澤 光Aizawa Hikaru
- コンサルティング事業本部 コンサルティングサービス室 室長 兼 第四事業部 ダイレクトグループ グループ長
不動産や法人を活用した財産防衛策の立案・実行に従事し、財産と想いを次世代に承継するための支援を提供。最適な選択肢を見つけられるよう、中立的な立場で家族全体の意向調整もサポートすることを信条とする。
当社の30年にわたるナレッジを集約した書籍を発行し、セミナー登壇実績も多数。
趣味:学び(税理士資格の勉強中)、ギター、サウナ
- 専門分野
- 土地持ち資産家、金融資産家向けコンサルティング
- 資格
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
- 著書
- 「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策