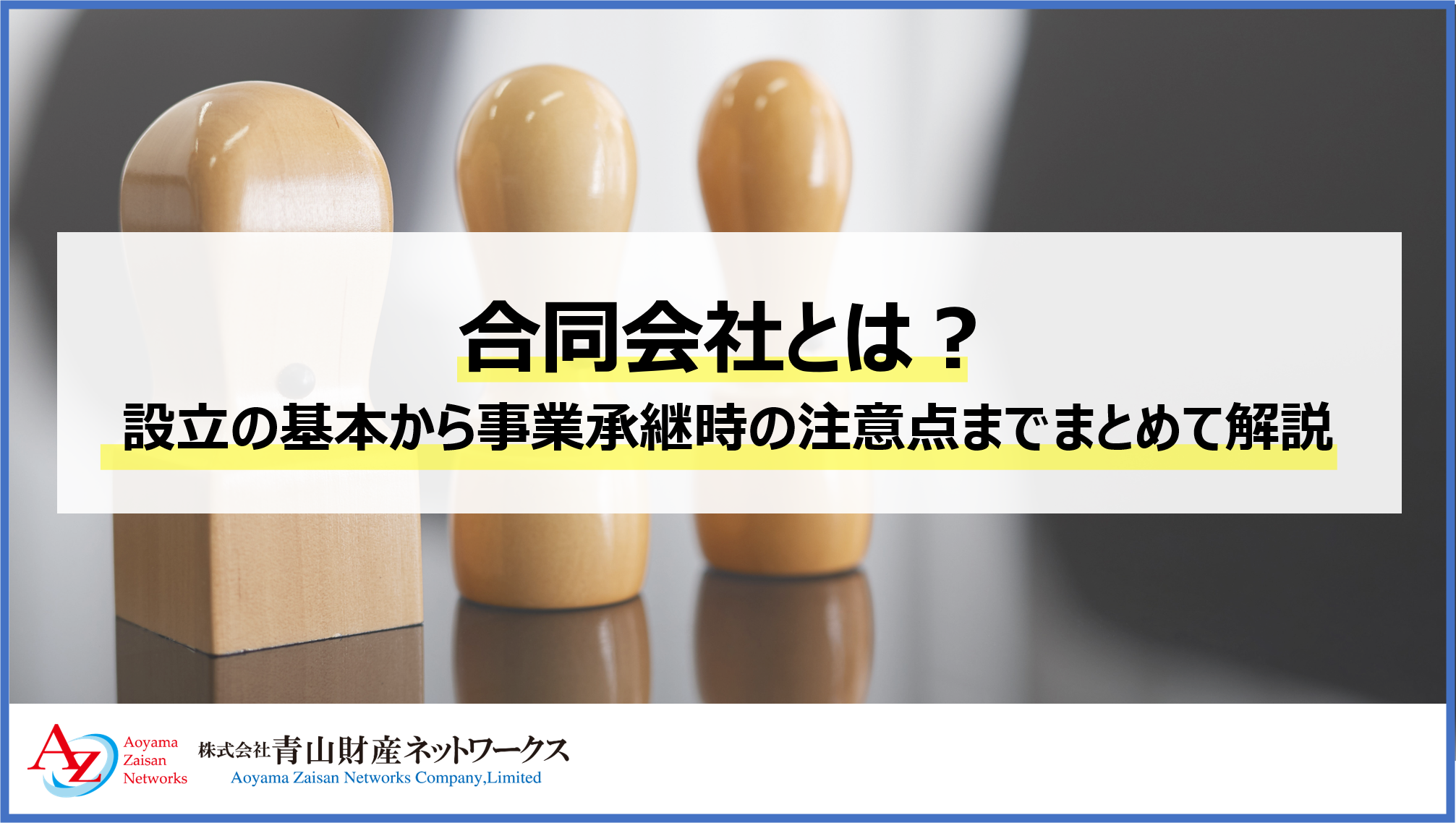近年、合同会社の設立は増加傾向にあります。2024年の新設法人全体に占める割合を見ると、株式会社が65.6%で最多ですが、合同会社は27.4%と次点であり、4社に1社が合同会社になっています。(出所:帝国データバンク「2024年「新設法人」動向調査」
合同会社が増加している理由は、株式会社と比べて、設立や維持にかかる費用や手間の負担が少ないことがあげられます。他方で、合同会社は持分会社という形態であるため、事業承継や相続あるいはM&Aにおいて、持分会社がどのような扱いや評価になるのか、疑問を感じることも多いでしょう。
そこで本記事では、合同会社のオーナー経営者や経営承継者を対象に、合同会社の事業承継や相続に際しての、持分の扱いや評価について解説します。
1.合同会社における「社員」と「持分」
最初に、合同会社が属する持分会社に特徴的な規定である「社員」と「持分」について、主に株式会社との比較を通じて解説します。
1-1.会社の種類
法律上の権利・義務の主体になることができる「人」には、自然人(人間)と法人(組織・団体)とがあります。法人には多くの種類(法人格)がありますが、その1つが「会社」です。会社とは、事業をおこない営利(利益)を上げることを目的としている組織で、会社法により規定されています。
会社法では、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類の会社が定められています。(旧有限会社法で規定されていた「有限会社」は、現在新設することはできませんが、特例有限会社として存続は可能です。)
なお、株式会社以外の「合同会社、合資会社、合名会社」は「持分会社」と総称されます(会社法第575条)。
1-2.合同会社における「社員」とは
日常用語では、「社員」は、会社と雇用契約を結んでいる従業員を指すことが一般的です。しかし、会社法上での「社員」とは、持分会社に出資して、会社の所有や経営に関与する構成員のことです。持分会社の社員は、株式会社における出資者である「株主」に似ており、どちらも会社に対する最終的な権利の帰属者です。簡単にいうと、会社が解散する際に、会社に帰属する財産(残余財産)が帰属する主体が、持分会社の社員、あるいは株式会社の株主になります。
しかし、他の面で、株主と社員とでは、与えられる権利や義務の範囲、内容に異なる部分があります。
1-2-1.株式会社は「所有と経営の分離」
株主は残余財産に対する権利だけではなく、会社に対する経営支配権も有しています。ただし、経営業務の執行は、株主総会で選出された取締役に委任します。その点で、株式会社「所有と経営の分離」により成り立つといわれます(実際上、中小企業では株主が取締役に就いている会社が大半ですが、その場合でも、形式的には株主総会での決議により取締役が選任されます)。
1-2-2.持分会社は社員が直接経営に関与する
持分会社の社員について、会社法では「社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する」と定めており(会社法第590条第1項)、社員は、出資者=会社の所有者であると同時に、経営業務を執行する者と規定されています。定款に定めれば経営業務執行を、社員以外の人に委任することは可能ですが、業務執行者としての最終的な責任は社員が負わなければなりません。
1-2-3.責任範囲の違い
株式会社の株主は、会社が倒産した場合などの債権者への責任について、出資額を限度とした有限責任が負わされています。出資額以上の賠償責任などを負う必要はありません。一方、持分会社の社員の責任は、会社の種類により異なります。
合同会社は、出資持分の範囲のみの責任を負う有限責任社員のみで構成されます。この点、株式会社の株主に似ています。他方、合資会社は、有限責任社員と無限責任社員とで構成されます。そして合名会社は、無限責任社員のみから構成されます。無限責任社員は出資額以上の賠償責任などを負わなければならない可能性があります。
1-3.持分会社における「持分」とは
持分会社における「持分」は、株式会社における「株式」に対応する概念です。
株式会社においては、出資者(株主)の出資割合や権利・義務(株主の地位)の割合は、株式により示されます。それと似て、持分会社において、出資者(社員)が出資した財産の割合や、会社に対して持つ権利・義務(社員の地位)の割合を示す概念が「持分」です。
1-3-1.持分会社における出資と持分との関係
株式会社における株式は、各株主の出資額に応じて割り当てられます。つまり株主としての権利・義務の割合は、出資額と比例しています。
一方、持分会社では、各社員の出資額と関係なく、各社員の持分の割合を定款で自由に定めることができます。
例えば、A、B、C、3人の社員が、A=20%、B=30%、C=50%の割合で出資をしているとします。その場合に、持分割合を、例えば各自3分の1ずつと均等にしてもよいのです(定款に特段の定めを設けなければ、出資割合に応じることになります)。
そこから、各社員への利益配当や社員総会(持分会社の最高意思決定機関。株式会社の株主総会に相当)での議決権割合も、定款で自由に定めることができます。例えば、上述のように出資割合が異なる3名の社員がいる場合に、社員総会の議決権は「1人1議決権」と決めても構いません。株式会社では、このような自由な設計はできません。
1-3-2.持分の数え方
株式は、発行済み株式数100株、保有株式数10株などと計数的に表すことができますが、持分はそのような計数的な数え方をすることはできません。各人の持分の保有量は、全体の出資額の33%とか、3分の1といった割合で表します。ただし、定款の定めや会計処理の便宜上、持分を「口」という単位で計数化することがあります。10%の保有を10口とする、といった具合です。
1-3-3.持分の移転(譲渡や相続)に対する制限
株式会社の株主が保有する株式は、原則的に自由に第三者に譲渡することができます(会社法第127条)。ただし、非上場企業で定款において、すべての株式の譲渡制限が定められている会社(=会社法上の非公開会社)の場合は、株主総会または取締役会の承認が必要です。
また株主が死亡した場合、株式は相続財産となり、株式を承継した相続人に株主の地位は承継されます(名義書き換えなどの手続きは必要です)。
一方、持分会社の社員(業務執行社員)が保有する持分を譲渡する際は、原則として他の社員全員の承諾が必要です(会社法第585条第1項)。ただし、定款で承諾要件を緩和する定めを設けることで、譲渡手続きを柔軟に設計することも可能です。
また、持分会社の社員が死亡した場合、原則として、その社員は退社することとなり持分が相続されることはありません。相続人には持分の払戻請求権が相続されます(ただし、定款で例外を規定できます)。
このような違いがあるのは、株式会社の株式が単に出資と出資者の権利・義務を表すものであるのに対して、持分会社の持分は出資者であることに加えて、経営を担う構成員であることを表すものであり、持分の移転が組織の人的な結び付きに変更を与えるものであることから、制限的になっていると理解できます。
2.合同会社の持分の「評価」の意義
そもそも、持分を「評価する」とはどういう意味であって、どんなときにそれが必要となるのでしょうか。以下では、合同会社を前提に説明していきます。
2-1.合同会社の持分の評価とは
合同会社の持分保有者(社員)は、会社に対して利益配分や残余財産分配などを請求できる財産的な権利を有しています。そのため、持分は財産的な価値を持つものと考えられます。
その財産的な価値は、その時点での会社の財務(資産・負債)状況等により異なります。そこで、現時点で持分の財産的な価値を金銭に換算したら"いくら"になるのか、見積もることを「持分の評価」といいます。
上記の説明からわかるように、持分の評価額は会社の財産状況により異なるものとなるため、必ずしも出資額=評価額とはならない点に留意してください。
2-2.持分の評価の種類
持分の評価は目的によって、市場価値評価と、課税財産評価とに大別できます。
前者は、持分の払戻しや譲渡などの際に、いくらで払戻しや譲渡をするのかという価格を決定するための評価です。事業承継の計画において、後継者への持分移転のコスト試算や、M&A時の企業価値の提示、さらには資金調達時の担保価値の算定など、経営戦略の判断材料となります。
後者は、相続税、贈与税、所得税などの課税額を算定する際に、持分の課税財産としての価格を求めるための評価です。経営者として、事業承継や相続における課税コストを予測し、対策を講じる上では、なるべく正確な評価を把握しておくことは大切です。
市場価値評価や課税財産評価が必要されるのは、持分になんらかの変化や移転が生じる場合が多いでしょう。代表的なケースとしては、「退社時の払戻し」「相続・贈与」「譲渡」が想定されます。
3.退社時の払戻しに関連する持分評価
株式会社では、株主が会社に対して出資金の払戻し(返還)を請求することはできません。その代わり、原則的に株式の譲渡は認められているため、株式を換金したい場合は第三者(株式の発行会社を含む)に株式を譲渡して対価を得る方法を採ることができます。
一方、持分会社の場合は、持分の譲渡を自由におこなうことができません。その代わり、会社法で、出資金の払戻しが規定されています。「出資の払戻し」(会社法第624条)と「退社に伴う持分の払戻し」(同第611条)です。
「出資の払戻し」の規定による払戻しは、社員が請求した場合におこなわれるもので、出資金の一部の払戻しであれば、社員のままで請求することもできます。
ただし、合同会社の場合、定款を変更して出資の価額を変更する手続きが必要であり、また払戻金額にも一定の制限があります。社員でいるままで、出資金の一部だけを払戻してもらうというのは、実務上かなりレアケースだと思われます。
他方、「退社に伴う持分の払戻し」では、会社法第611条に「退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる」とあり、社員が退社する場合に、原則的におこなわれる手続きとされています。
そこで以下では、一般的な「退社に伴う持分の払戻し」の場合における、持分の評価方法、課税関係、および手続きについて解説します。
3-1.退社に伴って払い戻される持分額の算定
「持分が払い戻される」と聞くと、出資した金額がそのまま返還されるようなイメージを持つかもしれません。しかし、払い戻される持分の金額について会社法では、「退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない」(会社法第611条第2項)と規定されています。つまり出資額そのままではなく、その時点での会社の財務状況に応じた「時価」での財産額を把握した上で、その額を、退社する社員の出資割合に応じて按分して算定された額が払い戻されます。
3-1-1.払戻金額の算定方法に法律の規定はない
なお、この「時価」を計算する具体的な方法については、法律に規定はありません。一般的には、貸借対照表を時価で洗い直して計算する時価純資産方式や類似業種比準価額方式、時価純資産額とDCF(Discounted Cash Flow)法による評価を混合する方式などが用いられます。DCF法は、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて企業価値を算出する方法です。また、類似業種比準価額方式は、同業他社の財務指標を参考に評価額を算定する方法です。
どのような計算根拠を用いるのかについては、定款に定めておくことが一般的です。
会社の財務状況に応じて払戻金額は変わり、出資額よりも多くなることもあれば、少なくなることもあります。もし会社が債務超過(時価純資産額がゼロ以下)であれば、通常払戻金額はゼロとなります。
3-1-2.手続き上の注意
払戻金額が、会社の剰余金(資本剰余金+利益剰余金)の額を超える場合、官報公告等の債権者保護手続きが必要となります(会社法第635条)。また、払戻額が資本金減少(減資)を伴う場合は、それとは別に、債権者保護手続きが必要となります(会社法627条)。
3-1-3.払い戻される持分金額の計算例
【設例】
退社する社員が出資した金額:300万円(社員全員の出資額の合計:1,500万円)
退社する社員の持分割合:20%
払戻額の算定方法:時価純資産額に応じて按分すると定款に規定
退社時における会社の時価純資産額:3,000万円
【払い戻される持分金額】
3,000万円×20%=600万円
3-2.持分払戻金額の課税評価
社員が退社した場合に受ける持分の払戻金額は、所得税等の課税対象となる場合があります。その計算方法は、以下のようになります。
3-2-1.払戻し金が純資産のどこから支払われるのかを確認
まず、払戻しの原資となる合同会社の純資産は、大きく分けて下記からなります。
(A)資本等(資本金、資本剰余金)
(B)利益剰余金
会社は、払戻金額を(A)(B)のどちらから拠出するのかを区分する必要があります。
払戻金額=(A)資本等からの払戻し+(B)利益剰余金からの払戻し
3-2-2.払戻し金の内訳ごとの所得区分と課税関係
社員が受け取る払戻金額のうち、(A)に該当する部分は「譲渡収入」、(B)に該当する部分は利益配当に類似した性質を持つ所得である「みなし配当所得」とされます。
払戻金額=譲渡収入+みなし配当所得
この譲渡収入のうち、①「その社員による出資額」までの部分は、もともと自分のお金だったものを返してもらう意味があり、非課税とされます。
また、もし出資額を超える譲渡収入((A)部分からの払戻し)がある場合は、②「譲渡所得」とされます。(出資額を超える譲渡収入がなければ、譲渡所得はゼロ)。
②譲渡所得=(A)譲渡収入-①出資額
以上をまとめると、以下のようになります。
払戻金額=(①出資額+②譲渡所得)+(B)みなし配当所得
| 原資の区分 | 内容 | 所得の種類 | 課税 |
|---|---|---|---|
| (A)資本等 | ①払戻金額のうち「資本金等からの払戻し」部分で、出資額(社員が払い込んだ金額)までの部分 | 所得ではない | 非課税 |
| ②払戻金額のうち「資本金等からの払戻し」部分で、社員が払い込んだ金額(出資額)を超える部分 | 譲渡所得 | 譲渡所得課税 | |
| (B)利益剰余金 | 払戻金額のうち「利益剰余金からの払戻し」部分 | みなし配当所得 | 配当所得課税 |
なお、②の譲渡所得課税は、株式等の譲渡の場合と同じ20.315%(所得税、復興特別税、住民税の合計)で申告分離課税となります
また、③の配当所得課税は、総合課税となります。実務上は、会社が払戻金を支払う際に、源泉徴収をおこないます。
3-2-3.課税評価額の計算例
【設例】
退社する社員が出資した金額:300万円(社員全員の出資額の合計:1,500万円)
退社する社員の持分割合:20%
払戻額の算定方法:時価純資産額に応じて按分すると定款に規定
退社時における会社の時価純資産額:3,000万円(うち、資本金1,000万円、資本剰余金500万円、利益剰余金1,500万円)
【払い戻される持分金額】
3,000万円×20%=600万円
(600万円のうち、300万円は資本剰余金から、300万円は利益剰余金から支払われる)
【課税表額】
・300万円は、出資額相当であり、非課税。
・出資額相当を超える譲渡所得はゼロ。
・300万円はみなし配当所得として配当課税(配当課税は他の所得と合算した総合所得となるため、課税額は他の所得による)
4.相続税法における持分評価
合同会社の持分が相続や贈与される場合、原則として課税財産(相続税や贈与税が課税される対象)となります。その場合、いくらの評価額(課税価格)となるのかは、相続税法上で規定されている財産評価方法によります。そして、相続税法上の財産評価法は、上記3の項目で説明した所得税法上の評価とは基準が異なることに、注意が必要です。
また、合同会社の持分の相続が、大きく2つのパターンがある点も要注意です。
4-1.持分の相続①定款に持分の承継の規定がない場合、相続人は「持分の払戻請求権」を相続する
合同会社の社員は死亡すると退社します(会社法第607条第1項第3号)。その場合の持分の相続については、「相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる」(同第608条第1項)と定められています。
この「定款で定めることができる」という規定は、逆にいうと、定款で特段の定めをしていなければ、相続人は持分を承継できないということです。その場合は、当然、相続人が社員の地位を承継することもありません。
では、定款の定めがない場合、相続人は持分に関してなにも相続できないのかといえばそうでなく、「払戻請求権」つまり出資持分相当額の金銭の交付を会社に請求する権利(債権)を相続することとされます。被相続人(死亡した社員)が、もし存命中に退社していたとすると、持分の払戻しを受ける権利があります。その権利を相続したと考えるのです。
4-1-1.払戻請求権に基づいて払い戻す場合の会社による持分の評価
相続人は、相続した持分の払戻請求権に基づいて、持分の払戻しを会社に対して請求し、払戻しを受けることができます。
この場合の払戻金額の算定方法は、法律で定められていません。そのため、会社は定款の定めなどに基づいた計算方法で払戻金額を決定します。
実務上は、次に述べる課税評価額の算定と同様に、相続発生時点での時価純資産をベースとして、それに被相続人の持分の割合を乗じた金額とすることが多いようです。
相続人がそれ以外のDCF法等に基づいた評価を主張したり、会社がそのような計算で算定したりすることも可能です。ただし、課税上の問題が生じる場合があります。この点は、4-1-4で確認します。
4-1-2.払戻請求権の課税評価
相続により承継された払戻請求権は、相続税の課税財産となります。その評価方法は、下記となります。
相続発生時点における会社の時価純資産額×被相続人の持分の割合
(時価純資産額は、財産評価基本通達に基づき、資産を時価評価し負債を控除して求める)
4-1-3.課税評価額の計算例
【設例】
死亡した社員が出資した金額:300万円(社員全員の出資額の合計:1,500万円)
死亡した社員の持分割合:20%
退社時における会社の時価純資産額:3,000万円
【払戻請求権の相続課税財産評価額】
3,000万円×20%=600万円
4-1-4.実際の払戻金額と課税評価額に差異がある場合
上記の課税評価額は、あくまで相続税を計算するための相続財産としての評価額です。4-1-1で述べたように、多くの場合、会社はその評価額に準拠して払戻額を決定しています。ただし、必ずしもそうしなければならないわけではなく、実際の払戻額が課税評価額よりも大きいことも、小さいこともありえます。
その場合でも、相続税上の課税評価は、あくまで4-1-2に示した計算方法による評価額となります。相続税課税評価額(ひいては相続税額)は、実際の交付金額とは無関係に定められるものです。
4-1-5.実際の払戻金額にみなし配当所得が含まれる場合
払戻金額が「資本等の金額」を超える場合、その超えた金額部分は"被相続人への"みなし配当所得とされます(相続人の所得ではない点に注意)。
相続人は、相続発生から4か月以内に被相続人の準確定申告をおこない、必要に応じてみなし配当所得にかかる納税をします。
4-1-5.持分の払戻請求権が債権であることによる留意点
持分の払戻請求権は、株式の相続のような有価証券の相続ではなく、請求権という債権の相続です。そのため、相続税課税評価額の計算においては純資産価額に基づき評価するものの、株式の相続において純資産価額で評価する場合に適用される法人税相当額の控除等はできません。また、評価計算方法に配当還元方式を用いることもできません。
4-2.持分の相続②定款に規定がある場合、相続人は持分を承継して社員となる
合同会社の定款に、「社員が死亡した場合、一般承継人が持分を承継する」といった定めがある場合、被相続人の持分は相続人が承継し、相続人は合同会社の社員となります。
この場合、その時点で持分の払戻しはないため、会社による持分の評価や所得税課税の問題は生じません。
4-2-1.持分会社の出資の課税評価
このケースでは「持分会社の出資」が相続されたものとして評価されます。
持分会社の出資については、財産評価基本通達194「持分会社の出資の評価」や、国税庁質疑応答事例において「取引相場のない株式の評価方法に準じて評価する」ものとされています。
「取引相場のない株式」とは、一般的に売買されることのない非上場企業の株式のことです。その評価方法は、財産評価基本通達178~193に定められていますが、かなり複雑なためここでは詳細には立ち入らず、どのような評価方法があるのかについてのみ確認します。
取引相場のない株式の評価方法には、下記のような種類があります。
取引相場のない株式の評価方式は、株主構成や株式を承継する株主の所属により、原則的評価方式(純資産価額方式、類似業種比準価額方式、併用方式)と特例的評価方式(配当還元方式)に分かれます。その上で、原則的評価方式の場合に、どの方式を用いるのかを、評価会社の規模、特定会社(株式保有特定会社、土地保有特定会社などの資産管理会社、等)に該当するか等により定めていきます。
例えば、同族株主が50%超の株式を保有する場合や、会社規模が「小会社」に該当する場合は純資産価額方式が適用され、評価額が高くなる傾向があります。
4-2-2.贈与の際の課税評価
持分を贈与する場合、受贈者(贈与を受ける人)の年間受像額が贈与税の基礎控除(年110万円)を超える場合は、受贈者に贈与税が課税されます。贈与された持分の財産評価は、上記の相続の評価に準じます。
5.持分を譲渡する場合の評価
合同会社(持分会社)の社員が持分を譲渡することに関して、会社法では、「社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない」(会社法第585条第1項)と定めています
つまり、他の社員全員の承諾があれば、持分を譲渡することは可能です(業務非執行社員の場合は、業務執行社員全員の承諾によります(同第2項))。
ただし、全員の承諾はハードルが高く、また、定款の変更・登記など、事務的な手続きも煩雑です。
そもそも、合同会社などの持分会社は、社員が出資すると同時に経営にも関与し、人的つながりの強い小規模な組織であることが一般的です。そのため、社員間での譲渡の場合を除き、特別な事情がない限り第三者への持分譲渡がおこなわれるケースは非常にまれだと思われます。
5-1.合同会社のM&A譲渡による事業承継はできるか?
株式会社の事業承継においては、親族内、社内に後継者がいない場合の、いわゆる第三者承継としてのM&A譲渡は、中小企業でもかなり一般化してきました。
では、合同会社ではどうかといえば、合同会社のM&A譲渡による事業承継は、現在のところ、かなりレアケースのようです。
その理由として、まず合同会社の数自体が少ない(新設法人の約4分の1)ことに加えて、株式会社とくらべて小組織で、小規模に事業をおこなっているが多いため、買い手の認知度が低く、譲り受けニーズが少ないという点があります。
それに加えて、上述のように持分譲渡は社員全員の同意が必要など、手続きの敷居が高いことや、株式会社と異なる内部統制、財務・税務などになじみがないといったことも、M&Aが少ない理由のようです。
ただし、合同会社がおこなっている事業そのものが優良であれば、譲り受けニーズが存在するケースはもちろんあります。
そのような場合、合同会社の持分を譲渡するのではなく、①合同会社を株式会社に組織変更してから、株式譲渡する、②特定事業のみを対象とした事業譲渡をする、といった方法により、M&Aを実施して事業承継がおこなわれることが一般的です。
5-2.持分を譲渡する場合の価値評価(バリュエーション)
持分を譲渡する場合は、売り手と買い手の相対取引となります。譲渡価格は原則的に、両者が合意できれば、どのように定めても自由です。ただし、通常は、株式会社のM&Aで一般的に用いられている企業価値評価(バリュエーション)の方法に準じて、その持分の時価を合理的に評価します。
経済合理性のある算定基準に基づいた評価がなされなければ、通常は売買が成立しません。また、課税評価上の時価と乖離した価格での譲渡は、課税上の問題が生じる場合があります。
5-2-1.持分譲渡の際の代表的な価値評価方法
M&Aなどで持分を譲渡する場合の、代表的な価値算定方式には下記のようなものがあります。
5-2-2.持分を譲渡して得た所得に対する課税評価
社員が保有する合同会社の持分を第三者に譲渡(売却)して収入を得た場合、以下の算式により、課税対象となる譲渡所得を求めます。取得原価とは、払い込んだ出資金額、譲渡費用とは、譲渡に際して必要となった手数料などです。
譲渡価額(譲渡収入)-(取得価額+譲渡費用)=譲渡所得
この譲渡所得に対する課税は、株式等に係る譲渡所得等として、20.315%の申告分離課税となります。
5-3 高額・低額な譲渡による課税関係
持分の譲渡において、時価(適正価格)から大きく乖離した(低額または高額な)価格で譲渡がおこなわれた場合、課税上の問題が生じる場合があります。なお、この場合の時価は、相続税評価額(4-2-1.持分会社の出資の課税評価を参照)を基準とします。
個人が売り手で、著しく高額な価格で持分を譲渡した場合、売り手個人には、上述の譲渡所得課税のほか、時価と譲渡価格との差額に贈与税(買い手が個人)または一時所得の所得税(買い手が法人)が課税させる場合があります。
また、適正時価よりも、著しく低額で譲渡した場合で、買い手が個人の場合、買い手の個人に贈与税が課税される場合があります。
さらに、買い手が法人で価格が適正時価の2分の1未満の場合、売り手の個人には時価で譲渡したものとみなして所得税が計算され、買い手の法人には法人税が課税される場合があります。
これらの追加的な課税を避けるためには、税理士など第三者の見解も採り入れながら、時価からあまり乖離しない価格を設定することがポイントです。
6.合同会社の事業承継と持分評価対策
最後に、合同会社の事業承継における注意点を、特に持分の評価や移転に関連するポイント絞ってまとめます。
6-1.持分の移動や社員の地位についての定款の整備を進める
すでに見てきたように、合同会社の持分は、その譲渡に際して社員全員の承諾が必要となり自由に譲渡できないこと、社員が死亡した場合、定款に定めがなければ相続人が持分を承継して社員になることができないこと、などの制限があります。
これらのことを知らなかったり失念していたりして、なんの準備もしておかないと、いざ後継者に事業承継をしようとしたとき、不可能になる恐れもあります。
反面で、合同会社には株式会社より幅広い定款自治が認められています。
その特徴を理解した上で、例えば、社員間の持分譲渡については承諾要件を緩和したり、社員が死亡した場合には相続人が持分を承継して社員になる旨を定款に定めたりしておくことがなによりも重要です。
6-1-1.1人合同会社は特に注意
特に注意しなければならないのは、社員が1人だけの合同会社です。このような合同会社において、社員が死亡した場合に相続人が持分を承継できる旨を定款に定めていなければ、社員が死亡すると社員ゼロになり、その時点で会社を解散しなければならなくなります。1人合同会社の場合、定款に「相続人が持分を承継する」旨を明記するか、予備的に後継社員を指定する定款変更をおこなうことで、解散リスクを回避できます。
6-2. 持分の課税評価の仕組みを理解し、適切な準備を行う
合同会社の持分は、相続や贈与の際に「取引相場のない株式」として評価されるため、評価方法や会社の状況によって課税評価額が変動します。評価方法には複数あり、一般的には以下のような傾向があります。
- 配当還元方式:配当額を基準に評価され、評価額が比較的低くなる傾向
- 類似業種比準方式:配当、利益、簿価純資産の3要素を基準に評価
- 純資産価額方式:会社の純資産を基準に評価され、評価額が高くなる傾向
これらの評価方法は、会社の規模や業績などの要件によって適用が異なります。たとえば、会社規模が「小会社」と判定されると、純資産価額方式が適用されるため、総資産や売上の増加により「小会社」に該当しないようにすることで、評価方法の選択肢が広がる可能性があります。
また、以下のような要因も評価額に影響を与えることがあります。
- 役員退職金の支給:退職金の支給により純資産が減少し、純資産価額方式による評価額に影響を与える可能性があります
- 類似業種比準方式の3要素の変動:配当、利益、簿価純資産の水準が評価額に影響します。
- 持株会社の設立:持分の管理や移転の方法に影響を与える可能性があります。
- 贈与税の非課税枠の活用:長期的な持分移転により、評価額の変動リスクを分散することができます。
これらの要因を理解し、事前に準備を行うことで、持分の評価に対する影響を適切に把握し、円滑な事業承継や資産移転につなげることが可能です。
まとめ
合同会社の持分の評価は、特に事業承継の準備をする際の重要な要素です。合同会社の経営者や後継候補者であれば、まず、その評価方法の基本はしっかりと理解しておきましょう。
その上で、これから事業承継準備に着手されるのであれば、①定款の見直し:持分譲渡や相続時の承継ルールを明確化。②持分評価額の事前試算:税理士と協力し、持分評価額、相続税や譲渡所得税等と試算する。③専門家の活用:法務・税務の専門家(例:青山財産ネットワークス)に相談し、計画的な承継準備を進める、の順で取り組まれるとよいでしょう。