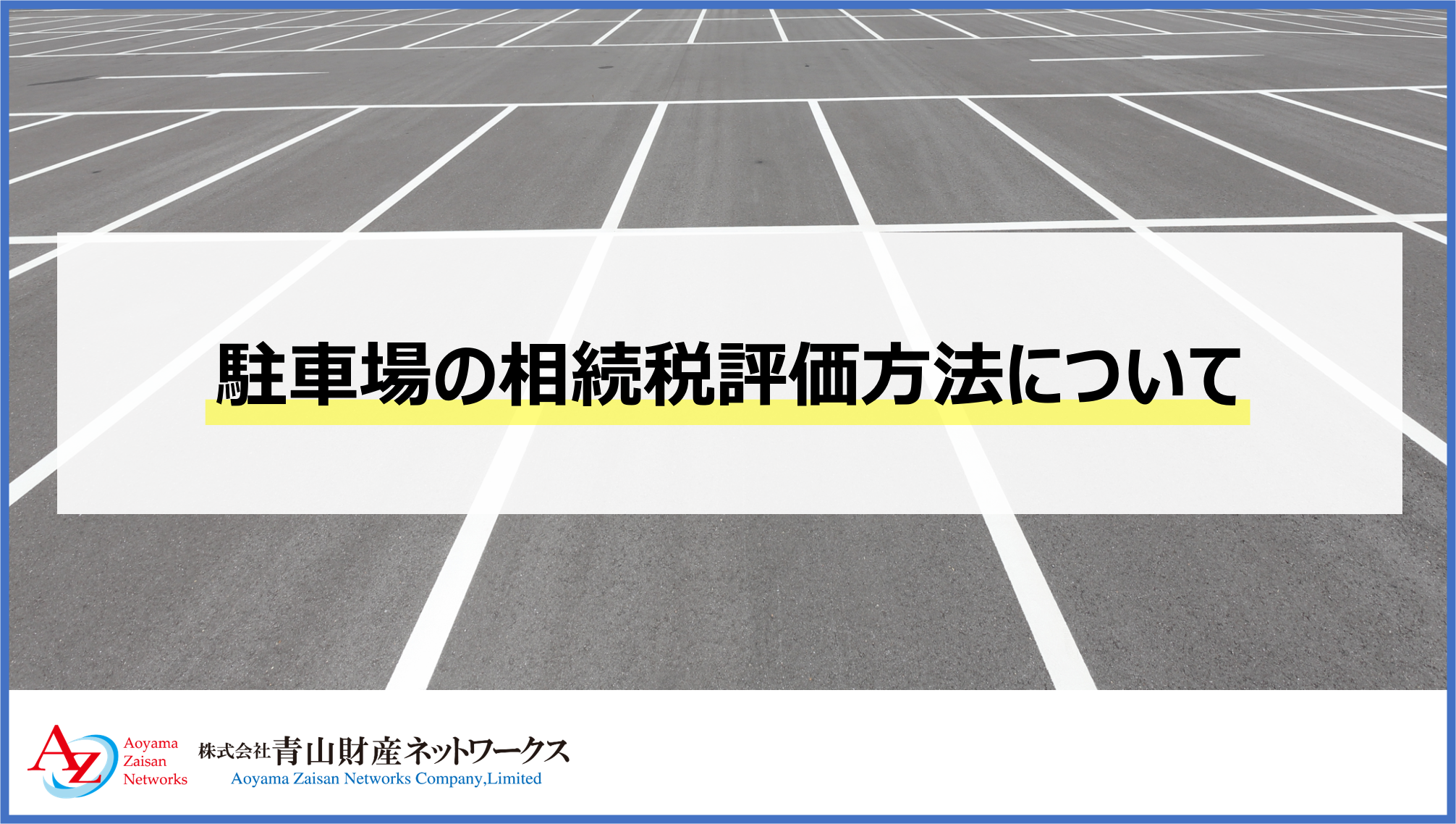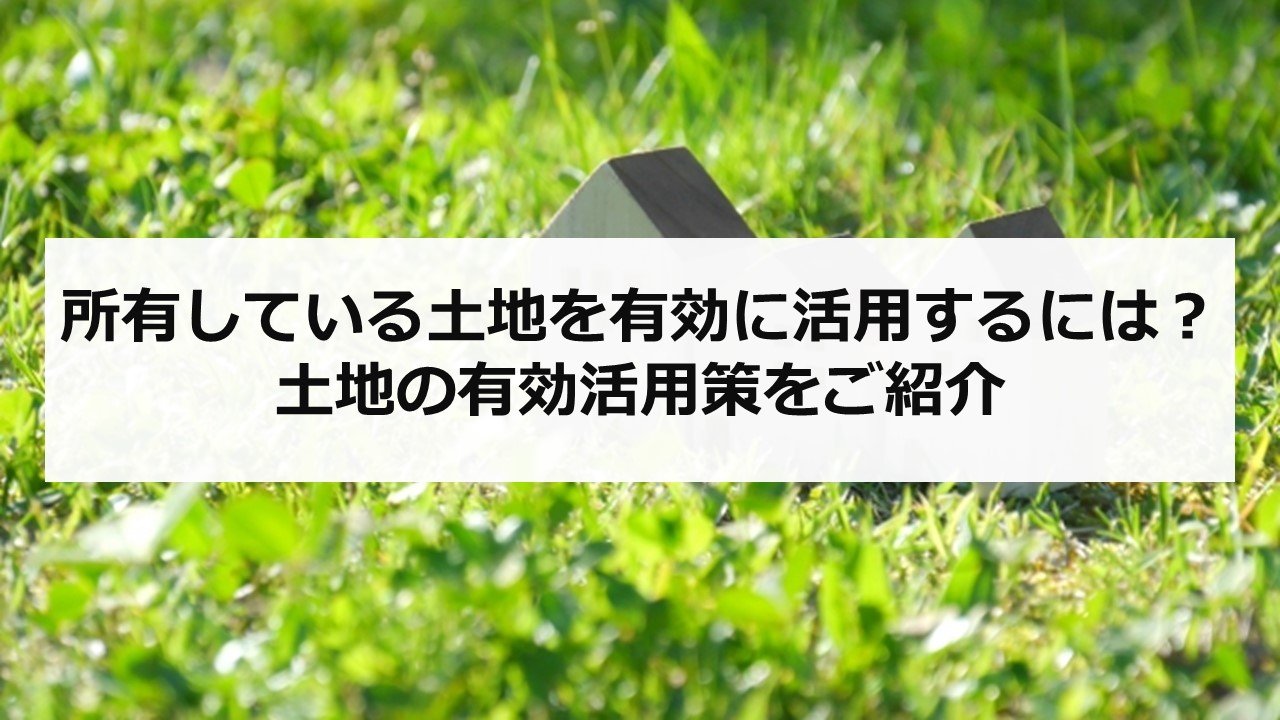土地を相続した人の中には土地の有効活用を考えている人も多いと思います
土地活用の中には経営が難しいものや高額の費用がかかるもの、専門知識が要求されるものもあり、予想以上の労力がかかる場合もあります。
そのため、土地活用は相続した土地に適合した活用方法を選ぶことが重要です。
本記事では相続した土地の活用方法、活用方法の選択時のチェックポイントなどを詳しく解説します。
相続した土地を活用しないリスク
相続により土地を取得できても、活用しなければリスクが発生します。その場合の主なリスクは下記の3つです。
- 固定資産税などの維持費を払い続ける
- 空き地や空き家の管理義務を負う
- 次の相続が発生すると、また相続税を負担することになる
固定資産税などの維持費がかかる
相続した土地を活用する、しないに関わらず、土地を所有することにより固定資産税などの維持費はかかります。
固定資産税のほかにも、土地の維持管理費は別途発生します。
このように相続した土地は所有しておくだけでコストがかかるので、手放す予定がないのであれば、活用の検討をおすすめします。
空き地・空き家の管理リスク
土地を相続すれば自動的に管理義務を負うことになります。
相続した空地を管理しないでおくと、防災や防犯の観点から以下のようなリスクが発生します。
- 空地や空き家への放火リスク
- 不法投棄場所に使われるリスク
- 空き家が老朽化してしまい災害時に壊れるリスク
- 空き家が犯罪に使われるリスク
- 景観悪化による近隣住民からの苦情が発生するリスク
例えば空き家が老朽化し倒壊した際に、通行人がケガをしたり、隣家の塀や住宅を壊したりしてしまうと、損害賠償請求されるおそれもあります。
このように、相続した土地をそのままにしておくと、コストだけでなくさまざまなリスクも発生してしまいます。
相続した土地の活用方法を選択するときの5つのポイント
相続した土地の活用方法を選択するにあたり、チェックしてほしいポイントは次のとおりです。
- 土地の用途を制限する法的規制の確認
- 周辺地域のニーズと需給バランスの調査
- 自分で経営できる方法かを見極める
- 初期投資と収支のシミュレーション
- 活用手法ごとのリスクを把握する
土地の用途を制限する法的規制の確認
さまざまな法令や規制により、土地の活用方法は制限されます。
■代表的な法規制
・都市計画法:建物の建築を制限
・宅地造成等規制法:宅地造成を制限
・農地法:農地以外の活用を制限
・都市緑地法:良好な都市環境を守るための法律
・地すべり等防止法:災害防止のために活用を制限
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律:災害防止のために活用を制限
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律:災害防止のために活用を制限
周辺地域のニーズと需給バランスの調査
周辺地域の市場調査も忘れずに行う必要があります。駐車場を経営したとしても、周りに駐車場がたくさんあり、そこに空きスペースが多ければ、その候補地では供給が需要を上回っています。
そこで駐車場を始めても固定資産税や所得税の負担後に、安定した収益を得続けるのは難しくなるでしょう。
下記の方法で周辺地域の傾向を把握することをおすすめします。
駐車場:直接現地に出向いて周辺地域の駐車場の利用状況を確認する、または駐車場検索サイトで利用状況を確認する
トランクルーム:トランクルーム検索サイトで利用状況を確認する
戸建て賃貸:不動産会社に問い合わせる
県や市区町村のホームページでも人口などの動向や統計を確認できます。
本格的に地域の需要を確認したい場合は、土地活用に特化している不動産会社に相談するとよいでしょう。
自分で経営できる方法かを見極める
興味のある土地活用方法でも、自分の経営能力に見合っているか否か冷静に考える必要があります。土地活用方法によってはプロ級の専門知識や高額の費用を要求されるものもあります。自分の身の丈に合った方法を選ぶことが大切です。
建物を建設する場合の費用など、初期費用がどれくらい必要かに関しては土地活用の専門家に相談するのがおすすめです。客観的なアドバイスをしてくれるでしょう。
自身で経営できない場合は、土地を業者に貸して経営代行してもらうのも選択肢の一つです。代行手数料を支払うため収入は減りますが、経営で頭を悩ませなくて済みます。
初期投資と収支のシミュレーション
相続した土地を活用する際には、収支のシミュレーションが必要です。
なぜなら土地を活用しても利益が出なければ、維持費や負債ばかりかさみ収支がマイナスになるからです。
例えばアパートやマンションの賃貸経営をするケースでは、主に以下の初期コストや維持コストがかかります。
- アパートやマンションの建築資金
- 不動産投資ローン(例えばアパートローン)の支払金利
- 土地や建物にかかる固定資産税
- アパートやマンションの共用部分の公共料金
- アパートやマンションのリノベーション費用
- アパートやマンションの管理費用
- アパートやマンションの損害保険料(例:火災保険料、地震保険料)
活用手法ごとのリスクを把握する
リスクを把握しないまま土地活用を始めてしまうと、思わぬ事態が発生した際にキャッシュフローが悪化してしまう可能性があります。
例えば賃貸マンションやアパート経営を行う際のリスクは、主に以下のとおりです。
- 空室リスク
- 賃料の変動リスク
- アパートローンの金利変動リスク
- 建物の老朽化リスク
- 家賃の滞納リスク
- 入居者によるトラブルリスク
- 災害リスク
土地の活用方法や活用する土地の立地、状況によっても、リスクの大きさや種類は異なります。
土地活用を行う際には、信頼できる不動産会社や土地活用業者に相談し、リスクの説明をしてもらいましょう。
相続した土地の活用方法
相続した土地の活用方法として一般的なものとして、下記の6つが挙げられます。
- 駐車場
- 太陽光発電
- トランクルームやコインランドリー
- 戸建て賃貸
- 賃貸マンションやアパート
- 売却
この他にも、有料老人ホームや認可保育園等の社会福祉施設も挙げられます。建築費等の事業コストが増加している中で、市や区からの補助金を受けられるケースもあり、リスクが低く安定した賃貸経営を行えることにもつながります。但し、向いている土地や、行政などの補助金の指定などの制約条件があるため、検討している土地で、どのような活用が向いているのか、利用できる特例等についての情報を幅広く抑えることが、土地有効活用のスタートと考えられます。
それぞれ見ていきましょう
駐車場

駐車場経営は、毎月安定した収入を得やすい土地の活用方法です。
さらに駐車場の建設費用は、マンションやアパートの建設と比較すると費用も安いので、初期費用をそれほどかけたくない方に向いています。
駐車場経営は、月極駐車場とコインパーキングに分けられます。
月極駐車場の収入とコスト
月極駐車場の収入は利用客からの賃料収入です。利用客とは月額契約を結びますが、その金額は面積や立地条件によって大きく変動します。
<主な初期費用>
月極駐車場経営を始めるには、主に駐車スペースの整備費用と必要な設備投資がかかります。
土地を駐車場として利用するために最低限必要な整備費用は以下の通りです。
- アスファルト舗装:1平方メートルあたり約3,000~5,000円が目安
- 区画線引き: 車1台分のスペース(約2.5m×5m)につき1,000~2,000円かかります
駐車場の安全性や利便性を高めるための設備費用は以下の通りです
- 防犯カメラ: 1台あたり約30,000~100,000円
- 照明設備: LED照明1基あたり約20,000~50,000円
- 看板設置: 月極駐車場の案内や利用規約を明示するための看板作成に10,000~30,000円
<主な運営費用>
- 集金費: 自分で集金を行う場合は発生しません。
- 清掃費: 業者に委託する場合は発生しますが、自分で行う場合は基本的に不要です。
- 電気代: 駐車場に照明などを設置している場合に発生します。
- 保険料: 火災保険や損害賠償責任保険に加入する際に必要となります。
- 町内会費: エリアによっては支払いが発生する可能性があります。
その他、各種税金などがかかります。
コインパーキング経営の収入とコスト
主な初期費用
- アスファルト舗装:1㎡につき約5,000円
- 精算機:40~50万円
- フラット板:1台につき約10万円
- 照明・看板設置:約70万円
主な運営費用
- メンテナンス・修理費
- 業者への管理・運営料の支払い
- 各種税金
月極駐車場のメリット
- 土地を舗装しなくても運営することができる
- 長期契約が多いため、収入が安定しやすく、未払いが少ない
- フラップ板や精算機といった設備が不要なため、いつでも事業を始められ、初期費用も抑えられる
月極駐車場のデメリット
- 競合他社の多い地域では整備されている駐車場に人気が集まる傾向がある
- 定期的な巡回や防犯カメラの設置といった対策が必要である
- 借り手が見つからず、長期間空きスペースが生じるリスクがある
コインパーキング経営のメリット
- 管理を委託することで手間がかからない(ただし、月々の管理費用が発生するため、初期費用の抑制とあわせて、長期的なコストバランスの見極めが重要)
- 立地が良ければ高い稼働率を期待できる
- 変形地や狭小地など、本来活用しにくい土地でも経営できる可能性がある
コインパーキング経営のデメリット
- 立地条件によっては空車のリスクがある
- 出入り口のゲート・フラップ板・照明・精算機などの設備投資が必要なため、自主運営で始める場合は初期費用が高くなる
- 賃料以上の収入は得られない
駐車場経営に向いている人
- 初期費用を抑えたい人(特に、一括借り上げ方式の場合)
- 手間をかけたくない人(特に、一括借り上げ方式や管理を業者に委託する場合 )
駐車場に向いている土地
- 人の多い住宅地や繁華街
- 5坪以上の土地
駐車場の経営方式
自主管理方式:
- 施工から管理まで自分自身で行う
- 管理費用がかからないため利益は最大化できるが、手間や時間的負担がかかる
管理委託方式:
- 業者が駐車場の管理を行う
- 管理費用がかかるため利益は減るが、手間を省ける
一括借り上げ方式:
- 運営会社が施工集客・管理を一括して行うため、利益は少ないが最も手間がかからない方式
- 駐車場の契約状況に関わらず賃料は固定となる
- フリーレントで初期費用負担を0にすることもできる
(フリーレントとは、本来であれば土地オーナーが支出する初期費用を運営会社が立て替え、初期費用を毎月の賃料で相殺する仕組みです。)
経営に時間や労力をかけられない、あるいは集客に自信がないときは管理委託方式か一括借り上げ方式をおすすめします。
太陽光発電
土地に太陽光パネルを設置し、電気の売却により収益を生み出します。
自ら経営するほか、土地を太陽光発電業者に貸して賃料を得るという方法もあります。
固定価格買取制度の利用により、国が最長20年間は電気を買い取ってくれるため、集客しなくても当面の間は収支が安定しやすいでしょう。
太陽光発電の最大の強みは、長期間の安定収入が確保されていることです。
太陽光発電の収入とコスト
収入は発電量×単価で計算されます。
| 土地の面積(㎡) | 100㎡(約30坪) | 500㎡(約150坪) |
| 設置容量(kW) | 10kW | 50kW |
| 年間電気量(kWh) | 約11,400kWh | 約57,000kWh |
| 買取単価(2025年度) | 屋根設置以外:10円 屋根設置: 9月まで11.5円 10月~3月は調達期間/交付期間が5年までは19円、調達期間/交付期間が6~20年は8.3円 |
入札制度対象外については8.9円 |
| 買取単価(2026年度) | 調達期間/交付期間が5年までは19円 調達期間/交付期間が6~20年は8.3円 |
入札制度対象外については8.6円 |
| 売却可能電気量 | 70% | 100% |
| 年間収入(年間電気量×買取単価×売却可能電気量) | 単価10円とすると約80,000円 | 単価8.9円とすると約500,000円 |
■費用目安
| 初期費用 | 設置費用:1kWにつき22~25万円 必要に応じて整地費用など |
| 運営費用 | メンテナンス・修理費:1年間で数万~数十万円 各種税金 |
■初期投資
太陽光発電パネル、パワーコンディショナーの購入費、架台の取り付けや配線などの工事費、補助金の申請手続きなど、初期投資の費用は多岐にわたります。
太陽光発電のメリット
- 電気の買い手を探さなくていい
- 長期的に安定収入を得られる
- 専門知識がなくても運用可能
- 手間が少ない
- 維持費が比較的安い
- 自家消費できる
太陽光発電のデメリット
- 利益が少なめ
- 季節によって利益が変動しやすい
- 天災に弱い
- 太陽光発電が多い地域の場合は出力抑制がかかることも
- 盗難のリスクがある
- メンテナンスが必要なことや廃業時の設備の処分が難しかったり、処分費用等の負担が発生する
太陽光発電に向いている人
- 手間をかけたくない
- リスクを避けたい
- 安定した運営をしたい
太陽光発電に向いている土地
- 日当たりがよい土地
- 送電設備が整っている土地
- 周辺に住宅がなく、近隣トラブルの懸念がない土地
相続した土地が広く、日当たりがよければ、ソーラーパネルを設置して太陽光発電を行うのもおすすめです。
発電した電力を売却すれば、長期的に収入を得られます。
太陽光発電の経営方式
自営方式:
- 土地のオーナーが太陽光発電設備を自己資金で設置
- 発電した電力の売電収入は、経費を差し引いた後、全額オーナーの収益となる
土地を貸す方式:
- 太陽光発電事業者に土地を賃貸する
- オーナーは地代収入を得る
トランクルームやコインランドリー

コインランドリー経営の収入とコスト
コインランドリーは初期費用を抑えつつ、収益化を狙えます。
騒音が多い地域や日当たりが悪い地域など、賃貸経営が向かない土地でも経営しやすい特徴があります。
ただし、コインランドリーは水道料金や電気代などの維持費がかかるので、収支計画をしっかりと立てておかなければなりません。
トランクルーム経営の収入とコスト
トランクルームの収入は、「1部屋あたりの賃料」と「稼働している部屋の数」で決まります。賃料の全国的な目安は以下の通りです。
- 屋外型(1坪あたり):約9,000円
- 屋内型(1坪あたり):約17,000円
トランクルーム経営には、初期費用と運営費用がかかります。
<主な初期費用>
- 屋外型: 主にコンテナの購入費用がかかります。目安として、1つのコンテナ(約4部屋分)で約100万円です。
- 屋内型: 物件の改装費用が中心となります。元々小分けにされたスペースであれば改装費は抑えられますが、広いワンフロアを細かく区切る場合は、1坪あたり約10万円を見込んでおくと良いでしょう。
<主な運営費用>
- 管理料: 業者に管理を委託する場合、収入の10〜15%が目安です。
- 電気代: 月々約2万円程度かかります。
- 各種税金: 固定資産税などがかかります。
これらの他、仲介手数料・宣伝広告費・監視カメラ設置費用等がかかる場合が想定されます。
コインランドリー経営のメリット
- 狭い店舗面積でも開業できる
コインランドリーの店舗の平均面積は70㎡程度です。
- 高収益が狙える
コインランドリー経営の収入は、70㎡程度の店舗面積で月60万円から80万円程度です。年間で720万円から960万円程度の売上が見込めます。
学生や単身赴任のサラリーマンの多い立地で始めれば、安定的な収入が期待できるでしょう。また、雨や雪の日が多いと乾燥機の売上が伸びます。
- 退去や不払いのリスクがない
他人に土地を貸すわけではないため、空室リスクや賃料の不払いのリスクがありません。
コインランドリー経営のデメリット
- 初期費用が高額
コインランドリーを経営するには、初期投資として4,000~5,000万円の開業資金が必要となります。
- ライバルが現れやすい
コインランドリー経営に免許は不要なので、ライバルが現れやすい面があります。
一般的に、コインランドリーの商圏は2km圏内とされますが、この範囲内で新たな出店があると固定客を奪われるかもしれません。
- 完全な無人経営ではない
コインランドリーは無人で経営できるものの、店舗の清掃や、乾燥機や洗濯機のメンテナンス、顧客からのクレームの対応などには自分で対応するか、対応を業者に委託する必要があります。
- 所有地で需要があるとは限らない
周辺に顧客となり得る学生や単身赴任のサラリーマンが少なければ、コインランドリーに対する需要は見込めません。
コインランドリーへの需要が見込めない立地であれば、別の活用方法を検討しましょう。
トランクルーム経営のメリット
- 低コストで手間も少ない
トランクルーム経営は、比較的低いコストで始められます。マンションの一室・オフィスの一角などのように小規模から始めれば費用を抑えることが可能です。
- 立地の制約が少ない
トランクルームは、賃貸住宅としては不利な立地でも十分な需要が見込める場合があります。近隣に住宅地があれば、駅から距離があっても利用客が見込めるためです。保管物の劣化防止のため、むしろ直射日光を避けることが望ましいという面があり日当たりが悪くても問題ありません。
トランクルーム経営のデメリット
- 満室になるまでに時間がかかる
トランクルームは満室になるまでに時間がかかる傾向があります。開業当初は、地域での認知度向上や利用ニーズのばらつき、潜在顧客の少なさなどから集客に苦労する可能性があります。早期の投資回収を重視する方には不向きかもしれません。
- 満室にするための広告宣伝費が必要となる
トランクルーム事業では、利用者が自ら情報を見つける「プル型」の集客ではなく、事業者側から積極的にアプローチする「プッシュ型」の広告宣伝が不可欠です。満室稼働を目指すためには、初期投資の一部として十分な広告宣伝費を確保する必要があります。
- 競合が出現した場合に差別化を図りにくい
トランクルーム市場の拡大に伴い、競合他社の参入が増加しています。トランクルームのサービス内容は事業者間で類似していることが多く、差別化が難しい点が課題です。
コインランドリー経営が向いている人
- 高い収益を追求したい人
- 将来性のある分野で事業を展開したい人
トランクルーム経営が向いている人
- 短期間での投資回収を期待する人
- 初期費用を低く抑えたい人
コインランドリー経営が向いている土地
- 人口が密集している土地
- 駅チカなど交通アクセスが良い土地
- よく目立つ土地
トランクルーム経営が向いている土地
- 住宅地が近くにある土地
- 小規模な土地
- マンションやオフィスビルが近くにある土地
コインランドリーの経営方式
賃貸経営:
- 所有する賃貸マンションのテナントスペースをコインランドリー会社に貸し出す
- 一度契約すれば長期間の安定した家賃収入が期待でき、設備導入費用や店舗管理の手間はコインランドリー会社が負担するため、オーナーの負担が少ない
委託運営:
- コインランドリーに必要な設備はオーナーが用意し、店舗の日常業務や利用者対応などの運営を専門会社に委託する
- オーナー自身の手間が大幅に軽減される
フランチャイズ運営:
- 専門会社のフランチャイズサービスに加盟し、そのノウハウを活用して運営する
- 加盟料は発生しますが、既に知名度のあるブランドを使用でき、設備仕入れ先の紹介や立地調査などのサポートを受けられる
自社運営:
- 設備導入から店舗のコンセプト、レイアウトまで、オーナー自身が全てをコーディネートし、運営する
- フランチャイズ加盟料などが不要なため、収益性が高い可能性がある
トランクルームの経営方式
管理委託方式:
- 土地のオーナーがトランクルーム自体を用意し、集客や契約といった経営業務も担当
- 清掃などの管理業務のみをトランクルーム事業者に委託
一括借り上げ(サブリース)方式:
- 土地のオーナーがトランクルームを準備し、それを事業者に一棟丸ごと貸し出して、経営と管理をすべて任せる
- オーナーは固定の賃料を受け取る
事業用定期借地方式:
- 所有する土地だけをトランクルーム事業者に一定期間貸し出す
- トランクルームの設置や経営はすべて事業者が行うため、土地のオーナーは地代のみを受け取る
戸建て賃貸
相続で一軒家の実家が残されたのであれば、そのまま賃貸する選択肢もあります。
自分が住むことは難しく、借り手の需要があれば最適な手段です。
戸建て賃貸とは、一戸建て住宅を他人に貸し出して賃料を得る方法です。従来は、転勤などに伴い一時的に戸建て物件を貸し出す方法が主でした。しかし、最近では相続した空き地の活用方法として、相続空き地に賃貸用の戸建てを建て賃貸経営する人が増加しています。
戸建て賃貸の収入とコスト
- 家賃収入:地域や物件の条件により異なるものの、月額10万~15万程度が一般的です。
- 主な初期費用:建築費が2,000万~3,000万円程度になることが多く、これらに加え頭金や諸費用がかかります。
- 主なランニングコスト:ローン返済や管理委託費、保険料や修繕費など、一定のランニングコストがかかります。
戸建て賃貸のメリット
- 借主を見つけやすく、家賃も高く設定できる
戸建て賃貸は需要が上回っている傾向なので、借主が見つかりやすいです。
部屋数が多い戸建てであれば、賃料が高くても需要が期待できます。ただし、立地条件が悪かったり、建物が老朽化していたりすれば、借主が現れない可能性もあります。
- 土地が小さくても始められる
所有地の面積が小さくアパート建設ができない場合でも、戸建て賃貸であれば建設できるかもしれません。不整形地でも、条件を満たせば建築できる可能性があり、土地の形状に応じた柔軟な設計が可能です。ただし、建築には建築基準法に基づく接道義務や建蔽率などの制限があるため、事前に確認が必要です。
- 比較的長く住んでもらえる
戸建て賃貸は、多くの場合、子どもがいる家庭が入居します。室内が広く部屋数が多ければ、子どもが大きくなっても住み続けてもらえるでしょう。長く住んでもらえれば、長期間にわたる家賃収入が見込めます。
- 入居者同士のトラブルが起こらない
基本的に戸建て賃貸の入居者はひと家族であるため、入居者同士のトラブルが発生しません。入居者同士のトラブルが発生しないことは、オーナーにとって非常に大きなメリットです。
ただし、近隣住民とのトラブルが発生した場合は対応する必要があります。入居審査の時点で借主の属性もしっかり確認しましょう。
- 借主に買い取ってもらえる可能性もある
借主が契約した賃貸期間以降も住み続けたいと希望した場合、戸建てを買い取ってもらえることもあり得ます。アパートやマンションと比較すると、一般的に戸建て住宅は売却しやすいです。
戸建て賃貸のデメリット
- 空室リスクがある
戸建て賃貸の場合、入居者はひと家族です。その家族が退去してしまうと家賃収入は0になります。一方、アパート賃貸であれば、空室があってもほかの部屋が埋まっていれば空室分の賃料をカバーできます。
また戸建て賃貸の場合、一度空室が発生すると、次の入居者がいつ決まるかは分かりません。3月や4月といった賃貸需要の時期に入居者が決まらないと、そのまま空室が続くことも珍しくないのです。
- 自分で使いたくなっても使えない
賃貸として貸し出せば、賃貸期間中は土地や建物を自分の好きなように利用できません。賃貸とは別の土地活用をやりたくなっても、入居者がいる賃貸期間は何もできないのです。
借地借家法28条に規定される正当事由がなければ、入居者を退居させることは非常に難しいでしょう。
- メンテナンス費用がかかる
戸建て賃貸の場合、メンテナンス費用がどれぐらいかかるか見積もっておくことが必要です。外壁や水回りなど、修繕しなければならない箇所が多ければ、修繕費用も高額になってしまいます。特に屋根や外壁など、大規模な修繕が少なくても数十年に一度は必要です。
戸建て賃貸経営が向いている人
- 不動産投資のリスクを最小限に抑えたい人
- 長期的な視点で資産形成を目指したい人
戸建て賃貸経営が向いている土地
- 狭小地(※)
- 不整形地(※)
- 住宅地
※狭小地や不整形地であっても、戸建てであれば比較的賃貸経営として土地活用しやすいという意図でご紹介
戸建て賃貸の経営方式
普通借家契約:
- 契約期間は通常2年
- 期間満了後も借り主が希望すれば契約が更新されるため、長く住み続けることが可能
- 借地借家法に基づき借主が手厚く保護されており、貸し主の一方的な都合による貸主の退去は原則として認められない。
定期借家契約:
- 契約期間は契約時に期間が明確に定められる
- 契約の更新はなく、期間満了時には借主は退去しなければならない。ただし、貸し主と借り主双方の合意があれば、再契約は可能
アパートや賃貸マンション
賃貸経営のメリットとしては複数の入居者が見込めるので、利益が大きくなりやすいことや通常の賃貸物件の場合、入居者は1~2年は同じ物件に住み続けるケースが多いので、利益も安定しやすいことが挙げられます。
一方、賃貸経営のデメリットとしてマンションやアパートの建設には、費用がかかることが挙げられます。建設する建物の規模が大きければ建築費用も高額になるため、アパートローンの利用が必要になる場合も少なくないでしょう。アパートローンを借り入れる場合、収支を計算して、キャッシュフローがマイナスにならないか十分に検討する必要があります。
以下ではアパート・賃貸マンションごとに説明します。
アパートの収入とコスト
アパートとは、階数が2階から3階程度の集合住宅で、部屋それぞれを独立した住居にしたものです。アパート経営とは、アパートを他人に貸し出して、賃料を得るビジネスのことを指します。
アパート経営においては、60坪以上の土地があるとよいでしょう。
都市部で60坪以上の土地を保有することが困難でも、土地面積が20坪程度以上で、建築基準法などの要件を満たせば、小規模なアパートなら建築も可能です。ただし、狭い場所でアパートを建てると、建築コストの割に部屋数が少なくなりやすいため、賃料を高くしないと採算割れになるリスクがあります。
アパート経営の主な収入は家賃ですが、それ以外にも複数の収入源があります。
- 家賃: 各部屋の賃料です。空室やフリーレント期間が発生すると、その分の収入は途絶えます
- 共益費/管理費: 共用部分の維持管理費用として入居者から徴収します。
- 礼金: 入居時に借主から受け取る一時金で、退去時に返還義務はありません。
- 更新料: 賃貸借契約を更新する際に借主から受け取る費用です。
- その他の収入: アパート敷地内の自動販売機の売上や、屋根に設置した太陽光発電システムによる売電収入などが該当します。
アパート経営の主な初期費用は以下の通りです。
- アパート建設費:ほとんどは本体工事費で、その相場はアパートの構造や階数によって異なります。
- アパートローン関連費: ローンを組む場合に発生する事務手数料、保証料、印紙代などで、建設費の約10%を目安とします。
- 登記費用: 新築した建物の「所有権保存登記」や、ローンを組む場合の「抵当権設定登記」にかかる費用で、目安は20万~50万円程度です。
- 各種税金:不動産取得税など
- 各種保険料:火災保険、施設賠償責任保険など
アパート経営の主な維持費用
- 維持・管理費: 共用部分の清掃、備品手配、賃料の収受・督促、入居者からの苦情対応など、日常的な管理業務にかかる費用です。
- 修繕費: アパートの経年劣化に対応するための費用です。
- ローン返済(非経費):アパートローンを利用している場合、毎月のローン返済が発生します。家賃収入とローン返済のバランスを考慮した事前の予算計画が重要です。
- 各種税金:所得税(非経費)・住民税(非経費)・固定資産税 など
※上記は、アパート経営を継続する上で必要となる支出全般を「維持費用」として整理しており、一部は税務上の経費に該当しないものも含まれます。
賃貸マンションの収入とコスト
賃貸マンション経営における主な収入源は以下の通りです。
- 家賃:賃貸経営の収益の大部分を占めます。
- 共益費:集合住宅の共用部分の維持管理費用として、家賃と一緒に毎月入居者から徴収します。
- 礼金:賃貸契約時に初期費用として入居者がオーナーに支払う謝礼金です。入居者に返還されないため、オーナーの直接的な収入となります。
- 更新料:賃貸借契約を更新する際に、入居者がオーナーに支払う費用です。一般的には2年ごとの更新時に、家賃の1〜2ヶ月分が相場とされています。
- その他の収入:物件に駐車場がある場合や自動販売機を設置することなどによる収入です。
賃貸マンションの主な初期費用は以下の通りです。
アパート建設費以外の初期費用は、物件の建築価格の8%〜10%が目安とされています。主な内訳は以下の通りです。
- 物件建築費用: 最も大きな割合を占めます。
- 登記費用: 物件の登記にかかる費用です。
- 印紙税: 契約書作成時に必要な税金です。
- 不動産取得税: 物件取得時にかかる税金で、請求までに時間差があります。
賃貸マンションのランニングコストは、毎月の家賃収入から支払う維持・管理費、税金、融資返済金などで構成され、家賃収入の60%〜80%が相場とされています。
具体的な項目として主なものは以下の通りです。
- 管理委託費:管理会社に委託する場合、家賃収入の5%程度が相場です。サブリースの場合、家賃収入の10%〜20%が相場となります。
- 損害保険料: 火災保険や地震保険など、災害リスクに備えるための保険料です。
- 管理費用: 共用部分の電気代、清掃費、常駐管理人の人件費など。
- 修繕費・積立金: 建物は経年劣化するため、定期的な修繕や大規模修繕が必要です。数千万円かかることもあるため、計画的な積立が重要です。
- リフォーム費用: 部屋の状況が悪くなった場合など、入居者の入れ替え時に行う原状回復のための費用です。
- 入居者募集のための広告費: 新たな入居者を募集する際にかかる費用で、家賃1ヶ月分が目安です。
- 税理士費用: 確定申告などの税務手続きを依頼する場合にかかります。顧問契約の場合、年間20万〜30万円が一般的です。
アパート経営のメリット
- 収益が安定しやすい
賃貸の需要がある立地なら、一般的に家賃収入は安定するでしょう。空室が発生したり、家賃の値下げを要求されたりすることもあるかもしれませんが、収入の見通しは立てやすいです。
- 空室による賃料減をカバーできる
戸建て賃貸やワンルームマンションでは、借主が1人です。この借主が退去すると、入居者が現れるまで家賃収入がない状態です。戸建て賃貸やワンルームマンションをローンで購入していた場合、空室が続いている間のローン返済金を自己資金で賄わなければなりません。
しかしアパートの場合、複数の部屋があるため、空室が発生してもほかの部屋の賃料が空室による賃料減をカバーしてくれます。したがって、入居者が1人でもいれば収入が0になりません。
- インフレ(物価上昇)に強い
インフレとは、商品や不動産などのモノの値段が上がり、お金の価値が下がることです。
インフレが進行すると、一般的に不動産価格は上昇傾向に向かいます。物価上昇に伴い、建物の原材料費や土地価格も上がるためです。お金の価値が下がっても、不動産の資産価値は下がりづらいです。インフレの状態が続いている場合、十分な預金があるのであれば不動産に変えることも選択肢の一つです。
アパート経営のデメリット
- 自己資金が必要になる
アパートローンを借り入れられるとはいえ、アパートを建設するにはある程度の自己資金が必要になります。
アパートを建てる際に必要な自己資金は、建設費の10~30%程度とされており、例えば5,000万円のアパートを建てるのであれば、500~1,500万円が目安として必要です。
ほかの活用方法より自己資金が多く求められるため、ネックになってしまう方も多いかもしれません。
- 収益が得られない可能性がある
アパートローンなどの借入金が多い状態では、空室が増えることによりキャッシュフローがマイナスになるかもしれません。
キャッシュフローがマイナスにならないよう、立地条件のよい場所でアパート経営を行い、かつ過大な借入をしないことが必要です。
- 修理費用が発生する
アパートの修理責任は、原則として貸主にあります。アパートの内装で修理が必要な箇所が生じても、入居者が故意に破壊したものでない限り、貸主は入居者に修理費用を請求できません。
壁紙の張り替えなどの小さな修繕のほかにも、屋根や外壁などの修理修繕も少なくても数十年に1回は行う必要があります。
- 災害リスクがある
地震や火災などの災害はいつ発生するか誰にも分かりません。地震には地震保険、火災には火災保険で、事前に保険に加入することで備えることが必要です。水害については、過去の記録やハザードマップを調べ、水害が発生した場所やマップが赤くなっている場所は避けましょう。
- 早急な現金化が難しい
アパートの収益が悪くなったからといって売却しようとしても、すぐには買い手がつきません。アパートそのものを買いたいのは、同じくアパート経営を行いたい方になることがほとんどですが、収益性の悪いアパートは避けられるからです。すぐに現金が必要なときでも、現金化に時間がかかります。
賃貸マンションのメリット
- 安定収入を見込める
一般的にマンションはアパートに比べ家賃を高く設定できます。また、住戸数も多数確保できるので、アパートよりも安定した収入を見込めるでしょう。
- インフレに強く、資産になる
マンションは、土地と建物からできています。
2025年3月に国土交通省が公表した「令和7年地価公示」によると、2022年1月から12月までの地価動向は、全用途平均・住宅地・商業地において2年連続で上がっているとのことです。
建物の経年劣化により、築年数の増加に従って、建物評価は下がっていくといわれます。しかし、マンション経営においては利回りを高くすることで、建物の評価を上げられます。
ちなみに、建物評価額が上がれば、マンションを売却したときにキャピタルゲインを得られます。立地や入居率によりキャピタルゲインは左右されますが、マンションを建てたときの費用よりも多く手元に残れば、マンションを売却した後の生活も安心でしょう。
- ローンの活用で資金効率がよくなる
マンション経営において、建築資金などの事業費を調達する際にアパートローンを借りることができれば、資金効率(自己資金配当率)が上がります。
資金効率とは、マンションなどの賃貸住宅の購入の際に支払った自己資金に対する、年間の収益(キャッシュフロー)の割合のことです。資金効率は、下記の計算式で算出されます。
資金効率 = 年間の収益 ÷ 自己資金の投資額 × 100
資金効率の数字が高いほど、投資によって効率よく収益を上げているということです。
通常、アパートローンを利用するときは、自己資金で総事業費の10%から30%を調達し、残り70%から90%をローンで調達することが多いです。自己資金で総事業費の30%を調達するとき、ローン額は自己資金の2.3倍となり、自己資金で10%を調達するならローン額は自己資金の9倍となります。自己資金調達の割合が低いほど、資金効率は上がるということです。
賃貸マンションのデメリット
- 始めるときに多額の自己資金が必要になる
アパートローンを借りるときには、自己資金を捻出しなければなりません。それは、マンション経営についても同じです。
仮にマンションの総事業費が4億円であれば、自己資金を4,000万円から1億2,000万円の範囲内で用意する必要があります。
- 収支が赤字になるリスクがある
例えば以下のような状態では、マンション経営は赤字に陥るリスクがあります。赤字になると、収益でローンを返済できないため、自己資金からローンを返済しなければならなくなります。
・入居率が減少して、空室率が増大するという状況が継続している
・フルローン利用などで、家賃収入に対するローン返済額の割合が大きい場合
- 大規模な修繕費用がかかる
一般的に、マンションは建てられてから10年ほど経過すると、建物の共用部分(屋根や外壁、廊下、エレベーターなど)や住戸部分(給湯器、水回り設備など)が劣化してきます。
劣化したところを維持管理するのはオーナーの役目です。マンションの規模によりますが、次のような修繕費用がかかります。
・共用部分:12~15年周期で、数十万~数百万円単位
・住戸部分:築10年を経過したタイミングで数万円以上
マンション経営においては、大規模修繕を見越した上での収益管理が必須となります。
災害危険区域や土砂災害特別危険区域などの災害指定地域内にマンションがあった場合、土砂崩れや洪水、高潮などの災害に見舞われるリスクが高くなります。したがって、災害危険区域では、マンションや戸建住宅などの住居用建物の建築は原則として禁止されています。
建築が禁止されているため、後から災害危険区域と知ることはないでしょう。とはいえ、マンション経営を考えていたら災害危険区域で建築できなかった、という可能性も0ではないため、所有する土地が災害危険区域内ではないか確認しておく必要があります。
アパート経営が向いている人
- 入居者のニーズを理解し、信頼を得て長く住んでもらえるよう気配りができる
- 入居者や管理会社、業者などと円滑なコミュニケーションが取れる
- しっかりとした計画性を持ち、それを実行できる
賃貸マンション経営が向いている人
- 長期的な視点で、目先の利益に惑わされず経営を続けられる
- まとまった自己資金があり、空室や家賃滞納などのリスクを管理できる
- 市場調査や物件選定、入居者管理など、様々な情報を収集・分析できる
アパート経営が向いている土地
- 東西に間口が長く、整った形の土地
- 住宅街に位置する土地
- 周辺に食品スーパーなどの生活施設がある土地(望ましい)
賃貸マンション経営が向いている土地
- 都内なら30坪以上、郊外なら120坪以上の土地(望ましい)
- 最寄り駅は、通勤に便利な路線にある土地(望ましい)
- 駅から徒歩10分圏内の土地(望ましい)
アパートの経営方式
サブリース:
- サブリース会社が物件を一括で借り上げ、入居者との契約や管理業務をすべて代行
- 空室に関わらず一定の家賃収入が得られる
管理委託:
- 専門の管理会社に管理業務を委託する方法で、最も一般的
- 専門知識が必要な業務を任せられる。
自主管理:
- オーナー自身がすべての管理業務を行う方法
- クレームやトラブルへの対応、適切な管理のための経験やノウハウが求められる
賃貸マンションの経営方式
自主管理:
- 不動産オーナー自身が、建物の管理、入居者管理、資金管理など、賃貸管理のすべてを行う
- 管理費用がかからないため、利回りを高め、キャッシュフローを改善できる可能性がある
- クレーム対応、家賃回収、入居者募集など、手間と時間が非常にかかる
一般管理:
- 賃貸管理業務を専門の管理会社に委託する
- 管理会社が専門知識とノウハウで対応するため、オーナーの手間や精神的負担が大幅に軽減される
- 数多くの管理会社の中から、信頼できる業者を見極める必要がある
サブリース:
- サブリース会社がオーナーから物件を一括で借り上げ、サブリース会社が独自に入居者を募集し、管理を行う
- 空室や滞納リスクを気にせず、安定した収入が期待できる
- 家賃から保証料が引かれるため、利回りが低下する可能性がある
相続した土地の活用が難しいときは、土地の売却の検討も
様々検討してみたが活用が難しいという時は土地を売却するのも一つの手です。土地を売却すれば売却益が手に入ります。
ただし、賃料などの継続的な収益は諦めなければなりません。
とはいえ、相続した土地の価格が上がるとは見込まれず、安定した収益を得られそうな活用方法がなければ、売却することも選択肢の一つといえます。
まとめ
相続した土地は、放置せずに活用することで収益化が可能です。賃貸住宅や駐車場など様々な方法がありますが、それぞれにコストやリスクが異なるため、まずは現状を分析し、10年・20年後といった長期的な収支シミュレーションを行うことが大切です。
ご自身の資産を最大限に活かすためにも、「現状分析」と「長期目線での戦略立案」は欠かせません。ぜひ、豊富な実績と専門知識を持つ青山財産ネットワークスへご相談ください。お客様一人ひとりに最適な土地活用のプランをご提案いたします。
*本記事に掲載している税率等は2025年4月時点の情報です。
監修者
- 相澤 光Aizawa Hikaru
- コンサルティング事業本部 コンサルティングサービス室 室長 兼 第四事業部 ダイレクトグループ グループ長
不動産や法人を活用した財産防衛策の立案・実行に従事し、財産と想いを次世代に承継するための支援を提供。最適な選択肢を見つけられるよう、中立的な立場で家族全体の意向調整もサポートすることを信条とする。
当社の30年にわたるナレッジを集約した書籍を発行し、セミナー登壇実績も多数。
趣味:学び(税理士資格の勉強中)、ギター、サウナ
- 専門分野
- 土地持ち資産家、金融資産家向けコンサルティング
- 資格
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
- 著書
- 「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策