
不動産投資に興味をお持ちの方であれば、「不動産小口化商品」という言葉を一度は目にしたことがあるかもしれません。不動産投資と聞くと、一棟まるごとの購入に数千万円~億単位の資金が必要だと考え、二の足を踏む方も少なくないでしょう。
不動産小口化商品は、一つの不動産を小口に分割し、複数の投資家に対して販売される投資商品です。少額から参加できる手軽さから注目を集めており、多くの投資家に支持されています。
本記事では、不動産小口化商品の仕組みをはじめ、確定申告時の流れや確定申告しないリスク、不動産小口化商品のメリット・デメリットまでを分かりやすく解説していきます。
不動産特定共同事業法に基づく不動産小口化商品について
不動産小口化商品は不動産特定共同事業(FTK)法や金融商品取引法などに基づいて販売される、不動産を小口に分けた商品です。この章では不動産特定共同事業(FTK)法に基づく不動産小口化商品について解説します。
不動産特定共同事業について
この不動産特定共同事業(FTK)とは、国土交通省が管轄する許可制の事業で、投資家から資金を集めて不動産の売買や賃貸を行い、そこから得た収益を投資家に分配する仕組みです。
不動産特定共同事業が誕生した歴史は、1980年代後半の日本の不動産バブルと密接に関わっています。1980年代のバブル期、不動産小口化商品が急増しました。
資金力のない一般の投資家も不動産投資に参加できるようになりましたが、バブル崩壊後に事業者が破綻したケースが少なくなかったため、社会問題となりました。
こうした混乱を受け、投資家保護と健全な不動産投資市場の発展を目的に「不動産特定共同事業法(不特法)」が1994年に制定され1995年に施行されました。
この法律により、不動産特定共同事業を行うには国土交通大臣または金融庁長官、各都道府県知事のいずれかの許可の許可が必要となり、事業者の資質が厳しく審査される体制が確立されました。
不動産特定共同事業は施行後も、時代の変化や投資商品・事業参入者の多様化に対応するため2013年・2017年・2019年と法改正が行われます。
特に2017年改正では、「小規模不動産特定共同事業制度」が創設され、クラウドファンディング型の資金調達など新しい形態の参入が容易になり、中小企業や地域の活性化に寄与している面があるといえるでしょう。
不動産小口化商品が注目される背景
最近、不動産小口化商品の注目度が高まっている理由として、主に以下の点が挙げられます。
手持ちの資金から投資を開始できる
人気エリアの不動産を取得するには多額の費用が必要ですが、不動産小口化商品は少額から投資可能です。そのため、元手が少ない方や、損失リスクへの不安が大きい場合に適しているとされています。
不動産小口化商品は不動産投資を小さく始められる
不動産小口化商品は、一般的な現物不動産投資に似た手法でありながら、高額物件でも、一口あたり約100万円から購入可能です。
現物不動産投資に興味はあるものの、投資を集中させることに抵抗がある方や、投資を少額から始めたいと考えている方にとっては、不動産小口化商品は利便性の高い選択肢です。
これらの点をまとめると都心優良不動産に少額で投資が可能である点こそが、数ある不動産投資の中で不動産小口化商品が選ばれる理由といえるでしょう。
不動産小口化商品で所得税の確定申告が必要になる場合
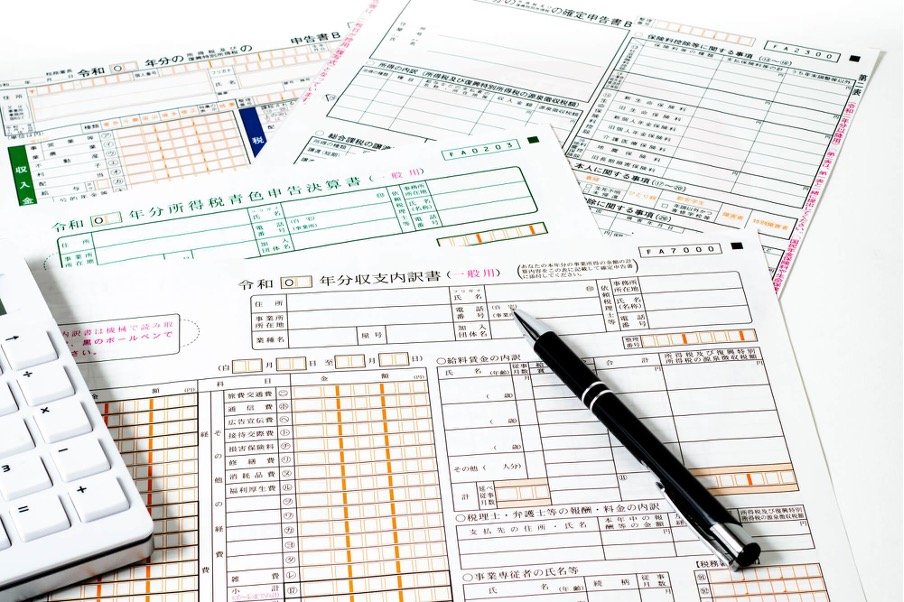
不動産小口化商品を購入しても、必ずしも確定申告が必要なわけではありません。しかし、そこから得られる収益によっては確定申告が求められます。具体的には個人の場合で給与所得がある方であれば、給与所得とは別に所得が年間20万円超になった場合、確定申告の手続きが必要です。
なおここでいうのは「収入」ではなく「所得」なので注意しましょう。所得は、収益から経費を差し引いて算出できます。
また所得が20万円を超えなくても、例えば以下のようなケースでは、不動産小口化商品を保有しているかどうかに関わらず、確定申告が必要となるので確認しておきましょう。
- 年末調整で住宅ローン控除を適用していないので控除したい
- ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用していない
- 医療費控除を適用したい
- 給与を2カ所以上の会社から受け取っている
任意組合型と匿名組合型の違いと所得税の確定申告への影響
この章では不動産小口化商品の任意組合型と匿名組合型の違いや、その違いによる確定申告への影響について解説します。
任意組合型とは?
任意組合型では、事業者は投資家と共に「共同事業体」の一員として活動します。組合の業務は業務執行組合員に選ばれた事業者が代表して執行しますが、投資家も経営に関する意思決定に参加する権利を持ちます。
例えば、不動産をいつ・いくらで売却するかといった出口戦略については、情報を開示した上で、組合員の同意を得ることが求められます。
これにより事業者の手間は増えるものの、投資家もより深く責任を担うことになります。
不動産の所有権は「共有」
不動産は投資家全員の「共有財産」となり、各投資家はそれぞれの出資比率に応じた持分を所有します。
匿名組合型とは?
一方匿名組合型では、投資家は経営判断に関わらず、運営はすべて事業者の裁量で進められます。投資家の意見を事業に反映させる必要がないため、スピーディーな意思決定が可能です。
実際、市場ではこの匿名組合型が主流となっているケースが多く、理由の一つに「運営のしやすさ」があると考えられます。
不動産の所有権は「なし」
このスキームでは、不動産の所有権は事業者の単独名義となり、投資家には所有権は一切ありません。
投資家にとっての違い
投資家にとって特に重要なのは、「自分が不動産の所有者になるかどうか」という点です。任意組合型では、所有する単位は小さくても実際の不動産に出資する感覚に近く、共有持ち分を通じて現物不動産の権利を直接保有します。
一方で匿名組合型は、実物不動産に出資するというよりも、J-REITのような不動産ファンドに出資するのに近く、所有ではなく「運用益を得る」スタイルです。
そのため、「事業者が資金を集める手段」としての性格が強いといわれることもあります。
確定申告としては任意組合型の場合、不動産の所有権を持つため「不動産所得」として申告します。
得られた分配金収入は現物不動産投資と同様に「不動産所得」となります。減価償却、経費計上(持分割合による)や、青色申告特別控除(10万円または55/65万円、規模等による)が利用可能です。財産管理報告書などで収支内容を確認し、青色申告決算書を作成して申告します。
匿名組合型の場合「雑所得」として申告します。分配金は「雑所得」として扱われます。経費計上の幅は現物不動産よりも狭く、減価償却などは不可。青色申告特別控除などは適用できません。
補足:賃貸型について
なお、賃貸型という形式は、事業者は不動産の所有者ではなく、投資家が所有する不動産を借り受け、それをテナントなどに貸し出して収益を上げる仕組みです。これは、個人オーナーが不動産をサブリース会社に貸し出す構造に近いと考えられます。
所得税の確定申告の方法|白色申告と青色申告の違い
不動産所得に関する確定申告には、「白色申告」と「青色申告」という2つの方法があります。それぞれの特徴と違いを見ていきましょう。
白色申告
白色申告は、すべての個人納税者が利用できる基本的な申告スタイルです。大きな特長は手続きが簡単な点で、帳簿も単式簿記と呼ばれる簡易的な方法で記帳できます。
そのため、初めて確定申告を行う人や手続きに不慣れな人でも取り組みやすいのがメリットです。ただし、白色申告では青色申告のような税制上の各種の特典(控除など)は基本的に受けられません。
青色申告
青色申告は不動産所得・事業所得・山林所得のいずれか(または複数)がある場合に選択できます。青色申告では複式簿記による記帳が求められるため、白色申告に比べて帳簿管理や申告が複雑になります。
その分最大65万円の青色申告特別控除が受けられるなど、税制上の優遇があります。青色申告を利用するには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出が必要ですが、その年(申告する年)の1月16日以後、新たに不動産の貸付けをした場合には、「青色申告承認申請書」はその事業開始等の日から2カ月以内の提出が求められます。
提出が遅れた場合、その年は青色申告が利用できないので注意が必要です。
青色申告の控除額は3種類
青色申告の控除額は、要件に応じて以下の3つのパターンに分かれます。
- 10万円控除:複式簿記や電子申告などの条件を満たさない場合は、10万円の控除が適用されます。こちらは簡易簿記での記帳でも認められ、比較的ハードルが低い方法です。
- 55万円控除:55万円の控除を受けるためには、不動産賃貸が事業的規模であるなど一定の要件を満たしていることが条件です。事業的規模かどうかは、社会通念上「事業」と認められるかが基準となりますが、特に反論がなければ「5棟10室基準」で判定されるのが一般的です(例:アパート5棟または10室以上)。
- 65万円控除:55万円控除の条件を満たした上で、e-Taxでの申告または優良な電子帳簿保存を行うと、控除額が65万円に引き上げられます。
なお電子帳簿保存に関しては以前は事前承認が必要でしたが、現在は特別な手続きなしに導入可能となっています。
青色申告のそのほかのメリット
青色申告には控除以外にも、以下のようなメリットがあります。
- 所得が赤字となった場合、ほかの所得と損益通算が可能(白色申告も可)
- 最大3年間、赤字を翌年以降に繰り越して控除できる(白色申告では基本的に不可)
このように、たとえその年が赤字で申告義務がない場合でも、税制上の各種特典を受けられることから青色申告を選ぶのは有効な手段といえるでしょう。
不動産投資における確定申告の進め方
不動産投資を行っている方が確定申告をする際は、次のステップを順に進めることでスムーズに手続きを終えることができます。
- 1.必要書類の準備
- 2.決算書の作成
- 3.確定申告書の作成
- 4.申告手続きの実施
以下でそれぞれのステップについて詳しく説明します。
1. 必要書類の準備
まず行うべきは、申告に必要な書類をきちんとそろえることです。例えば、不動産購入時の売買契約書や、入居者との賃貸借契約書などが該当します。
初めて申告を行う方は、必要な書類の確認や準備に予想以上の時間がかかる場合があります。そのため、確定申告の受付期間(例年原則2月16日~3月15日)よりもずっと前に準備を始めておくと安心です。
また、書類の紛失を防ぐためにも、不動産関連の資料は一括して保管しておくことをおすすめします。
2. 決算書を作成する
書類が整ったら、次は決算書を作成します。これは、不動産から得た収入や支出した経費をまとめた書類で、所得を正確に把握するために必要です。白色申告の場合は「収支内訳書」と呼ばれる簡易的な書式を使用します。
3. 確定申告書の作成
決算書の作成が終わったら、次は確定申告書を作りましょう。
この書類には年間の収入、必要経費、社会保険料控除、基礎控除などを記載し、最終的に課税対象となる所得と納税額を算出していきます。
申告書の具体的な記入方法や形式は、国税庁のホームページからも確認できます。
4. 確定申告を提出する
最後に、完成した決算書(もしくは収支内訳書)・確定申告書・添付書類をまとめて提出します。提出方法は次の3通りです。
- 税務署の窓口に直接持参
- 税務署へ郵送で提出
- インターネット経由で「e-Tax」を利用
書類の記入に不安がある方は、税務署に直接行って職員に確認しながら提出するのが安心です。
なお、インターネットを使った申告方法「e-Tax(イータックス)」は2004年から運用されており、国税庁のサイト上で申告書の作成・送信・納税までがオンラインで行えます。
マイナンバーカードと事前登録が必要ですが、スマートフォンからも手続きできるため、忙しい方には特に便利な方法です。
不動産小口化商品で赤字が発生した場合の扱い
一般的な区分所有マンションで赤字が出た場合、その損失はほかの不動産収入の黒字と相殺したり、給与所得などと損益通算したりすることが可能です。
一方で、不動産小口化商品で損失が出た場合、その分の経費を所得から差し引くことは原則として認められていません。したがって、実際に赤字であっても「収支ゼロ」として申告しなければならず、ほかの所得や物件の収益と通算して税金を減らすことはできません。
特に購入初年度は不動産取得税や登録免許税など初期費用の負担が重く、実際には赤字となるケースも見られます。また、建物部分の比率が高く設定されており、毎年の減価償却によって赤字になることを前提にした商品も存在します。
このような商品に投資する場合、赤字部分が切り捨てられるため、注意が必要です。
なお、「赤字を回避するために減価償却を行わない」という選択肢を検討する方もいるかもしれませんが、個人で申告する場合、減価償却の計上は義務とされており任意で取りやめることはできません。
確定申告をしないとどうなる?税務上のペナルティ
確定申告が義務づけられているにもかかわらず、期限内に申告を行わなかったり、意図的に所得を隠したりした場合には、厳しい罰則が科されることがあります。
この章では、それぞれのケースごとに課される主なペナルティについて解説します。
無申告加算税
申告期限を過ぎても確定申告を行わなかった場合に課される追加の税金です。2024年から制度が見直され、状況に応じて段階的に税率が変わります。
ただし以下の条件をすべて満たす場合は、期限後に申告しても無申告加算税は課されません。
- 申告期限から1カ月以内に自主的に申告している
- 「期限内に申告する意思があった」と認められる事情がある
この「意思があった」と認められるケースとは、以下の両方に該当することが必要です。
- 期限後申告に関わる税金を、法定納期限までにすべて納付している
- 過去5年間に、無申告加算税・重加算税を課されたことがなく、また無申告加算税の不適用を受けていない
延滞税
延滞税は、申告期限を過ぎて税金を納めた場合に発生する「利息」のような性質のものです。無申告加算税とは別に課されます。税率は以下のとおりです。
- 申告期限の翌日から2カ月以内:年7.3%または「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低いほう
- 2カ月を超えた後:年14.6%または「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほう
重加算税
意図的に所得を隠したり、書類を偽造したりと不正があった場合に課されるもっとも重い加算税です。
状況に応じて段階的に税率が変わります。
重加算税がほかの加算税と異なるのは、納税者の「悪質な意思」が問われる点です。故意の不正行為と判断されるため、ほかの税よりも重い制裁が科されます。
ほ脱(脱税)について
「ほ脱」とは、いわゆる脱税のことで、これは税法に違反する犯罪行為です。所得税法では、帳簿の虚偽記載などの不正行為があった場合、以下のような刑事罰が定められています。
- 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方
- 仮に不正がなくても、確定申告を意図的に行わなかった場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方
が科される可能性があります。
確定申告が必要であるにもかかわらず申告をせず、収入の存在自体を隠すといった行為は、典型的な脱税の例です。期限に間に合わなかった、あるいは記載ミスがあったといったケースとは異なり、非常に重い処罰の対象となります。
必要であるにもかかわらず申告を怠ったり、不正に収入を隠したりすると、多額の税金に加えて罰則も科される可能性があります。正確かつ期限内の申告を心がけましょう。
不動産小口化商品のメリット・デメリットと向いている人

不動産小口化商品にはさまざまなメリット・デメリットがありますので、この章で解説します。また向いているといえる人の特徴も合わせて解説します。
不動産小口化商品のメリット
- 不動産のプロが厳選した物件に投資できる
- 不動産所有者として資産運用ができる
- 不動産の管理・運用の手間を省ける
- 分割して相続しやすい
- 比較的リスクが少ない
不動産小口化商品の大きな利点は、不動産のプロが厳選した物件に投資できることです。
彼らは安定した収益が見込める物件や、将来的に価値が上がる可能性のある物件を厳選しています。個人では知り得ないような商業ビルや商業施設など、専門的な情報が必要な物件にも安心して投資できるでしょう。
不動産小口化商品のデメリット
- 空室リスクがあり、収益の受け取り頻度が少ない
- 元本保証がなく、値下がりの可能性もある
- 運用期間中の途中解約ができない商品もある
- 物件を担保に融資を受けられないため、自己資金が必要
入居者が決まらず空室が続けば、賃料収入は減少します。将来的に不動産価値が下がると、売却時に収支がマイナスになる可能性もあるでしょう。
また、不動産小口化商品の中には、途中で解約できないものもあります。もし解約が可能だとしても、実際の不動産と同様に仲介が必要で、すぐに現金化できないケースが多いので、商品選びは慎重に行ってください。
一般的な不動産投資では、投資物件を担保として融資を受けられるケースがあります。しかし、不動産小口化商品は物件を担保に融資を受けることができません。そのため、購入する際は自己資金が必要となります。
不動産小口化商品に向いている人
不動産小口投資は、すべての投資家に適しているわけではなく、ある特定のニーズや状況にある方に特にメリットがあります。ここでは、不動産小口投資にマッチしやすいタイプの投資家をご紹介します。
借入を避けて自己資金だけで運用したい人
一般的な不動産投資では、多くの場合、物件購入のために金融機関から融資を受けます。ただ、借入には金利負担や月々の返済義務が伴うため、ローンに抵抗を感じる方にとっては参入しづらい面があります。
それに対し、不動産小口投資は少額の自己資金で始められるため、融資を利用せずに投資を行いたい人に向いています。
手間をかけずに不動産投資をしたい人
通常の不動産投資では、賃貸管理や物件の維持など、オーナーとしての業務が発生します。管理会社に委託することもできますが、委託費用がかかり、最終的な判断は投資家自身に委ねられることも少なくありません。
その点、不動産小口投資では、物件の管理や運営はすべて事業者側が行うため、投資家は運用の手間をかけずに分配金を受け取ることができます。
投資先を複数に分けてリスクを減らしたい人
資産運用において分散投資はリスク軽減の基本です。とはいえ、通常の不動産投資では一件あたりの投資額が高額になりがちで、物件数を増やすのが難しく、結果としてリスクが集中することがあります。
不動産小口投資であれば、比較的少額で複数の物件に出資できるため、資産を複数に分散しやすくなります。
まとめ
不動産小口化商品は少額から複数の物件に分散投資でき、リスクを抑えた資産運用を望む人に向く商品です。ただし、提供事業者の信頼性や物件選定の基準をよく理解した上で投資を始めることが肝心です。
また空室リスクや事業者の経営破綻リスクなど、不動産投資特有の危険性もあるため、リスクとリターンのバランスを十分に検討し、自身の運用方針に合った商品を選ぶことが求められます。
不動産投資は長期運用が基本ですので、じっくりと計画を立て、着実に資産形成を進めましょう。
不動産小口化商品については、弊社青山財産ネットワークスにぜひご相談ください。
監修者
- 相澤 光Aizawa Hikaru
- コンサルティング事業本部 コンサルティングサービス室 室長 兼 第四事業部 ダイレクトグループ グループ長
不動産や法人を活用した財産防衛策の立案・実行に従事し、財産と想いを次世代に承継するための支援を提供。最適な選択肢を見つけられるよう、中立的な立場で家族全体の意向調整もサポートすることを信条とする。
当社の30年にわたるナレッジを集約した書籍を発行し、セミナー登壇実績も多数。
趣味:学び(税理士資格の勉強中)、ギター、サウナ
- 専門分野
- 土地持ち資産家、金融資産家向けコンサルティング
- 資格
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
- 著書
- 「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策



