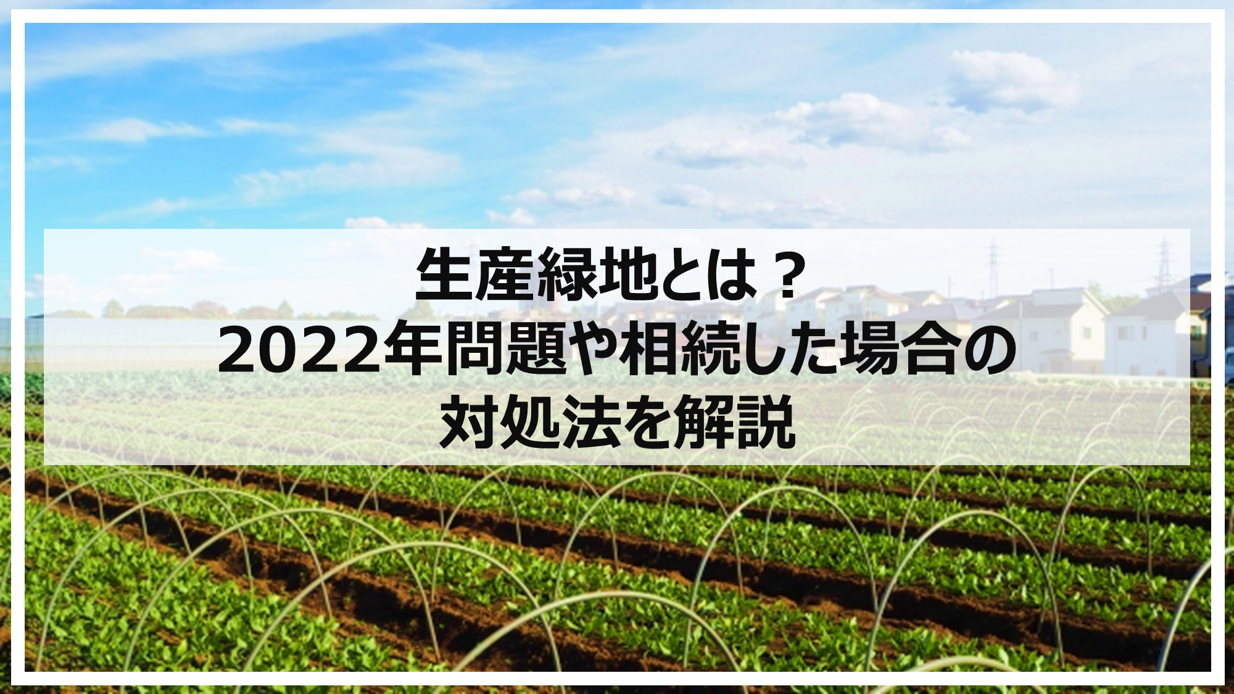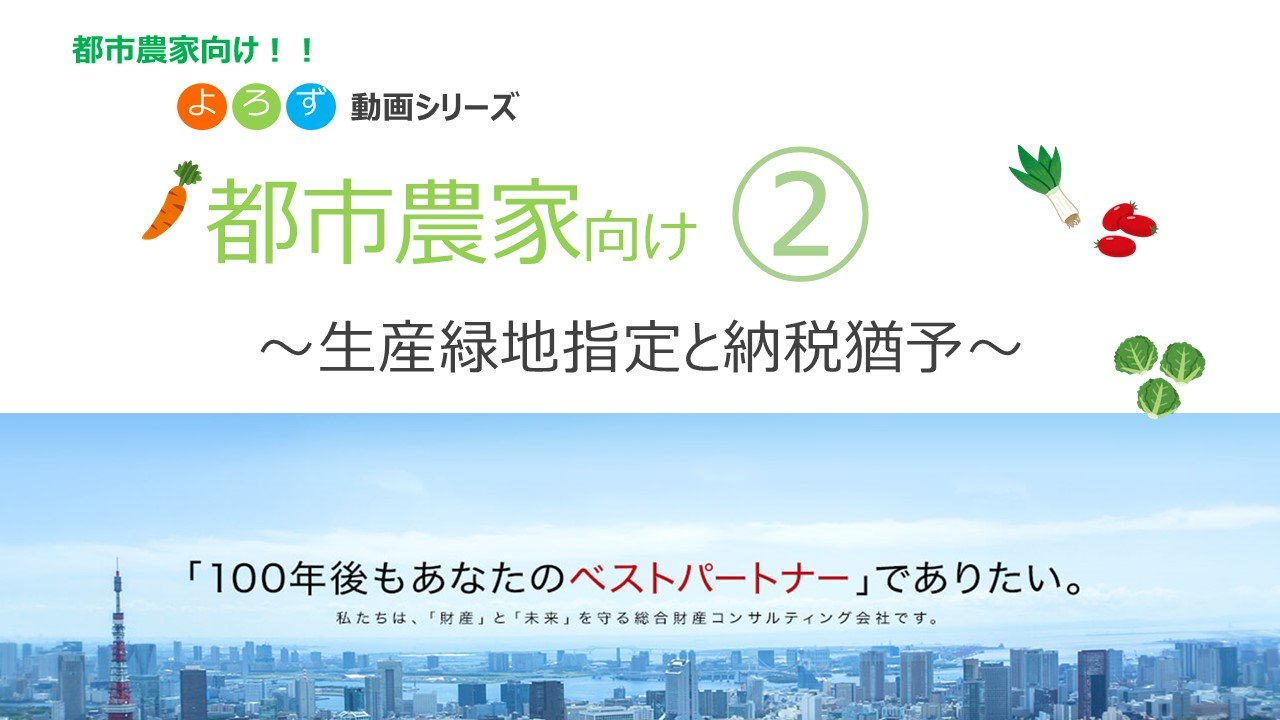生産緑地制度とは、市街化区域内の農地を保全するために設けられた制度です。生産緑地に指定された農地には、固定資産税が宅地並みから農地並みに軽減されたり、相続税の納税猶予が適用されたりするなどの利点があります。一方で、農地以外の用途への転用が禁止されるなど、土地利用に制限がかかるという側面もあります。
生産緑地に指定された農地は厳密に管理されているため、その特性を踏まえて一定の評価減が認められています。この記事では、生産緑地における相続税評価額について詳しく解説します。
関連記事:
関連記事:
生産緑地とは
生産緑地とは、都市の環境を良好に保つことを目的として、市街化区域内の農地を計画的に保存するために指定された土地のことです。市街化区域は、すでに都市化が進んでいる地域や、今後10年以内に市街化が予定されている地域を指します。
生産緑地に指定されると、その土地を農地として維持管理する義務が生じ、最長30年間その状態を保つ必要があります。
生産緑地にはさまざまな制限がありますが、同時に「買取りの申出」という制度も存在します。この制度では、生産緑地が指定された告示の日から30年が経過した日以降、またはその告示後に農林漁業の主な従事者が死亡した場合など、所有者は市町村長に対してその生産緑地を時価で買い取ってもらうよう申し出ることができます。
生産緑地制度が誕生した背景
高度経済成長期に都市部への人口流入が進んだ結果、緑地が急速に減少しました。この都市化と人口増加により、ヒートアイランド現象や大気汚染などの環境問題が悪化し、住環境が大きく影響を受けました。
緑地が減少することで、地盤の保持や水分の保持機能が低下し、自然災害が頻発するようになったのです。これらの問題に対処するために、1974年に生産緑地法が制定され、農業と都市環境の調和を図るとともに、良好な都市環境の形成が目指されました。
それでも地価の上昇や土地不足の問題は解消されず、1992年に生産緑地法が改正されました。
生産緑地に指定されることのメリット
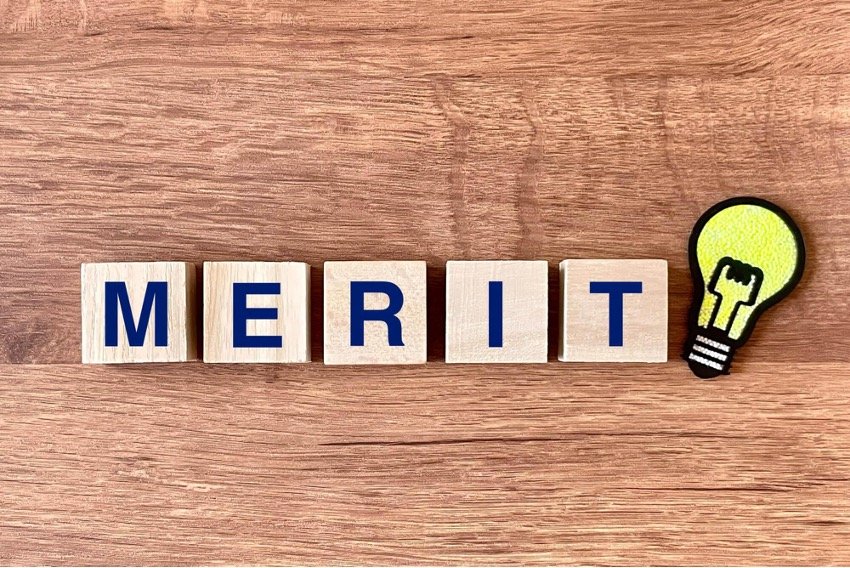
農地が生産緑地として指定されると、固定資産税の軽減や、贈与税・相続税の納税猶予といった優遇措置を受けることができます。
本章では、生産緑地の指定によるメリットについて解説します。
固定資産税が減額される
生産緑地に指定されると、固定資産税を低く抑えられます。生産緑地は市街化区域にあるものの、農業以外の利用が制限されているため、固定資産税は一般農地と同じ扱いとなり、税負担が軽減されます。
相続税・贈与税の納付猶予、免除を受けられる
生産緑地を相続や贈与により取得した後継者が、一定の条件を満たして農業を継続する場合、贈与税・相続税の納税が猶予され、最終的に免除される可能性があります。具体的に猶予される税額は以下の通りです。
- 贈与税:本来納めるべき贈与税の全額
- 相続税:通常の評価額で計算された相続税と、農業投資価格(※)に基づいて算出された相続税の差額
(※農業投資価格とは農業を続ける前提で設定された売買価格であり、宅地としての評価額よりも低く抑えられています。)
この制度では、当初は納税が猶予されますが、一定の条件を満たし続ければ最終的に免除されます。
生産緑地の相続税の評価方法
生産緑地の相続税評価額は、その土地が生産緑地でない場合の評価額から、一定の控除割合を適用して算出されます。
具体的な計算方法と控除割合は以下の通りです。
生産緑地の相続税評価額 = その土地が生産緑地でない場合の評価額 × {1 - (以下の(1)または(2)のいずれかに該当する割合)}
(1)
課税時点において、市町村長に買取り申出を行うことができない生産緑地は、買取りの申出ができるまでの期間に応じて、以下の控除割合が適用されます。
5年以下:10%
5年超 10年以下:15%
10年超 15年以下:20%
15年超 20年以下:25%
20年超 25年以下:30%
25年超 30年以下:35%
(2)
課税時点において、市町村長に買取り申出を行っている、または申出が可能な生産緑地
控除割合:5%
相続税の納税猶予を受けるには?
被相続人の範囲(納税猶予の対象となる農地の所有者)
以下のいずれかに該当する者が、納税猶予の対象となります。
- 死亡時点まで農業を営んでいた者
- 生前に農地を一括贈与し、贈与税の納税猶予を適用していた者
- 死亡時点まで特定貸付けまたは認定都市農地貸付けを行っていた者(※)
相続人の範囲
- 相続税の申告期限までに農業の経営を開始して、後も継続して農業を営む者
- 生前一括贈与を受けた者
- 相続税の申告期限までに特定貸付けまたは認定都市農地貸付けを行った者
納税猶予の対象となる農地等(猶予適用農地)
被相続人が生前に農業に使用していた農地または特定貸付け・認定都市農地貸付けを行っていた農地(※)のうち、以下のいずれかに該当するものが納税猶予の対象となります。
- 被相続人から相続により取得し、遺産分割が確定している農地等
- 生前に贈与税納税猶予の対象となっていた農地等
- 相続の年に、被相続人から生前一括贈与を受けた農地等
(※)特定貸付け:市街化区域外の農地(採草放牧地を含む)が対象。
(※)認定都市農地貸付け:生産緑地地区内の農地が対象。
生産緑地の相続に関する手続き
生産緑地を相続した場合、その指定を維持するか解除するかにかかわらず、所有権移転登記・農業委員会への相続届け出・市区町村役場への届け出が必要です。
生産緑地の指定を解除したい場合は、これらの手続きを終えた後に、買取り申出を行うことが求められます。特定生産緑地の制度を利用する方法もあります。
不動産の所有権移転登記を行う
生産緑地を相続した場合、不動産の所有権移転登記が必要です。
農業委員会への相続届出を行う
生産緑地を相続した際には、農業委員会への届け出も必要です。届出先は農地が所在する市町村の農業委員会で、届出の期限はおおむね10か月以内とされています。
市区町村役場への届出を行う
生産緑地変更届に相続前後の所有者の氏名などを記載し、市区町村役場に届け出をします。
市区町村役場での手続きは地域によって異なる場合があるため、事前に役場へ確認しましょう。
特定生産緑地の制度を利用する
申出基準日(生産緑地が指定された告示の日から30年が経過した日)までに特定生産緑地として指定を受けた場合、買取り申出ができる時期が延長されます。
生産緑地に関する相続税の取扱い

生産緑地には、相続税の納税猶予の適用があります。ここでは、その納税猶予を受けるための条件や手続きについて詳しく説明します。
相続税の納税猶予制度
前述した通り、納税猶予を受けるためには、被相続人が死亡時点まで農業を営んでいた・生前に農地を一括贈与し、贈与税の納税猶予を適用していたなどの条件を満たす必要があります。
また、相続人は相続税の申告期限までに農業の経営を開始し、後も継続して農業を営む・生前一括贈与を受けたなど、いずれかの要件を満たしていることが条件となります。
納税猶予を受けるための手続きの流れ
納税猶予を受けるには、税務署での手続きが必要です。相続税申告書に納税猶予に関する書類を添付して申請するため、相続税の申告期限内に準備を整えましょう。相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
納税猶予に必要な書類
| 必要書類 | 取得場所 |
| 相続税納税猶予に関する適格者証明書 | 生産緑地を管轄する農業委員会 |
| 特例適用農地の明細書 | 生産緑地を管轄する農業委員会 |
| 相続税納税猶予の特例適用農地等該当証明書 | 生産緑地を管轄する市役所 |
| 担保提供書 | 国税庁のホームページからダウンロード |
| 抵当権設定登記申請書 | 法務局 |
| その他特例の適用要件を確認する書類 | - |
さらに、納税猶予された相続税額とその利子を合わせた金額に相当する担保を準備する必要があります。
また、納税猶予を継続するためには、相続税申告期限から3年ごとに税務署へ継続届出書を提出することが求められます。
相続税の納税猶予を受けた場合の注意点
相続税の納税猶予には、適用が中止される場合があるため注意が必要です。
以下のような状況に該当すると、納税猶予が中止される可能性があります。
- 生産緑地を贈与や譲渡した
- 生産緑地を転用した
- 障害や疾病がないのに、使用貸借権や賃借権を設定して貸し付けた
- 生産緑地での農業をやめた
- 3年ごとの継続届出書を提出しなかった
- 生産緑地の買取り申出を行った
- 生産緑地の指定解除が行われた
生産緑地は指定から30年経過後に買取り申出が可能になります。しかし、買取り申出をすると、それまで猶予されていた相続税を支払わなければならなくなるので注意が必要です。
納税猶予が中止されると、猶予された税額に対して利子税が加算されます。利子税は、相続税申告期限の翌日から猶予が中止されるまでの日数に応じて課されます。
利子税を考慮すると、特例を受けない方が有利な場合もあります。もし相続が近い場合、経済状況を慎重に見極めて決定することが重要です。
生産緑地に指定されるデメリット
生産緑地は税制面での優遇措置がありますが、いくつかのデメリットも存在します。
生産緑地の2022年問題
2022年に生産緑地問題が注目された背景には、生産緑地の指定解除条件があります。1992年に導入された生産緑地制度では、制度開始と同時に指定を受けた土地が、30年後の2022年に解除要件を満たす仕組みとなっていました。そのため、多くの土地所有者が自治体に買い取りを申し出ることが予想され、土地価格の下落が懸念されました。これを受けて、国は特定生産緑地制度の制定や、建築規制の緩和、農家レストランの設置可能といった対策を講じています。
生産緑地として管理を続ける必要がある
生産緑地に指定されると、その土地を農地として管理する義務が発生します。農業を続けていれば問題ないですが、市区町村への報告や立入検査を受けることが求められる場合があります。
宅地化や建物の新築・開発ができない
生産緑地では、基本的に宅地化や建物の新築・開発は認められていません。ただし、倉庫や温室などの農業に必要な施設、作物の加工・販売設備などについては、市区町村の許可が得られれば設置が可能です。
なお、生産緑地は指定解除の要件を満たさなければ、宅地や農地として売却することもできません。
まとめ
現在生産緑地となっている田畑を相続発生時に残すのか、活用・売却するのかを検討する上で、生産緑地の相続税評価額を認識しておくことは重要です。
また、2022年問題と言われる宅地の供給過多は特定生産緑地制度の制定等により発生していませんが、いずれにしても今後承継・運用・管理を見つめ直す必要があります。
監修者
- 相澤 光Aizawa Hikaru
- コンサルティング事業本部 コンサルティングサービス室 室長 兼 第四事業部 ダイレクトグループ グループ長
資産家の方々が抱える「資産を守り、次世代へつなぐ」という課題に向き合い、不動産や法人を活用した円滑な財産の承継・運用・管理をサポートしてきました。
私が何より大切にしているのは、「まずお話をじっくり伺うこと」。資産の規模や構成だけでなく、ご家族の想いや背景を丁寧に理解したうえで、収益性の向上や財産分割などを一緒に考えていきます。なぜなら、家族の数だけ“正解”があると考えているからです。
「〇〇が気になっている」「何から手をつければいいかわからない」といったご相談を多くいただきますが、「専門家に任せる」のではなく、「一緒に進めていく」スタイルを大切にしながら、これまで多くのご家族の資産承継に伴走してきました。
- 専門分野
- 土地持ち資産家、金融資産家向けコンサルティング
- 資格
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
- 著書
- 『「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策』
(青山財産ネットワークス刊)
資産承継における実務と心情の両面に寄り添った内容が評価され、2021年11月には紀伊國屋書店新宿本店のビジネス書ランキングで第1位を獲得しました。