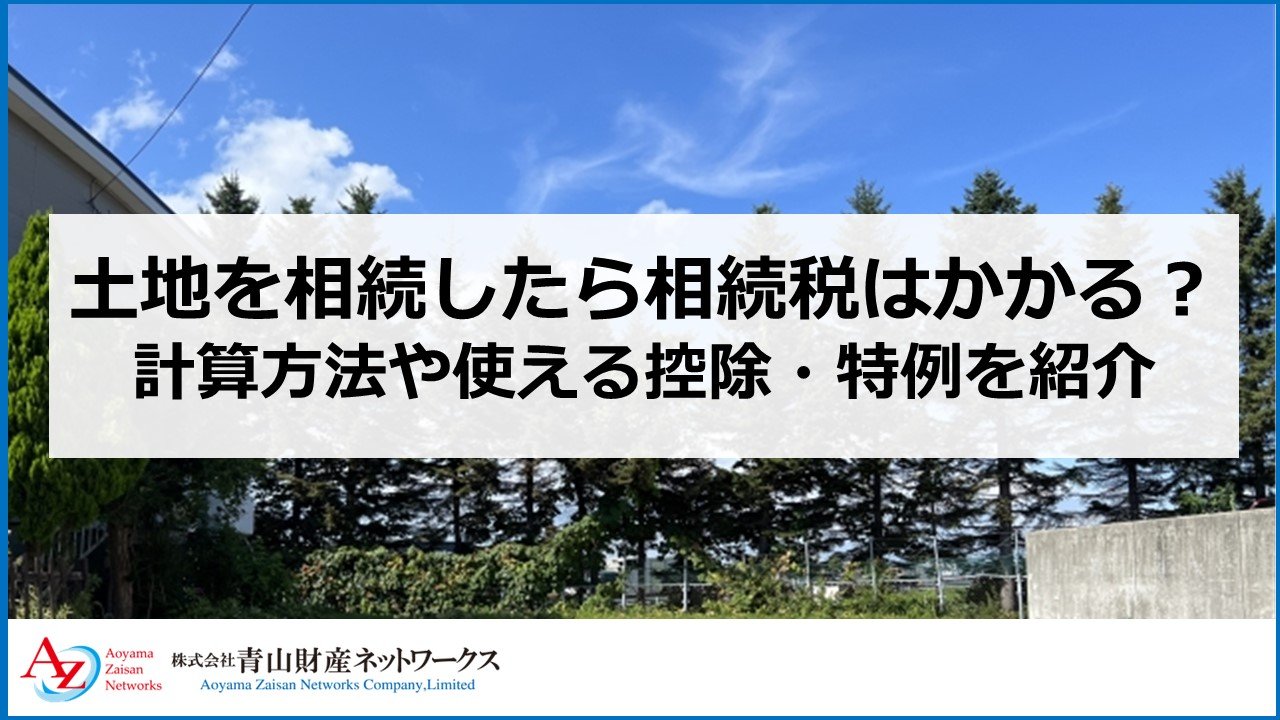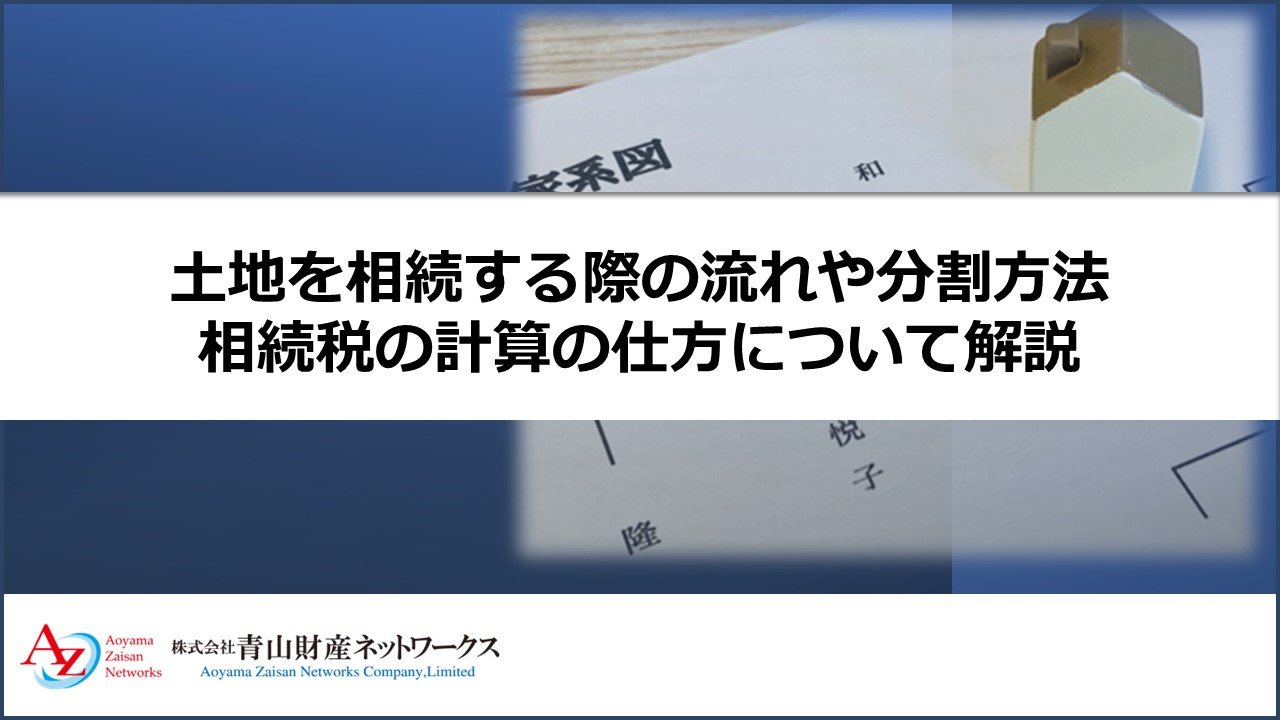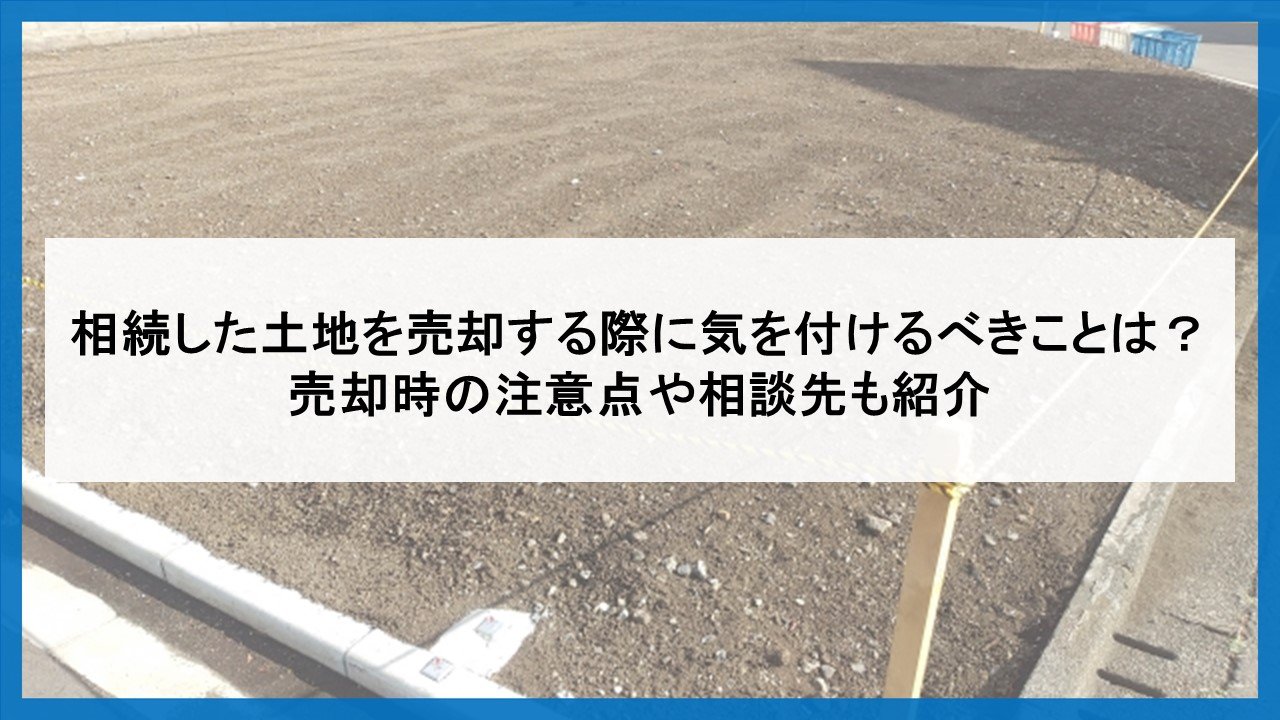遺産を相続する際、具体的な方法が分からず困ることは珍しくありません。特に、土地と現金を両方相続するケースでは、相続人同士でどのように分け合えば円満に解決できるか悩む方が多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、相続した土地と現金を分ける方法や相続手続きの流れについて詳しくご紹介します。また、トラブルが起こりやすい事例や注意すべきポイントについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
土地の相続は争いが起きやすい?
相続財産になり得る資産には現金や有価証券のほかに不動産も含まれますが、不動産の相続はトラブルを引き起こすリスクが高いため、注意が必要です。
この章では、不動産相続に関する現状について説明します。
土地の相続は金額が大きい
国税庁は相続財産の詳細について調査し、結果を発表しています。「相続税の申告事績の概要」によると、例年、相続財産の中でも土地は金額として大きな割合を占めています。
相続財産の金額の構成比としては、令和5年で土地が31.5%、現金・預貯金等が35.1%、有価証券が17.1%、家屋が5.0%、その他が11.4%と、土地は相続財産の金額の3割以上を占めており、現金・預貯金等と並ぶほどに大きい金額であることが分かります。
不動産は相続分で争いが生じやすい
現金と異なり、不動産の相続はトラブルが発生しやすいという現実があります。その大きな理由は、不動産の物理的な分割が非常に困難であること、その価値が一見して明確でないこと、相続方法についての判断が難しくなることからです。
現金であれば、相続人全員にほぼ均等に分けることができ、価値もすぐに分かるため、トラブルが起きにくいです。しかし、不動産はそのままでは分けられないため、どのように処理するかが問題となります。
また不動産の相続においては、その評価額が市場の動向や周囲の状況によって変動するため、価値をどのように計算するかで争いが生じることもあります。
不動産の価値は土地や建物の面積、立地条件、築年数など、さまざまな要素が絡み合って決まります。これらの要素をどのように評価し、相続人同士でどのように分けるかについては、意見が分かれることも少なくありません。
例えば、相続人全員が不動産の売却を希望したとしても、相続人同士で売却益をどう分けるかについての意見が合わない場合があります。
また、ある相続人が不動産の売却を希望する場合でも、その物件がほかの相続人にとっては思い入れが深かったり、売却した結果金銭的に不均等になったりするケースもあり得るため、感情的な対立も起こりやすくなります。
さらに、たとえ親しい兄弟姉妹であっても、不動産やお金が関わると、些細な誤解が大きな争いに発展することは少なくありません。特に、相続人同士での話し合いが不足していたり、一部の相続人が独断で決定を下したりするようなことがあると、ほかの相続人がその決定に反発して深刻な対立に発展することがあります。
このような事態を避けるためには、事前に相続の計画をしっかりと立てておくことが非常に重要です。相続人同士でよく話し合い、誰がどの不動産を相続するのか、またその価値の評価方法について合意を得ておくことが、後々の争いを防ぐ鍵となります。
さらに専門家に相談し、相続に関する法律的なアドバイスを受けておくことも大切です。事前に遺言書を作成しておくことも、相続の際に争いを防ぐ手段として有効です。
特に、不動産は家族間での感情的な結びつきが強くなるため、事前の準備をしっかりと行っておくことが、後々の平和な相続を実現するためには欠かせない要素といえるでしょう。
問題解決には現金化が有効
相続人が相続した不動産を利用しないのであれば、その不動産を売却して現金化することで争いを避けることができるでしょう。
しかし、相続した不動産はほかの共有者と合意しない限り、売却や貸し出しができません。そのため、不動産をそのまま放置するケースが多く見受けられます。利用できない不動産を相続してしまうと、固定資産税だけが負担となり続けることになります。
不動産を一度相続すると、その後の手続きが煩雑になることが多いため、早い段階で相続人全員が納得できる形で現金化して、均等に分配する方法がもっとも効果的な選択肢といえるでしょう。
土地と現金を分けるための4つの分割方法
相続財産に不動産が含まれている場合、その不動産の遺産分割は、次の4つの方法のいずれかで行われます。
現物分割
現物分割とは、遺産を実物のままで分ける方法です。例えば、遺産として預金と土地がある場合、長男が預金を、次男が土地を相続するという方法が現物分割に該当します。
代償分割
代償分割とは、特定の相続人が遺産を受け継ぐ代わりに、ほかの相続人に対して金銭での補償を行う方法です。
例えば遺産が土地(評価額2,000万円)のみの場合、長男が土地を相続する代わりに、次男に1000万円の代償金を支払うという形です。この方法をとることで、遺産を売却せずに保有し続けながら、公平な分割を実現できます。
ただし、代償金を支払う相続人にはそのための資金が必要になります。
換価分割
換価分割は、遺産を売却して得た売却代金を相続人の間で分ける方法です。
もし、相続人の中で不動産を引き継ぎたい人がいない場合、不動産を売却することで公平に遺産を分割することができます。ただし、売却には時間がかかる場合があり、その点がデメリットとなることもあります。
共有分割
共有分割は不動産を特定の相続人に渡すのではなく、相続人全員で共有する形にする方法です。この方法を選ぶと、不動産は相続人全員の共有財産となります。
共有分割の利点は、法定相続分に基づいて各相続人の持ち分を決めることで、公平に遺産を分けることができる点です。しかしリスクも伴うため、共有分割を選ぶ際には将来の問題を考慮して慎重に判断することが重要です。
土地の相続におけるトラブルとは?

土地を相続する際に、どのような問題が生じるのでしょうか。
現物分割における問題
相続する土地に一定の広さがある場合、土地をいくつかの区画に分けて現物分割することができます。どの区画を誰が相続するかという点で、相続人同士のトラブルが起こることもあります。
代償分割に関連する問題
土地を相続する人がほかの相続人に代償金を支払うための十分な資金がないと、代償分割を実施することができません。
換価分割での問題点
土地を売って現金とする換価分割では、売却に際し相続人全員の合意が必要です。そのため、価格や売却自体についての合意が難しい場合、トラブルに発展することがあります。
共有分割で生じる問題
共有分割は、相続人同士でトラブルが起きやすい分割方法です。相続した土地を共有することで、遺産分割協議は一見スムーズに進むかもしれません。しかし、その土地をどう使うかで意見が分かれることがあります。
土地と現金を相続する際の手続きの流れ
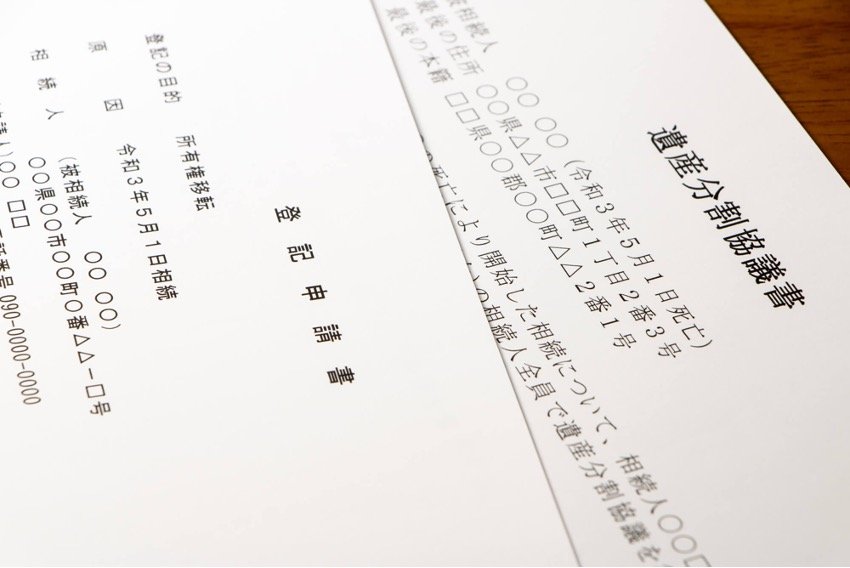
土地や現金を相続する際には、遺言書の確認、相続人・相続財産の確定、そして遺産分割協議や相続登記などの手続きを踏む必要があります。事前にこれらの手順を理解しておくことで、スムーズに計画的に進めることができます。
もし手順を知らないまま進めると相続手続きが滞り、思いどおりに進まないことがあり、トラブルを招くことも考えられます。土地や現金などの相続財産を適切に分割するためにも、事前に進行手順をしっかり確認しておくことが重要です。
この章では、土地と現金を相続する際の具体的な流れについて詳しくご説明します。
遺言書の有無を確認する
故人が遺言書を作成していた場合、その遺言書に記載された内容に従って、土地や現金などの相続財産を相続人間で分割します。遺言書には主に次の3種類があり、それぞれの保管場所は異なります。
- 自筆証書遺言:遺言者または法務局で保管
- 公正証書遺言:公証役場で保管
- 秘密証書遺言:遺言者で保管
遺言書は法的効力が強く、法定相続分よりも優先されるため、遺言書に記載された財産分けの内容が、法律で定められた相続分と異なっていても、遺言書の内容が優先されます。
相続財産と相続人を確定する
次に、専門家に相談して、土地や現金などの相続財産および相続人を確定させます。相続財産や相続人が確定しないと、遺産分割を進めることができません。
もし遺言書が存在しない場合、法定相続人とその割合に従って、土地や現金などの財産を分割します。
相続財産には土地や現金だけでなく、借金やローンなどの負債も含まれるため、それらの有無も確認する必要があります。借金が多い場合、相続放棄を選択することも検討できます。
また、土地の固定資産税評価額は以下の方法で確認できます。
- 毎年送られてくる固定資産税の課税明細書で確認
- 役所で固定資産課税台帳を閲覧
- 役所で固定資産税評価証明書を取得
法定相続人の調査が必要な場合は、被相続人の戸籍謄本を見ます。
遺産分割協議を実施する
遺産分割協議は相続人全員で土地や現金などの財産の分配方法について話し合い、合意を形成するプロセスです。
財産の分け方に関して全員の合意が得られた場合、遺産分割協議書を作成します。この協議書には、すべての相続人の署名と捺印が必要です。
もし財産の分け方について合意が得られない場合は、遺産分割調停・遺産分割審判にて裁判所に財産分配の決定を頼む方法もあります。
またコンサルティング会社などの専門家に依頼して協議を進めることも可能です。専門家に任せることで、協議や手続きに関する負担を減らし、トラブルを未然に防ぐことにつながります。
遺産分割協議での財産分配決定に際して、専門家のアドバイスを受けることも一つの選択肢です。
相続登記を行う
土地や現金などの財産の分割が決定した後は、相続登記を行う必要があります。相続登記とは、不動産などの名義を相続人に変更する手続きです。
相続登記を行わないままでいると、その不動産を売却したり、融資の担保として利用したりすることができなくなります。また、ほかの相続人が不正に遺言書を偽造するなどのトラブルに巻き込まれるリスクもあります。
2024年4月1日から、不動産の相続登記は義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。義務化後、期限内に登記しなかった場合、最大10万円の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。
なお義務化以前に相続した不動産についても、相続登記が必要です。
相続登記の手続きは、専門家に依頼することが可能です。専門家に依頼すると報酬がかかりますが書類作成や手続きにかかる時間と手間を省き、正確に進めることができます。
まとめ
遺産を分割する際には、トラブルに発展することが少なくありません。円満に遺産を分けるためには、遺産分割協議書を作成することや、不動産相続に詳しいコンサルティング会社などの専門家に相談することが有効です。
少しでもお悩みございましたら、ぜひ青山財産ネットワークスまでご相談ください。
監修者
- 相澤 光Aizawa Hikaru
- コンサルティング事業本部 コンサルティング総合力推進室 室長
資産家の方々が抱える「資産を守り、次世代へつなぐ」という課題に向き合い、不動産や法人を活用した円滑な財産の承継・運用・管理をサポートしてきました。
私が何より大切にしているのは、「まずお話をじっくり伺うこと」。資産の規模や構成だけでなく、ご家族の想いや背景を丁寧に理解したうえで、収益性の向上や財産分割などを一緒に考えていきます。なぜなら、家族の数だけ“正解”があると考えているからです。
「〇〇が気になっている」「何から手をつければいいかわからない」といったご相談を多くいただきますが、「専門家に任せる」のではなく、「一緒に進めていく」スタイルを大切にしながら、これまで多くのご家族の資産承継に伴走してきました。
- 専門分野
- 土地持ち資産家、金融資産家向けコンサルティング
- 資格
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
- 著書
- 『「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策』
(青山財産ネットワークス刊)
資産承継における実務と心情の両面に寄り添った内容が評価され、2021年11月には紀伊國屋書店新宿本店のビジネス書ランキングで第1位を獲得しました。