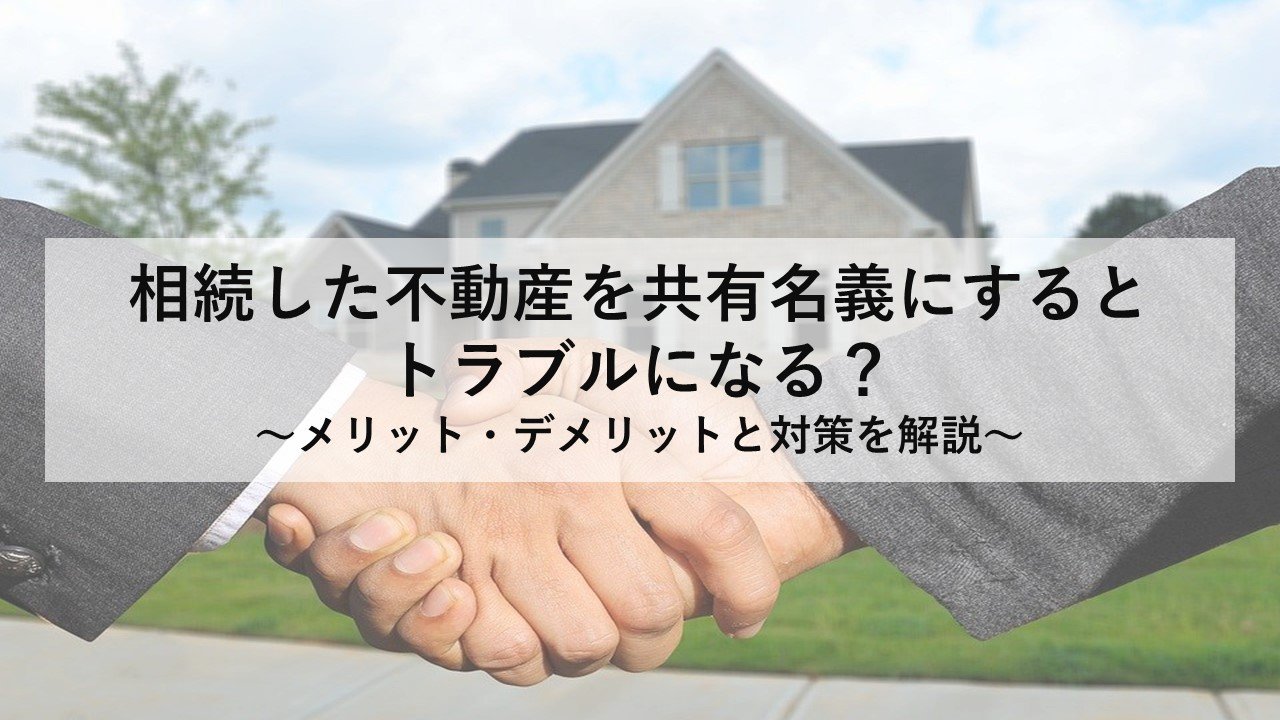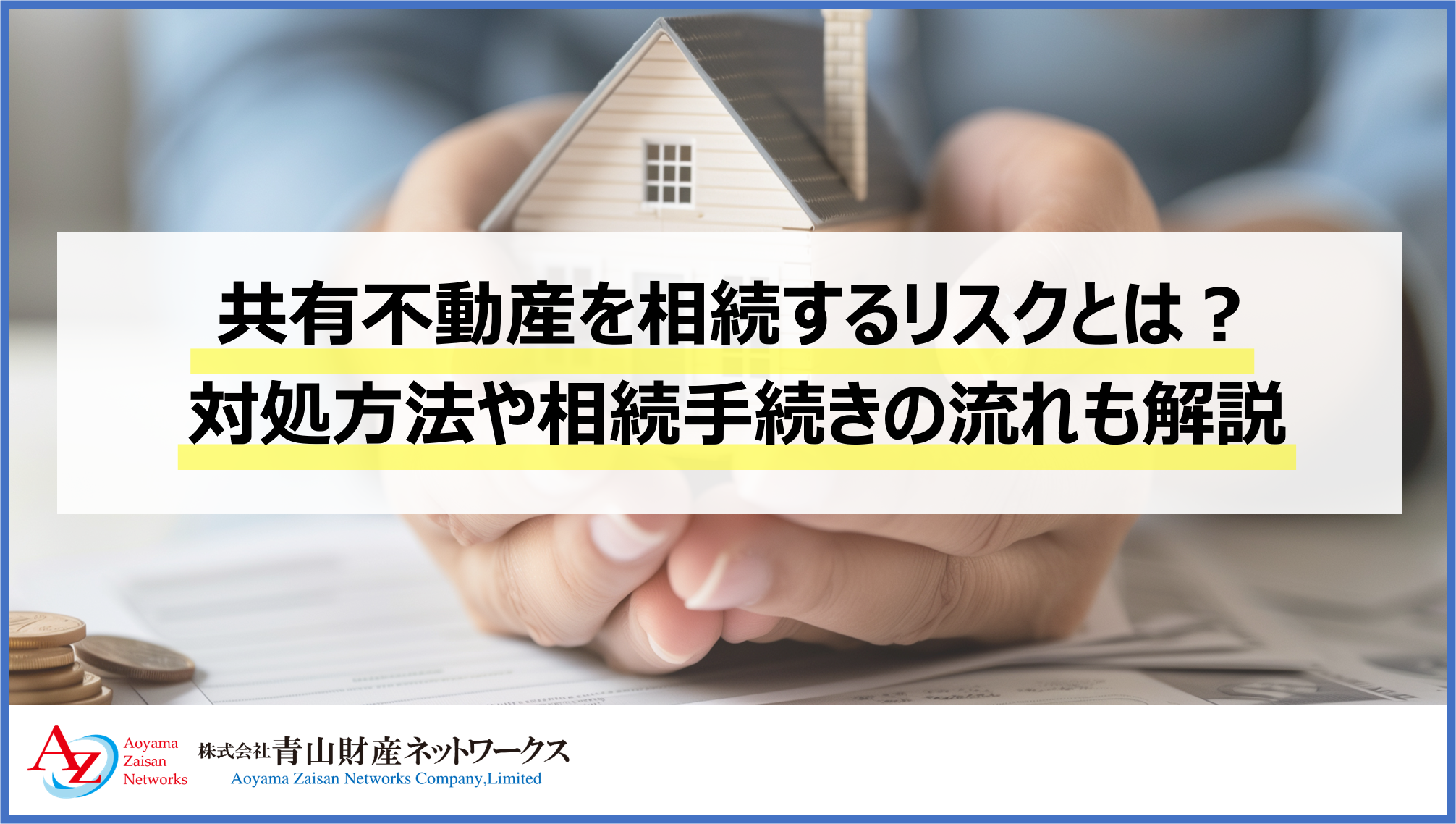親から相続する財産に、現金以外にも建物・土地といった不動産が含まれているケースもあるでしょう。現金であれば公平に等分することも可能ですが、不動産は均等に分割することが難しい財産です。不動産を相続するとき、兄弟で公平に等分するにはどういった方法を取ると良いのでしょうか。
この記事では、兄弟でトラブルなく不動産を分割する方法や、相続時の注意点を解説します。
兄弟で不動産を相続するとき
基本的に相続人が兄弟のみであることを前提にすると、親から財産を相続する際、不動産を相続する場合は兄弟で等分するのが基本です。しかし、土地などは公平に分割するのが難しく、兄弟同士でトラブルに発展する恐れがあります。
不動産を相続したら兄弟で等分する
不動産を相続したときは、他の遺産と同様に相続人で分割して相続します。遺産のうち、被相続人に配偶者がいれば2分の1、被相続人の子ども(ここで言う兄弟)が残りの2分の1を分配して相続するのが原則です。
遺言書があれば、その遺言書の記載通りに遺産を分割します。ただし、親を介護していたことで他の兄弟よりも多く相続できる「相続の寄与分」や、被相続人から多額の生前贈与を受けた兄弟には「特別受益」があったとして、相続分の調整が行われるケースもあります。
土地などの不動産は相続しても公平に等分するのが難しい
不動産は、現金のように均等に分割するのが難しい財産です。評価基準によって不動産の価値は変わるため、相続時に兄弟間でトラブルになる可能性があります。
不動産を相続する際に兄弟でトラブルなく分割する方法
不動産を相続するとき、兄弟同士でトラブルなく公平に分割する方法として、「遺産分割協議」や「分筆」、「代償分割」や「換価分割」が挙げられます。この他に、「相続放棄」を行うケースもあります。
遺産分割協議を行う
遺産分割協議とは、被相続人が他界した後に、相続人同士で遺産を分ける方法を決める話し合いのことです。遺産分割協議自体に期限はありませんが、「寄与分」や「特別受益」の主張ができる期間が、相続開始を知った日から10年以内に限定されます。そのため、実質10年以内には、協議を完了しなければなりません。また、相続税の納税義務がある人は、相続税の納税期限を考慮し10ヶ月以内に協議を終わらせると良いでしょう。
協議の合意後は、合意した内容を遺産分割協議書に記載します。誰がどの財産を相続したのかといった情報を確認できるため、後々のトラブル発生を防げるでしょう。
分筆して現物分割する
分筆とは物理的に土地を区切って分割する方法で、土地を相続した場合は土地の分筆が可能です。兄弟それぞれが別々の土地として相続でき、用途によっては税金も抑えやすいというメリットもありますが、測量や登記申請などの費用がかかります。
分筆は、兄弟全員が土地をそのまま相続したいときに有効な方法です。しかし、分筆によって土地が極端に狭くなり、価値が下がってしまうケースも見られるため注意しましょう。
代償分割を行う
不動産を相続する人に十分な経済力があるならば、代償分割も検討できます。代償分割とは、土地などの不動産を相続した人が他の相続人に代償金を支払うことで、公平に分割できる方法です。相続した不動産を、自宅や事業用に使用している場合に向いています。
土地であれば単独名義で相続できるのがメリットですが、代償金額の決め方でトラブルが起きる可能性もあるため注意が必要です。代償分割で不動産を相続した人が、他の兄弟に代償金を支払う場合、受け取る側に贈与税が課税されるケースもあります。特に、代償金額が時価を大きく上回る時は、課税関係について確認した方が良いでしょう。
換価分割を行う
不動産を売却し、その売却金を兄弟で分割する方法が換価分割です。不動産でなく現金の分割になるため、公平に遺産を分割できます。
売却した不動産は手放すことになり、売却益には譲渡所得税が課税されます。
なお、換価分割を行うには、相続人全員の同意が必要です。相続人の中に不動産の取得を希望する者がいる場合は売却ができず、換価分割は選択できません。
相続放棄する
相続する遺産より負債の方が大きい、不動産の相続に関わりたくないといったとき、相続放棄が行われるケースがあります。相続放棄とは、遺産を相続する権利・義務を放棄する手段です。相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」を提出して申し立てを行います。申請には、1人につき800円の収入印紙代がかかります。
相続放棄を行うと、被相続人が残した負債の相続を免除してもらえますが、預貯金など利益になり得る財産も相続できません。相続放棄後に相続可能な遺産が見つかっても、遺産分割協議には参加できない仕組みです。
兄弟のうちの1人が相続放棄した場合は残りの兄弟で遺産を分割しますが、兄弟全員が相続放棄したケースでは、被相続人の親族が相続人となります。
不動産を相続するときに兄弟でトラブルが起きやすいケースとは?
不動産の相続時に兄弟同士でトラブルが起きやすくなる状況として、以下の5つのケースが考えられます。
遺言書が作成されていない
遺言書は必ず作成しなければならないものではありませんが、遺言書が作成されていれば、その内容を基に遺産を分割できるため、トラブルの発生を抑制できます。
遺言書がない場合は、基本的に遺産分割協議によって遺産の分割内容を決めていきます。しかし、協議では相続人全員が合意するまで話し合いを続けなくてはなりません。話し合いが長引いたり、なかなか合意を得られなかったりすると、兄弟同士で揉めてしまう原因にもなります。
相続する財産の大半が土地などの不動産
不動産は、現金のように均等に分割するのが難しい財産です。相続する財産の大半が不動産で、そのほとんどが土地である場合、兄弟同士で揉める可能性があります。土地を売却して、その売却金を分割する換価分割を選ぶケースもありますが、その土地に兄弟の誰かが相続の対象となる不動産に住んでいるのであれば、換価分割はできません。
土地の相続人に十分な資金力があれば、代償分割が可能です。分筆を選択する際は、話し合いで解決する必要があります。
遺留分の侵害がある
遺留分とは、最低限保障されている相続割合(取り分)のことで、対象は配偶者の他に子どもや親、孫などです。遺言書があっても、遺言で一部の相続人が多めに財産を相続する内容が記載されている場合、「相続した遺産が遺留分より少ない、遺留分を侵害された」と主張する相続人が出てくる可能性があります。
なお、遺留分を侵害している内容の遺言は有効です。
寄与分の主張がある
寄与分とは、無償あるいは無償に近い貢献があったこと、例えば被相続人の介護・看護をしていた相続人がいた場合に、法定相続分よりも多くの財産を取得できる制度です。寄与分の主張により、他の兄弟よりも多く財産を相続できるケースがあります。
例えば、兄と弟がいて親と同居する兄が被相続人である親を介護していた場合、弟に対して寄与分を主張することが可能です。兄の主張に対して弟が納得すれば、相続に関するトラブルには発展しないでしょう。しかし、納得しない場合は、家庭裁判所での調停になります。
特別受益の主張がある
被相続人が生前に、相続人である特定の兄弟に財産の贈与をしており、その兄弟が利益を得ていたことを指すのが特別受益です。親から土地などの生前贈与を受けていると、他の兄弟から特別受益を主張されるケースもあります。
特定の兄弟が特別受益に相当する贈与を受けていた場合、兄弟間の相続財産に差が出ることが認められています。特別受益は遺産を前渡ししたと見なされることから、他の兄弟の相続割合を多くして調整するのが特徴です。
相続分に差が出るとトラブルにつながりやすくなりますが、特別受益は明確な理由がないと、ほとんどの主張が認められません。
兄弟で不動産を相続する際の注意点
不動産を相続する際は、兄弟同士で揉めないためにも以下の6つのポイントに注意しておきましょう。
異母兄弟・養子でも法定相続分は同じ
相続する際は、実の兄弟だけでなく異母兄弟や養子の兄弟であっても法定相続分は同じです。母親が違う兄弟以外に、婚姻関係になかった子どもでも、認知されていれば父親の相続人になります。養子縁組した養子は、親の法定血族になるため、相続に関する権利は実子と変わりません。
相続人が複数いると土地は共有状態になる
遺産分割協議が成立するまでの間、相続した土地は兄弟全員で共有する状態になります。また、代償分割などの分割方法を選択するか、単独で相続する人を決めるかしないと、個人の意思で処分や売却はできません。
土地が共有状態だと固定資産税を連帯納付しなければならない
固定資産税は毎年発生し、納税通知書が代表相続人に送付されます。納税通知書が代表相続人に届くことから、共有者間で法定相続分などに応じて負担割合を決めておくことが重要です。
共有名義の不動産で固定資産税を納付する際は、相続人の中から1名を代表して納めます。その後は、代表者は共有している持分に応じて、他の相続人にそれぞれの納付額を請求していく流れです。相続人のうち、固定資産税を支払わなかった人がいた場合、他の相続人が支払わなければなりません。
兄弟で分割の合意ができないときは遺産分割調停の申し立てを行う
兄弟で相続する不動産の分割について合意ができない場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行います。遺産分割調停とは、公平な立場の調停委員が当事者の間に入り、合意に向けた話し合いを行うことです。調停が成立したら、調停調書の内容に従い遺産分割を進めていきます。
相続登記は2024年4月から義務化されている
相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。そのため、不動産を相続したことを知った日から、3年以内に登記を行う必要があります。正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意しましょう。
なお、相続登記の義務化は過去の相続に関しても適用されるため、2024年4月1日以前に相続した不動産でも、2027年4月1日までに登記を完了させなければなりません。遺産分割協議が難航するなど、期限内に正式な相続登記が難しい場合は、「相続人申告登記」という暫定的手続きを利用できます。
兄弟間のトラブルを防ぐためには専門家への相談も検討する
兄弟で不動産を相続する際に困ったことや不明点があれば、弁護士や税理士、司法書士、市役所・区役所に相談すると良いでしょう。特に、弁護士は相続に関するトラブルの相談に強いのがメリットです。早めに相続対策や分割方法などを相談できれば、兄弟間のトラブル防止につながります。
まとめ
兄弟で不動産を相続する場合は、現金を相続するよりもトラブルに発展するケースが増える恐れがあります。そのため、換価分割や代償分割といった分割方法を検討する必要があるでしょう。相続する不動産を兄弟で揉めずに分割するには、遺産分割協議を行ったり専門家に相談したりする方法も有効です。専門家への相談を検討する際は、青山財産ネットワークスにご相談ください。
監修者
- 相澤 光Aizawa Hikaru
- コンサルティング事業本部 コンサルティングサービス室 室長 兼 第四事業部 ダイレクトグループ グループ長
資産家の方々が抱える「資産を守り、次世代へつなぐ」という課題に向き合い、不動産や法人を活用した円滑な財産の承継・運用・管理をサポートしてきました。
私が何より大切にしているのは、「まずお話をじっくり伺うこと」。資産の規模や構成だけでなく、ご家族の想いや背景を丁寧に理解したうえで、収益性の向上や財産分割などを一緒に考えていきます。なぜなら、家族の数だけ“正解”があると考えているからです。
「〇〇が気になっている」「何から手をつければいいかわからない」といったご相談を多くいただきますが、「専門家に任せる」のではなく、「一緒に進めていく」スタイルを大切にしながら、これまで多くのご家族の資産承継に伴走してきました。
- 専門分野
- 土地持ち資産家、金融資産家向けコンサルティング
- 資格
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
- 著書
- 『「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策』
(青山財産ネットワークス刊)
資産承継における実務と心情の両面に寄り添った内容が評価され、2021年11月には紀伊國屋書店新宿本店のビジネス書ランキングで第1位を獲得しました。