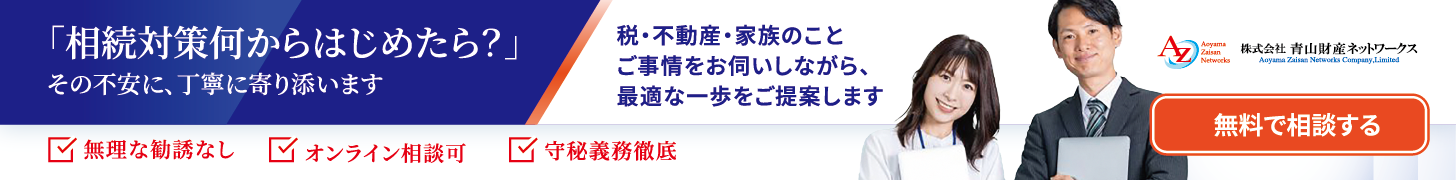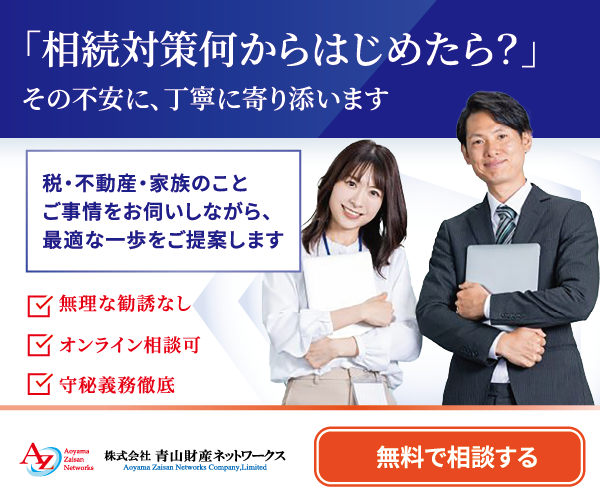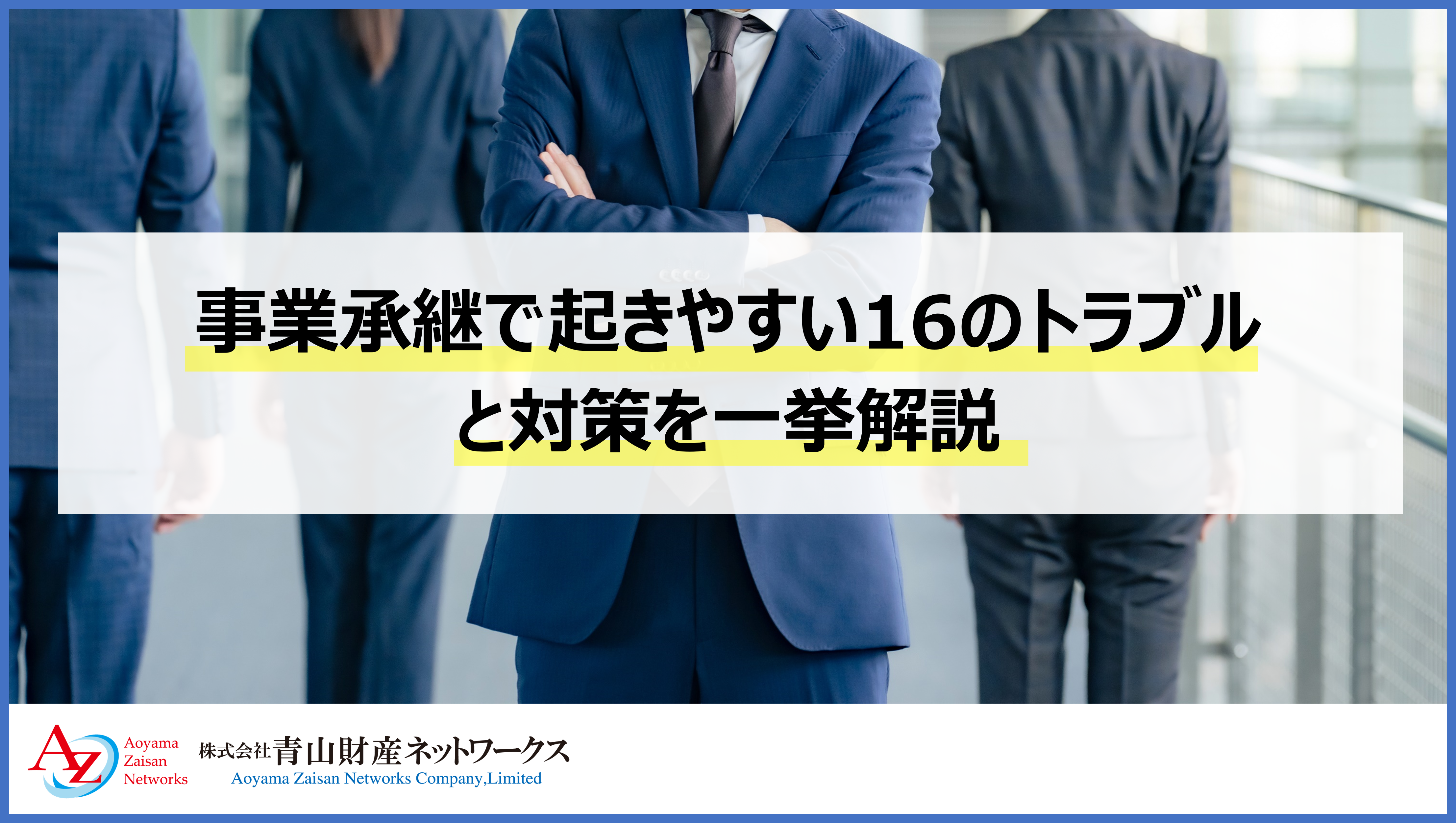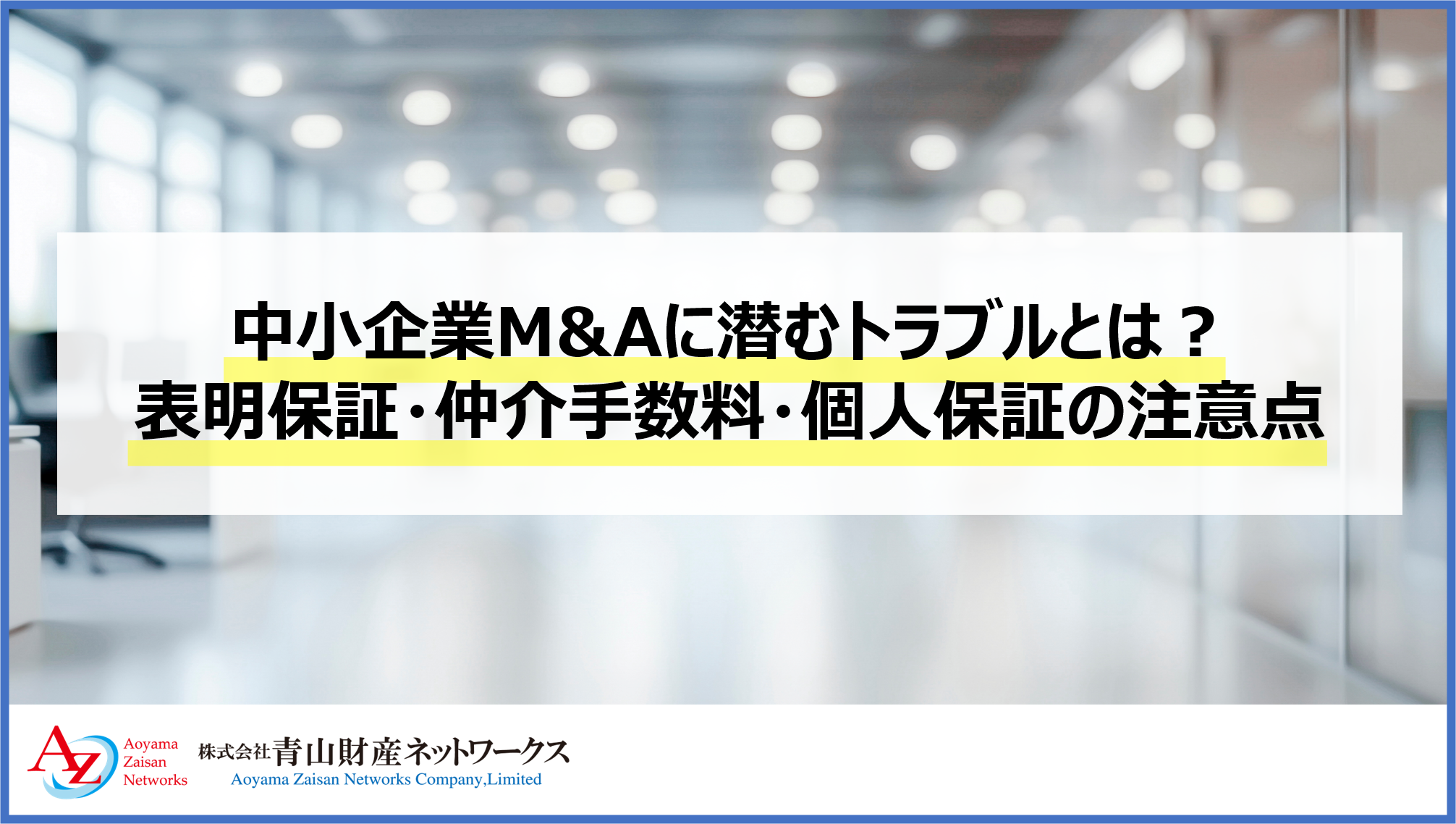中小企業の事業承継において、自社株は経営支配権と財産権の両面から大きな影響を持つ資産です。
非上場企業であるがゆえの株価評価の難しさ、相続税負担の重さ、相続人間でのトラブルなど、自社株をめぐる相続・承継トラブルは年々増加傾向にあります。
特に、株価の高騰によって相続税が支払えないケースや、経営に関与しない親族への"ありがた迷惑"な株式相続、準備していた死亡退職金の未支給といった問題は、事業継続を危うくしかねません。
本記事では、自社株承継に関する代表的なトラブル事例と、それに対する実務的な対策ポイントをわかりやすく解説します。
自社株は「扱いにくい資産」
自社株は、経営支配権(株主総会議決権)を表すと同時に財産的な価値を表すという2面的な性質があります。後継者への自社株の承継という場面では、この2面が相反する場合があります。承継後の経営支配権の安定という点では、なるべく多くの割合の自社株を後継者にまとめて承継させることが望ましくなります。一方、経営者個人の資産の承継(相続、遺産分割)という点では、複数の相続人がいる場合、後継者だけに株式を集中して承継させることは、公平な遺産分割の阻害要因となりかねません。経営安定化のための自社株集中承継と、公平な遺産分割という、相反する課題を共に解決するための対策を講じておかないと、いわゆる"争続"と呼ばれるような遺産分割争い、ひいては、会社経営をも巻き込んだ"お家騒動"のような事態になりかねません。
また、自社株は会社の業績・財務の状況が良好なほど、株価が高くなりますが、株価が高いほど事業承継の際の自社株移転コスト(相続や贈与であれば課税コスト、譲渡であれば譲渡対価)が高騰してしまう問題が生じます。かといって、業績・財務を悪化させて会社の価値を毀損させるのでは、本末転倒です。
さらに、自社株は通常、第三者に売却できる市場性が乏しく、現金化が困難なため、非常に扱いづらい資産でもあります。
このような自社株の複雑な性格をよく理解しておかないと、様々なトラブルの要因となります。
トラブル1 自社株を相続した後継者が相続税を支払えず、事業を売却
非上場企業株式(取引相場のない株式)の相続税評価には複数の方法があり複雑ですが、基本的に業績や財務状態がよい会社ほど、評価額が高くなります。最近業績が良かったり、厚い内部留保を蓄えていたりする会社では、想像以上に相続税評価額が高くなり、課税負担が増える場合があります。場合によっては納税負担のために事業継続ができなくなることもあるのです。
1-1.設例
社歴が80年以上になるH社は、強いブランド力を持つ老舗企業です。3年前に着手した新規事業が好調で、老舗企業にもかかわらず、毎年売上成長を実現しています。
2代目となるH社長は60歳の若さでしたが、あるとき、不幸にも交通事故に巻き込まれて亡くなってしまいました。H社長には35歳になる長男のX氏がいます。X氏はH社の業務執行役員に就いており、いずれ社長を継ぐものと、本人も周りも考えていましたが、H社長が急逝したことで、すぐに事業承継をせざるをえなくなりました。
H社長の配偶者はすでに亡くなっており、相続人はX氏ひとりです。
主な相続財産の内容とおおまかな相続税評価額は、H社の自社株の評価額が約7億円、自宅の土地建物が2億円、本社の土地建物が2億円、貯金や上場株式などの金融資産が約1億円で、合計で約12億円です。負債はありません。
事業承継はまだ先のことと考えていたX氏は、自社株の評価額についてきちんと確認したことはありませんでした。しかしH社は近年業績が非常によく、また長年の内部留保の蓄積で財務状態もよいため、思った以上に高い評価となりX氏を驚かせました。そしてそれ以上にX氏を驚愕させたのは、顧問税理士が試算した相続税の概算です。約5億7,000万円もの相続税を、10か月後に納税しなければならないというのです。相続財産のうち、仮にH氏の自宅が2億円で売却できたとしても、それと金融資産1億円をあわせて約3億円にしかならず、2億7,000万円ほど納税に不足します。教育費のかかる子ども2人を抱えているX氏に、個人資産はあまりありません。
悩んだ結果、X氏が出した答えは事業売却でした。本業ではなく、好業績を続けている新規事業を新会社に切り離してから、M&A譲渡することにしたのです。幸い、買い手はすぐに見つかり、X氏は約4億円の譲渡対価を得ることができました。所得税やM&A仲介会社への報酬を支払っても3億円程度のキャッシュが残り、なんとか相続税を納税することができました。しかし、せっかく軌道に乗った新規事業を売却して、みすみす会社成長の芽を摘んでしまったことが、X氏には心残りでした。
1-2.対策ポイント
「仮に、いま相続が発生したら、自社株はいくらで相続税評価されるのか」を、正確に把握している経営者は少数派でしょう。まして、後継候補者がそれを把握していることはほとんどないのが実情でしょう。そのため、設例のように不慮の事故などによって突然相続が発生すると、想像していた以上に自社株の評価が高く、相続税の納税資金が確保できないという状況に陥ることもあります。
こういったトラブルを防ぐには、少なくとも年に1回は税理士に自社株の評価と、相続税の概算見積を依頼し、経営者と後継候補者の両者が把握しておくことが、まず必要です。あわせて、実際に相続が発生した場合、納税資金が足りるのかを確認し、もし足りなさそうなら、その手当て方法も準備しておかなければなりません。例えば、生命保険や社長の死亡退職金を利用する方法などは、よく用いられています。
トラブル2 高額な自社株式を相続して"ありがた迷惑"の遺族
被相続人となる経営者が「親心」から、経営に関与していない相続人にも自社株を相続してあげよう考えてしまうことがあります。
しかし、経営に関与しない相続人にとって、自社株を相続されてもメリットはほとんどありません。その一方で、株式の相続税評価が高ければ、高額な相続税を支払わなければならず、不満に感じることが多くなります。場合によっては、それが親族間でのトラブルに発展することもあります。
2-1.設例
I社長が創業したI社は、堅実な成長を続け、業界では上場企業に準じる中堅企業に成長しました。I社長は、65歳のときに会長職に退き、代表取締役には長女のY氏が就きます。代表取締役交代の時点で、I会長が自社株の51%、Y氏が49%を保有しています。それから5年後に、I氏が亡くなって相続が発生しました。相続人は、Y氏の他に、Z氏(長男)がいます。I氏は遺言で、自社株について、自身が保有していた持分(発行済み株式総数の51%)の半分(同25.5%)をY氏に、残りの半分をZ氏に相続させると指定していました。株式総数の74.5%はY氏、25.5%はZ氏が保有することになります。
Z氏は現在、I社と無関係の会社で働いており、I社経営に関与するつもりはありません。しかし、I社長は、I社が将来株式市場へ上場できると考えており、そのときに備えてZ氏にも大きな資産となる可能性のあるI社株を相続させておいたほうがいいだろうと、親心で考えていたのでした。
Z氏とY氏が相続したそれぞれ25.5%の自社株の評価額は約2億円ずつです。それ以外にZ氏とY氏はそれぞれ、約1億5,000万円の金融資産と評価額1億5,000万円相当の不動産を相続しました。つまりそれぞれ5億円ほどの遺産を相続しています。その結果、それぞれが支払う相続税は約2億円になります。
Y氏は相続した金融資産に自らの貯蓄5,000万円を加えて相続税を納税できました。しかし、Z氏にはその余裕がありません。不動産を売却するか、担保にして融資を受ければ納税できます。
しかしそれよりもZ氏にとって、I社株は不要の財産だと感じられました。株式上場は、I氏の夢でしたが、いつになるかわかりません。というより、傍目から見ていて創業者のI氏ほど経営能力が高くないY社長の指導で上場が実現できるとは、Z氏には信じられませんでした。I社経営に興味のないZ氏にとって、非上場のままで配当もないI社株は、単に相続税を増やすだけで"ありがた迷惑"の遺産です。
そこでZ氏はY氏に対して、自分の保有株の一部をY氏個人か、I社で買い取ってくれないかと打診しました。しかしY氏はその申し出をけんもほろろに断ります。困ったZ氏は自社株を買い取ってくれそうな会社がないかを探しました。そして、知人からR社という会社を紹介され、コンタクトを取ることにしました。
2-2.対策ポイント
自社株を相続させる際には、相続人に経営に関与する意思があるのかなどを十分に確認した上で、課税も含めた経済的なメリットとデメリットを十分に考慮して相続させるようにしましょう。経営に関与する意思がない相続人には自社株は相続させず、相応の価額となる代替資産を準備しておき、相続させるようにしたほうがいいでしょう。生命保険を活用した代償分割を用いることも一法です。
また、相応の価額となる他の資産や、生命保険の用意ができず、どうしても自社株を経営に関与しない相続人に相続させたい場合、「取得請求権付株式」という種類株式を活用する方法もあります。普通株式では、会社が株主から株式の買い取りを請求されても、会社がそれに応じて株式を買い取る義務はありません。
(ただし、定款で譲渡制限が定められている株式において、第三者への譲渡承認を求められて、会社がそれを承認しない場合は、会社または会社の指定する第三者が買い取らなければなりません。)
しかし、取得請求権付株式では、会社は株主から請求された株の取得(買い取り)を拒否することができないのです。会社の剰余金に余裕があることが前提となりますが、取得請求権付株式を相続させることで、自社株の現金化を前提にしておく方法もあります。なお、取得請求権付株式は、先に説明した「取得条項付株式」と名前が似ていますが、正反対の性格を持つものである点に注意してください。
トラブル3 遺族のために準備した社長の死亡退職金が支払われない
自社株を相続する遺族の納税資金対策として、社長の死亡退職金が準備されることがあります。しかし、想定された死亡退職金の支給がなされずに、遺族と会社との間でのトラブルとなる場合があります。
3-1.設例
J社長は、まだ20代の長男X氏にいずれは会社を継いでもらいたいと考えていました。また、X氏もいずれは会社を継ぎたいと考えていましたが、30代までは海外での経験を積みたいという希望があり、J社には入社していませんでした。
J社の自社株は、J社長が70%、J社長の妻が30%を保有していました。J社長は、自分に万一のことがあった場合は、自分の保有株はすべてX氏に相続させようと考えていましたが、そうなると心配なのは相続税です。J社長が保有する株の評価は10億円ほどで相応に高額な相続税の納付が想定されます。
そこでJ社長は、会社を加入者、自分を被保険者で、そして受取人を会社とする保険金8億円の生命保険に加入しました。そして、自分に万一のことがあった場合は、得られた保険金を原資として8億円の役員退職金(死亡退職金)を遺族に支払うことを、取締役会で決議します。その生命保険契約には、法人税の繰り延べ効果もあり、当時業績が好調だったJ社にとって一石二鳥だと、J社長は考えていました。
保険加入から5年後に、J社長は病により亡くなりました。残されていた遺言どおり、自社株はすべてX氏が相続しました。
一方、会社から遺族に死亡退職金が支給されましたが、その金額は4億円(妻とX氏に2億円ずつ)でした。X氏が納付しなければならない相続税は5億円ほどで、2億円の死亡退職金では、自社株以外に相続した金融資産をあわせても、まったく不足しています。X氏は生前のJ社長から4億円の死亡退職金が得られるのでそれで相続税を納付するように聞かされており、また遺言にも同様の記載があるため、後任の代表取締役となったQ氏に抗議しました。
Q氏の言い分は「たしかに保険に加入した時点では、8億円の支払いは可能だと見込んでいたが、その後業績が低迷し、財務状況も悪化したので、現在では4億円しか支払えない」というものです。
X氏は、銀行からの借り入れによって相続税は納付するとともに、取締役を相手取って訴訟を起こしました。しかし、結果は敗訴となりました。その後、X氏と妻は、保有するJ社株を、競合のP社にM&A譲渡します。譲渡対価によって銀行の借り入れは返済できましたが、いずれは自分が経営につきたいと考えていたJ社は、他社の手に渡ってしまったのでした。
3-2.対策ポイント
会社が加入する生命保険と役員退職金(死亡退職金)とを組み合わせて、万一の際の相続税対策にする方法は、よく用いられています。役員退職金の課税負担は少なく、課税の繰り延べ効果が得られる保険契約もあるため、業績が好調な企業にとっては、メリットが感じられる方法です。
ただし、その際に見落とされがちなのは、必ず想定した退職金が支払われるとは限らないという点です。オーナー社長が存命中であれば、当然、他の取締役はその意向に従うでしょう。しかし亡くなった後の場合、その意思の影響力は低下します。残された取締役が会社経営に対する強い責任感を持っていれば、それゆえに、オーナー社長の生前の意思に背く判断をするという可能性も生じてきます。
また、そもそも会社が役員退職金を支給する義務が発生するのは株主総会決議、または定款での定めにより、支給金額または算定方法が明示されている場合のみだという点も覚えておきましょう(「役員退職慰労金規程」などの社内規定が法的拘束力を持つ場合もあります)。
それらがない場合は、会社に役員退職金の支給義務はありません。したがって、設例のように取締役会決議だけでは、会社に役員退職金支給義務は発生しません。
さらに、株主総会決議や定款の定めがあったとしても、その中に会社の裁量条項が盛り込まれていたり、あるいは、会社の業績が著しく悪化している場合などは、支払い義務が限定的だとされる場合もあります。
いずれにしても、遺族の相続税対策のために確実に死亡退職金を支給させたいのであれば、株主総会決議、定款による規定、役員退職慰労金規程の整備など、入念な準備をしておく必要があります。また、財務面から見て、現実的にその支給金額の支払いが可能なのかを、定期的に見直すことも必要でしょう。
まとめ
自社株は、多面的で複雑な性格を持つ資産です。その性質を十分に理解しておかないと、よかれと思って相続人に承継させた自社株が、その意図とは裏腹に親族間のトラブルを生んだり、経営に悪影響を及ぼしたりすることになりかねません。
経営支配権と財産権、事業承継と相続、さらには株価対策にまで目配りした「自社株対策」を講じるには、経営だけではなく相続に関する税務、法務についての高度な知見を持つ専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。私たち青山財産ネットワークスは、これまでに数多くの企業の自社株対策をサポートしてきた実績を持ちます。自社株の承継についてご心配のある経営者の方は、お気軽にお問い合わせください。
- 松川 洋平Matsukawa Yohei
- 執行役員 コンサルティング事業本部 第一事業部 部長
1983年兵庫県生まれ。早稲田大学 商学部 卒業。
辻・本郷税理士法人にて、相続・事業承継の税務業務に従事、デロイト・トーマツ税理士法人にて、事業承継のコンサルティング業務に従事する。
2018年に株式会社青山財産ネットワークスに入社し、上場・非上場問わずオーナー経営者に対して、財産の承継・運用・管理の総合コンサルティングを提供している。
- 専門分野
- 企業オーナー向けコンサルティング
- 資格
- 税理士
- 著書
- 事業承継 親の心子知らず 子の心親知らず~19の失敗事例から導く「思い」「理解」「感謝」のない対策の行方~