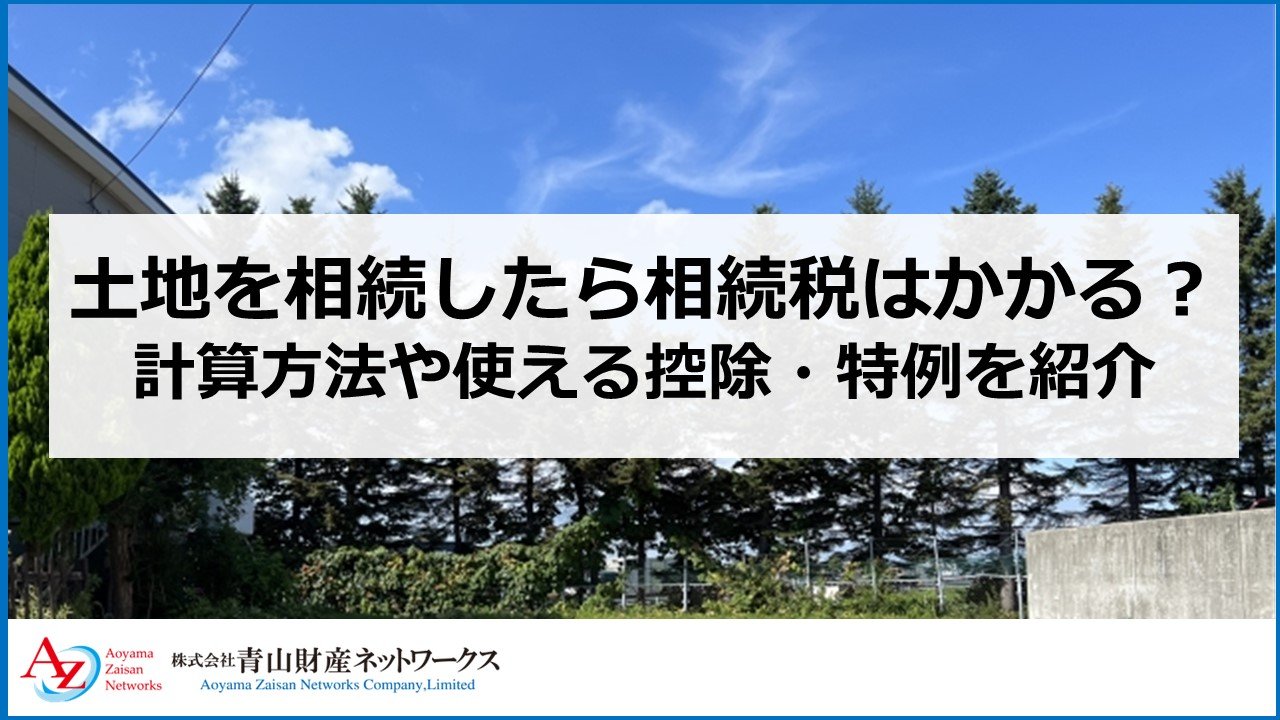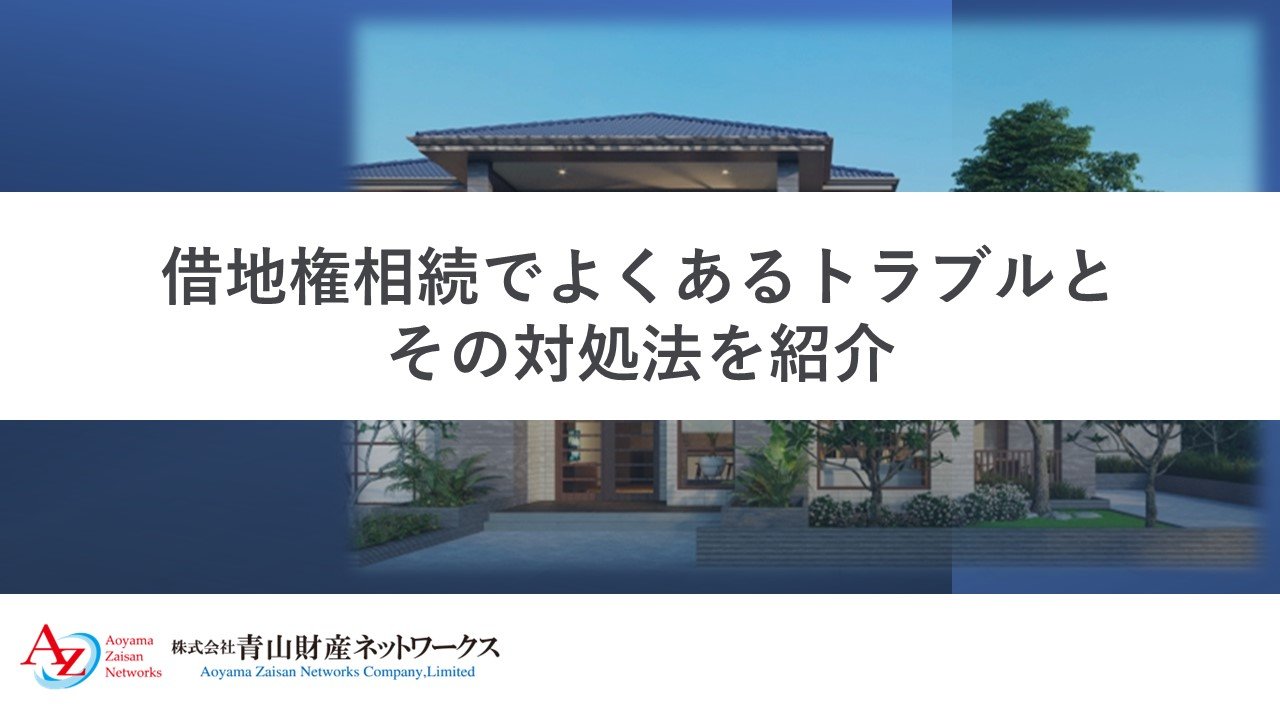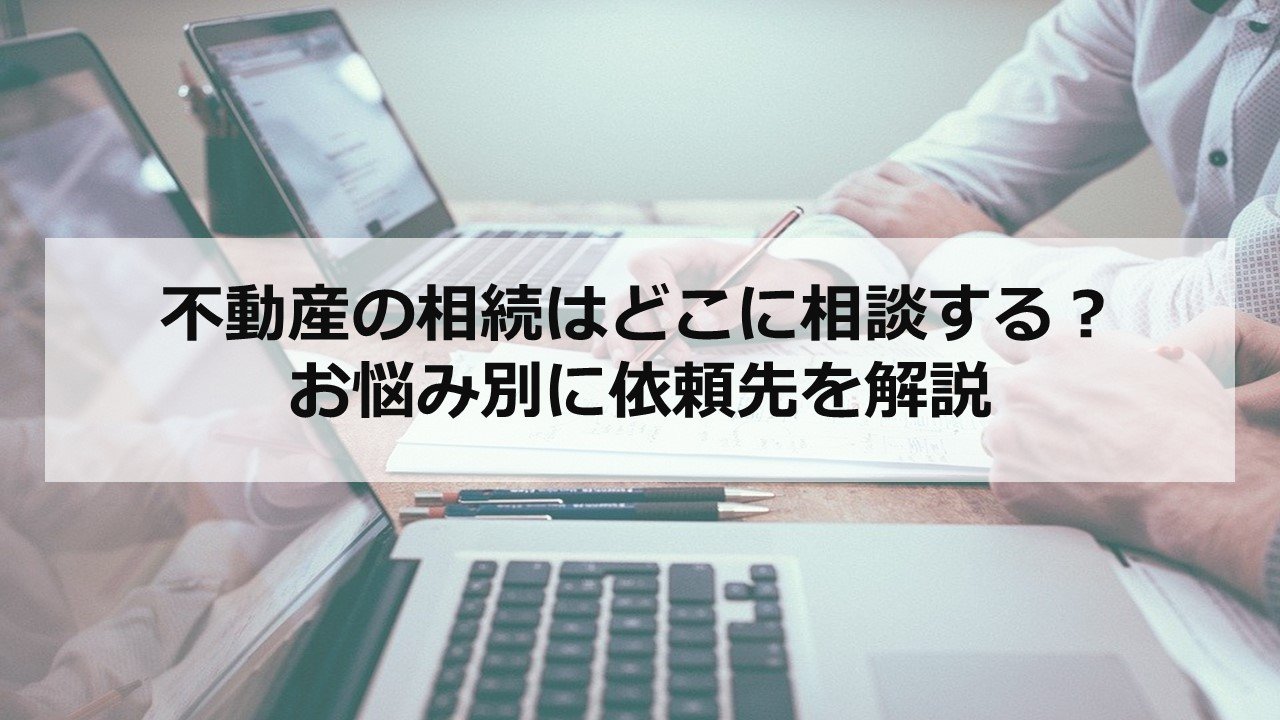不動産を相続したら、そのまま住居として住んだり賃貸として活用したりと、さまざまな方法が考えられます。遠方で住み続けることができない、立地などの条件が悪く賃貸経営はできない、などの場合には、多くの方が「売却」という手段を選びます。
ただ、初めての不動産売却の場合、まず何から始めればいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。税金のことなども考えると、誰に相談して良いかわからずに流されるまま売却してしまい、知らずに損をしてしまう……ということもあり得ます。
この記事では、「相続した不動産の売却」に焦点をあて、売却までの流れから税金に関する疑問まで徹底解説します。最後まで読めば、不動産売却への不安が軽くなるでしょう。
相続した不動産を売却したい!まずはどうする?
不動産を相続しても、住居として住み続けることができず空き家になってしまったり、すぐに運用をする目処が立たずに放置をしてしまうということはよくあります。
放置された不動産には固定資産税が発生し、所有しているだけでかなりのお金がかかってしまいます。
そんな時は、売却も検討してみましょう。
相続した不動産の売却をするにはまず、相続人の確認から始め、遺産分割協議、相続登記を行います。それぞれの段階で行う手続きや注意点を、次項から詳しく解説いたします。
売却までの流れ
まずは、相続発生から売却までの流れを大きく4つのステップに分けてご説明いたします。
- 1.相続発生
- 2.遺産分割協議
- 3.相続登記(名義変更)
- 4.売却
各項目ごとに解説いたします。
1.相続発生
相続が発生した際には、法定相続人の決定が必要になります。法定相続人の決定において、重要なのは遺言書の有無です。遺言書があれば遺産の分割は遺言書にならって行われますが、遺言が無ければ原則として、「法定相続分」で分割されます。被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本をもとに子供、父母、被相続人の兄弟姉妹の順序で法定相続人を決定していきます。
実家で遺言書が見つかった場合は偽造などを防止するため家庭裁判所による「検認」が必要で、勝手に開封してはいけません。公正証書遺言の場合には、公証役場にある「公正証書遺言検索システム」で探すといいでしょう。法務局より「相続情報一覧図」にして証明してもらう制度も利用できます。
2.遺産分割協議
相続人が複数いる場合は、「遺産分割協議」を行います。協議をしたら終わりではなく、必ず「遺産分割協議書」を作成する必要があります。この書類には、相続人すべての証明押印が必要です。
遺産分割協議は裁判外での話し合いとなるため、法的拘束力はありません。遺産分割協議書の提出期日はないので「作成をいつまでに行わなければいけない」という縛りがなく、じっくりと納得するまで話し合いを進めることができます。
そのため、自分の欲得主張を譲らない者も出てきますし、なかなか相続人全員が署名捺印をしない事態が発生しがちです。協議が進展しないときは、家庭裁判所において遺産分割調停を申し立てる必要があることも念頭においておきましょう。
3.相続登記(名義変更)
相続登記とは、不動産の所有権を登記上相続人に変更する手続きのことで、名義変更とも呼ばれます。相続人が複数おり、不動産の分割方法が協議できちんと決まっていれば、1名を代表者として、代表者に所有権を移すといった方法をとることが多いです。
申請先は法務局になりますので、必要書類を提出して行います。以下の提出が必要になります。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 被相続人の出生から記載がある戸籍謄本
- 被相続人の住民票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 相続関係説明図
- 所有者移転の登記申請書
「所有者移転の登記申請書」は法務省の公式サイトを確認し、指示に従って作成します。
参考:法務省 公式サイト
ただし、相続登記は個人で行うのは大変な作業であり、複雑な手順による申請ミスを防ぐためにも司法書士への委任が一般的になっています。
4.売却
不動産を売却する手順は、相続した不動産と一般的な不動産による違いはありません。知り合いなどに個人的に売却をする以外は、不動産会社へ売却を依頼します。 主な流れは以下になります。
- 1.物件、土地の調査を行い、査定価格を確定する
- 2.不動産会社と媒介契約を締結する
- 3.不動産の購入希望者との条件交渉を行う
- 4.売買契約を締結する
- 5.決済し、引き渡しを行う
- 6.売却完了
売却後、遺産分割協議の内容によっては、利益を相続人間で分割します。
売却をする上での注意点

続いて、売却時の注意点について解説いたします。相続した不動産をスムーズに売却するために、事前に確認しておきたいポイントは以下の3つ。
- 1.相続人の確認
- 2.相続登記を忘れずに行う
- 3.査定は複数の会社に依頼する
一つずつ見ていきましょう。
1.相続人の確認
相続人の確定には被相続人の戸籍謄本さえ取得すればいいようにも思えますが、亡くなった時点ではなく、出生の時点から戸籍謄本で調べる必要があります。連絡も取りあっていて親子間、兄弟間の関係が良好である場合、だれが相続人なのかは心配しなくてもわかります。ただ、高齢者の方が被相続人の場合は、親族に知らせずに養子縁組をしていた事例は決して少なくありませんし、兄弟が知らないうちに離婚や再婚をしていたということも実際にはあります。自分が周知していない相続人が突如現れるということもあるため、相続人確定は重要です。
相続人の数によって売却手順は変わる
なぜ相続人の確認が重要な手順なのかと言うと、相続人が一人だけか、または複数人いるのかによって売却の手順が変わるためです。一人の相続人が全ての遺産を相続することを、「単独相続」と言います。相続人となる人物がもともと一人しかいなかったケースに限らず、他の相続人が相続放棄をして結果的に単独相続となる場合もあります。単独相続であれば、先ほどご紹介した売却の流れのうち遺産分割協議は行わない形で売却ができます。複数の相続人によって相続をする場合は、以下の方法で分割を行い、売却します。
| 現物分割 | 不動産をそのまま相続人の一人が取得する。 その他の相続人は預貯金などの遺産を取得する。 |
|---|---|
| 代償分割 | 不動産を一人が取得するが、他の相続人に土地評価額相応の分割金額を支払う。 |
| 換価分割 | 不動産を売却後、収入金額を相続人で分割する。 |
代償分割と換価分割では、先ほどご紹介した売却の流れのうち、決済・引き渡し後に相続人間で金銭のやりとり等が発生する形になります。
相続人の数が曖昧なまま分割方法について決めるのはトラブルの元です。連絡先を知らないから、疎遠だからといって他の相続候補者への連絡を怠ってしまわずに、相続人の数は確実にしてから遺産分割協議を始めるようにしましょう。
2.相続登記を忘れずに行う
遺産分割協議でトラブルがあった場合などに、協議が締結したことで一段落してしまい、相続登記をせずにそのままにしてしまうケースがあります。相続登記には期限の決まりがないため、このようなことが起こってしまうのです。続した土地をいざ手放そうとした時に、相続登記をしていないと売却することができません。また、相続人が複数人いた場合、ほかの相続人が相続登記をして勝手に土地を売るといったトラブルも発生しかねません。相続人が決まった時点で、すみやかに相続登記の申請を行うようにしましょう。
その他にも、相続登記のために必要な書類や手続きが多く、途中で挫折してそのままにしてしまうといったケースも考えられます。確かに相続登記は、個人ではなかなか手間がかかり難しい作業です。その場合は無理せず、司法書士等の専門家に依頼することをおすすめします。
相続登記には、登記事項証明書・住民票・必要書類の取得費用として1,000~10,000円程度と、司法書士に依頼する場合は司法書士報酬が数万円~10万円程度が相場となっています。
3.査定は複数の会社に依頼する
売却のため、不動産を査定する際に不動産会社や不動産鑑定士に依頼をしますが、1社だけの評価額をうのみにせず複数の会社に査定を依頼するようにしましょう。なぜなら、相続した不動産の売却となると不動産にあまり詳しくない、不動産売買に慣れていない依頼者であると思われ相場よりも安い値段で査定をされる場合があるためです。また、相続した不動産の立地にあまり土地勘がないと、査定額が適正かどうかの判断も難しいでしょう。相続した不動産の売却は、一般的な不動産の売却よりも、慎重に進める必要があります。
ウェブ上で、不動産の一括査定が行えるサービスも広く普及しています。中には最大6社の査定額を比較できるものもありますので、このようなサービスもうまく活用して査定を行うようにしましょう。
相続した不動産を売却する際にかかる税金とは?

不動産を相続し、売却するとなると、気になるのが税金です。この場合税金は、相続で発生するものと売却で発生するものの2種類があります。
相続をすることで発生する税金
| 税金の名称 | 税額 | 課税内容 |
|---|---|---|
| 相続税 | 取得金額によって異なる。 1,000万以下…10% 他 |
相続によって取得した金額に対して発生する税金 |
| 登録免許税 | 課税標準である固定資産評価額×0.4% | 名義変更にかかる税金。支払先は司法書士 |
売却をすることで発生する税金
| 税金の名称 | 税額 | 課税内容 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 売買契約書の金額に応じて異なる。2,000~100,000円ほど | 売買契約書に貼付する印紙代。 |
| 課税所得税 | 所有期間によって異なる。 | 売却による刊益に対して発生する税金。 |
| 住民税 | 所有期間によって異なる。 5年以下…譲渡所得の9% 5年以上.譲渡所得の5% |
|
| 復興特別所得税 | 所有期間によって異なる。 5年以下.譲渡所得の0.63% 5年以上…譲渡所得の0.315% |
令和19年まで上乗せされる所得税。 |
こうして比較すると、譲渡所得税の税率がかなり大きいことがわかります。しかし、譲渡所得税には控除や特例があるので、上手く活用をしましょう。次の項から、詳しくご説明いたします。
税金の特例
譲渡所得税には、「3,000万円特別控除」という制度が利用できます。住居を売却した際に利益が発生しても、利益の金額が3,000万円以下であれば譲渡所得税の課税額が0円になるというものです。また、所有期間の長短に関わらず控除が受けられるという点もポイントです。不動産売却においては譲渡所得税の税率が最も高いため、これは是非とも受けたい控除と言えるでしょう。
ただし、この特例には対象者と適用要件が厳しく決まっています。次項に適用を受けるための適用条件と、申請するための手続きについて解説をしていきます。
3,000万円特別控除は、①自己居住用と②空き家の特例があります。ここでは、①自己居住用を例にご紹介いたします。
対象者と適用要件
それでは、3,000万円特別控除の6つの適用要件をご紹介いたします。
- 1.自分が住んでいる家屋を売り、家屋と一緒に敷地や借地権を売ること。
- 2.売った年の前年及び前々年に同じ特例、またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
- 3.売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
- 4.売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
- 5.災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
- 6.売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
引用元:国税庁ホームページ No.3302 マイホームを売ったときの特例
4の項目を見ると、他の特例との併用ができないように思えますが、今回ご紹介している①自己居住用の場合は「相続税の取得費加算」と「軽減税率の特例」が適用できます。
特例を受けるための手続き
続いて、3,000万円控除を受けるための手続きをご紹介いたします。
特例を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告書に「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]」を添えて提出してください。
なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。
引用元:国税庁ホームページ No.3302 マイホームを売ったときの特例
控除を受けるには、確定申告での書類提出が必要になります。
この特例においては、申請者がその住宅の持ち主であったことを証明することが重要となります。そのため、場合によっては戸籍の写しも合わせて提出する必要があるので、ご注意ください。
3年以内に売却すべき?「相続税の取得費加算」とは
特例は「3,000万円控除」以外にも存在します。よく、「相続した不動産は3年以内に売却すべきだ」と言われる理由である、「相続税の取得費加算」という特例です。相続した不動産を売却して利益が生じた場合、課される所得税を軽減できるという内容です。
取得費加算の特例とは、譲渡所得税を算出する上での特例計算法の一つです。譲渡所得税の所得金額の計算式は以下です。
収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)
簡単に説明すると、取得費が増えることで、収入金額から引かれる金額が増やせるというイメージです。
先ほどの「3,000万円控除」は全てのマイホームが対象でしたが、「相続税の取得費加算」は相続によって所有している不動産を売却した際の利益が対象となります。
そのため、不動産の相続をする上で必ず知っておきたい特例と言えるでしょう。取得費加算の適用要件
それではさっそく、適用要件を見ていきましょう。適用要件は3つあり、これらの要件を全て満たしていなければこの特例は利用できません。
- 1.相続または遺贈による取得財産であること。
- 2.相続時に相続税を納税していること。
- 3.相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に売却していること。
この要件から、「相続した不動産は3年以内に売却すべき」というセオリーが生まれたようです。
この3つの要件をしっかりと理解しておきましょう。
相続した不動産の売却は早めにすべき?
財産を相続した場合、相続税がかかってきます。さらに所得税まで払わなければならないの?と、疑問が浮かぶかもしれませんが、所得税は売却で発生する課税なので、遺産相続とは種類が異なります。税金を支払うことは義務であるため、少しでも負担を少なくするには特例を活用することが大切です。特例の適用条件には事細かく条件があり、なにかと3年目の年度までに申告しないといけない項目も多く、知らないだけで損をしてしまうこともあるかもしれません。時期を逃したせいで条件外となり適用を受けられなくなる、といった事態は避けたいものです。そのため、相続時の手続きは早く、前もっての対処が求められます。
一方で、目先のことばかりを考えて売却するのも部分最適となり本質的ではありません。相続した不動産の収益構造や、将来の収支を分析し、全体を把握した上で売却すべきかを検討をしていくことをおすすめします。
まとめ
不動産相続の流れから相続した不動産の売却についてご紹介いたしました。
家族が遺した不動産を手放すことは、大きな決断です。それでも、固定資産税の長期的な納税などを考えて、売却をした方がいい場合というのはもちろんあります。そのような時には、少しでも負担を少なくできるよう、税金の特例や控除を上手く活用していきましょう。一方で、本当に売却すべきかどうかを考え直すことも必要です。収益構造や将来の収支を分析し、ご自身やご家族に最適となる選択を行っていくことが重要です。
相続した不動産の売却で困ったら、大きなトラブルを防ぐためにも、相続関係のサポートを中心に行っているコンサルティング会社へ相談してみましょう。不動産相続のプロフェッショナルなら、あらゆるケースの相談にも対応できます。一人で抱えてしまいがちな相続関係の悩み事は、プロに任せることをおすすめします。
青山財産ネットワークスは創業30年以上、上場している独立系の総合財産コンサルティング会社として、相続・事業承継・不動産の様々な課題解決のご支援をしています。不動産の売却はもちろんのこと、その不動産を本当に売却すべきかも含め、収益構造や将来の収支の分析から、全体最適となるご提案をいたします。
不動産売却にまつわる相談・解決事例はこちら