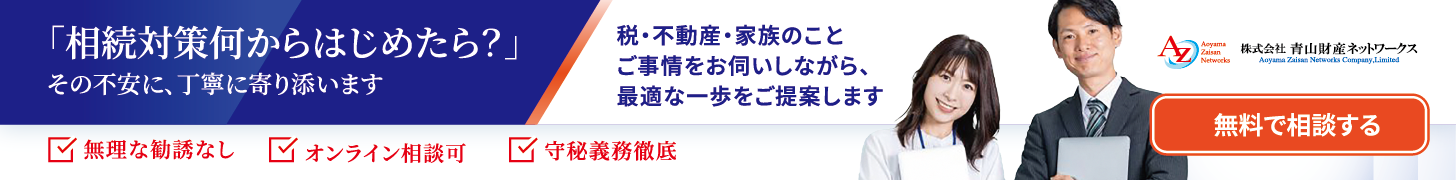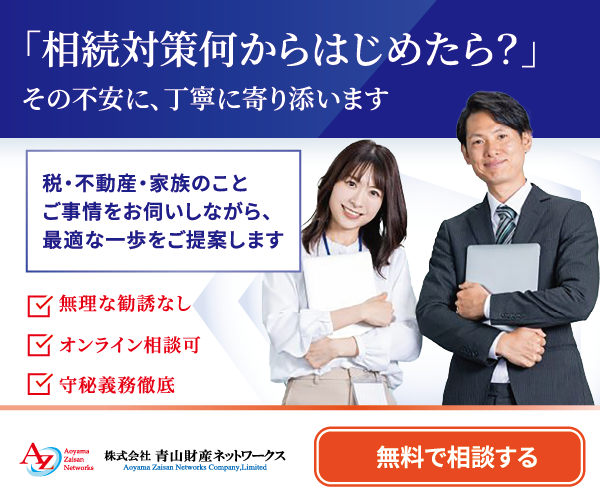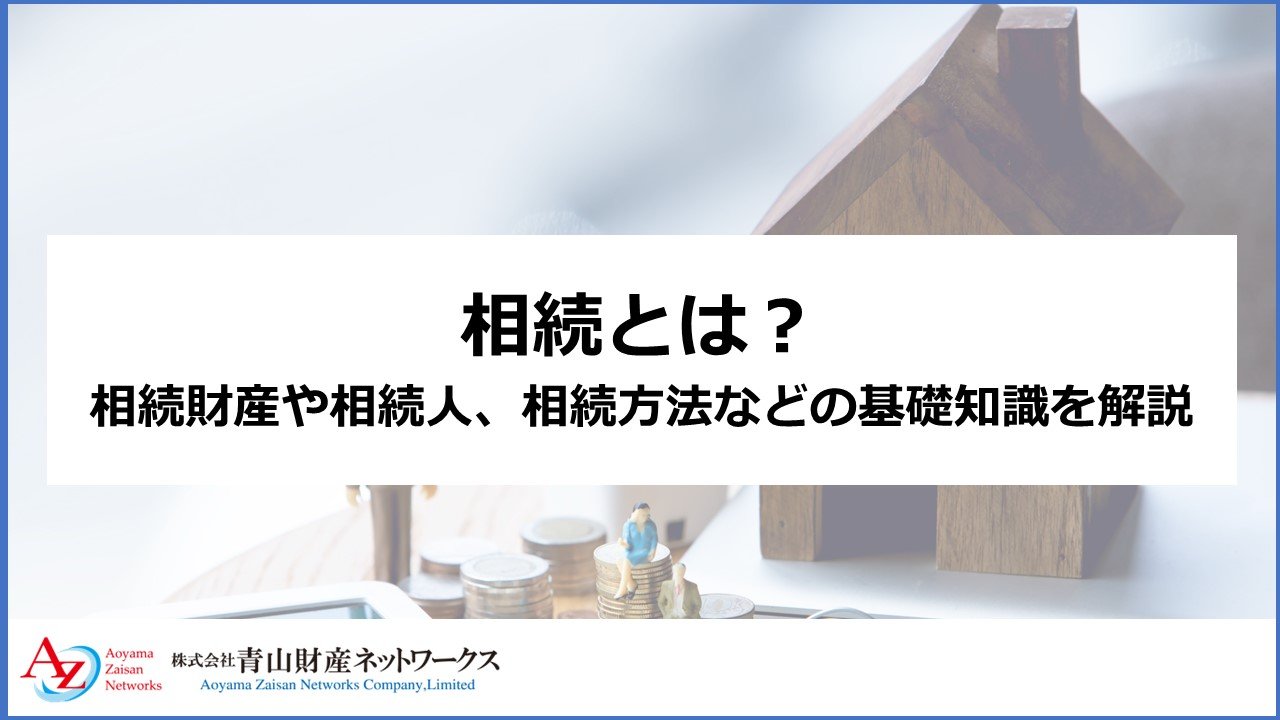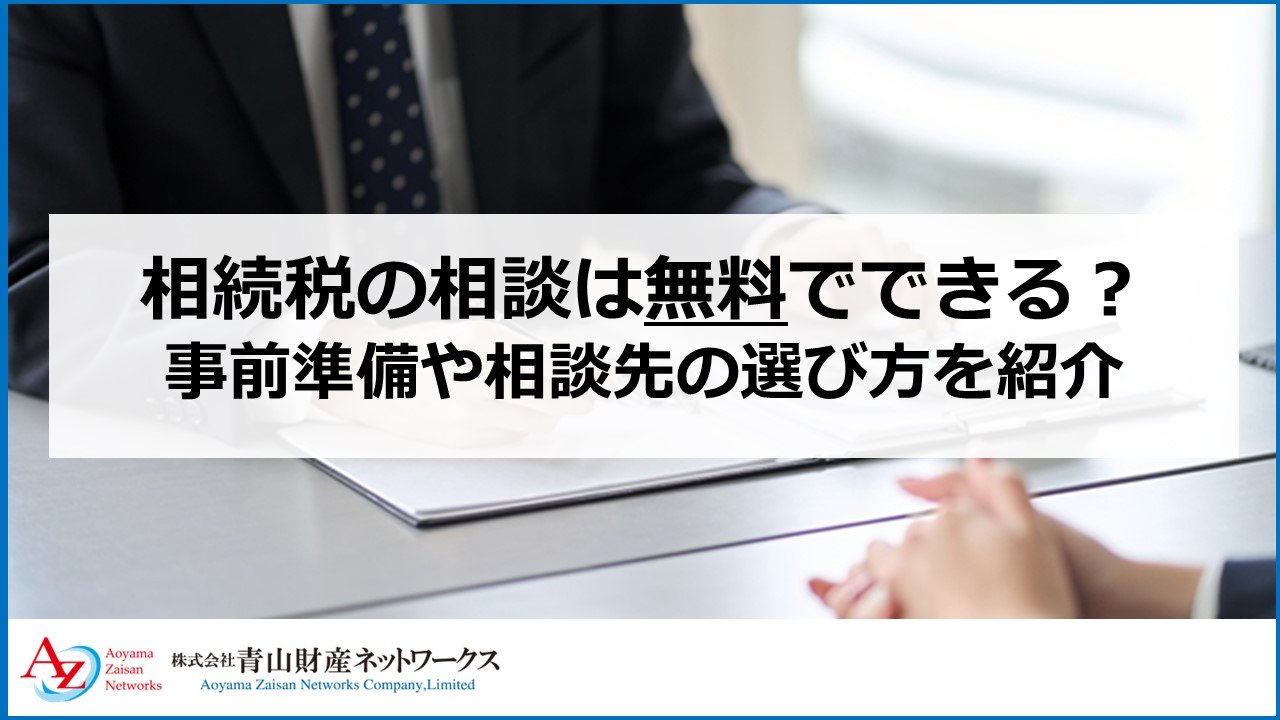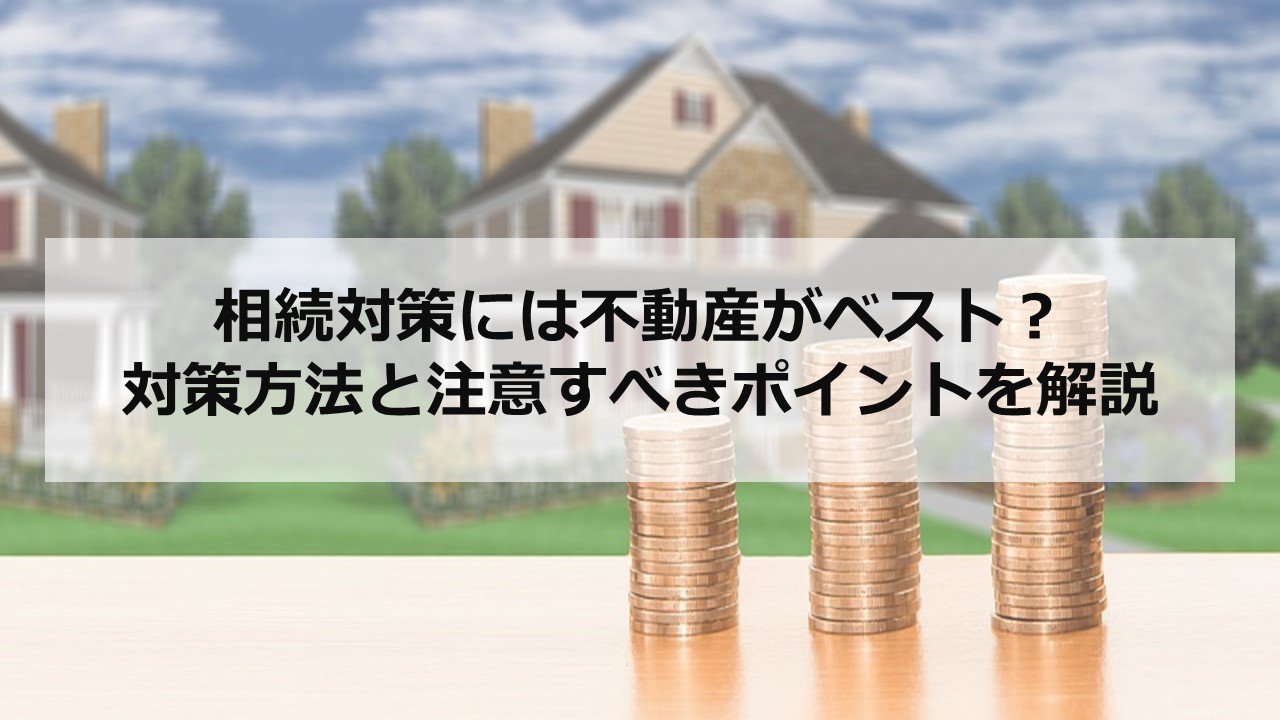親族から土地を相続した場合、その場所に賃貸用物件を建てるなど土地を有効活用するという手段や、相続した土地を売却し、現金化してから他の資産へ組み換えるという手段などがあります。土地を売却して利益を得た場合、金額に応じた税金を納める必要があり、利益の額によって税金の額は変動します。
この記事では、相続した土地の売却時に発生する税金の種類や、相続した土地を売却するメリットとデメリット、税金の計算方法、負担を軽減させる控除、土地の売却を進める際の相談相手などについて解説します。
相続した土地の売却時に発生する税金

土地を相続すると、まず課される税金が相続税です。そこからさらに相続した土地を売却した場合には、相続税に加えて、各種税金を支払うことになります。
代表例は、土地の名義を変更する際の登録免許税、土地の売買契約書などの書類に必要な印紙税、譲渡して発生した利益に対して課される譲渡所得税などです。
こちらでは、土地の売却時に発生する税金について解説します。
登録免許税
相続や売買などによって土地の名義等を変更する際に、法務局に支払う税金です。
土地の相続時には当該土地の固定資産税評価額の一定割合を支払うほか、金融機関から土地を担保に抵当権を設定して住宅ローン等を借りていた場合、その抵当権を抹消する手続きである抵当権抹消登記を行う際にも、土地1筆につき1,000円を支払います。
印紙税
印紙税とは、売買契約書や領収書等の文書を作成した際に課税される税金です。
不動産の売買においては、課税文書と呼ばれる文書に貼付しなければならない印紙が必要で、この印紙を購入することで税金を支払う仕組みです。
契約書1通ごとに課税され、収入印紙を売買契約書に貼り付けて納税します。印紙税の金額は、土地の売却代金によって異なります。
譲渡所得税
土地の売却で「利益(譲渡所得)」が出た場合、譲渡所得に所得税と住民税が課税されます。さらに、2037年までは復興特別所得税も課税されることになっています。
譲渡所得は「売却した価格」ではありません。土地を売るまでには、土地の取得費、売却時の手数料など、さまざまな費用がかかっています。このうち、売買に直接要した費用と認められる経費を、売却した価格から差し引いたものが譲渡所得です。土地を売却した結果、これらの収支がマイナスになれば土地売却による譲渡所得税は発生しません。
なお、不動産の譲渡所得に課される所得税と住民税は「分離課税」として扱われます。会社員の給与所得や個人事業主の事業所得などとは切り離して課税されるのが、分離課税の仕組みです。譲渡所得税の内訳については、以下のとおりです。
所得税
土地売却の所得税を割り出す上で必要となる数字は、「土地の取得費」と「土地の譲渡費用」の2つです。具体的な取得費と譲渡費用の例を紹介します。
取得費
- 土地の購入代金
- 購入時の税金(印紙税、登録免許税、不動産取得税など)
- 測量費
- 建物解体費
- 不動産会社に支払う仲介手数料 など
譲渡費用
- 不動産会社に支払う仲介手数料
- 印紙税
- 測量費
- 建物解体費、樹木などの撤去費用
- 土壌汚染調査等の調査費用(譲渡の条件になっているもの) など
譲渡所得税のうち、所得税の税率は土地を所有していた期間で2つに分かれます。土地を売却した年の1月1日現在で所有期間が5年超の「長期譲渡所得」の場合、所得税率は15%です。一方、土地を売却した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」の場合、所得税率は30%となります。
住民税
土地の譲渡所得には、所得税と同様に住民税も課税されます。住民税土地の所有期間によって税率は異なります。長期譲渡所得の場合は5%で、短期譲渡所得であれば9%です。
復興特別所得税
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源の確保を目的に設けられた税金です。2013年から2037年まで、各年の所得に対して課税されます。相続した土地を譲渡したことで所得税が発生した場合は、復興特別所得税も含まれます。
所得税額に税率2.1%を乗じた金額が、復興特別所得税の税額です。復興特別所得税の税率は所得税の税率と連動して変わり、長期譲渡所得であれば0.315%、短期譲渡所得なら0.63%となっています。なお、所得税が発生しなければ、復興特別所得税は発生しません。
仲介手数料等の消費税
仲介手数料とは、不動産売買の仲介を依頼した不動産仲介業者に対して、売買が成立した際に支払う成功報酬を指します。不動産仲介業者は、仲介というサービスを提供する対価として手数料を得ており、仲介手数料には消費税が課税されます。消費税は物品やサービスを購入する側が支払うため、仲介手数料の消費税は土地売却の依頼者負担です。
相続した土地を売却するメリット
相続した土地は、自身の住居を建てることも、アパートや駐車場にして貸し出すことも可能です。
こちらでは、他の選択肢と比較して土地を売却する主なメリットについて取り上げ、解説していきます。
固定資産税を納税する必要が無くなる
不動産を所有している場合、固定資産税と都市計画税が毎年課税されます。土地を相続時の状態のまま放置していても課税されるため、注意が必要です。
土地を売却すればこの2つの税金を納める必要が無くなるため、負担を軽減することができるというメリットがあります。
相続税の納税資金にできる
土地を売却することで得た現金を相続税の支払いに充当することができ、残ったお金があれば自身の資産として手にすることができます。
相続した時点で手元にまとまった現金が無く、土地を売却しなければ相続税を支払うことができない場合の手段として有効です。
土地を管理する手間がかからない
土地は更地の状態で管理や手入れをせずにいると、廃棄物を不法投棄されたり近隣住民によって無断使用されたりと、様々な問題が発生しやすいリスクがあります。
そんな中、土地を売却すれば、管理する手間や労力をかける必要はありません。
相続した土地を売却するデメリット
相続した土地を売却することで、税金や管理費などの金銭的な負担から解放されます。
ただ、それは同時に土地の所有権を持っていることで得られるメリットを、将来にわたって手放すことを意味します。また、土地の売却には様々な経費がかかり、手続きも複雑です。
そうしたデメリットをあらかじめ理解したうえで、土地の売却が自身に適した方法かを見極めてください。
土地からの収益が得られない
駐車場やアパート・マンションなどの土地活用によって、賃料収益を得る機会が無くなります。
また、土地の売却益は地価によって変動するため、タイミングによっては期待していたほどの収益が得られないリスクも十分に考えられるでしょう。
その土地にどんな価値があるのか、しっかり見極めた上で売却することをおすすめします。
売却までの諸経費がかかる
土地は法務局で相続登記をして、相続税を支払った上で、不動産業者を通して売却します。相続登記時には登録免許税、戸籍謄本や住民票といった必要書類の取得費用がかかります。
自分で書類を揃えるのが難しい場合は司法書士へ依頼することができますが、その際にも別途費用が必要です。
売却時にも譲渡所得税・印紙税などの税金に加え、不動産業者への仲介手数料もかかります。
なお、仲介手数料の上限額は国土交通省の告示を踏まえ、下記の速算式で求められます(消費税除く)。
- 売却金が200万円以下の金額:5%
- 売却金が200万円を超え400万円以下の金額:4%+2万円
- 売却金が400万円を超える金額:3%+6万円
相続した土地を売却するために必要な手続き
親族から土地を相続して、さらに売却する場合は、さまざまな手続きを踏んでいく必要があります。こちらでは、相続した土地を売却するために必要な手続きについて、解説します。
不動産登記の名義変更
相続した物件を売却する場合は、名義変更を行う必要があります。なお、売却の如何に関わらず2024年4月1日より不動産を相続した際の登記が義務化されるため、相続が発生したら必ず変更するように注意しなければなりません。
不動産会社に売却を依頼する際に必要な書類の例
- 登記簿謄本または登記事項証明書
- 購入時の売買契約書
- 物件購入時の重要事項説明書
- 固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
- 土地測量図・境界確認書 など
買主への土地引渡しに必要な書類の例
- 登記識別情報、権利証
- 本人確認書類
- 実印、印鑑証明書
- 住民票 など
不動産会社を探す
相続した土地を売却する場合、基本的に不動産の売買仲介を手掛ける会社に相談することになります。土地も更地、駐車場、農地などの利用状況によって、売却の仕方や売却先が変わるためです。また、相続税には納税の期限があり、特例の利用にも期限があるため、スムーズに土地の買い手を見つけてくれる不動産会社を見つけることが大切です。
確定申告を行う
相続した不動産を売却して譲渡益が発生した場合は、所得税や住民税の納税も必要です。税金を支払うタイミングは、土地売却の翌年の確定申告です。譲渡益があるにも関わらず確定申告をしない場合、無申告加算税や延滞税が加算される恐れがあります。
相続した土地の価格を調べる方法
土地の価格は、エリアや利便性など様々な条件を考慮して概算が算出されます。社会情勢によって目まぐるしく変動するため、定価はありません。
そうした土地の価格は、基準となる指標によって決められています。こちらでは、土地の価格を調べるための指標について解説していきます。
公示価格
公示価格とは、国や都道府県などの行政や公的機関が毎年決定している不動産の評価額です。
公示価格は土地取引における客観的な指標で、土地・住宅の売却時には近隣の相場の傾向を把握するのに役立ちます。
公示価格は、国土交通省のホームページにある「土地総合情報システム」内の「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」から調べることができます。
このページでは、不動産の取引価格や地価公示などを閲覧可能ですので、土地を売りたい場合、売却価格の設定やタイミングを決める上での参考になるでしょう。
路線価
路線価とは、道路に面している1㎡あたりの土地価格を意味しています。国税庁が各道路に設定し、毎年1月1日時点の調査結果を、その年の7月に公表するという仕組みです。
相続が発生した際は、路線価を使って相続税評価額を算出することになります。
路線価は、国税庁のホームページにある「路線価図・評価倍率表」で確認することができます。
同様に、一般財団法人・資産評価システム研究センターのホームページにある「全国地価マップ」でも調べることが可能です。
固定資産税評価額
固定資産税評価額とは固定資産税の税額を計算する際に用いられる基準価格で、年度の初めに各市町村から送られる固定資産税の納税通知書に記載されています。
また、固定資産税だけでなく、都市計画税や不動産取得税、登録免許税などの税金を計算するための基準でもあります。
相続した土地にかかる税金の計算方法

土地の相続で発生する税金は、それぞれ算出方法が異なります。条件によって計算方法が変わる場合があり、結果として納めるべき税金の額も大きく変わることがあるため、慎重に算出することが重要です。
各種税金の具体的な税率については、税を管轄する国税庁のホームページで確認することができます。
登録免許税の場合
登録免許税は、「不動産の価格(課税額)×税率」で計算し、100円未満は切り捨てます。税率は一律ではなく、「売買」「相続、法人の合併または共有物の分割」「その他」と、移転登記の内容によって異なります。
具体的な税率は国税庁のホームページから確認することが可能で、相続の場合の計算式は以下の通りです。
「登録免許税=相続登記をする不動産の固定資産税評価額×0.4%」
たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の場合、登録免許税は12万円です。
なお、2025年3月31日までは不動産の価値が100万円以下の土地を相続した場合、登録免許税が課されません。また、相続により土地を取得した個人が所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合、死亡した個人を土地の名義人とするための登記についても登録免許税が免除されます。
法令改正により2024年4月1日から相続登記は義務化されるため、土地を相続した場合には注意が必要です。
| 内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(措法72) |
|---|---|---|---|
| 売買 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 令和8年3月31日までの間に土地の移転登記を受ける場合1,000分の15 |
| 相続、法人の合併または共有物の分割 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | - |
| その他(贈与・交換・収用・競売等) | 不動産の価額 | 1,000分の20 | - |
印紙税の場合
土地の売却で発生する印紙税は、契約金額(土地の売却価格)に応じて異なります。具体的には、売却価格が大きくなるにつれて印紙税の額は大きくなるという仕組みです。
2027年3月31日までの間に土地の移転登記を受ける場合、売買契約書に記載する金額と印紙税の関係は、以下の通りです。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
譲渡所得税の場合
土地は、購入や譲渡に諸費用がかかるため、売却時の価格がそのまま譲渡所得とみなされるわけではありません。
この点を加味した上で、譲渡所得税の金額は算出されます。具体的には、以下の計算式が用いられています。
「譲渡所得税=譲渡所得×税率」
譲渡所得は、「売却金額」から「購入にかかった費用と売却にかかった費用」を差し引いた額です。その金額に税率をかけて、譲渡所得税を算出します。
また、一定の要件を満たしていれば、課税対象の譲渡所得を軽減する控除が適用されます。
この譲渡所得税の税率は、土地の所有期間で変動します。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下(短期譲渡所得)であれば39.63%で、所有期間が5年を超えていれば(長期譲渡所得)20.315%です。
相続で取得した不動産や株式は、被相続人の所有期間を引き継ぎます。
相続した土地を売却する際に適用される特例
土地の売買では非常に大きい金額が動くため、税金の額も大きい傾向にある一方で、様々な特例が用意されています。
こちらの項目では、土地の売却時に適用される税金の特例の種類を紹介します。
相続税の取得費加算
相続で取得した土地や建物、株式などを一定期間内に譲渡した際、相続税額の一定額を譲渡資産の取得費に加算できる特例です。
全てのケースに適用されるわけではなく、特例を受けるためには以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 相続や遺贈(遺言で特定の人に財産を贈ること)で財産を取得している。
- その財産を取得した人に相続税が課税されている。
- 相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に売却している。
相続した空き家の3,000万円特別控除
相続開始から3年が経過する日の年の12月31日までに、被相続人(亡くなった人)が生前に居住していた家屋およびその土地を一定期間内に売却した際、要件を満たしていれば空き家を売却して得た所得から最高で3,000万円を控除することができます。
この特例は、「空き家特例」と呼ばれています。対象となる空き家として認定されるのは、以下に挙げる主な要件を満たしている家屋が対象です。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
ただし、建物と土地の合計譲渡価額が1億円を超える場合、特例は適用されません。同様に、2回以上に分割して売却しても、通算して1億円を超えているかどうかで判定されます。
この特例が受けられる期間は2023年12月31日まででしたが、期限が延長され2027年12月31日まで適用されることになりました。
居住用財産(マイホーム)の3000万円特別控除
自宅として利用していた居住用不動産(マイホーム)を売却した際、発生した譲渡所得から最高3,000万円が控除されます。もともと相続人が被相続人と同居していた場合や、相続した住宅を自宅として利用していた場合などに適用されます。
売主の居住用不動産であること、譲渡先が配偶者・直系血族・同族会社などではないこと、前年や前々年にこの控除を利用していないことが主な要件です。ただし、この特例を受けることを目的とした入居、自宅の建て替えや引っ越しの際の仮住まいとしての使用などは、適用の範囲外です。
土地の売却を検討する際に必要なこと

土地の売却は、売却のタイミングや必要資料の有無など、状況に応じて通常よりも多くの支出が発生することがあります。そこで土地を売却するかどうかを検討する際、「ここは注意しておいたほうがいい」という点について解説します。
適切な売却のタイミングを見極める
土地は、所有期間が5年以下(1月1日を5回またがない)と短い場合は、売却時に課税される所得税は30%で住民税が9%です。しかし、5年を超えると所得税率も住民税率も下がり、それぞれ15%と5%になります。このように、「5年」を境界に土地を売却した際の税率は大きく変わります。
そのため、不動産の市況などを考慮しながら、どのタイミングで売却するのが最も適切なのかをしっかり見極めることが大切です。
なお、土地を相続や贈与で取得した場合、被相続人が土地を買い入れたときに購入金額や手数料、取得時期などの情報も引き継がれます。そのため、被相続人が土地を取得したタイミングが相続・贈与より5年以上前だった場合、税率は変動しませんのでご注意ください。
取得費の証明資料は徹底的に調べる
土地の譲渡所得の計算には、その土地を購入したときにかかった費用が必要です。しかし、古い物件の中には、取得費を証明できる資料がないというケースも見受けられます。取得費が不明の場合、「売却価格の5%が取得費」として計算することができますが、これを「概算取得費」と言います。この場合では、売却した価格のおおよそ9割以上が課税の対象です。
契約書以外の資料によって取得費を証明できる場合もあります。手元に契約書など取得費がわかる資料がない場合、購入先となった不動産仲介会社などに連絡して契約書や請求書、領収書の控えが保管されているかを確認しましょう。契約が比較的新しい場合、相手先で保管されているかもしれません。また、購入代金として支払った金額の記載のある通帳、不動産の分譲当時のパンフレットなども、有効な資料になり得ます。
相続した土地の売却にかかる税額のシミュレーション
相続した土地を売却した場合、実際にどれくらいの税金がかかるものなのでしょうか。いくつかのケースを想定して、かかる税額をシミュレーションします。
土地の取得費が判明している場合
条件
- 譲渡(売却)価格:3,000万円
- 取得費:2,000万円
- 譲渡費用:150万円
- 所有期間:10年
譲渡所得は、「土地の譲渡価格-取得費-譲渡費用」で算出されます。そのため、このケースでは
3,000万円-2,000万円-150万円=850万円
つまり850万円が譲渡所得になります。
この場合の所有期間は10年であるため、長期譲渡所得の税率が適用されます。長期譲渡所得の税率は20.315%で、
850万円×15.315%=約130万1,700円
このケースでの最終的な譲渡所得税は、約130万1,700円です。
また、相続後10年保有していた場合は「長期譲渡所得」に分類されるため、譲渡所得にかかる住民税の税率は5%。
850万円×5%=42万5,000円
42万5,000円を住民税として、給与所得にかかる住民税とは別で課されます。納付方法は、給与に対する住民税と別納することも、給与から天引きすることも可能です。
土地の取得費がわからない場合
条件
- 譲渡(売却)価格:3,000万円
- 取得費:不明
- 譲渡費用:200万円
- 所有期間:10年
この条件では、諸事情により取得費が判明していないため、概算取得費を用いて計算します。概算取得費は譲渡価額5%となり、取得費は150万円です。また、所有期間が10年ということで長期譲渡所得の税率が適用されます。
(3,000万円-150万円-200万円)×15.315%=405万8,400円
このケースの譲渡所得税は、405万8,400円となります。
なお、譲渡所得には住民税が課されます。長期譲渡所得に適用される税率は5%のため、
(3,000万円-150万円-200万円)×5%=約132万5,000円
が住民税の金額となります。
まとめ
相続した土地を売却すれば、現金を得ることができます。ただし、利益があれば基本的に譲渡所得税が発生します。利益の金額によっては税金が数百万円、数千万円単位になる可能性もありますが、さまざまな特例を有効活用することで、税の負担を大きく軽減できるかもしれません。また、納得いく売却益を得るためにも、売却するのであれば適切なタイミングを見極めることが大切です。
土地の売却を検討する際は、譲渡所得や特例などについて丁寧に調べるなど、しっかりと準備をした上で臨みましょう。
青山財産ネットワークスの特徴
青山財産ネットワークスでは、税理士、司法書士、不動産鑑定士などの国家資格を有する専門家が150名以上在籍し、30年以上の豊富な経験に基づき、お客様やご一族にとって最適な財産構成を実現する総合財産コンサルティングを提供しています。その一環として、土地有効活用コンサルティングを数多く提供してきた実績があります。
土地の評価額は立地、市場価値などを総合的に判断し、お客さまにとって最良の選択となるよう一気通貫で支援いたします。土地の売却はもちろん、相続後の運営までサポートをご希望される方も、ぜひご相談ください。
不動産売却にまつわる相談・解決事例はこちら
監修者
- 相澤 光
- 青山財産ネットワークス 財産コンサルタント 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、シニア・プライベートバンカー、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
不動産や信託の活用を軸とした永続型の財産承継コンサルティングを現場の最前線で行っている。節税目的の相続対策に警鐘を鳴らし、「財産全体が最適」となる承継・管理・運用を土台とするファミリーコンサルティングを幅広く手掛ける。ナレッジを集約した書籍を発行。セミナー登壇実績多数。YouTubeにて動画コンテンツも配信中。
- 著書
- 青山財産ネットワークスの30年に渡るノウハウをまとめた『「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策』を執筆。2021年(11月15日-11月21日)紀伊国屋書店新宿本店ビジネス書ランキング第1位

- ※役職名、内容等は2023年10月時点のものです。