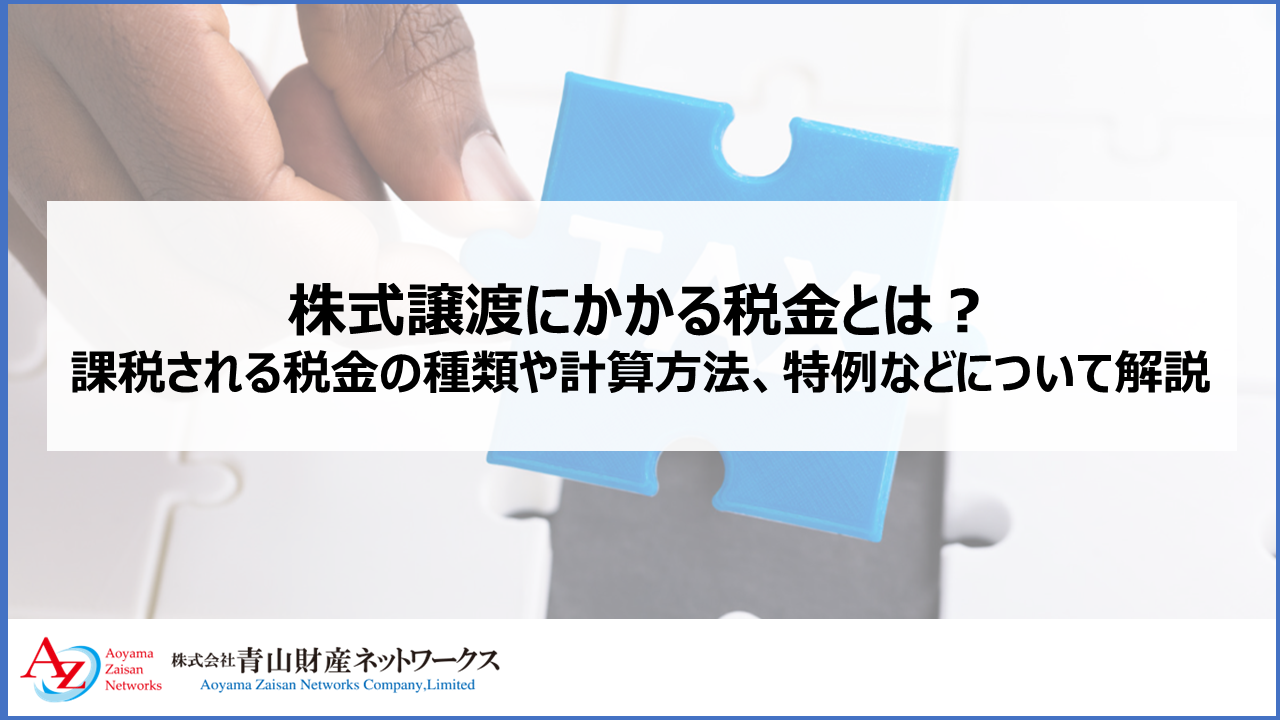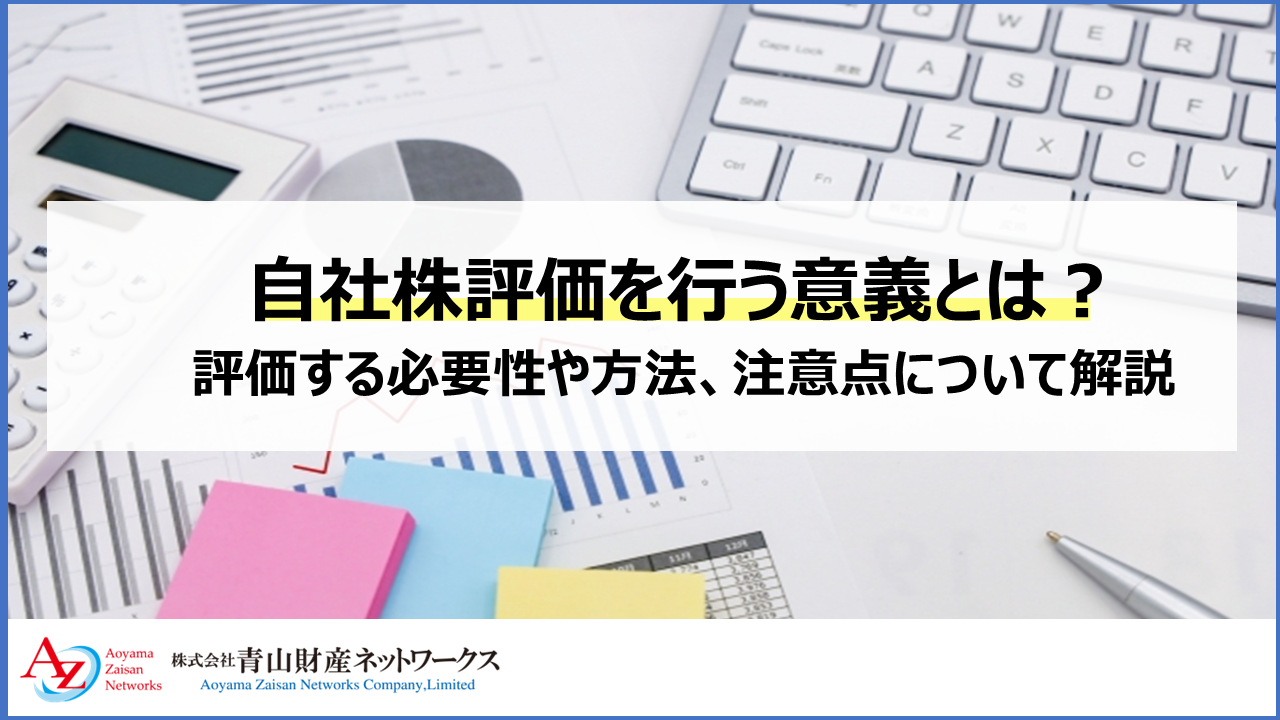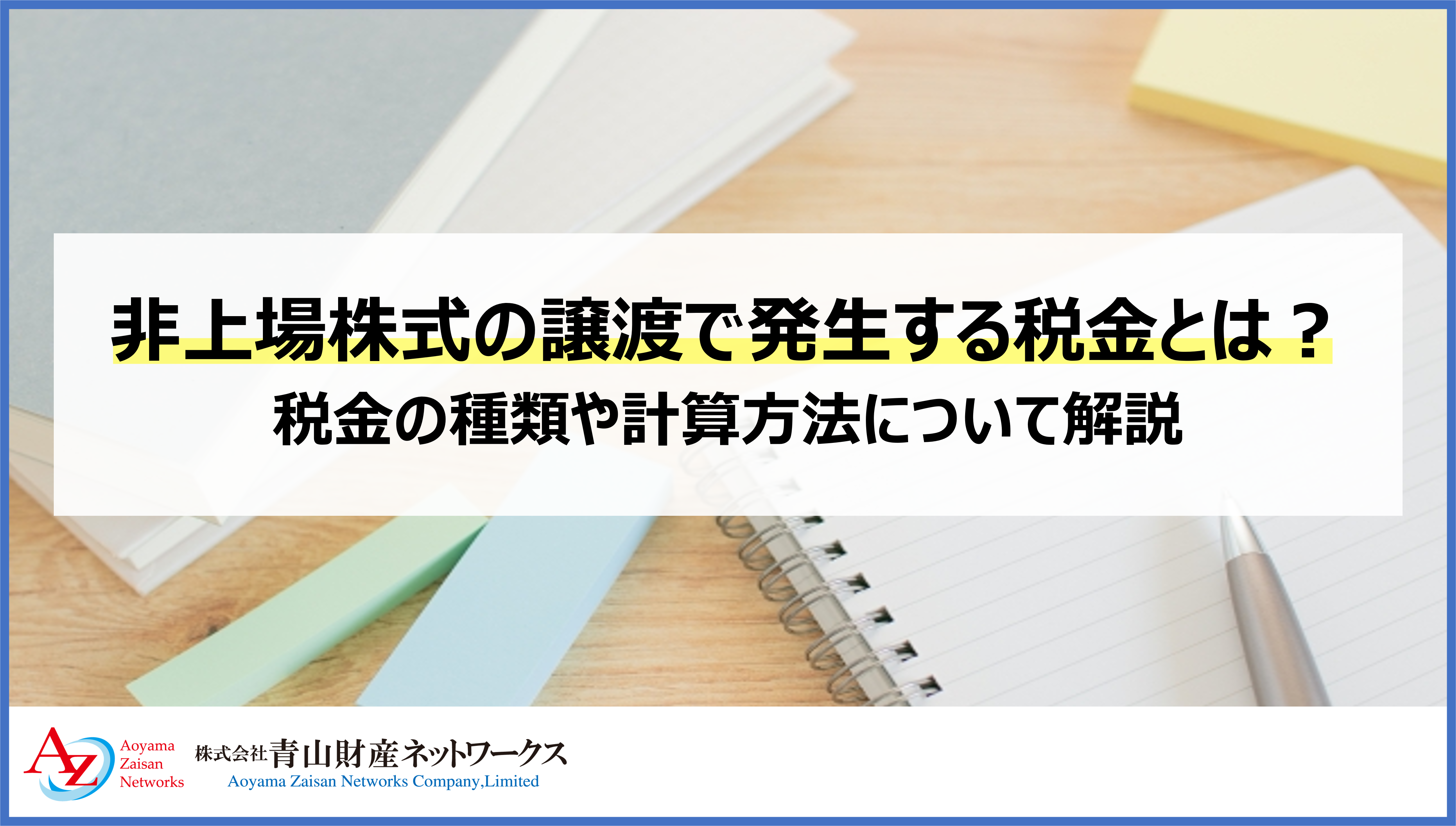株式譲渡とは、誰かが保有している株式を別の人に移転させる仕組みです。この株式譲渡は、中小企業の経営者が子などの親族に事業を引き継ぐ際に行われることが多く、金銭的なやり取りがない「無償」で実施することもできます。
無償の株式譲渡ということで、金銭的な負担が少ないような印象を持っているかもしれません。しかし、実際には多額の費用がかかる可能性も考えられます。無償の株式譲渡を検討しているのであれば、事業承継や株式管理などの選択肢も視野に入れながら、しっかり理解を深めることが重要です。
そこでこの記事では、株式譲渡の概要や無償で株式譲渡を行うメリットとデメリット、無償で株式譲渡を行う流れ、発生する税金、無償での株式譲渡を行う際の注意点などについて解説していきます。
株式譲渡とは

M&Aの手法として多く活用されている株式譲渡ですが、具体的にはどのような仕組みなのでしょうか。まずは、株式譲渡についての基本的な考え方や事業譲渡との違いなどについて確認してきましょう。
株式譲渡の概要
株式譲渡とは、株式を譲渡する会社(売り手)の株主が、保有する株式を譲渡される側(買い手)に売却することで経営権を譲り渡す方法です。株式譲渡では、売り手が持つ財産や取引先との契約など資産はもちろん、借入金などの負債も買い手に移ることになります。
株式譲渡は、中小企業がM&Aを行う際の手法として、多く活用されています。ただし、売り手が多くの負債を抱えているなど経営状態が悪い場合、取引は成立しにくいことが懸念点です。
事業譲渡との違い
事業譲渡とは、会社が営む事業の一部あるいは全部を譲渡する方法です。株式譲渡の場合、売り手の経営権は買い手に移りますが、事業譲渡では買い手に移動するのは事業のみで、経営権はそのまま残ります。
譲渡できる対象は、事業とそれに付随する設備や商品といった「有形資産」、従業員の雇用契約や取引先との関係、ブランドや営業ノウハウなど「無形資産」も含まれます。なお、売り手は譲渡したい事業や財産を選び、その上で譲渡することが可能です。
無償での株式譲渡で考えられるメリット・デメリット
株式譲渡は、金銭と引き換えに行う有償の場合だけではなく、無償で行われるケースもあります。無償での株式譲渡にはメリットだけでなくデメリットもあるため、自分が当事者となった際にどのような影響があるのか、あらかじめ理解しておくことが重要です。
メリット1/事業を続けながら手続きを進められる
株式譲渡は、株式を譲渡された側に経営権を移す取り組みです。事業譲渡の場合は、他社に事業が移るため、業務を引き継ぐことになります。しかし、株式譲渡は経営者が変わるだけで、事業を止める必要がありません。さらに、従業員や取引先の承諾も不要です。自社の事業を続けながら譲渡の手続きを進められるのは、無償の株式譲渡の特徴と言えるでしょう。
メリット2/手続きが比較的簡易
他のM&Aの手法と比較しても、株式譲渡は手続きが簡易的です。当事者の間で株式を無償譲渡する契約を締結し、株主名簿の書き換えが行われたら、基本的に譲渡は完了します。このように、成立までにそれほど手間や時間がかからないのは、無償の株式譲渡の大きなメリットです。
デメリット/金銭的な負担が生じる
無償の株式譲渡を行うと、譲渡する側には、売却によって得られる金銭的な対価がありません。さらに、無償での譲渡であっても法人税やみなし譲渡所得税などの税金もかかります。
譲渡を受ける側も、個人や法人といった状況に応じて贈与税や法人税、所得税といった税金が発生します。加えて、株式譲渡で会社の経営を引き継いだ場合、プラスの資産だけではなく借入金などのマイナスの資産も継承することにも注意が必要です。
このように、無償であっても株式譲渡を行うことで金銭的な負担が生じる可能性があることは、念頭に置いておきましょう。
無償で株式譲渡を行う流れ
有償での譲渡と同様に、無償で株式譲渡を実施する場合にも複雑な手続きを踏んでいく必要があります。こちらでは、無償で株式譲渡を行う際の基本的な流れについて解説していきます。
株式譲渡承認請求
中小企業の多くは非上場企業です。非上場企業では、株式の売買に関して譲渡制限が設けられています。そのため、株主が株式を譲渡する場合にまず必要な手続きは、会社の承認を得るために、株式譲渡承認請求書を作成して提出することです。
株式譲渡承認請求書には、譲渡する株式の数、譲渡先の名称や所在地などの情報を正確に記載して、譲渡先に提出します。
取締役会あるいは株主総会での承認
株式譲渡承認請求を受けた会社は、譲渡の承認手続きに入ります。取締役会が設置されている場合は取締役会で、取締役会の非設置会社は株主総会で承認を得ることになります。
関係者への決議内容の通知
取締役会または株主総会で株式の無償譲渡が承認されたら、その旨を関係者に向けて通知します。通知の期限は、原則として承認請求日から2週間以内です。なお、期限内に通知がない場合は、決議は承認されたとみなされます。
株式の無償譲渡契約の締結
株式を譲渡する側と受ける側で、株式譲渡契約を締結します。
譲渡契約は口頭での約束も有効ではありますが、トラブルを避けるためにも書面で契約書を残しておくとよいでしょう。契約書で重要なのは、当事者の氏名や住所、譲渡する株数、譲渡日など当事者間で合意した内容を明確に記載することです。
株主名簿の書き換え
契約が締結されて無償の株式譲渡が成立したら、株主名簿の書き換えが必要になります。株主名簿とは、対象企業の株主の氏名や住所、株式保有数、株券番号の一覧です。株主名簿の書き換えは、株式の譲渡が成立したことの証明となるため重要なプロセスと言えます。
無償の株式譲渡で発生する税金
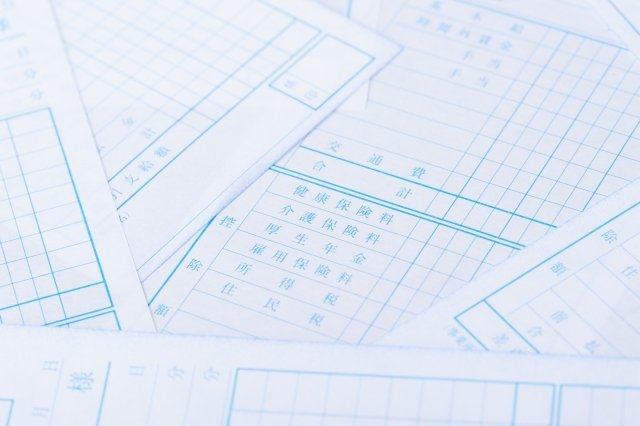
株式譲渡を無償で行う場合でも、税金が発生する場合があるため、株式譲渡損益が出る可能性がありますります。どのような税金が課されることになるのか、株式の譲渡が法人から個人の場合、法人から法人の場合、個人から法人の場合のそれぞれについて見ていきましょう。
法人から個人の場合
譲渡する側が法人で受ける側が個人の場合には、譲渡側と譲受側の関係性によって、かかる税金が異なります。譲受側が自社の役員や従業員のように、双方に雇用関係があれば、譲渡された株式は賞与として扱われます。その上で、役員の場合は損金不算入となるため、法人税の支払いが必要です。自社の役員や従業員でない個人への譲渡でも、同じく法人税がかかります。なお、譲渡を受ける個人に対しては、どのような場合でも所得税が課されます。
法人から法人の場合
法人間での無償の株式譲渡では、時価相当額の株式受贈に対して法人税が課されます。これは「みなし譲渡」と呼ばれていて、金銭などの対価を受け取っていなくても、時価で資産を売却して利益を得たとみなされる考え方です。
そのため、譲渡する側は、株式を時価で売却した場合と同額の法人税が課されます。譲渡を受ける法人は、株式を時価で取得したことになり、時価を受贈益として会計処理して法人税を納めます。
個人から法人の場合
個人から法人に無償で株式譲渡をすると、法人間での譲渡と同様に時価で譲渡されたものとみなされて、時価で譲渡した場合の譲渡所得に応じた税金が課されます。無償の場合だけでなく、時価の2分の1未満の金額で譲渡された場合も同じです。無償譲渡した側の個人には、みなし譲渡額に応じた贈与税が発生します。贈与税には年間110万円の基礎控除があり、贈与額が現金など他の財産との合算で110万円以上の場合に課税される点が、法人による譲渡との相違点です。譲渡を受ける法人側にも、みなし譲渡額に応じた法人税が発生します。
株式譲渡を無償で行う際の注意点

無償での株式譲渡は、仕組みや手続きをしっかりと理解しておかなければトラブルに巻き込まれてしまう恐れがあります。こちらでは、株式譲渡を無償で行う際の注意点について解説していきます。
法人譲渡契約書は作成しておく
株式譲渡の場合、有償と無償とを問わず、契約書の作成が法律で義務付けられているわけではありません。しかし、何か問題やトラブルが発生した場合、契約書がない場合は解決が難しくなります。そうしたリスクを回避するためにも、当事者で話し合って契約書を作成しておくことが望ましいでしょう。
契約書の内容は、当事者の話し合いによって決まります。ただし、「株式が無償で譲渡される」「譲渡日まで株式を売却・無償譲渡しない」「株式の無償譲渡後に株主名簿の書き換えを実施する」の3つの条件は記載しておくのが無難です。
無償譲渡でも税金は発生する
株式を他者に譲渡する場合、購入や売却といった金銭のやり取りはありません。しかし、たとえ無償であっても所得税や法人税などの税金が発生します。株式を譲渡する側も譲渡される側も、無償での譲渡だからと言って金銭的な負担が全くないわけではないため、どれくらいの税金を払うことになるのかをあらかじめ計算した上で譲渡契約を締結することが重要です。
場合によっては新たに株券を発行する必要がある
定款で自社を「株券発行会社」と定めている場合、その会社は株券を発行することになります。そのため、株券発行会社における株式譲渡は、株券の発行・交付によって完了します。
株式譲渡で株主の変更が行われたら、株券発行会社企業は新たな株券の発行が必要です。株券が発行されないと譲渡は無効になってしまうため、定款は確認しておくことが望ましいと言えます。
まとめ
無償の株式譲渡は、他のM&Aの手段と比べて手続きが簡易的です。そのため、中小企業がM&Aを行う際などには、よく採用されています。ただし、無償であっても税金は発生するため、どれくらいの税負担があるのかについては注意が必要です。
また、株式を無償譲渡する際、契約書を交わすことは義務ではありません。しかし、契約を結んでいないことがトラブルを生む原因になる恐れもあります。よりリスクを抑えやすい事業承継の方法もありますので、M&Aや税についての専門家のサポートを受けながら検討してみてはいかがでしょうか。
青山財産ネットワークスの特徴
青山財産ネットワークスでは、税理士、司法書士など、国家資格を有する専門家が150名以上在籍し、30年以上の豊富な実績に基づき、お客様のご希望に沿って、相続、事業承継、財産の承継・運用・管理に関するさまざまなご提案をしております。お客様とその親族の方々にとって最良の結果になるようプランをご提案いたしますので、ぜひご相談ください。
- 松川 洋平Matsukawa Yohei
- 執行役員 コンサルティング事業本部 第一事業部 部長
1983年兵庫県生まれ。早稲田大学 商学部 卒業。
辻・本郷税理士法人にて、相続・事業承継の税務業務に従事、デロイト・トーマツ税理士法人にて、事業承継のコンサルティング業務に従事する。
2018年に株式会社青山財産ネットワークスに入社し、上場・非上場問わずオーナー経営者に対して、財産の承継・運用・管理の総合コンサルティングを提供している。
- 専門分野
- 企業オーナー向けコンサルティング
- 資格
- 税理士
- 著書
- 事業承継 親の心子知らず 子の心親知らず~19の失敗事例から導く「思い」「理解」「感謝」のない対策の行方~