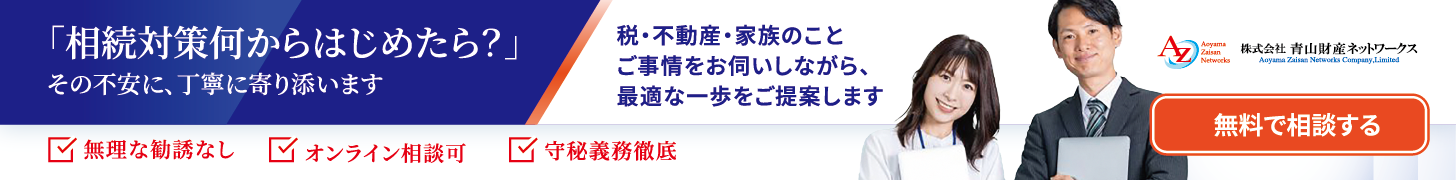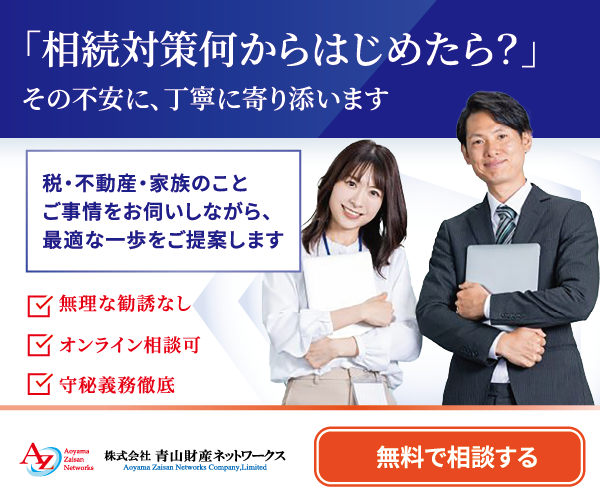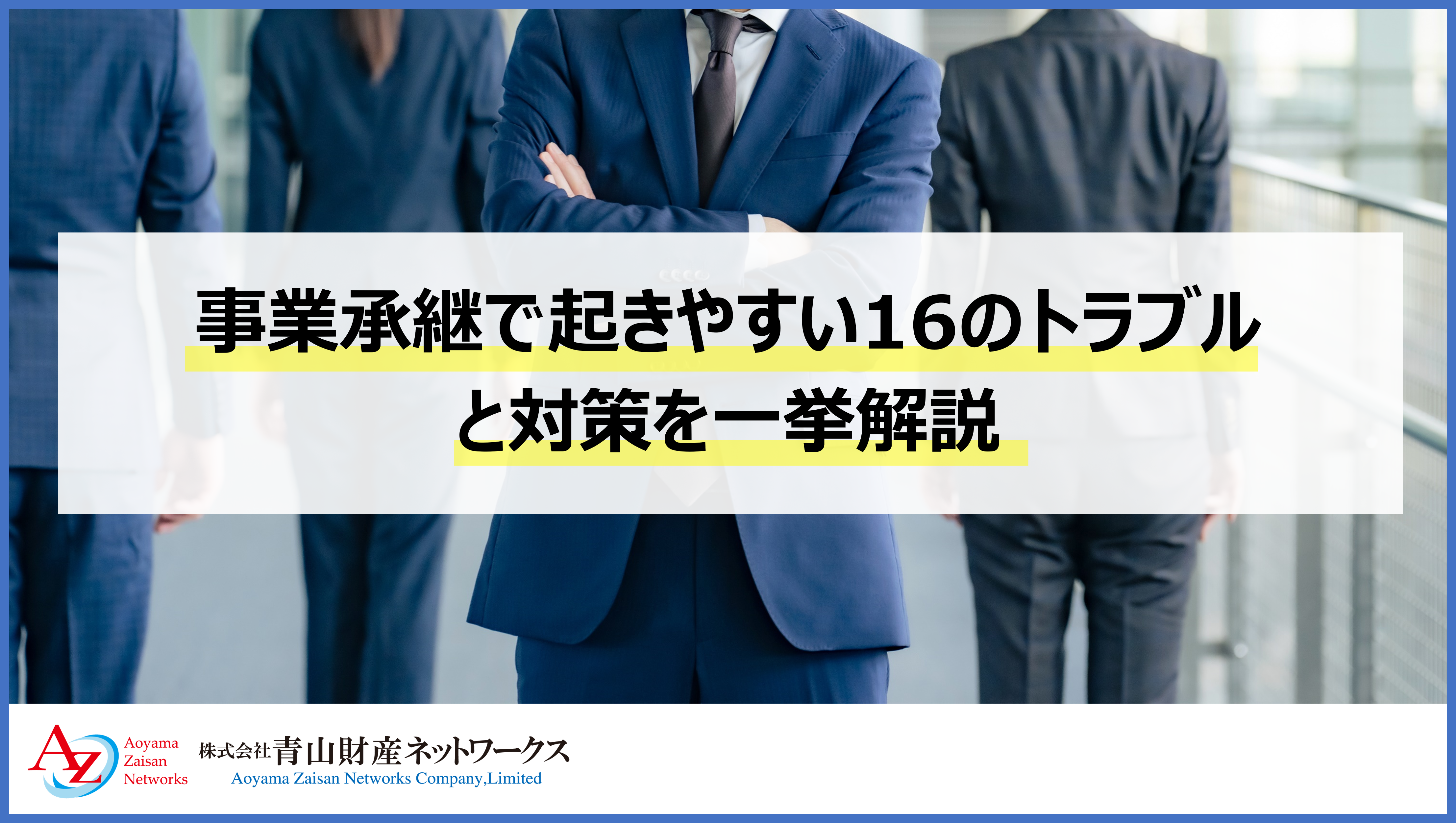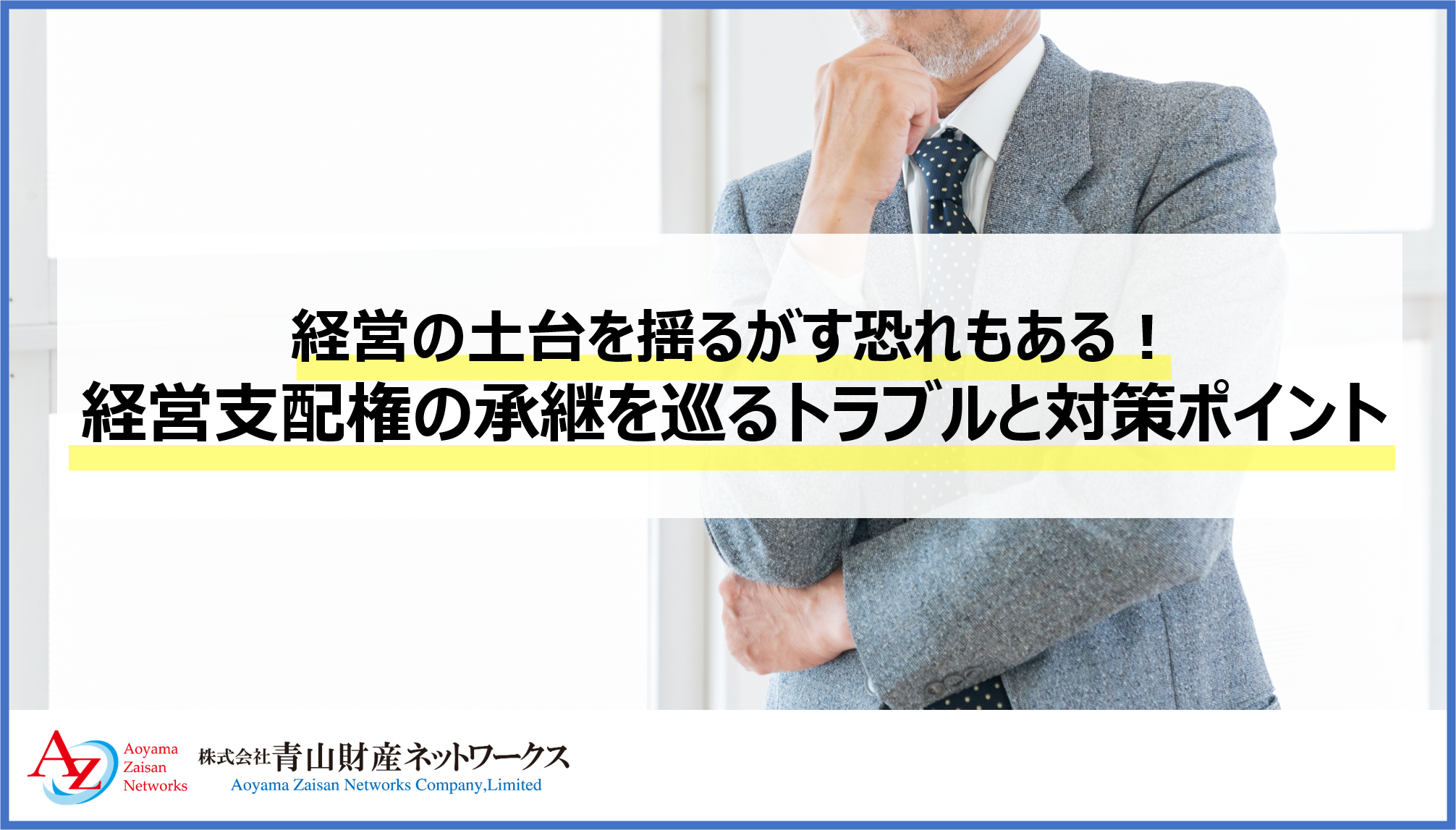事業承継の中心は、現経営者に代わって後継者となる人物が、経営支配権と業務執行を引き継ぐことにあります。これは会社にとって、その経営を支配し業務を執行する主体が変わるという繊細で本質的な変化です。
だからこそ、モノや制度の入れ替えなどとは異なり、コミュニケーションのすれ違いや感情のもつれ、あるいは健康上の問題など、人間関係に起因する、想定外のトラブルが生じてしまうことがあります。
本記事では、人にまつわるトラブルによって事業承継に失敗した4つの代表的な事例と、そのようなトラブルを防止するためのポイントを解説します。
事業承継でもっとも重要なのは「人」の承継
会社を経営するのは人です。経営者がいなければ経営は成り立ちませんし、経営者に能力・適性・意欲がなければ事業は行き詰まります。そのため、事業承継においてもっとも重要となるのは「人」の承継、すなわち、資質や適性に優れた後継人材を確保し、確実に経営のバトンを渡すことです。
しかし、後継者を確実に確保することや、その人物が会社を託すにふさわしいかを見極めるのは、決して容易ではありません。じっくり時間をかけて「この人材なら経営を任せられる」と判断しても、人の心は変化することがありますし、病気や不慮の事故など、想定していなかった事態に直面することもあります。
すべての変化の可能性を予見することはできませんが、なるべく変化に対応できるよう、選択肢を準備して人の承継の準備を進めないと、事業承継が頓挫してしまうことがあります。
トラブル1 後継者が不在で廃業に追い込まれる
後継者不在により休廃業に追い込まれる中小企業は増えています。東京商工リサーチの「2024年『休廃業・解散企業』動向調査」によると、2024年の休廃業・解散企業数は6万2,695件であり前年比大幅増となっていますが、このうち半数以上の廃業理由が「後継者不在」でした。黒字であっても後継者不在により廃業を選択するケースも多いのです。
1-1.設例
A社を営む経営者のA氏は非常に優秀でしたが、反面、いわゆる「ワンマン経営者」であり、業務の細かいところまで自分が指示を出していました。A社は、コロナ禍以後、業容が悪化し、慢性的な低収益体質となり、ほとんど利益が残らない状況が続いていました。
60代半ばになり体力の衰えを感じ始めたA氏は、事業承継を考えます。A氏には3人の子がいましたが、いずれも他社で働いていました。A氏は3人と話し合いましたが、3人とも会社を継ぐ気はありませんでした。次に、A氏は社内の役員やめぼしい社員に相談をしてみましたが、長らくワンマン経営を続けていたため経営を担えるような人材が育っておらず、また、自社株の譲渡費用の問題もあり、こちらも後継者は見つかりません。それでも、A氏は「M&A仲介会社に依頼すればすぐにM&Aで承継できるだろう」と楽観的に考えていました。しかし実際に仲介を依頼したところ、A氏が受け入れられるような条件で引き受けてくれる買い手は見つかりませんでした。業績・財務が悪化していたことに加えて、社内の業務遂行にA氏の属人性が高いことも理由でした。体力の落ちていたA氏は承継をあきらめて、A社を廃業することにしました。
1-2.対策ポイント
事業承継の類型には「親族承継」「社内承継」「第三者承継(M&A)」の3パターンがあります。
以前は、子を中心に親族で承継をするのが、中小企業の事業承継の多数派でした。しかし、少子化や意識変化などを背景に親族承継は減少しており、現在では親族外での承継の割合のほうが多くなっていることを認識しておきましょう。
親族に後継者がいない場合、社内での承継を考えるのであれば、当然ながら経営を任せられる人材を育成しておかなければなりません。候補人材には、経営に関する一定の権限を委譲し、責任を取らせるなど、時間をかけた育成施策を講じる必要があります。また、社内承継でネックとなるのが自社株の移転費用です。その対策をどうするのかも早期から考えておかなければなりません。
第三者承継(M&A)を検討するのであれば、買い手が対価を支払っても引き継ぎたくなる、魅力的な企業に経営の磨き上げをはかっておく必要があります。顧客に対する提供価値、市場におけるポジショニング、業務フローなどを磨き上げ、それが業績や財務の数字に反映されていることが大切です。これは、親族承継や社内承継の場合も必要なポイントです。そもそも「引き継ぎたくなる会社・事業なのか」という点を客観的な視点で見直し、不十分な点があるのなら改善していきましょう。ただし、経営改善には時間もかかります。だからこそ、事業承継へ意識を向けるのは早ければ早いほどよいのです。
トラブル2 後継者になると信じていた子にその気がないと知ってあわてる
「子は親の背中を見て育つ」「言わなくても気持ちは伝わっている」、そんな思い込みで、子が当然後継者になると思っていたのに、いざ話をしてみたらあてがはずれた......。そんなケースもよくあります。
2-1.設例
B社長には一人息子の長男がいました。長男が大学の経営学部に進学するとき「お前もいずれは経営者になる。これからの経営には理論も重要だから、基礎をしっかり勉強をしておけ」といって激励しました。長男も「わかった」といって、4年間真面目に勉学に励み、優秀な成績で大学を卒業し、大手商社に就職しました。
B社長は、長男が商社である程度の期間仕事を学んだら、自社に入って経営幹部となり、ゆくゆくは後継者になることを当然の将来だと考えていました。しかし、就職後、長男は海外に長く赴任し、その後は結婚して家庭を持ったことなどもあり、承継についてじっくりと話し合う機会を持っていませんでした。
長男が就職してから10年ほど経った頃、B社長がそろそろ自社に入ってはどうかと伝えたところ、「会社に入る気も、継ぐ気もまったくない」と言われて、大きなショックを受けました。
2-2.対策ポイント
経営者自身は、子が会社を継ぐことが当たり前だろうと思っていたのに、実は子にはまったくそんな気は無かったということはよくあります。また、子自身も若いときにはよく考えずに、なんとなく「そういうものだろう」と思って承継に前向きな言動を示すこともあるでしょう。しかし、子が社会人となって仕事の経験を積んだり、自分の家庭を持って、一家の大黒柱になったりすると、以前の考え方が変わってしまうことは珍しくありません。そのことが悪いとはいえません。
大切なことは、親のほうから「子が継ぐのは当たり前」「話さなくてもわかっている」といった思い込みを捨てて、定期的に面と向かってきちんと会話をして子の意思を確認することです。例えば、正月やお盆に一家で集まる機会があるのなら、その際に「家族会議」の場を設けて、将来のことを話し合う、といった具合です。
職人タイプの経営者には、家族に対して自分の気持ちを言葉で表すことが苦手な人もいます。しかし、それも大切な経営者の仕事だと肝に銘じて、自分がどう考えているのかを率直な言葉で伝えた上で、子の気持ちを話してもらいましょう。その上で、子が承継を忌避する障害(例えば債務保証や配偶者の反対など)があるのなら、それらを解決できないか具体的に考えます。
トラブル3 オーナー社長が認知症をわずらい事業承継ができなくなる
日本人の高齢化に伴い、認知症やその予備軍である軽度認知障害(MCI)の患者数も右肩上がりで増加しています。厚生労働省の調査によると、2024年時点で、65歳以上の高齢者に占める認知症患者と軽度認知障害(MCI)患者をあわせた数は約558.5万人で、高齢者人口の約27.8%(3.6人に1人)を占めています。そして、これは経営者も例外ではありません。経営者が重い認知症になった場合、事業承継を進めたくても進められない事態になりかねません。
3-1.設例
67歳になるC社長は、1年ほど前に、軽度認知障害(MCI)の診断を受けていました。当初は物忘れが多い程度でしたが、その後急速に認知症が進行し、適切な経営判断が不可能になってしまいました。
C社の取締役会はC社長、X専務、Y氏の3名で構成されていました。X専務はC社長と一緒に会社を起ち上げた古参役員、Y氏はC社長の長男です。
業務遂行が不可能になったC社長が、代表取締役のままでは問題です。X専務は、取締役会決議において、C社長を代表取締役から解任し、当面、自分が代表取締役に就いてはどうかとY氏に相談しました。
しかし、Y氏は親族外のX氏に会社の実権を握られることを嫌ってこれに反対します。とはいえ、まだ若いY氏はX専務と比べて業務経験も浅く、社内や取引先からの信認も薄いため、Y氏が代表者になることについてはX専務が反対しました。2名の意見が対立しているため、取締役会の決議ができません。また、株主総会でC社長を取締役から解任するという方法もありますが、C社の株は、C社長が70%、Y氏が20%、そして会社業務には一切関与していないC社長の妻が10%を保有しています。C社長の議決権行使は意思能力の点で疑義が生じるため現実的ではありません。
Y氏は、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、裁判所が指定する弁護士を法定後見人として後見が開始されました。それにより、C社長は取締役(代表取締役も)を退任します(民法653条3号)。その後、新しい取締役1名を選任するための株主総会開催を後見に求めましたが、X専務とY氏が推す新取締役候補が異なる人物であったため、後見人はどちらが被後見人(C社長)の利益に資するか判断できないとして、議決を留保しました。
その後、X専務は、裁判所に一時取締役(仮取締役)選任の申立てをおこない認められたものの、Y氏がその無効とX専務の取締役退任を求めて提訴するという泥沼の争いに陥ってしまいました。
3-2.対策ポイント
株主総会議決権の過半を持つオーナー経営者が認知症を患い、経営者としても株主としてもどちらも意思決定できない状態になると、会社は非常に困った状態に陥ります。法定後見人を選任すれば、後見人により本人の財産や権利の保全は図られますが、それはイコール、会社にとっての利益となるとは限りません。会社の利益とオーナー個人の利益が相反する場合もあり、その場合、後見人はオーナー個人の利益を優先します。
また、設例にある新取締役選定の議決権行使のように、どちらのほうが被後見人の利益になるかわからない意思決定については、後見人は避ける傾向があります。
このような打つ手無しの状態に陥ることを避けるためには、認知症になった場合を想定して、対策を講じておくことが必要です。まず必要なのは自分に万一のことがあったときに経営業務を代理し承継する後継候補者を定めておくことです。その上で、
- 後継候補者を任意後見人とする「任意後見契約」を締結しておく
- 経営者を委託者・受益者とし、後継候補者を受託者とする「民事信託(家族信託)契約を締結しておく
といった方法が考えられます。
トラブル4 信頼していたナンバー2が相続後にクーデター
後継候補者が独り立ちして経営を担えるようになるまで、補佐してくれるナンバー2がいれば心強いと考える社長は多いものです。しかし、ナンバー2と呼ばれるほどの実力を備える人物は、相応に野心も強いことが多いのです。自分がいなくなった後でも、自分に従ってくれるほど忠誠心の強いナンバー2は、普通の中小企業にはまず存在しないと考えるべきでしょう。
4-1.設例
F社長は晩婚で、長男のX氏を授かったのは40歳のときでした。そのX氏が大学を卒業してF社に入社したときF社長は62歳です。いずれは長男のX氏に会社を継いでもらいたいと考え、またX氏もその気はあったのですが、いかんせん、当分先のことになります。そこで、F社長は、将来長男が承継するとしても、その前の「中継ぎ」として、別の人間が最低でも数年程度は経営を担う必要があると考え、その役割を、社内でF社長につぐ"ナンバー2"と目されていた営業部長のQ氏にまかせることにしました。
F社長はQ氏に「自分に万一のことがあったら長男に後を継いでもらいたいが、そのときに彼に力量が足りないようなら、あなたが社長になって会社を守ってもらいたい、そして将来は長男にバトンタッチして欲しい」と懇願します。Q氏はまかせてくださいと快諾し、社内にも、当面の次期社長候補はQ氏で、その後は長男X氏にバトンタッチという路線が周知されました。
それから5年後、67歳のときにF社長は病気で急逝します。遺言どおりに遺産分割がおこなわれ、F社の全株式はX氏が承継しました。しかし、その時点でX氏はまだ27歳です。業務経験も不足していましたし、なによりほとんど自分より年上の社員となる社内の人心掌握がまったく不十分で、とても社長は務まりません。想定通り、Q氏が雇われ社長となりました。
ところが、社長についたQ氏は、それまでのF社の経営方針を大胆に変更していきます。故F社長が、そしてX氏も大切なものだと考えていた経営理念までも変えてしまったのです。X氏はQ氏に苦言を呈し、対立しました。ところが社内の空気は、大半がQ氏に同調的です。幾度かの言い争いを経て、ついに我慢の限界を超えたX氏はQ氏を取締役から解任し、自らが代表取締役に就任しました。すると、Q氏は社内でも成績のいい優秀なメンバーを引き抜いて、同業種の会社を設立します。そして、F社の顧客をどんどん奪いはじめたのです。もとより経営者としての経験もないX氏は、こうなるとなすすべがありません。それからわずか3年ほどで、F社は倒産に追い込まれたのでした。
4-2.対策ポイント
後継者が確実に事業を承継するための土台は、自社株の集中による経営支配権の確保です。しかし、後継者が経営や事業の実質を把握し、自分だけで事業を回していける実力を持っていなければ、中身のない箱だけを抱えているようなものです。ナンバー2と呼ばれるほどの実力で箱の中身を把握している人間がいれば、たやすく経営の実権を奪われるトラブルに結びつきます。
極端にいえば、中小企業には社長と実力が伍するようなナンバー2はいないほうがいいのです。あるいは、そういったナンバー2が2,3名いる場合は、相互に牽制し合うので、それもよいでしょう。
設例のようなケースの場合、後継候補者のX氏を早期に経営者として育成しておくことがポイントです。
また、場合によっては、株式をプライベートエクイティファンドに譲渡し、ファンドが中継ぎ経営をおこない、5~10年程度あとに後継者(X氏)が株を買い戻すという方法も考えられます。
まとめ
「金(財)を残して死ぬ者は下、仕事(事業)を残して死ぬ者は中、人を残して死ぬ者は上」。
これは、明治から昭和にかけて活躍した政治家、後藤新平の言葉だといわれており、プロ野球監督の野村克也が好んで引用したことから広く知られています。企業経営者にとって最後の、そして最大の仕事は、自分が亡き後も会社と事業を守り育ててくれる「人」を残すことであり、その仕事をトラブルなく成し終えてこそ、経営を真に成功させたといえるのではないでしょうか。しかし、人との関係だからこそ、想定外のトラブルが生じることもあります。そこで大切なのが、過去のトラブル事例などに学びながら、様々な事態に対応できるように、プランAだけではなく、プランB、プランCといった選択肢を用意しておくことです。多くの事業承継をサポートしてきた青山財産ネットワークスにご相談いただければ、御社の状況に即したプランニングをご提供できます。
- 松川 洋平Matsukawa Yohei
- 執行役員 コンサルティング事業本部 第一事業部 部長
1983年兵庫県生まれ。早稲田大学 商学部 卒業。
辻・本郷税理士法人にて、相続・事業承継の税務業務に従事、デロイト・トーマツ税理士法人にて、事業承継のコンサルティング業務に従事する。
2018年に株式会社青山財産ネットワークスに入社し、上場・非上場問わずオーナー経営者に対して、財産の承継・運用・管理の総合コンサルティングを提供している。
- 専門分野
- 企業オーナー向けコンサルティング
- 資格
- 税理士
- 著書
- 事業承継 親の心子知らず 子の心親知らず~19の失敗事例から導く「思い」「理解」「感謝」のない対策の行方~