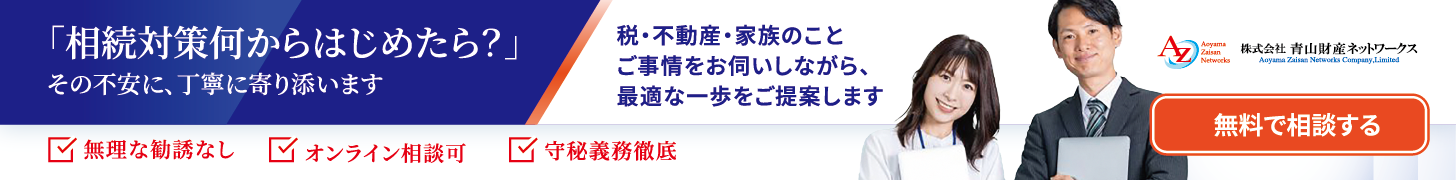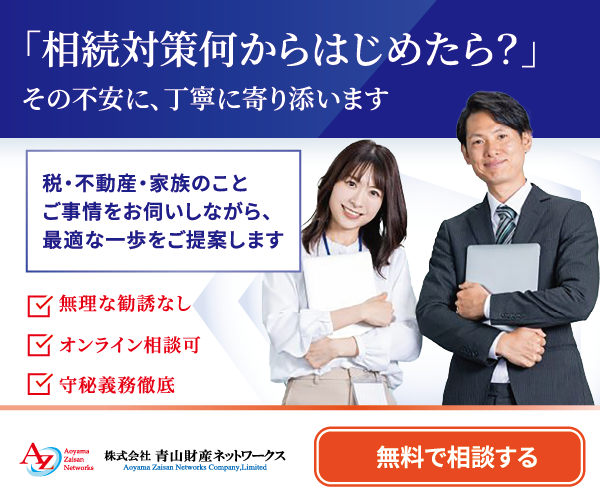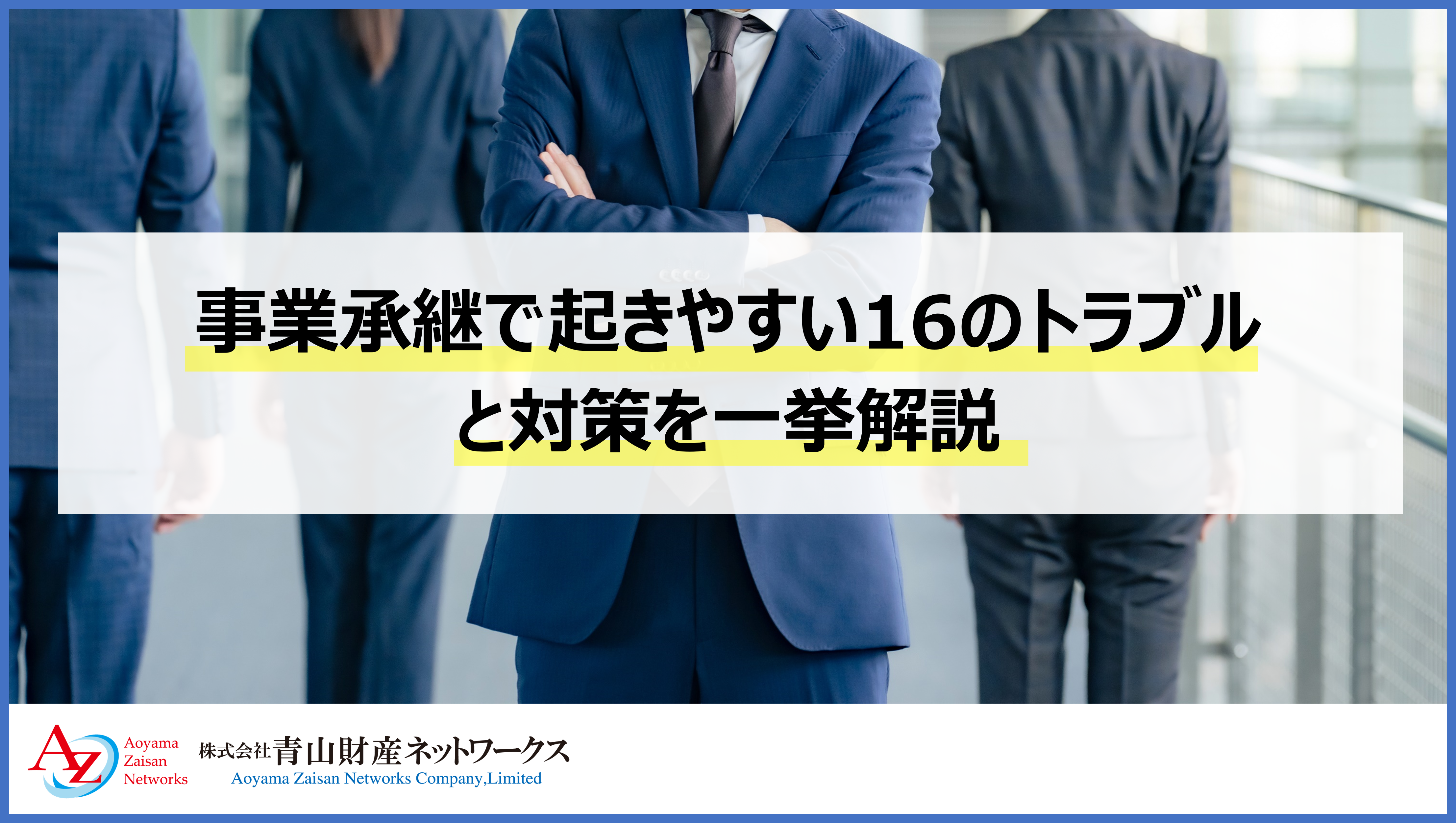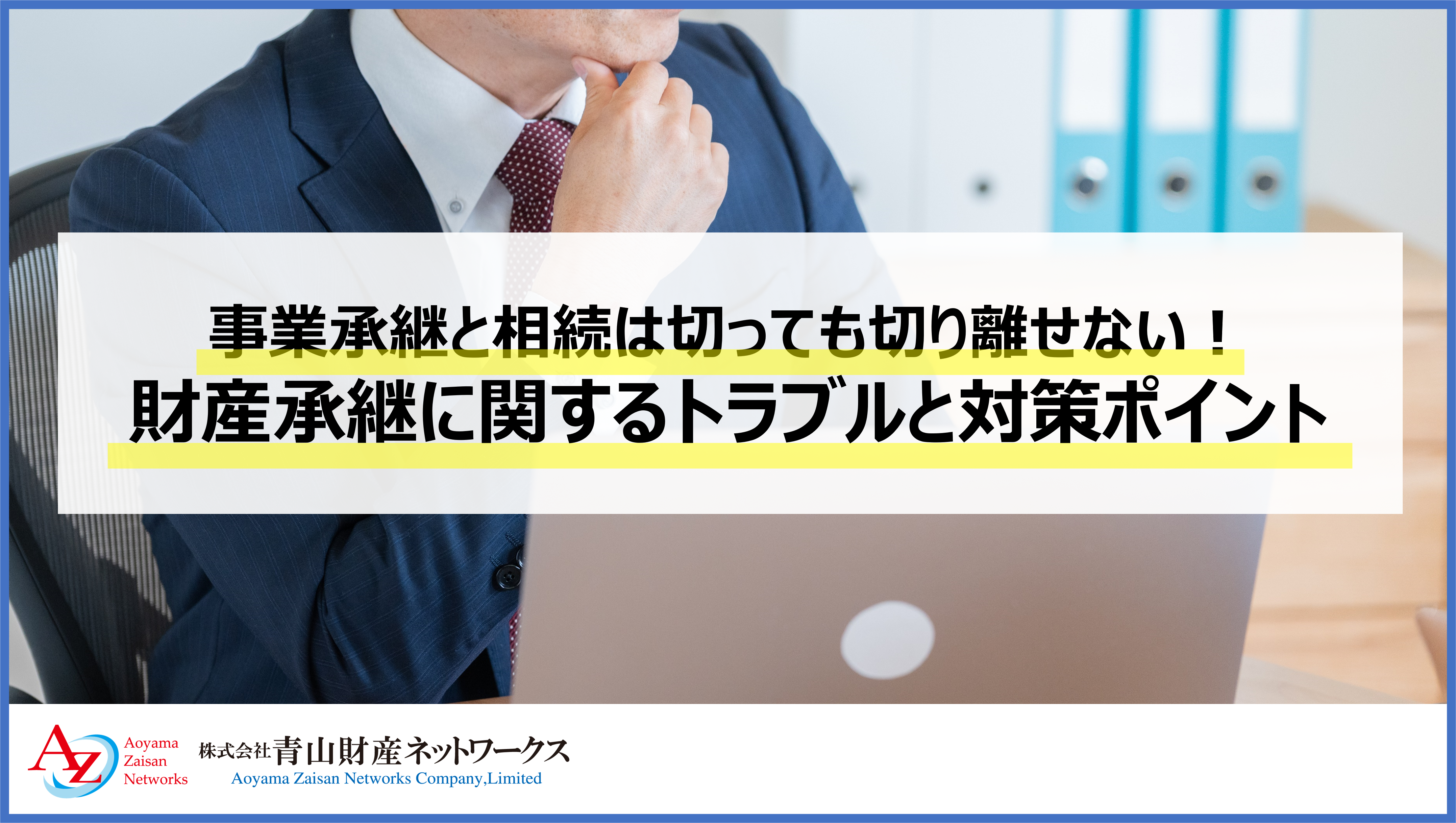「経営権を巡るトラブル」は、事業承継を進める中で最も深刻なリスクの一つです。自社株の分散や誤った贈与は、想定外の人物が経営に関与する事態を招きかねません。本記事では、実際に起きたトラブル事例をもとに、経営支配権を円滑に承継するための注意点と対策を解説します。
経営支配権の承継とは
事業承継で引き継がれるべき3大要素は、「経営支配権」「資産」「無形資産」とされています。株式会社では、経営支配権を持つのは株主であり、株主が取締役に経営業務執行を委任する仕組みになっています。経営支配権は株主が保有する株式数(=議決権数)に応じて分与されます。経営支配権の承継とは、株主の地位を承継することであり、具体的には株主総会で議案を可決できるだけの議決権を持つ自社株を後継者に承継させることになります。
経営安定化のためには、代表取締役となる後継者に経営支配権が集中するように、株式を集中して承継させることがセオリーとされています。どのくらい集中させればよいかといえば、可能であれば株主総会の特別決議を可決できる3分の2以上、少なくとも普通決議を可決できる2分の1超の議決権割合です。
では、経営者がそれだけの議決権を保有していればそれで経営支配権の面は安泰かといえば、実はそうともいえないのです。少数株主にも様々な権利が付与されているため、議決権の大半を経営者が保有していたとしても、少数株主に起因するトラブルが生じるリスクはあります。
その意味でも、自社株を誰に(後継者、それ以外の親族等に)、どんなタイミングで、どれだけ移転するかは、株式会社の事業承継でもっとも核になる部分だといえます。これを安易に考えてしまったことによるトラブルは後を絶ちません。
トラブル1 自社株を、複数の子に公平に相続したためにお家騒動が勃発
オーナー経営者が自社株を保有したまま死亡すると、自社株は遺産(相続財産)となります。もし、複数の相続人がいて、遺産に占める自社株の割合が大きい場合、経営権の集中と遺産分割との兼ね合いが問題になります。また、会社の経営状況によっては、自社株が高額な相続税評価になる場合があり、相続税の納税の問題も生じます。
1-1.設例
D社で株式を100%保有するオーナー経営者のD社長が、代表取締役についたまま病気で亡くなりました。
相続人は、D社長から後継候補者として指名され経営者としての薫陶を受けてきた専務取締役のX氏(長男)と、取締役のY氏(次男)、そしてD社とは関係ない仕事をしているZ氏(三男)です。
相続財産の内容は、自社株(10億円相当)、自宅土地建物(1億5,000万円相当)、本社土地建物(1億円相当)、銀行の定期預金(4億円)でした。
D社長は遺言を残しており、各自の承継内容は以下のように定められていました。
- X氏:自社株の45%(4億5,000万円相当)、自宅土地建物(1億5,000万円相当)、預金1億円、計7億円相当
- Y氏:自社株の40%(4億円相当)、本社土地建物(1億円相当)、預金1億円、計6億円相当
- Z氏:自社株の15%(1億5,000万円相当)、預金2億円、計3億5,000万円相当
相続評価額には差がありますが、自社株は経営に関与する者が多く持つ必要があること、また換金性に乏しいことなどの理由があるので、できるだけ公平に分配していると理解して欲しいとの旨が遺言書には記されていました。Y氏とZ氏はやや不満でしたが、遺言があり、遺留分の侵害もないため、遺産分割は上記の通りにおこなわれました。
X氏が新社長となった事業承継後、X氏とY氏の間に経営方針を巡る意見対立がしばしば生じるようになってきました。しかし、もう1名の取締役であるQ氏(親族外)は、基本的にX氏に賛同しており、取締役会では最終的にはX氏の提起する方針が採用されていました。
その状況に不満を抱いたY氏は、遺産分割に不満を持っていたZ氏を巻き込んでクーデターを画策します。Z氏から委任状を取り付け、臨時株主総会の開催を要求して、X氏の取締役解任決議を可決したのです。さらに自分の息のかかった社員を取締役に抜擢し、取締役会も支配しました。
しかしその後、Y社長の経営刷新策はことごとく裏目に出て、D社の業績は急速に悪化していきました。
1-2.対策ポイント
相続という観点からは、複数の子が相続人となるとき、できるだけ公平に遺産分けをしてやりたいと思うのは親として当然の心情です。相続人間で大きな不公平が生じる遺産分割は親族間に感情の軋轢を生み、後々まで尾を引きます。場合によっては、遺留分侵害額請求の訴訟沙汰となる恐れもあります。
反面、事業承継という観点からは、1人の後継者にできるだけ自社株(経営権)を集中させることが、経営安定化のポイントとなります。
「公平な遺産分割」と「自社株の1名への集中」という2つの課題は相反する部分がありますが、以下のような方法で事前に準備をしておけば、解決は可能です。
①自社株以外の資産を増やし、相続財産に占める自社株の割合を減らす方法
自社株以外の資産を増やし、自社株は後継者に集中して相続させる一方、後継者以外の相続人には自社株以外の資産を厚く相続させることで公平を図ります。
②生命保険を活用して代償分割をおこなう方法
現経営者(親)が被保険者かつ保険料の支払者となり、後継者(子)が受取人となる生命保険契約を締結しておきます。被相続人の死亡後、後継者は受け取った生命保険金で、後継者以外の相続人に現金を支払って、公平を図ります。この方法を「代償分割」と呼びます。なお、後継者が受け取った保険金は、相続財産ではなく、その相続人固有の財産とされ、遺産分割の対象にはなりません。
③種類株式を活用する方法
種類株式とは、株式の種類ごとに権利内容が異なる株式のことです(種類株式以外の株式は「普通株式」と呼びます)。
会社法では9種類の種類株式の類型が規定されていますが「拒否権付株式」は、1株でも保有していれば、会社の合併や取締役の選任・解任など、株主総会の重要決議事項に対して拒否権を行使できる株式です。通称「黄金株」と呼ばれます。黄金株を1株だけ発行し、後継者に相続させれば、普通株を公平に遺産分割したしとしても、重要事項について後継者の経営支配権を担保することができます。
また、「配当優先無議決権株式」という種類株式の活用も考えられます。これは文字通り、配当金を優先的に受け取る権利を持つ一方、議決権を持たない種類株式です。会社に配当金を支給できる財務的な余裕がある場合は、後継者以外の相続人にはこの種類株式を相続させて、配当金を受け取れることで納得してもらうという方法もあります。
トラブル2 自社株の生前贈与の後に親子が仲違いし、悔やんだ社長
一般的には、事業承継対策は早期からの取り組みが大切だという点が強調されます。しかし、あまりにも早くから後戻りできない「決め打ち」の対策を採るとトラブルにつながることもあります。
2-1.設例
30代で起業してビジネスを成功させたE社長は、税制についてもよく勉強しており、将来の事業承継に対して早期から対策を採る必要を感じていました。その1つとして取り組んでいたのが、後継候補者である長男への、自社株の生前贈与です。E社長の長男は、大学を卒業すると3年ほど他社に勤めてからE社に入社し、将来の社長候補として意欲的に様々な業務を経験しました。その様子を見て、E社長は承継準備として自分が55歳、長男が30歳になった年から、自分が持つ自社株の生前贈与を開始しました。毎年、200万円~300万円相当の自社株の贈与を続けたのです。贈与税の非課税枠は110万円なので、それを超える部分は長男が贈与税を納付しなければなりませんが、数万~10数万円程度なので、さほど大きな金額ではありません。その分、賞与を高めに支給していたので、長男も負担に感じることはありませんでした。
E氏は75歳で事業承継してリタイアしたいと考えており、そこまで20年かけて自社株の大半を贈与しておくというのがE氏の計画でした。
そうして10年ほど経ったとき、E社長と長男は、長男の家族をめぐる問題での意見対立から大げんかをします。そして、長男は辞表を叩きつけてE社を辞めてしまったのです。
E氏はぼうぜんとしましたが、関係を修復させることはできませんでした。そうなると、困るのが長男に贈与した自社株の扱いです。すでに全株式の30%ほどを贈与していましたが、今更「返してほしい」といっても、完全に関係がこじれてしまった長男が応じてくれる可能性は無さそうです。また。仮に長男がE氏に自社株を返すといって贈与してくれたとしても、株価は時価で7,000万円以上になっており、多額の贈与税が課税されます。
今後、別の人物に事業承継をするにしても、M&Aをするにしても長男が保有する株の扱いがネックになるでしょう。E氏は途方に暮れてしまいました。
2-2.対策ポイント
事業承継対策、特に自社株の移転に伴う課税コスト対策として、生前贈与は古くから用いられている手法です。確かに、課税コストを圧縮するという点では、贈与税の基礎控除を活用する方法は有効です。2024年からは相続時精算課税にも基礎控除が導入され、暦年課税の基礎控除と併用できるようになったこともあり、活用している方も多いのではないでしょうか。
しかし、ここで見逃されがちなポイントは、「一度おこなった贈与は取り消すことができない」という点です。親子とはいえ、事例のように、その関係が決定的に変化してしまうことはあり得ることです。
また、自社株に限らず、相続税対策として生前贈与をしたのはいいものの、その後に贈与者(親)の経済状況が悪化して、「やっぱり贈与をしなければよかった。返してほしい」と後悔するケースもよく見られます。そのようなときも、一度贈与した財産を返してもらうことは、かなり困難ですし、すでに費消されている場合は返したくても返せないでしょう。
取り消すことができない対策に頼り切ってしまうことは、あまりにリスキーです。事業承継においては、「生前贈与は節税になる」といった一面的な情報だけに惑わされることなく、様々な可能性を勘案して打ち手を考えなければなりません。
トラブル3 事業承継後に知らない株主がやってきて、経営に参画させろと要求
同族会社で株式が親族に分散していたり、創業時に名義株があったりした場合、社歴が長くなり株の相続が繰り返されると、現経営者がまったく知らない人物が株主になっていることがあります。少数株主だし、譲渡制限がついているからと放置していると、大きなトラブルに結びつく場合もあります。
3-1.設例
G社長は1年前に亡くなった先代社長(G社長の父)の後を継ぎ、G社の代表取締役に就任しました。ある日、G社長のもとに、Qと名乗る知らない人物から「自分は御社の株主だ。自分が保有する株をP社に譲渡したいので、承認してほしい」と連絡がありました。確認してみると以下のような経緯があったことがわかりました。
40年ほど前に先代社長が会社を創業したとき、先代社長のいとこに資本金1,000万円の5%(50万円)の出資をしてもらっていました。
そのいとこが亡くなり、配偶者(妻)が株を相続しました。その後、元配偶者は別の男性と再婚をします。そして、その再婚相手との間に子をもうけました。その子が、連絡をしてきたQ氏です。元配偶者が亡くなって、彼女が所有していたG社株を相続したといいます。経緯からもわかるとおり、現在、Q氏とG社長とに親族関係はありませんが、Q氏がG社の株主であることは間違いありません。そして、G社株は譲渡制限株式となっており、株主が第三者に譲渡する際には、発行会社の承認が必要とされるため、連絡を取ってきたのでした。
譲渡を予定している相手を聞くと、R社という会社だといいます。G社長は不審に感じました。ビジネス上の関係もまったくなく、上場の予定もない中小企業の株をわざわざ購入しようとする会社は、普通ありません。そこでG社長が顧問弁護士にR社のチェックを依頼したところ、いわゆる反社会的勢力に関係している企業だということがわかりました。当然、G社長は譲渡を承認しませんでした。Q氏は「それなら御社に買い取って欲しい」といいましたが、その希望価格は、G社の財務状況に照らして法外に高額だと感じられるものでした。結局、裁判に持ち込まれましたが、裁判所が算定した株価は、G社長の想定よりはるかに高く、Q氏の希望価格に近い水準でした。
G社長は、やむを得ずその金額で株を買い取りましたが、思わぬ資金流出により、G社で予定していた設備投資は、延期せざるを得なくなってしまいました。
3-2.対策ポイント
1990年改正以前の商法では株式会社設立に際して7人以上の発起人が必要だったため、いわゆる名義貸しのような形で株主名簿に記載されている少数株主がよく存在していました。これを「名義株」といいます。
また、それとは異なりますが、親族に出資してもらい少数株主になってもらっているとき、譲渡制限を設けている株であれば(通常はそうしています)、勝手に他人に譲渡されることはありません。しかし、相続による承継の場合は別で、会社の知らないところで、株主の相続人に株の所有権が移転している場合があるのです。社歴の長い会社になると、何度も相続が繰り返されて、赤の他人の手に自社株が渡っていることもめずらしくありません。すると、設例のようなトラブルの要因となるほか、M&A譲渡を検討する際の障害にもなります。
このような事態を予防するには、様々な方法があります。
まず、基本となるのは創業時の経緯を知っている創業社長が、事業承継の実行前に株主名義を確認し、名義株や少数株主の整理をしておくことです。
少数株主となっている人に連絡を取り、事業承継を控えているので株主を整理したいという事情を説明し、相応の対価を支払うので買い取らせてほしいといえば、多くの場合は心よく応じてもらえるはずです。
なお、名義株(株主が実際には出資していない)の場合は、まずは名義変更だけをお願いしてもよいでしょう。
いずれにしても、名義変更の確認書や株式売買契約書などの書類を作成して証拠を残しておきます。
そういった依頼をしても拒否される場合などに備えて、会社が株主の保有する自社株を強制的に取得する方法が用意されています。
①特別支配株主による株式等売渡請求
まず、オーナー経営者が自社株の90%以上を保有している場合に利用できるのが、「特別支配株主による株式等売渡請求」という方法です。特別支配株主とは、対象会社の総株主議決権の90%以上を保有する株主のことです。
特別支配株主は、その株式会社の株主の全員に対して、その株式会社の株式の全部をその特別支配株主に売り渡すよう請求することができると定められています(会社法179条1項)。注意点は、特定の少数株主の株式だけを買い取るということはできず、すべての株主の株式を買い取らなければならないという点です。
なお、特別支配株主による株式等売渡請求の実施にあたっては取締役会の決議が必要です。
②株式併合
複数の株を合わせてそれよりも少ない株式数にする方法です。例えば、100株を1株にするといった具合です。それにより少数株式を「端数株式」にします。すると、裁判所の許可を得た上で、端数株式をすべて会社が強制的に買い取ることができます。これも、特定の少数株主の株式だけを買い取るということはできず、すべての端数株式を買い取ることになります。
なお、株式併合の実施には、株主総会の特別決議が必要です。
③全部取得条項付株式、取得条項付株式の発行
これは事前に準備が必要な対策です。
会社法では、会社が株主から強制的に株を取得できるタイプの種類株式が、2類型定められています。
まず「全部取得条項付株式」です。これは、株主総会の特別決議を経ることにより、個々の株主の同意を得ることなく、会社がその株式の全部を取得できるという種類株式です。株主は会社の買い取りを拒否することができませんが、価格は協議できます。
もう1つ、あらかじめ定めた一定の事由が生じた際に会社が株式を買い取りできるのが、「取得条項付株式」です。例えば株主の死亡を事由としてその株式を取得できると定めておけば、株主はそれを拒否することはできず、相続によって承継されることを防止します。取得条項付株式では、買い取り方法や取得対価も会社が定めることができます(株主が不満であれば裁判所に申し立てることもできます)。なお、「全部取得条項付株式」と異なり、一定の事由が生じた際には会社の意思のみで買い取りを実施することができ、株主総会決議は不要です。
④定款に売渡請求を定めておく
これも事前に準備が必要な対策です。
定款に、株式の譲渡制限と共に売渡請求を定めておく方法です。これは、相続などによる一般承継で株式を取得した株主に対し、株主総会の特別決議により、その株式を会社に売り渡すよう請求できるという規定です。会社の買い取り価格は株主との協議で決めますが、まとまらない場合は裁判所に申し立てて決めてもらうことができます。
まとめ
自社株が多くの株主に分散している状態は、様々なトラブルの火種となります。とはいえ、経営者が自社株を100%保有することも、財政面や相続、あるいは内部統制などの観点から必ずしも最適とは限りません。成長を目指す企業であれば、第三者割当増資などを通じて出資を募ることが必要となる場合もありますし、スタートアップ企業であれば役員・従業員にストックオプションを付与することもあります。
自社にふさわしい株式政策・資本政策や事業承継を見据えた種類株式の活用などに、高度な専門知識が必要です。ご不明点やご心配点がある方は、経験豊富な専門家も在籍する青山財産ネットワークスにお気軽にご相談ください。
- 松川 洋平Matsukawa Yohei
- 執行役員 コンサルティング事業本部 第一事業部 部長
1983年兵庫県生まれ。早稲田大学 商学部 卒業。
辻・本郷税理士法人にて、相続・事業承継の税務業務に従事、デロイト・トーマツ税理士法人にて、事業承継のコンサルティング業務に従事する。
2018年に株式会社青山財産ネットワークスに入社し、上場・非上場問わずオーナー経営者に対して、財産の承継・運用・管理の総合コンサルティングを提供している。
- 専門分野
- 企業オーナー向けコンサルティング
- 資格
- 税理士
- 著書
- 事業承継 親の心子知らず 子の心親知らず~19の失敗事例から導く「思い」「理解」「感謝」のない対策の行方~