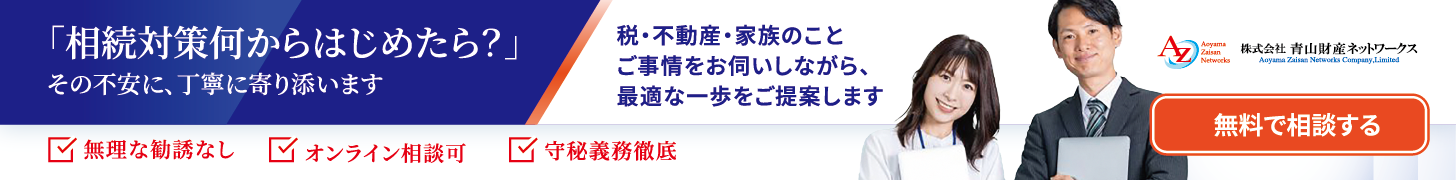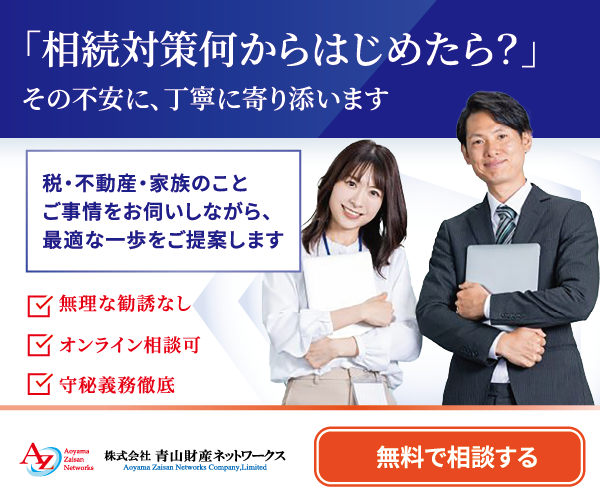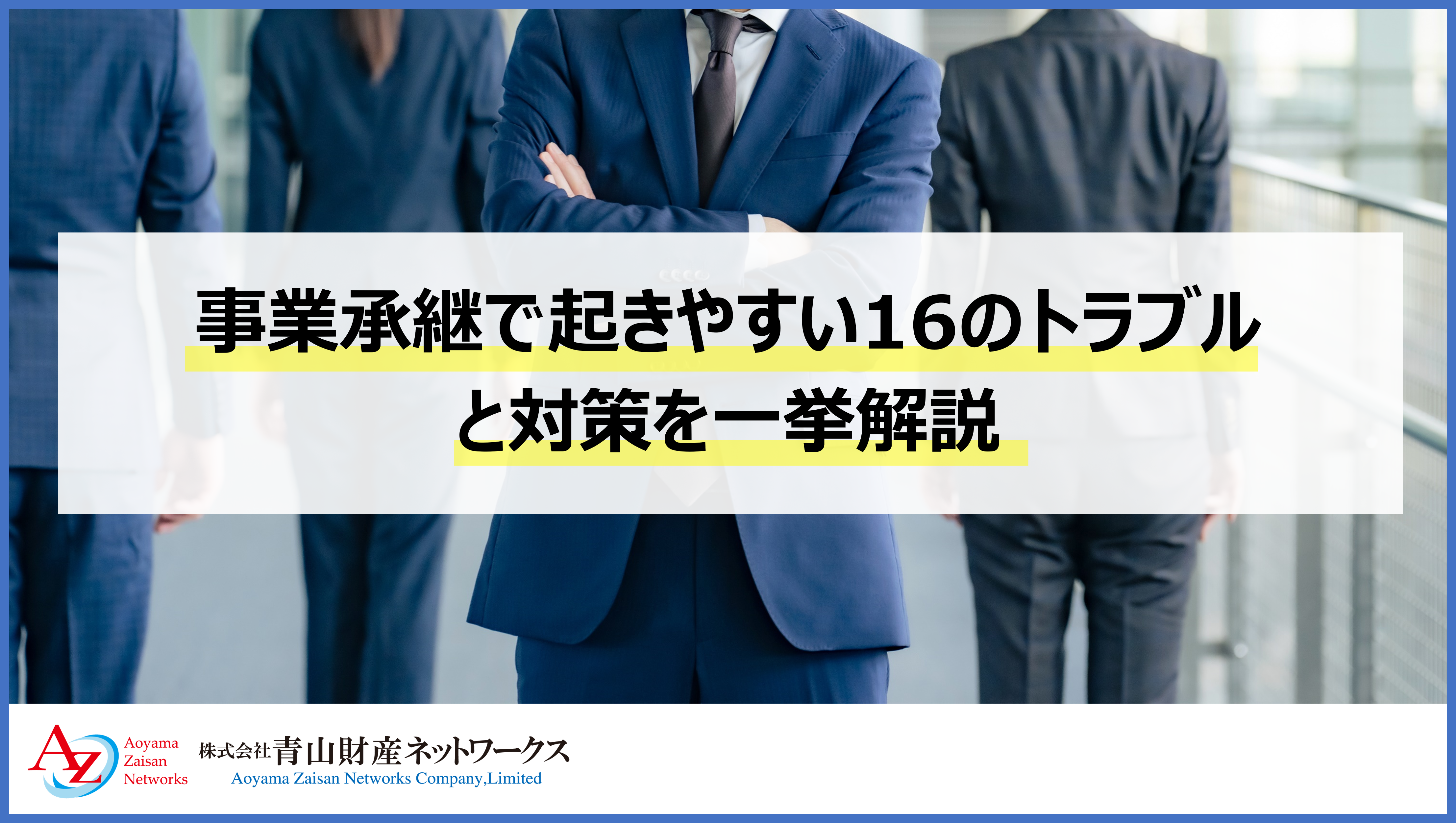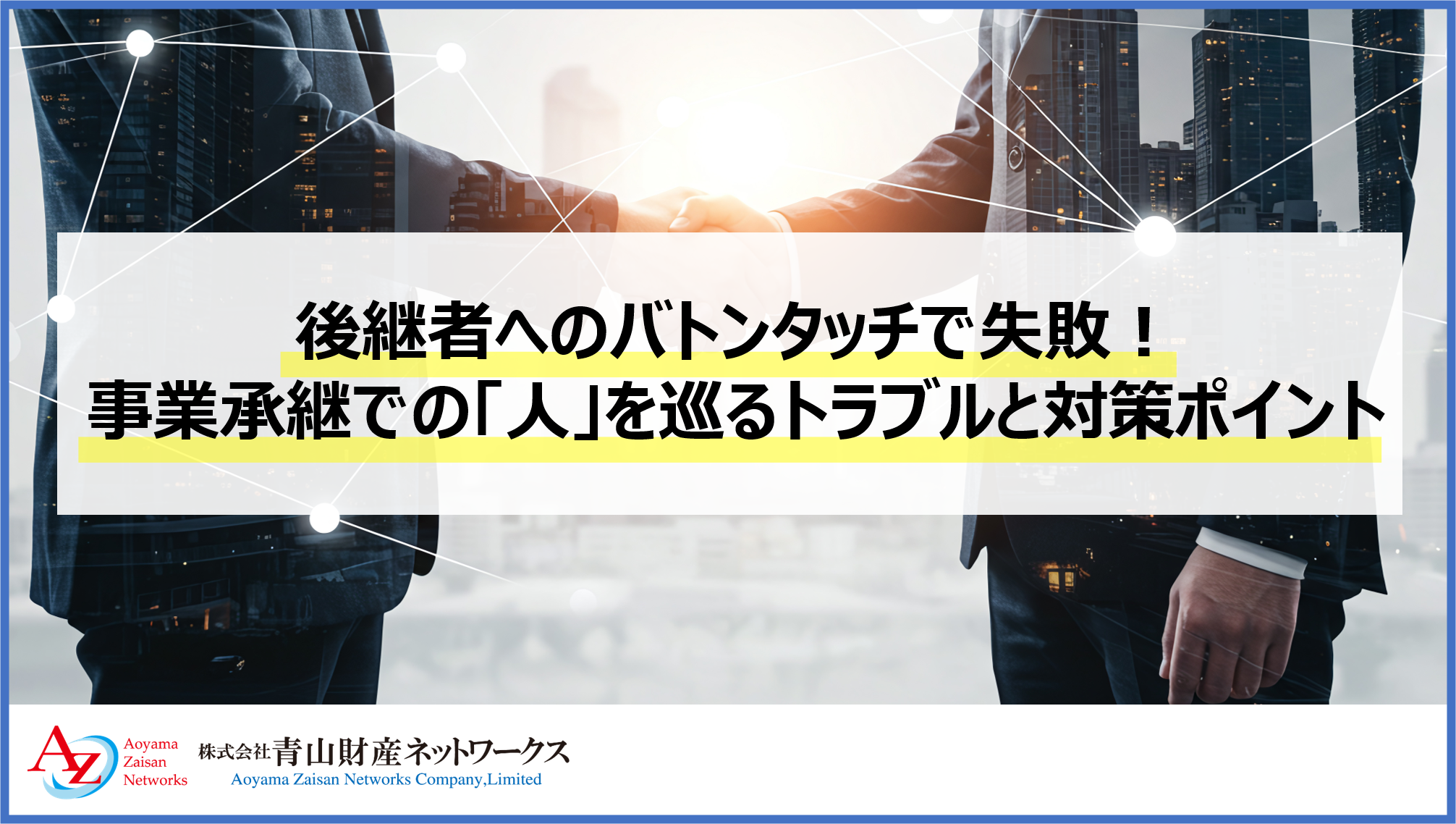事業承継や相続の際に、一定の課税コストを負担することは避けられません。納税は国民の義務であり、正しく納税するのは当然ですが、経営者として、できれば課税によるキャシュの流出を避けたいと思うのもやむを得ないところです。
だからといって、節税ばかりに意識が向くと、本来の目的である「円滑な事業承継」を阻害する可能性があります。
本記事では、そんな「過度な節税対策」によるトラブル事例と、それを避けるポイントを見ていきます。
本末転倒の「節税対策」とならないように注意
事業承継では、後継者への自社株の移転が必ず発生します。そしてその際には、移転コストが必ず発生します。例えば、相続や贈与による自社株の移転であれば、後継者に相続税や贈与税が課税されます。また、譲渡(後継者の買い取り)による移転であれば、現経営者が受け取る譲渡所得に対して所得税・住民税等が課税されます。
誰が、どのような形で支払うのかはバリエーションがありますが、課税コストを避けることはできません。
言うまでもなく、法律に従って納税をすることは国民の義務であり、それを違法に回避する脱税行為は論外です。
しかし、自社株の移転コストは株主(現経営者または後継者)や会社からのキャッシュ流出を意味し、キャッシュフローや財務状況の悪化を通じて経営を悪化させ、円滑な事業承継や承継後の経営安定を阻害する要因ともなります。そのため、株式移転の方法やタイミングに工夫を凝らすことで、課税コストの圧縮や将来への繰り延べ図る「節税対策」に取り組む経営者や企業も少なくありません。
しかしここで注意したいのは、「節税対策」をおこなうにしても、その目的はあくまで円滑な事業承継や安定した経営を実現することあって、節税自体が目的となるものではないはずだという点です。ところが、この点をどこかで勘違いしてしまい、節税することを至上命題のように考えて、過度な「節税対策」を講じて、本来の目的であった事業承継や経営安定化に悪影響をもたらすという、本末転倒の事態に陥ってしまうケースがしばしば見られるのです。
以下で、3つの事例を見ていきます。
トラブル1 節税対策で持株会社を作った結果、キャッシュが流出
事業承継対策として持株会社の設立が用いられることがあります。この方法は銀行融資を活用するため銀行が好業績の融資先によく提案するもので、「銀行スキーム」と呼ばれることもあります。このスキームを用いると、確かに相続税を圧縮することはできるのですが、他の面でのコスト増につながり、トータルで見ると、デメリットのほうが大きくなる場合があります。特に、現在のような金利上昇局面では、注意が必要です。
1-1.設例
N社長はメインバンクの担当者との会話の中で、最近体調が思わしくないので事業承継を考えたいが税金が心配だと述べたところ、持株会社を設立すれば相続税を節税できるといわれて、以下のようなスキームを提案されました。
まず後継者のX氏が100%株主となって、持株会社P社を設立します。次に、N社長が保有するN社の株をすべて持株会社P社に時価で譲渡します。その際、設立したばかりのP社にはお金がないため、N社長に支払う買い取り資金は銀行から融資を受けてまかないます。これで、N社はP社の100%子会社となります。
以後、N社は、利益からP社に毎年配当金を支払います。そしてP社はその配当金で銀行に融資を返済していきます。なおP社自体では事業活動はおこないません。
この体制となれば、後継者のX氏は、P社を通じて、実質的にN社の経営支配権を保有することになるので、経営支配権(自社株)の移転という点での事業承継は完了しています。将来、N氏が亡くなって相続が発生した際に株式の移動は発生しないので、自社株にかかる相続税の心配はなくなります。
また、持株会社が保有する株式の株価が将来上昇した場合に、含み益部分には法人税等相当額の控除(37%)が認められるルールがあります。これにより、将来X氏からその次の世代(X氏の子など)への事業承継がおこなわれる際の、P社の株価評価を抑制することができます。
この話を聞き、N社長よりもむしろX氏が乗り気となったため、実行に移されました。
その後、数年間はうまくいっていたのですが、あるときN社に強力な競合が出現し、利益が低下するようになってきました。配当は剰余金の分配可能額の範囲でしか出せないため、配当額も低下します。ついにP社の融資返済をぎりぎりまかなえる程度になってしまいました。もしこれ以上配当が下がれば、融資返済資金を他から手当しなければなりません。
その心配をしていた矢先、N氏が亡くなって相続が発生しました。ここでも想定外だったのは、相続税が意外と高額になったことです。
P社への自社株売却後、銀行はやはり節税対策として収益不動産の購入を勧めました。しかしN氏はそのころから体調が急速に悪化して、ほとんど寝たきりの状態になってしまったのです。そのため、不動産投資もせず、N社株の売却対価は、全額が貯金としてそのまま残されていたのです。譲渡益に対する所得税がかかったので、自社株の評価額そのままではありませんが、それに近い額が預金で残されていたため、期待していた相続税の圧縮効果は、ほとんどなかったのです。ただ、自社株と違って貯金の相続は、納税資金が確保できるという点ではメリットもありました。
X氏は、結局P社への多額の融資を実行できた銀行だけにメリットがあったようだと感じています。
1-2.対策ポイント
後継者が株主となって持株会社を設立し、事業会社の株を100%保有する方法は、実際によく用いられています。その時点で経営支配権の移転は完了するので、将来、自社株の値上がりを心配しなくて済む点や、親会社が保有する子会社株式の含み益部分に、法人税等相当額の控除(37%)が適用される点などは、確かにメリットがあります。
また、現経営者にとっては、事業会社の株を持株会社に譲渡することで譲渡対価が得られます。それをリタイア後の生活資金や趣味を楽しむ資金にすることもできます。
しかし、このスキームは、事業会社が親会社に対して、銀行への融資返済を十分にまかなえるだけの配当を出し続けられるということが前提になっています。仮に銀行融資の返済期間が10年なら10年間は高収益を続けて配当を出し続ける必要があります。
しかし、事業環境の変化が激しい現在、中小企業が10年先までも確実に高収益を上げ続けられると断言するのは、なかなか難しいことではないでしょうか。
また、事例にあるように、現経営者が得た譲渡対価を使わずに貯金したままにしている場合、評価減額がまったくない形で相続財産が残されてしまい、相続税の圧縮効果は得られません。収益不動産の購入により相続税対策とすることが銀行から推奨されることもありますが、収益不動産には経営リスクがあり、場合によっては損失を抱えることになります。また、もし直後に相続が発生すると、租税回避行為とみなされる心配も生じます。
メリットもある持株会社スキームですが、デメリットや注意点も少なくありません。この方法を検討する場合は、それらを十分理解した上で、第三者の専門家の意見も採り入れながら慎重に判断するべきでしょう。
トラブル2 事業承継税制を使ったが自由な経営ができない
中小企業の事業承継を推進するために、国も様々な支援策を用意しています。その1つが2008年に制定された経営承継円滑化法に基づく「事業承継税制」です。これは、後継者が先代経営者から株式や事業用資産を承継する際、一定の要件に該当すると、贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。さらに、後継者が次の世代に事業を承継した際などには、猶予されていた納税額が免除される場合もあります。
その反面、承継後、原則として5年間は、事業継続や雇用維持などの条件を満たし、毎年「継続届出書」を都道府県と所轄税務署に提出するなど要件が求められ、満たさないと猶予が取り消されるリスクがあります。
2-1.設例
O社長は、60代前半ですが、元気なうちに長女のZ氏への事業承継を完了してセカンドライフを楽しみたいと考えていました。また、Z氏も承継には前向きでした。ただ、自社株の移転が問題でした。O社の自社株評価額は約1億円で、Z氏に買い取る資金がありません。また全株を贈与すると、贈与税が5,000万円近くかかり、やはりZ氏には支払えません。
あるとき、O氏とZ氏は地元商工会のセミナーで事業承継税制の存在を知りました。この制度を利用すれば、贈与税の納税が猶予されるので、現時点では負担無しで自社株を移転できます。
より有利な制度となっている「特例措置」を受けるには、認定支援機関の認定を受けた計画書を作成して2025年度末(2026年3月31日)までに申請しなければならないと知り、急いで準備に取りかかりました。
準備から申請書の提出まで半年以上かかりましたが、無事に特例承継計画の確認を受け、株式の移転や代表取締役の交代を経て、県の認定を受けることができました。
その後、O社長は夢だった海外でのセカンドライフを楽しみたいといって、アメリカに移住してしまいました。Z氏はO社の経営に邁進していたものの、2年ほどたつと、O社事業ではなく別の新規事業に強い興味を持つようになります。Z氏が商工会などを通じて知り合った若手の経営者仲間には、起業とイグジット(M&A譲渡)を繰り返しながら、新規事業へのチャレンジを続けているシリアルアントレプレナーと呼ばれる起業家もいます。また、親から引き継いだ会社で、どんどんピボット(事業転換)を繰り返して、祖業とはまったく異なる事業形態を成功させている社長もいます。そういったアグレッシブな若手起業家たちとの交流を通じて、Z氏もM&Aや新規事業へのチャレンジを目指したい気持ちが日に日に強まりました。
しかし、そこでネックになったのは事業承継税制です。事業承継税制による贈与税の納税猶予の適用を受け続けるには、原則として最低5年間は事業を継続する必要があります。株式譲渡によるイグジットができないのです。また、従業員も原則として平均で80%の人数を雇用し続けなければならないため、大胆な事業のスクラップ&ビルドや合理化も困難です。
もし、それらのことをおこなってしまうと、猶予されている贈与税額に利子税も付加された税額を納付しなければなりません。その経済的な余力は、Z氏にはありませんでした。
イグジットに成功し、楽しそうに新規事業に取り組む経営者仲間を見ながら、Z氏は事業承継税制の適用を受けたことを、少し後悔していました。
2-2.対策ポイント
事業承継税制は、先代経営者から株式や事業用資産を承継する際の、贈与税や相続税が納税猶予される制度です。ここで押さえておかなければならないのは、あくまで「猶予」であって、基本的には「免除」や「非課税」となる措置ではないという点です。ただし、後継者が死亡する、あるいは、次の世代に事業承継するなどの要件を満たした場合には、原則として猶予されていた税額は免除されます。(なお、株式等の生前贈与に事業承継税制を適用した場合、贈与者(先代経営者)が死亡した際に、猶予されていた贈与税は免除されますが、贈与された株式等は相続財産に加算され相続税の課税対象とされます。その際、後継者が引き続き承継要件を満たしていれば、その株式等にかかる相続税が猶予されることとなります。そしてその後、後継者の死亡または次世代への事業承継などがあれば、猶予されていた相続税が免除されます)。
しかし、それ以外では、会社と事業を継続している限りにおいて納税が猶予される続けることになります。
もし事業承継税制の適用から5年以内にM&Aで会社を手放したり、事業を廃止ししたりした場合は、原則として猶予されていた納税額に利子税を加えた税額を納税しなければなりません。なお、5年間の継続要件を満たした後に、やむを得ず株式を譲渡する場合には、一定の条件を満たせば、その譲渡時の株価に基づいて納税額を計算する特例が適用される可能性があります。
さらに従業員雇用継続(平均80%)の要件や、毎年の書類提出なども求められます。納税が猶予されるかわりに、なにかと「縛り」が多いのが事業承継税制だといえます。
そのため、事業承継税制の適用にあたっては、制限事項を十分理解した上で検討なさることをおすすめします。
トラブル3 相続時精算課税で追徴課税、資料保存の落とし穴
相続時精算課税制度は、2024年に大きな改正があり、暦年課税と同様に、年間110万円の基礎控除が設定されました。以前は利用の少なかった相続時精算課税ですが、基礎控除の設定により使い勝手が向上したため、今後は利用が広がることが予想されています。
事業承継においては、相続時精算課税を選択して自社株を贈与すると、贈与時点での評価額に固定されるというメリットもあります。
一方、相続時精算課税では、贈与税の時効と関係なく、その選択をした年以後、すべての年に行われた贈与が相続時の相続財産に加算されるという特徴があります。その特徴を知らずに利用すると、思わぬ課税トラブルを引き起こすリスクがあります。
3-1.設例
P氏は20年前、父である先代社長から事業を承継してP社の代表取締役に就任しました。その年に、相続時精算課税の適用を選択し、3,000万円相当の自社株の贈与を受けました。その際、相続時精算課税の特別控除額である2,500万円分に対する課税は繰り延べとなり、500万円分に対する贈与税100万円のみを納税しています。
今年、その先代社長が亡くなって相続が発生しました。20年間で会社は大きく成長し、自社株の評価額も大きく上昇しました。しかし、20年前に贈与を受けて課税が繰り延べになっていた3,000万円分の自社株の評価は、当時の3,000万円のままです。P氏は当時、相続時精算課税を選択してよかったと思いながら、相続税の納税を済ませました。
それからしばらくして、税務署から尋ねたいことがあると連絡が入りました。その内容は、17年前と15年前、そして12年前に父から自分の口座に振り込まれたお金についてでした。当時、会社の経営状態が思わしくないときに役員報酬を取れず、P氏個人の生活資金を父から借りていたことがあったのです。金額は合計して800万円ほどです。後に、余裕ができたときに少しずつ返済しています。
税務署はその振込金額は贈与であるのに、当時贈与税の納税がされておらず、また、相続時に相続財産として加算されていないというのです。
P氏は、これは借入であって、その後返済しており、その記録は父の預金通帳に残っているはずだと主張しました。実際、余裕のあるときに、P氏は数十万円から100万円程度を返済として振り込んでいました。
しかし、税務署は証拠となる借用書などがなければ借入金とは認められないといいます。P氏から父への振り込み記録はあるが、それは借入金の返済ではなく、P氏から父への贈与だというのです。ただし、そちらは暦年贈与の基礎控除の範囲内なので非課税だというのが、税務署の言い分です。
P氏は借用書などを残していなかったため、800万円が借入金であることを証明できませんでした。
結局、800万円は相続時精算課税を用いて受けた贈与であり、相続時に相続財産に加算すべきだったのに漏れていたとされ、P氏は延滞税などを含めて500万円もの追徴課税を受けることになってしまいました。
3-2.対策ポイント
相続時精算課税はメリットもある制度ですが、一方では、暦年贈与にはないリスクもあります。
まず、贈与税の時効は6年(悪質な場合は7年)です。そのため、暦年贈与においては7年より以前の資金移動が、贈与かどうかが問題にされることは少ないと言われています(金額や状況にもより異なり、絶対に調査されないわけではありません)。
一方、相続時精算課税は、適用を選択した年以降におこなわれたすべての贈与について、相続時に相続財産に加算しなければならないルールとなっています。そのため、贈与税の時効とは関係なく、選択した年以降におこなわれた資金移動について、20年前でも30年前でも調べられ、それが贈与であるかどうかがチェックされます。
そこで、相続時精算課税を選択した年以降、その贈与者からの大きな資金移動があった場合は、その内容(贈与か、貸付か、出資か、など)を客観的に示せる証拠書類(借用書など)を保管しておかないと、将来の課税リスクが残ります。10年程度ならともかく、20年も30年も書類等を保管しておくことは、大変かもしれません。
相続時精算課税は、一度選択してしまうと、再び暦年課税に戻すことはできません。このようなリスクや手間もあることを理解した上で、慎重に選択の判断をしましょう。
まとめ
経営者や企業が正しく納税をすることは必要ですが、わざわざ多くの税金を支払う必要もありません。その意味で、「節税対策」に取り組むことが、すべて悪いというわけではないでしょう。しかし、税制は毎年、なにがしかの改正がおこなわれます。また、法律が変わらなくても、法の抜け穴を突くような「節税対策」は、国税庁の解釈変更などによりすぐに利用できなくなります。
そのため、税の専門家ではない経営者やご家族が、断片的な知識で「節税対策」に取り組むことは、かえって将来のトラブルや課税リスクを招きかねません。特に相続時精算課税のように、一度選択すると後戻りできない制度については、長期的な視点と最新の制度理解に基づいた判断が不可欠です。
青山財産ネットワークスでは、税理士法人や弁護士などの専門家とも連携しながら、相続・事業承継に関するご相談をトータルにお受けしています。
制度の正しい活用と、将来を見据えたご家族の資産設計のためにも、相続対策にお悩みの方はぜひ青山財産ネットワークスにご相談ください。
- 松川 洋平Matsukawa Yohei
- 執行役員 コンサルティング事業本部 第一事業部 部長
1983年兵庫県生まれ。早稲田大学 商学部 卒業。
辻・本郷税理士法人にて、相続・事業承継の税務業務に従事、デロイト・トーマツ税理士法人にて、事業承継のコンサルティング業務に従事する。
2018年に株式会社青山財産ネットワークスに入社し、上場・非上場問わずオーナー経営者に対して、財産の承継・運用・管理の総合コンサルティングを提供している。
- 専門分野
- 企業オーナー向けコンサルティング
- 資格
- 税理士
- 著書
- 事業承継 親の心子知らず 子の心親知らず~19の失敗事例から導く「思い」「理解」「感謝」のない対策の行方~